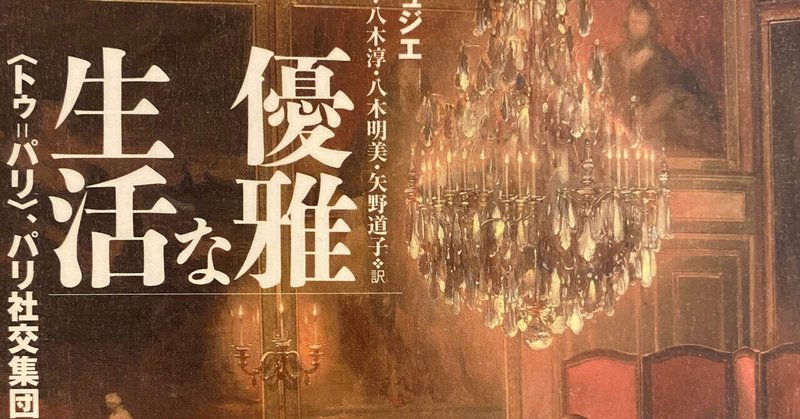
読書記録(2023年7月分)
暑すぎてバテてしまい、そこまで多くは読んでいないですが、いい本との出会いに恵まれました。
文芸書
①レオパルディ『断想集』
19世紀初めに活躍したイタリアの詩人で思想家のレオパルディ。厭世主義や悲観主義の括りに入れられることの多い人ですが、その穿った視線から繰り出される鋭利な断章の数々がとても面白かったです。気分が鼓舞する格言集の類では全くないですが、思索の補助輪のような形で置いておくのもいいかなと。
② アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグ『汚れた歳月』
田原桂一展のポートレイトで気になった作家で、エロティシズム溢れる異端の作家と思っていました。実際その通りなのですが、ストーリーで読者を運ぶというよりは、印象的なイメージを言葉で作り上げてそれに読者を浸らせるというものです。その意味で面白くはないです。ただ想像してみると痺れるような光景が浮かんできて、絵を眺めているような感じがします。
澁澤龍彦らの紹介で一時はブームだったそうですが、その後下火になって…、という中での新訳です。寿ぎましょう。
美術書・専門書
①アンヌ・マルタン=フュジエ『優雅な生活 トゥ=パリ パリ社交集団の成立 1815-48』
ナポレオンの時代が終わり王政復古のフランスにおける「社交」とはいったいどのようなものか、というありそうでなかった研究書。ロマン主義の芸術を育んだサロンなど、19世紀前半のフランス文化に興味がある人には本当におすすめできます。あの時代が立体的に迫ってくる気がしました。
なにより小話が面白く、遠い公爵や貴婦人の生活と苦悩も伝わってきて、一種この本自体がバルザックの小説味がありました。
②阿部成樹『アンリ・フォションと未完の美術史』
20世紀前半を牽引したフランスの美術史家アンリ・フォションの美術史とその方法論の形成を追った本。美術史の本というよりは「美術史学」についての本です。フォションが隣接領域の学問から用語や概念、そして方法論を拝借し、それを美術史学に応用して学問自体を豊かに広げようとする過程が印象的でした。
アルベルティが『絵画論』を記した時も、キケロの弁論術などから用語や概念を拝借していますし、学問の発展には異分野の要素を柔軟に取り込んでみる知的態度が必要だなと思います。
③アニエス・イズリーヌ『ダンスは国家と踊る フランス・コンテンポラリーダンスの系譜』
コンテンポラリーだけでなく、絶対王政期から続くフランスのダンスと政治の関係を軸にしたダンス史。この手の本は芸術性やスターたちの紹介と称賛に終始する感がありますが、こちらに関しては淡白にフランスのダンス文化がいかに官僚的な統制の中でもがいてきたか、ということが分かります。
日本人の舞踏家についての記述も見られますし、ダンスを表現として選んでいるアーティストの方は必読だと思います。
番外(ドキュメンタリー映画)
久しぶりに面白いと思える美術ドキュメンタリーでした。4つほどのレンブラントにまつわる話が展開されるので少し混乱しますが、それぞれが興味深いですし、あまり知ることのない世界が覗けます。
オランダのアムステルダム国立美術館がレンブラント作品を買おうとしたところ、予算の関係上難しいということになり、フランスのルーブル美術館と共同購入という形になります。しかし立場の強いルーブル側がこれを政治問題化させて、いつの間にかフランス優位に購入の話が展開されるなど、美術と政治、美術と金のシビアな問題は、投機対象の現代アートだけのものではないことが分かります。
おすすめです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
