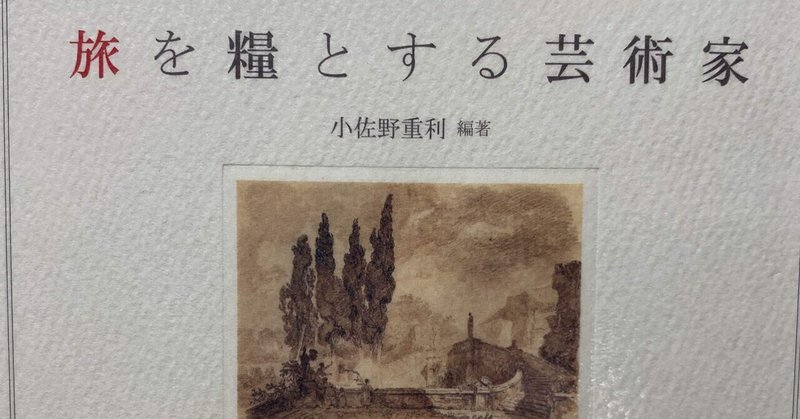
「読書感想文」旅を糧とする芸術家(2006年)
西洋美術史の巨匠たちは旅をどのように作品の進化に活かしたか、また彼らにとって旅はどのような意義があったか、についてまとめられた本。各著者の論考がまとめられている、論文集です。
目次
・美術の展開に果たした芸術家の旅行の意義
小佐野重利 (総論)
・さまよえるヤーコポ・デ・バルバリ
秋山總 (ルネサンス)
・1603年のルーベンスのスペイン行と二点の絵画
中村俊春 (バロック)
・イタリアへの旅 16世紀後半にローマとヴェネツィアを旅した北方画家たち
マリ・ピエトロジョヴァンナ (ルネサンス)
・ベラスケスのイタリア旅行
楠根圭子 (バロック)
・横断と遡行 18世紀フランスの画家とイタリア
阿部成樹 (ロココ)
これにベラスケスのイタリア旅行の記録と、モーリス・ドニの第二回イタリア滞在資料が載っています。

内容
全部を書き記すことはできないので興味深いところだけ。
総論として古代や中世の作家たちは移動したのか問題についてが検討されます。戦利品として美術品を掠奪することはあっても、アーティスト自身が国を離れて異国へ移る例がどれくらいあったのか。プリニウス や夥しい数の史料が引用され、頭が痛くなるところです。中世は逆に史料が乏しすぎて想像の範疇でしか検討ができません。
そこでエラスムスの『対話集』(1522年)の「向こう見ずな願掛け」にでてくる話、酔っ払った男たちがそのノリで巡礼を開始して客死するもの、を引いてきます。アナール派のリュシアン・フェーブルはこの挿話を、当時の人は王も市民も農民も巡礼しまくり、放浪好きで移動ばかりしていたことの表れだと言うことです。そこから色々考えていきます。
「旅を糧にした」というタイトルですが、総論を読み全部を読んだ限りでは、旅というより「巡礼」の方がニュアンスが近いです。逆に言えば今日の旅のニュアンスに「巡礼」が無さすぎるのかもしれません。
例えばフランドルの画家ロヒール・ファン・デル・ウェイデンは1450年にローマに旅行しています。それは前年に死んだ娘の大赦を得るためで、芸術以外の目的の旅をしていますが、結局フィレンツェに立ち寄り、フラ・アンジェリコを研究してその後の作品に活かしています。

巡礼×芸術の象徴的な例として記憶されるべきですが、ほとんどの場合は政治的な意味合いのある「随行」だというのが実際のところです。
画家は肖像画を描くという名目で有力者と近づけますから、スパイとして便利です。この全体の論考の特にバロックの章は旅というより政治紀行が面白いものになっていき、オイオイと思ってしまうわけです。
例えばルーベンス。イタリアのマントヴァの宮廷画家として働いていましたが、スペイン宮廷へ外交上の贈り物を持っていくという任務を任されます。しかし途中で立ち寄ったピサで、トスカーナ大公のフェルディナンド1世に、その秘密の贈り物の名録を全て知られており、目の前でお前らの目論みはお見通しだと言われたのです。その際「のろまのようにその場に立ち尽くしていた」と手紙で書き残しています。
マントヴァの宮廷にトスカーナ大公国のスパイがいるに違いないと連絡するあたりには、もはや画家なのか007なのか分からない臨場感がありました。ただこのスペイン旅行によってルーベンスはスペインの顧客をゲットすることになり、画家としての道が開けるチャンスになりました。

その際にスペイン宮廷にいた若いベラスケス は、ルーベンスのアドバイスでイタリアに行きますが、やはりスパイ容疑がかけられていました。論考では1640年頃の第二回イタリア滞在を中心に扱っていますが、在ローマのスペイン人枢機卿から「祖国スペインが経済的に危機なのに高い絵画を買い漁っているベラスケスはけしからん」と非難されているのが残っています。
紳士で節度ある画家のイメージがありますが、ベラスケスはイタリアでは開放感からか豪遊しており、黒人奴隷を連れたり、マルタという女性との間に子供が生まれ、後に警察を使って強制的に引き取ってしまったりと、画家の荒々しい負の面を見て取れます。これもまた旅の作用でしょうか。
時代が降ってもイタリアは芸術家にとっての聖地であり続けましたが、18世紀も後半になると巡礼というよりは観光や絵の取材という感じで、より今風の旅行に近づいてきます。理想を求めにイタリアに浸かるのではなく、あくまで感性は自分のところにあり、技芸を磨くための修行の一環というような軽さになっていき、巡礼感は乏しくなっていきました。
感想
①テーマが巨大過ぎるため、ロヒールやルーベンス、ベラスケスなど大巨匠の旅について書いても、旅と芸術の展開の関係はどのようなものかサンプルが少な過ぎる感は否めません。イタリアに行ったことで凡庸になった画家もいるはずですし、竹林舎の「西洋近代の都市と芸術シリーズ」のように大著かつ全6巻くらい要すると思います。
シンポジウム原稿のまとめとしてだけでは、本当に旅と芸術の展開の関係をそのように考えてしまっていいのか、というくらいサンプルが少ないので、この本から普遍的なことはほとんど何も言えないです。
②旅なのか移動・移住なのか。ルーベンスとベラスケスの論考は旅行について書かれていますが、他のはかなりの長期滞在です。留学や宮殿就職のことを旅と見なしているのは、明らかに違う意味合いになるのではないかと思います。そこの区別にあまり統一感がないのが気になりました。
③とにかく質が高い。全論文に発見と面白さ、そして読み応えがあります。日本を代表する西洋美術史家が集結して書いてますし、他の論文集とは密度が違うと思います。また、付録のベラスケスのイタリア旅行についての記述は、謎の多い画家の一面が知れて、彼の見方が深まると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
