
国際ベトナム語能力試験(iVPT) Aレベルを振り返る1 問題の特徴
2023年8月11日に国際ベトナム語能力試験(iVPT)のAレベルを受験してきました。この試験は例年2月に行っているのですが試験日は毎年出勤が必要な仕事と重なっているため受験する機会がありませんでした。しかし、今年はなんと8月にもAレベルの試験を開催するということで初めての挑戦です。
現在、日本で受験できるベトナム語試験としてはiVPTと実用ベトナム語技能検定試験(ViLT)があります。特にiVPTは日本の試験ではないということもあって情報が少なかったり実際に受験してみると出題傾向もかなり特徴的でしたので、外国語教師の視点からAレベルを分析してみたいと思います。さらに次の記事では私がやった試験対策も紹介していきます。
中国語教師から見たiVPTの特徴
iVPTの基本情報については公式HPをまず見てみましょう。
試験の主催などで主導的な立場にあるのは日本やベトナムの教育機関ではなく台湾の国立成功大学ベトナム研究センターである点がこの試験の最大の特徴です。このセンターのHPを調べてみるとiVPTのことが中国語で書いてあります。日本の公式HPよりも詳細な情報が詰まっているので中国語が読めるのであれば一読の価値ありです。
レベルはA, B, Cの3段階でCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に準拠しているとのこと。最近の語学テストはどんな言語でもCEFR準拠が当たり前になってきました。Aレベルですとリスニングとリーディングの2技能の問題しか出ませんが、Bレベル以上ではライティング・スピーキングが加わり4技能になります。
で、具体的な試験内容については日本の公式HPで販売している模擬試験問題が唯一の手がかりになります。取り寄せて問題を見てみましたが台湾を題材にした絵などが含まれており作問作業も台湾で行われているようです。語学テストで「どのようなスキルを重視して測定するか」や「どのような問題形式がスタンダードなのか」は国や地域によって慣習や考え方が異なるため、ベトナムではなく台湾で作っているというのは試験の性格を決める上でもかなり重要なファクターでしょう。中国語試験の場合でも中国大陸で作られたHSK(汉语水平考试)と台湾のTOCFL(華語文能力測驗)では出題スタイルが変わってきますし、iVPTもなんとなくTOCFLにスタイルが似ていると感じました。
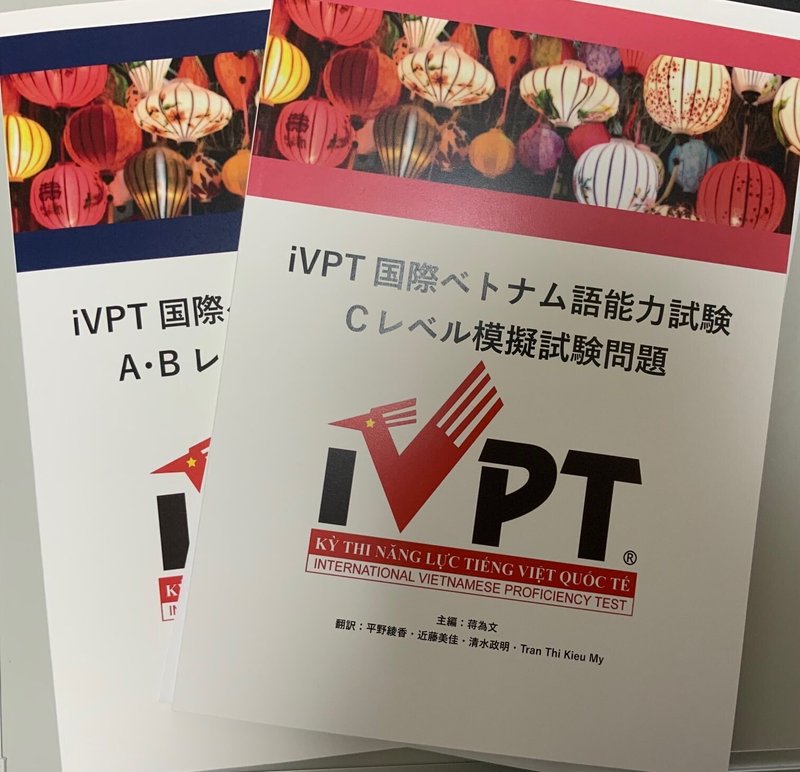
模擬試験と実際の試験を振り返ると、Aレベルでは以下のような点が特徴的だと感じました。なお、試験問題には著作権があるため問題そのものを紹介することはしません。
1. 文法知識よりも語彙知識が試される
日本で作られる語学試験は少なくとも中級レベルくらいまでは文法知識を問う問題が多く、文法構文やコロケーション、変則的な活用なんかが大好物です。そして上級レベルになると急に恐ろしいほど高度な語彙知識が大量に求められます(中国語検定とか典型例ですね)。
一方、iVPTのAレベルは「出てくる語彙を知っているかどうか」で正解か不正解かが決まる問題が多い気がしました。問題文に出てくる〇〇という単語を知っていれば正解、知らなければ4択でサイコロを振るような問題形式です。また、語彙のジャンルも傾向性がはっきりしていて「生活用語」がとにかく重要で、花の名前、動物の名前、果物の名前、家庭用品なんかがよく出てくる印象です。日本在住の学習者にとって厄介なのは台湾もベトナムも日本とは気候が違うので日本では馴染みのないものがよく出題される点です。果物ならマンゴスチン、スターフルーツ、スイカなど南国フルーツはどれも必修単語だと思いますし、「日本にいたから食べたことない!」と文句を言っても容赦無く出題されます。
その一方で、経済・法律・歴史・時事などの表現はAレベルではあまり出題されないため、ベトナム語のニュースや新聞記事を読むのは試験対策としてはあまり適していないと感じました。これはちょっと意外ですね。あと、台湾で作問されているためか台湾で流行らないものは出題されにくい印象があります。台湾では人気がない「サッカー」とか「中国」が正解となる問題が出てくる確率はきっと低いでしょうし、" Uỷ ban nhân dân"「人民委員会」などの社会主義系の単語もほとんど出ないのではないでしょうか。
こんな感じで「語彙を知っていれば正解、知らなければ不正解」という問題が多いので、自分の興味関心との相性が悪いとAレベルでもかなり苦労すると思います。例えば、ベトナム旅行が好きで市場を歩き回って買い物する人ならば普段から知ってる単語が多く出てくるでしょうが、出張メインのビジネスマンや専門分野でベトナムと関わる研究者だと自分の知ってる範囲の単語はあまり出題されません。また、語彙を知っているかどうかは運の要素も大きいので自己採点で不正解に気づいたとしても対策しづらい部分があります。例えば、ビジネスマンの方が「ほうき」や「ブランコ」という単語を分からなくて不正解になったとしても、その後にその単語が出てくる文章を読む可能性はかぎりなくゼロに近いでしょう。
2. リスニングは各問題一回のみ&会話になると速度が速くなる。
リスニングの放送回数は各問題で一回のみです。これはキツイですね。そして、会話パートがある場合だと問題のナレーションよりも話すスピードが速くなります。これも地味にツライです。会話が含まれる問題が不意に差し込まれている部分があるので、いきなり高速で話し出されても耳が追いつかないし挽回のチャンスもないんですよね …
というわけで、リスニングはとにかく出題形式と試験音声のクセを把握しておくことが必須です。これを知ることができる唯一の手段は模擬試験問題だけなので本気で受験する人には購入をお勧めします。ベトナム語の知識にかなり自信のある人でもリーディングなら初見で満点が取れると思いますが、リスニングは出題形式を知らないまま臨むと取りこぼす可能性が高いです。
3. iVPT Aレベルは初級レベルのテストではない
ということで、AレベルはiVPTの中では一番易しい問題なのですが初級レベルでは手も足も出ないくらい難しいです。私もベトナム語を8年間も勉強したはずなのですが結構取りこぼしていました。ただ、前述したようにこれらの取りこぼしは「自分があまり関心を持っていない分野の語彙を知らなかったこと」が原因なので対策にも限界を感じています。日本でもベトナムでもあまり使うことない生活用語をくまなく覚えるよりも、自分の専門分野に関する術語を覚えた方が今後の実りが大きいのでiVPTは当分卒業でいいかな。
と、いきなり卒業宣言してしまったのですが次の記事では自分のやった試験対策を紹介します。
(8月14日追加)
続編を書きました。
