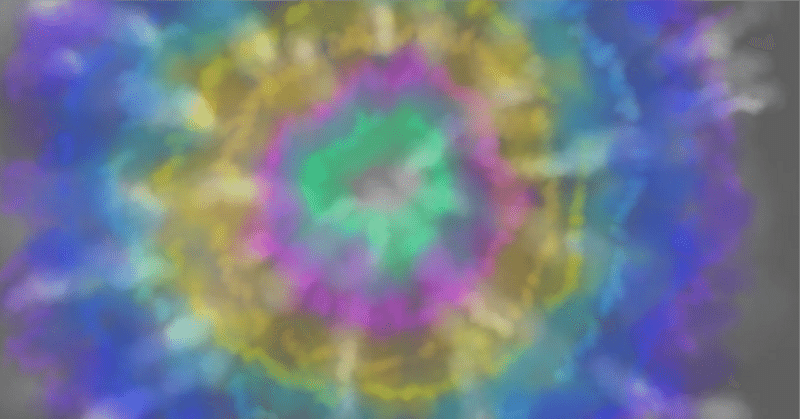
シミ(ショートストーリー)
気がつくと、大人の男がギリギリすれ違えるくらいの通路に横たわっていた。そこは、自分の手も見えないくらい真っ暗だった。俺はそこにあるはずの手で壁を触り、大きさを把握した。そして、目が覚めたときの状況と掛け合わせて現状を推察したというわけだ。
通路であるというのは憶測だった。左右に歩いたら壁に触れたが、前後には壁らしい壁はない。加えて、わずかに空気が流れているのを感じることが出来たからここが通路なのではないか?と予想を立てている。
妙に落ち着いてるように思われるかもしれないが、目覚めた直後は混乱した。先方と会うために道を歩いていた俺を、後頭部から鈍い痛みが襲った。そこから先の記憶はなく、次に見た景色は真っ暗だった。混乱の後、思考が働き始めると、自分が身をおいていたはずの安心できる日常が、一瞬で奪い去られてしまった事に気づいて深く絶望した。
そこから先は単純だった。絶望していても始まらない。とにかく状況を把握して、それからどうするかを考えよう。そう思い、今に至るのだ。
どうしていくかと考えていると、だんだんと目が慣れてきた。僅かだが、色を識別できるようになってきた。どうやらこの場所は、床に赤黒いマットのような物語敷かれているようだ。灯りが届かない真っ暗な闇の中、別の色を認識する事が出来た俺は、安心と不気味さの両方を同時に噛みしめることになった。
不気味だと思ったのは、床に敷かれた赤黒いマットのようなものが、まるで血のように見えるからだった。
「はぁ、」
あえて吐く息を声にのせてみたのは、自分がここに存在しているのかを確かめるため。ここまでの状況判断が頭の中で思ったことなのか?それとも声に出していたことなのか?を掴んでおきたかったからだ。
「少し歩いてみるか」
俺は思ったことを声に出しながら、状況を前に進めていくことにした。背中を伝う汗は冷たくて鮮明だ。それは、俺がまだ生きていることを証明してくれているような気がした。
今、自分が前に進んでいるのか、それとも、後退しているのかは、わからない。どれくらい歩いただろうか?そもそも今は何時なのか?いい加減目印になるものが欲しいと思うようになってきた。
わかったことももちろんある。この通路、右側に一定間隔で花瓶を置く台が設置されている。花瓶には花が生けてあり、その花の色は黄色だった。
「赤いマットに黄色い花」
なぜかは分からないが、覚えておかないといけない気がした。だから声に出して脳に記憶しようとしている。
不思議な気持ちなのだが、この花を見ると安心する。1つ、また1つと、花の黄色はどんどん鮮やかになる。明るい色になればなるほど、オレの心は晴れていく。
しばらく歩くと、滑車を引くような音が聞こえてきた。カラカラという乾いた音なのだが、耳を澄ますとそれ以外の音も聞こえた。口笛のようだった。
口笛は、Billy JoelのHonestyという曲を奏でているようだった。
俺がまっすぐ進んでいくと、カラカラという音と口笛の音はどんどん大きくなっていった。先程まで気にならなかったのに、ある地点からその音が怖くなってきた。
「これ以上先に進んではいけない」
小声でそう発してみた。発してみると頭がクリアになり、俺が今三択の渦中にいることが理解できた。ここをまっすぐ突き進む。全力で引き返す。目の前にある花瓶を置く台に身を潜め、死角から正体を探る。
ここまでの道は一本。どの道を選んでも体力勝負だった。
全力で口笛の方へ走った。口笛は同じテンポでHonestyを奏でた。息があがる。足がもつれる。
正体を見た。ホテルのボーイのような格好をしたピエロが、少しだけ前かがみの姿勢で水とバーボンを運んでいた。
俺は奴から嫌な気配を感じた。やつの目はサファイアのような青い光を放っていた。
ここは大人がギリギリすれ違えるくらいの通路。奴に捕まる確率は高い。でも俺は、ここを走り抜ける以外の方法を考える余裕を持ち合わせていない。
「うぉぉぉおおおお」
全力でピエロにタックルする。運ばれた水は飛び散り、バーボンを瓶が割れる。ボーイのようなピエロは人とは思えない、まるでおもちゃのような崩れ方をした。
俺はそのボーイの先にある真っ白な光に向かって走った。吸い込まれそうな真っ白な光の中へ、走ったのだ。
気がつくと、白い天井が見えた。周囲で女性が慌てているのをぼんやりとした頭で理解した。
しばらくすると意識と現実の焦点があってきた。白衣を着た男が、俺に向かって声をかける。
どうやら俺は、襲われた場所とは全然違う、路地裏のような場所で倒れていたらしい。頭から血を流しながら。
まぁまぁな重症だったようで、2日間も寝ていたようだ。
たまたま通行人が救急車を呼んでくれたから良かったものの、もう少し発見が遅れていたら、かなり危険な状態だったと医者から言われた。
結局、あの場所のことは何も分からなかった。夢にしてはリアルだったし、ちゃんとした手触りもあったのだ。
何よりも、夢から覚めたという感覚より、無事に帰ってこれたという感覚のほうが強かった。それはあの場所が、俺にとってリアルだったからだと思う。
俺はベッドから起き上がり左に視線をやった。壁には、俺が襲われた日に着ていた洋服がかかっていた。ふと目を凝らすと、身に覚えのないシミが付着していた。
俺は確信した。そのシミは水だったのだ。
看護婦が気晴らしにとかけてくれたラジオから、今日起こった事件に関する報道が流れていた。
その報道は告げたのだった。俺が向かうはずだった会社の人間が逮捕されたという事を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
