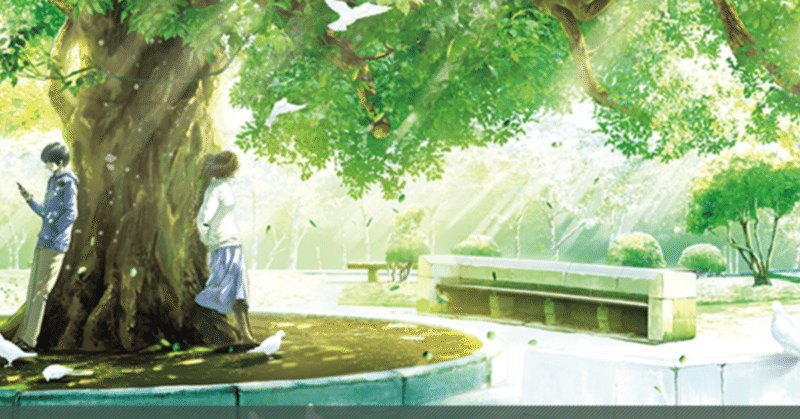
痛みの物語——「イタい」と「痛い」
いつ「痛い」と感じるか
指を扉に挟む、顔が電柱にぶつかる、転んで膝を床に打つ。痛い。わたしたちの体は、いとも簡単に、日々痛みを感じている。
痛いと言われるのは、体だけではない。こころもまた痛む。
誰かに嘘をついてしまう、好きな人に告白して振られる、友達にいじめられる。痛い。心も、日々痛みを感じている。
「痛い」の表記を少し変えると、別の意味が立ち現れて来る。「痛い」を「イタい」にすると、自分ではなく他人についてのことになる。
空気を読めない誰かの発言、SNSでの高飛車な態度、自分はかっこいいと言わんばかりの振る舞い。しばしば、目の前にいる「この人」は「イタい」人だと私たちは評価する。
「イタい」と「痛い」
しかし、「この人」が「イタい」とき、私は痛くないのだろうか。『青くて痛くて脆い』の主人公である田端楓(楓)は、大学入学直後に出会ったイタい存在である秋好寿乃(秋好)に対し、次のように評価している。
痛いし青くさくて見てられない、自分の信じる理想を努力や信じる力で叶えようとするし叶うと思っている純粋さ。でもそれを痛いだなんて思うのは、少なからず自分にもそんなことを思っていた覚えがあるからで、いわば彼女を痛いと思うのは過去の自分を恥ずかしく思っているからだ。
誰か「イタい」人がいたとき、どこか自分にもわかるところがあると感じてしまう。自分も本当はそうなりたかった、そうなろうとしていた。そんな自分自身と直面させられてしまうことで、心の痛みを感じてしまう。そしてしばしばわたしたちは、そうした自分の痛みから目を背けるように、他人を「イタい」と非難してしまう。
『青くて痛くて脆い』を貫くほかのテーマのひとつである「理想」に引き付けながら、もう少し詳しく見てみたい。
秋好は、大学の講義で質問の名を借り、「この世界に暴力はいらないと思います」と主張するような、理想論を語る人物である。大学1年生にもなって現実に反するような理想を純粋に語る秋好は、他の人たちから「イタい」人だとうわさされていた。先に引用したように、主人公の楓自身も秋好を「イタい」人だと判断した人物の一人である。
一方で、楓のなかにもそうした理想を追い求めてみたいという気持ちが存在する。しかし、大学1年生にもなって、ただ理想だけを追い求めることはもはやできない。理想に惹かれる気持ちと、理想に身を捧げられない状況とに挟まれたひとは、いずれかを選ばなくてはいけない。そして、現実を選びとりながらもなお、理想への未練がある人は、理想論者を「イタい」と評価し非難する。おそらく、楓もそうした人物である。そしてその「痛い」という非難はきっと、自分自身が押しつぶしてしまった、理想に惹かれる心の「痛い」という叫びでもある。
楓は、秋好の言葉を思い返しながら心の内で叫ぶ。
『全員がいっせいに銃を下ろすような理由があれば明日、戦争が終わる』
そんなこと言ってたな、お前。
痛い、痛い痛い痛い、理想論。
『だから何かを変えるのに間に合わないことなんて一つもない』
やめてくれ。
痛い痛い痛い。
胸の奥が、痛い。
秋好を非難する意味の「痛い」と楓自身の感じる「痛い」は、もはやここでは一つに混ざっている。他人を非難する痛みは、自分の痛みでもある。
「痛い」を引き受ける
物語の結末を明かさないようにしながら、主人公楓の最後のセリフだけをここで引用しようと思う。
その時もう一度、ちゃんと傷つけ。
「ちゃんと傷つく」とはいったいどういうことだろうか。どんな傷つき方を、どんな痛みの感じ方をしたら、わたしたちは「ちゃんと傷ついた」と言えるのだろうか。
この文章の最初でも書いたように、わたしたちは日々、痛みを感じている。そのなかには、すぐに忘れてしまうような些細な痛みもあれば、何年経っても消えてくれない大きな痛みもあるだろう。
「痛い」と感じることを繰り返す中で、ときにはわたしたちは痛みに麻痺し、「痛い」と感じなくなってしまうこともある。「痛い」と感じることを怖れるあまり、本当は「痛い」と感じていても、「痛くない」と言い張ってしまうこともある。
痛みは、あまりにありふれていて、そしてどうにも扱いづらい。「ちゃんと傷つく」とは、「自分の痛みを自分の痛みとして引き受ける」ということだとして、それはいったいどうすれば可能なのだろうか。口にするのは簡単でも、実際に「ちゃんと傷つく」に足る気持ちをもつのはそう簡単ではない。
青くて痛くて脆い
だからこそ、「ちゃんと傷つけ」と楓が自分自身に最後に語りかけることの意義は大きいだろう。『青くて痛くて脆い』のひとつの大きなテーマは、痛みにあるといってもよい。
『青くて痛くて脆い』は、こうした哲学的思索に耐えうるだけの強度をもつ作品である。まだ小説自体を読んでいない方にこそこの文章を読んでほしいという思いから、物語の中身にこそ踏み込まなかった。しかし、その中身は概念的な補助線を引きながら読むことのできるだけの、複雑なリアルを抱え込んだ物語になっている。
この文章は、そうした『青くて痛くて脆い』の読み込みの実験的試みであった。
痛いとはどういうことか。
わたしたちは、いつ痛いと感じるのか。
自分の「痛い」を引き受けるにはどうすればいいのか。
こうした問いに答えは、物語とともにあなた自身にこそぜひ探っていただきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
