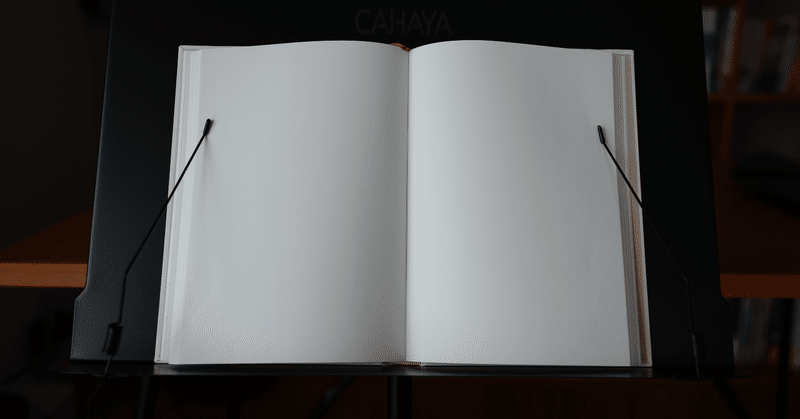
10月に読み終えた本
10月の最後の土日に神保町ブックフリマなるイベントが催されており、土曜に行ってきた。去年から始まったもので、神保町周辺の出版社とか書店などがそれぞれの場所で本を売る(オンラインでやってるところもあった)。ちょっと安く、あるいはけっこう安く本が買えるのでお得。
去年も行って、そのときは1冊しか買わなかったのだが、今回はそこそこ買ってしまった。クオンで2冊、白水社で4冊+α、本の雑誌社で1冊。ありがてえありがてえ……。他にもいくつか見て回ったが、これがこんなに安いんかというのがめちゃめちゃあり、欲望のままに買っていたらヤバそうだったので、自制した。
神保町はふつうの本も古本もあってたのしい。うまい飯も食べられるし、アウトドア用品も買えるので、一日いても飽きない。ちょっと住んでみたい。
このイベントも年1回と言わずもっとやってくれるといいなあと思う。大変なのだろうが。
見出し画像は白水社で売っていた束見本(A5判のハードカバー)。200円だったので思わず買ってしまった。
河合祥一郎『シェイクスピア――人生劇場の達人』(中公新書)
ちくま文庫、松岡和子訳のシェイクスピア全集を4冊(5作品)ほど読んで、ちと周辺知識も入れておきたいと思って読んだ。
まず伝記部分は、やはり、いまだに詳しくわかっていないことなどもあるそうで、こんなに作品はあるのに別人説とかグループ説があるのも頷ける。
次にシェイクスピア作品の特徴に触れられる。主観的な時間構造であったり、空間(舞台)の扱いの自在さ(これに関しては、この時代の劇場の構造も関わりがあるらしい)が取り上げられて、ただ戯曲を読むだけだとわからないことが知れておもしろかった。たしかに読んでみると、ト書きがあまりないなあと思っていたのだが、その理由がわかってなるほどなとなった。
韻文も特徴的として挙げられる。韻文でも、弱強五歩格とか四歩格とか、あるいは韻文ではなく散文を使ったりとか、さまざまな場面で書き方を変えているというのは翻訳をふつうに読んでるとあまり気づかないので、実際声に出して読むといいのかもしれない。
喜劇と悲劇については、『ハムレット』に倣って、悲劇をTo be, or not to be(あれかこれか)とするなら喜劇はTo be and not to be(あれでもあり、これでもある)な世界だと書いているのがおもしろかった。まじめ/ふまじめの境界線を撹乱する喜劇、神に代わって運命を定めようとする傲慢さから生まれる悲劇、なるほどたしかに、これまで読んできた戯曲もそういうふうに理解するとわかりやすい。そしてそれらは、最初のハムレットの伝記や生きた時代のことを知ると、理解が深まる。
もちろんこの解説以外にも理解する手口はあるだろうし、なにより戯曲なら観劇することだろうなあとあらためて思う。ただ、続けて読んでいくのにいろいろなヒントを得られてよかった。というわけで次は『リア王』かな。
キム・ジヘ『差別はたいてい悪意のない人がする――見えない排除に気づくための10章』(大月書店)
プロローグに、著者が使ったある言葉が「差別的」であると指摘された経験の話が書かれている。「私の中で、その言葉をあえて問題ではないと否定し、些細なことだと考えようとする防御機制が働きはじめたのだ」(4頁)と書かれていて、これを読んだときにあっ、と思った。自分がそういう指摘をされたというわけではないのだが、日常的に発したり考えたりする言葉を、「これは良くない表現なのでは」「いや、しかしこれはそういうことではなく……」というような弁護を、「なるべく」理屈っぽく考えるようなことがあり、そのような感覚を文章で読まされたような気がして、あっとなったのだと思う。
この本は、そういう感覚を、さまざまな歴史や社会学的、心理学的知見、法や政策などのさまざまな分野から照らし出す(韓国とアメリカの事例が主)。先に書いた、自分の弁護的感覚も、読みながらあっちからもこっちからも白日の下に晒されているような気持ちになり、なかなかさらりとは読み飛ばすことができなかった(文章自体は非常に読みやすいと思う)。
韓国の事情というのも全く知らなかったのだが、興味深かった。日本のことも知っているわけではないが、韓国における「闘争」もかなり苛烈なようで、驚いた。ただ、なんとなく、表面化して盛り上がる(?)運動の強度が高そうな印象がある。
個人的にはトイレについての議論ではじまる9章が興味深くて、公平を追求して「普遍性」に到達することが必ずしも「多様性」とはそぐわないということが、トイレの設計から見えてくる。形式的平等が被差別側から見ると実は差別の強化につながるというのも、少しブルデューなんかを思い浮かべた(構造的差別について考えた人だと思うので)。マイノリティが「違う」とされることは、すなわちマジョリティが「中立」であるということになって、そこで構造的差別の再生産が生じる。この「違う」というのを相対的に見ることで、みんながみんな違うという当たり前のことに気づくというのは、一周まわったなあという感じだが、景色は違って見えるように思う。
印象的だったところについてざっと書いてしまったが、シンプルに、読んで非常にためになった。良書です。
トーマス・ベルンハルト『破滅者』(みすず書房)
ベルンハルト、名前は聞いたことあるけど……という感じだったが、書店に並んでるのを眺めてたら興味が出てきたので、この『破滅者』を読んでみた。「ヴィトゲンシュタインの甥」と「破滅者」という小説が収録されている(元々はそれぞれで一冊になっていたらしい)。このふたつの作品はある意味「音楽小説」で、それをフックに読めるかなと思った。ちなみにベルンハルトは音楽も専門的に学んでいたことがあったらしい。
まず「ヴィトゲンシュタインの甥――最後の古き佳きウィーンびと」。この「ヴィトゲンシュタイン」とは哲学者のルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインのことだが、その「甥」(いとこの子らしい)の「パウル・ヴィトゲンシュタイン」のことが書かれている。パウルと言ったらルートヴィヒの兄で、「左手のピアニスト」として有名なあのパウルのことを思い出してしまうが、別人らしい。そういうこともあって最初はフィクションなのかノンフィクション(小説かどうかというより、事実かそうじゃないかという話)よくわからなかったが、実際にいた人だし、ベルンハルトとの親交も実際にあったことらしいというのがわかった(訳者あとがきにもそうある)。
というのも、事実を元にしているのだが、なんだか本当にあったことなのか不思議になるような出来事ばかりで、それはヴィトゲンシュタイン家というウィーン屈指の貴族の生活がまったく自分からすると現実味がないからというのもある。しかしその書き方も、出来事が行ったり来たりし、似たような文章を重ねたり、最初から最後まで段落がまったくなく流れるように進行するので、そういった文章の書き方も、不思議さの大きな理由なんだろうと思う。何かの形式を踏襲しているようなところが「音楽的」と言っていいかもしれない。
テーマも、重いことが書かれていたとしても、妙にカラッとしていて、パウルの思い出というにはあまりにも客観的な感じが、逆にぐいぐい読ませる。段落がないと書いたが、途中で止まっても再開する時にあまり足枷にならなかった気がする、読むのに何日かかかったのに。あと、あとがきにもあるけど、ウィーンの都市小説という趣も強くて、ああ、こんな街なのかあというのも知れて愉しかった。
そして表題作の「破滅者――グレン・グールドを見つめて」。サブタイトルにあるように、グレン・グールドが一つのテーマ(主題)になっている小説である(サブタイトルは邦訳に独自につけたものとのこと)。
「グレン・グールド」とはピアニストである「あの」グレン・グールドだが、この小説では「ヴィトゲンシュタインの甥」のときのように事実に基づいているわけではない。グレン・グールドとヴェルトハイマー、そして私という3人からなる話で、とくにヴェルトハイマーという男を中心にして、私が回想し、思ったことがひたすらに書かれる。オーストリアのザルツブルクにあるモーツァルテウム音楽院で、同じ師の元でピアノを学んでいたという3人の話(これもグールドの伝記的事実とは異なるらしい)。
この小説も、最初に短い段落が少しあるだけで、あとはまったく段落もなく、それが最後まで続く。「ヴィトゲンシュタインの甥」が音楽的と書いたが、こちらも明らかに音楽的な構造を意識して書かれている。3人の話題(主題)が何度も執拗に、変奏しながら語られ、そして、内容だけでなく文体も、「と私は思った」という表現がひたすら繰り返されたり、それが「と、彼はそう彼は言ったっけ、と私は思った」と変奏されたりする。グレン・グールドについて少しでも知っていれば、これは「ゴルドベルク変奏曲」をモチーフにしているのだろうなと気づくだろう。訳者あとがきでは、その文章の構造をしっかり曲の構造とも照らし合わせながら解説している。自分は「これは……ゴルトベルク変奏曲や!」となんとなく思っただけなので、あとがきを読んでそう遠くない直感が当たっていてホッとした(マグレ)。
自分も豊かな才能を持ちながら、グレン・グールドという天才に出会ってしまい、彼に「破滅者」と呼ばれ、そしてそのように「破滅」していくヴェルトハイマーの人生が痛ましい。「天才」であり「天災」であるようなグールドに出会うことで「自分」を生きることができなくなってしまうということ。嫉妬というのではないけれども、そういう、優れた誰かに出会うことで心がざわめく経験がないわけではないので、自分にも言葉が刺さるような気持ちで読んだ。以下、抜き書きしてしまうと若干凡庸になってしまうが、印象的だったところを引用する。
あらゆる人間は唯一その人だけの存在であって、 また実際にそれ自体として見ると全時代を通しての最大の芸術作品だ、と、そう私はいつも考えていたし、また考えることができた、と私は思った。ヴェルトハイマーはそう考えることができず、つねになんとしてもグレン・グールドに、あるいはまさにグスタフ・マーラーとかモーツァルトとかその仲間たちになりたかったのだ、と私は思った。そのことが彼を非常に早くから、そして繰り返し不幸の中に落とし込んでいた。私たちはべつに天才でなくても、唯一これきりの存在でいられるし、またそのことを認識できもする、と私は思った。
