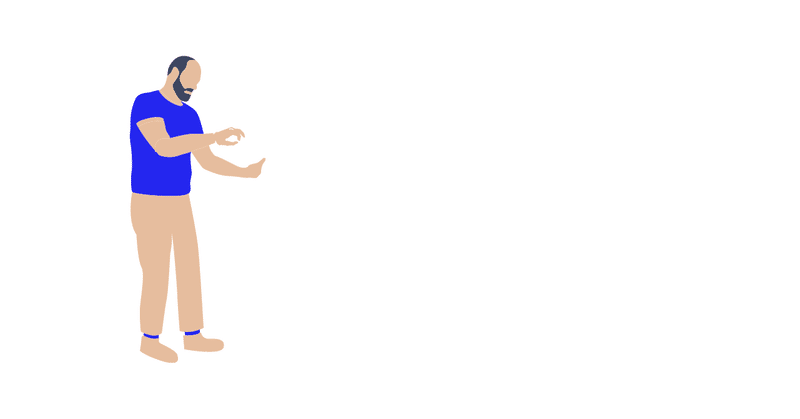
受診回数と服薬量の多い人がかかってしまう「ある病気」

頻回受診と多剤服用の原因
「毎日のように病院に行っています」「通院している病院は10軒を超えていると思います」「片手に乗らないくらいの薬を飲んでいます」
本人の行動に悩むご家族や福祉関係者の声です。
弊所の相談事例をみてみると、病院に行く回数が多い、いろいろな病院に行く、たくさんの薬を飲んでいるという方は、高齢、精神障害を患っている、生活保護を受給されているということが多いです。その理由として「医療費(薬代含む)の自己負担がない(もしくは少ない)」ということが考えられます。
医療費は国民健康保険加入者は二~三割負担ですが、生活保護制度の医療扶助については自己負担がありません。また、ほとんどの地域で高齢者や障害者に対して、医療費の自己負担額の一部または全額を助成する制度があります。こうした事実とその人の病気の症状が相まった結果、受診や服薬が増えてしまうということが考えられます。
コストはないが恩恵もない
弊所としてはこうした事実を背景に、本人の受診回数や服薬量が増えてしまうことは仕方のないことだと感じています。コストなく恩恵が受けられるとなれば、むしろそれは当然の行動と言えるかもしれません。
しかし、「コストもないが恩恵もない、むしろ代償を払わなくてはいけない」としたらどうでしょう。本人を心配するご家族や福祉関係者の「気休め」になるか「解決策」になるかは分かりませんが、本人に「ある病気」の話をしてあげてください。
受診回数と服薬量の多い人がかかってしまう病気
ある病気とは「医原病」。医療ミスや過剰医療によって体調不良や病気が引き起こされることです。
米国のジョンズ・ホプキンス大学が2016年に発表した調査結果では、アメリカ人の死因の第1位は心筋梗塞などの心疾患 、第2位は癌、 第3位は過剰な医療(医原病)でした。第3位の過剰な医療(医原病)とは、不要な検査、薬剤投与、健康診断のことです。 しなくてもいい検査や飲まなくもいい薬を飲むと余計に体調が悪くなります。加えて、投薬ミスや院内感染のリスクも高まります。受診や服薬をしているのに体調が悪いのであれば、それは本人にとって必要のないものなのかもしれません。
日本で行われている取り組み
一方日本では、厚生労働省が生活保護受給者の医療扶助による外来患者について、「頻回受診者に対する適正受診指導要綱」を定めています。
また「全国健康保険協会 協会けんぽ」は、多受診者への適切な受診の指導の取り組みとして、「適正受診指導文書」を発行しています。
「同じ病気で複数の医療機関を受診することは、それまでの治療を中断し、次の病院では新たに検査からやり直すなど、肝心の病気を長引かせることにもなりかねません。また、一般に医師が使う薬は、市販薬よりも強い薬効を示すものが使われており、 別々の医療機関から出された薬を同時に服用すると、薬の飲み合わせや適量以上の服用により、副作用や症状の悪化も心配されます」
〈多受診者への対応について〉適正受診指導文書より
さいごに
受診や服薬の先にあるべきものは「健康」です。しかし、受診や服薬がその健康を害してしまっては元も子もありません。また、そうした行動は自分自身で変えていくしかありません。まわりの人ができることは、事実に基づいた選択肢を丁寧に伝え続けていくことです。今回の記事がその一助になればと願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
