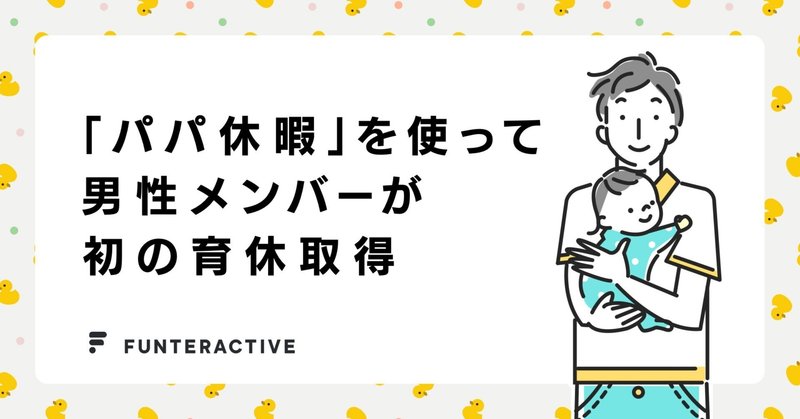
「パパ休暇」を使って男性メンバーが初の育休取得
こんにちは!ファンタラクティブPRの石原です。
社内で初めて、先月から育休を取り始めたメンバーがいるので、これを機に日本の法律で定められている産休・育休制度について調べてみました。
これから産休・育休の取得を考えられている方のご参考になれば幸いです。
また、ファンタで産休・育休って取りやすい?実際の雰囲気どうなの?というところもご紹介します。
(育休中のメンバーが戻ってきたら、育休中の過ごし方や育休前後の働き方などをインタビューしてまたご紹介したいと思います。)
産休・育休制度の基本と最新状況
産休・育休制度を調べるにあたり詳しそうな管理部のメンバーに話を聞いてみたところ、制度に関わる法律が短期間でよく変わるとのことでした。
ちょうど昨年も法改正があり、今年から順次施行されていく制度もあるそうです。
まずは制度の基本的な内容を整理してみました。
産休・育休制度の基本情報
産休=産前休業・産後休業とは
・労働基準法に基づく
・出産予定日の6週間前から、出産の翌日から8週間まで休める
・健康保険より、出産手当金がもらえる
育休=育児休業とは
・育児・介護休業法に基づく
・原則、子どもが1歳になるまで休める(一定の要件を満たす場合、延長可)
・雇用保険より、育児休業給付金がもらえる
男性も育休が取りやすくなる法改正
最近話題に上ることも増えてきた男性の育休取得。今回ファンタで育休を取得することになったメンバーも男性です。
2010年の育児・介護休業法改正により、「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」という両親ともに育休を取るため特例が制定されました。
厚生労働省の調査によると、パパ休暇に対する男性正社員の認知度は平成30年時点で36.1%だったようです。今でも認知度はまだまだ低そうですね。
パパ休暇
父親の育休を2回に分けて取得することができます。
(出生後8週間以内に父親が育休を取得していれば、その後も2回目を取得することが可能。)
パパ・ママ育休プラス
両親共に育休を取得する場合、原則子供が1歳になるまでの休業可能期間が、1歳2か月になるまでに延長できます。
今回の育休を取得したメンバーも「パパ休暇」を使って、休業を2回に分けています。

パパ休暇、パパ・ママ育休プラスについての詳しい資料はこちらをご覧ください。(厚生労働省の資料)
そしてさらに昨年6月に育児・介護休業法がまた改正されました。男女共に育休を取りやすくなり、夫婦で協力して育児を行うことができるようになります。また、男性が育休を取りやすくすること、女性の離職率を下げることなどもねらいとしてあるようです。
改正のポイント(厚生労働省のサイトより抜粋)
1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3. 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
これだけ読むとメリットが掴みにくいですが、簡単に言うと、より柔軟にさまざまなパターンで育休を取得できるようになりましたということです。
例えば次の図のように、出生後8週までの間、父親は基本働きながら母親の退院時や母親が実家から戻ってきた時などに分割して育休を取得できたり、1歳になった後も、今までは父母同じタイミング(1歳になった時と、1歳半になった時)でしか育休開始できなかったのが、開始時期を調整できるようになったので、お互い働きつつ分担して育児ができるようになります。

産休・育休については、厚生労働省をはじめさまざまな資料がインターネット上に公開されていますので、より詳しい情報を求めている方は探してみてください。(といっても資料や記事が膨大すぎて心折れる可能性はあります…)
こちらには、本記事作成に当たり参照した厚生労働省の資料をいくつか貼っておきます。
ファンタは20〜30代が中心のメンバー構成
「日本が用意している産休・育休制度については大体わかった、でも実際会社でその制度を使えるの?」というのが気になるところだと思います。
男性の育休取得率は令和2年度で12.65%(厚生労働省の調査資料はこちら)で、まだまだ低いと言えます。
社内で育休取得者の前例がない、とりづらい雰囲気、仕事が忙しい…などさまざまな理由があることが想像されます。
では、ファンタでは実際に産休・育休を取れるのか?
ファンタの現在のメンバー構成は、総勢17名で20〜30代が中心です。
結婚や出産のタイミングは人それぞれですが、比較的これから結婚・出産・育児を迎える世代が多く、メンバーたちの育児への関心も高いです。
(最近もSlackに「入籍しました!」という報告が流れてきたばかりです。)
ファンタのSlackには、代表を含め親メンバーたちが集うチャンネル「#club_childcare」があり、日々我が子のかわいい姿や育児に役立つナレッジなどが共有されています。

代表をはじめ社内には子育てに理解があり、応援してくれるような温かいカルチャーがあるなと感じます。
相談から育休取得開始までの流れ
今回のメンバーは、次のような流れで育休取得を進めてきました。
メンバーが事前に育休について調査
メンバーが代表に相談
代表、管理部、社労士で相談
担当プロジェクトでメンバー・代表から相談、調整
社内全体へ代表から周知
メンバーの育休取得開始
今回育休を取得したメンバーは、事前に制度の内容や最新情報を調べた上で、育休取得開始希望日の約4ヶ月前頃から代表に相談をしていたようです。(ちなみに昨年の法改正では、休業開始日の2週間前までに申請すれば良いことになりました。改正前は1ヶ月前まででした。)そこから社労士も交えて柔軟な対応方法を検討していきました。
プロジェクトについても、進行に問題ないようクライアントや社内の他メンバーと相談し代表がアサインを調整しました。
今後も会社としては柔軟に対応していく考えです。
育休は労働者の権利であり、会社の義務である
昨年第一子が生まれ、約1年間子育てを経験してきた代表井村に育休についての考えを聞いてみました。
井村:「我が家も昨年1月に娘が生まれて、パパ歴1年と1ヶ月になりました。
うちの場合は産後1ヶ月が妻の体調も本調子では無く子供の夜泣きも多かったので大変な時期でした。
お子さんの個性や家族の状況によって大変な時期は家族ごとに全然違うと思います。育休制度は社員として会社に勤めることで得られるわかりやすい権利の1つです。
家族で望んだ形の育休を取ってもらうことは会社として当然の義務なので、ファンタラクティブのメンバーには家族で話し合って最適な育休プランを立ててほしいなと思います。」
産休・育休を取ることに負い目を感じない世の中にしていきたいですね。そのためにファンタラクティブができることを、メンバーと一緒に考えて実行していきます。
ファンタラクティブでは現在、プロジェクトマネージャー、エンジニア、デザイナーを募集中です。
サービス開発、UI/UXデザインなどの仕事に興味がある方で、長く働きたい、そのためにメンバーにとって快適な働き方やカルチャーを私たちと一緒に作っていきたいと考えている方は、ぜひ一度お話ししてみませんか?
ご興味のある方は、以下のページの「エントリーする」からご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
