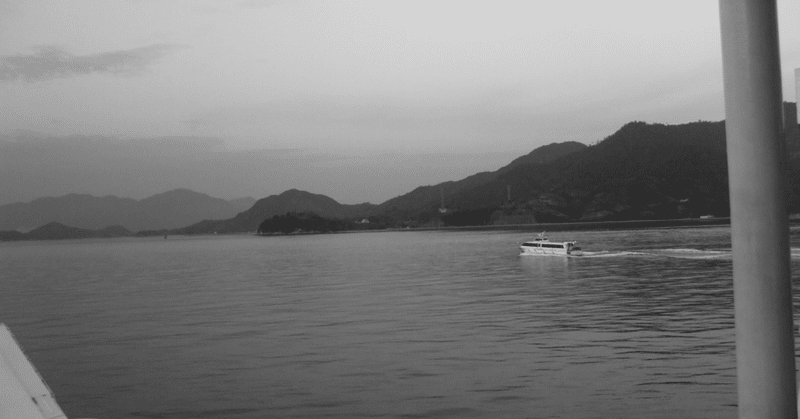
「リキッド・モダニティ 液状化する社会」 ジークムント・バウマン
森田典正 訳 大月書店
リキッド・モダニティ
ジークムント・バウマンの「リキッド・モダニティ」液状化社会を、また例によってチビチビ読んでいる。チビチビすぎてよく脈略を理解できていないのだが、要するに、今の社会は固定化された支配社会ではなく、「不在地主」の少数支配だ、ということ。そこには支配者はないわけではなく見えない。近代化社会の行き着いた先がここだった…とそんな具合かな?
バウマンはポーランド・ポズナニ出身で現在はイギリスの社会学者。ホロコースト研究と、ポストモダン社会論で知られ、この本は後者の集大成みたい。2000年の本。
(2010 03/23)
アイデンティティの椅子取りゲーム
簡単にいえば、「個人化」はアイデンティティを、「あたえられるもの」から「獲得するもの」に変え、人間にその獲得の責任、獲得にともなって生じる(あるいは、付随する)結果の責任を負わせることからなる。
本来の自分でなければいけない必然性は、近代的生活以外のどこにも存在しない。
(p42)
「アイデンティティの獲得」という作業は近代から付け加えられた。さらに、獲得するのは個人の自由であっても、その中身自体はお上からふってきたものだ。
また、階級差(そして性差)はこの時「副産物」として生成された、という。階級差にはプルデューの「社会資本」が影響するのだろう。
そう、そして現代はこのアイデンティティが、流動的になっている時代なのだ。まるで椅子取りゲームのように。
(2010 03/24)
第2章「個人」から、欲望と願望について。今の消費者操作の動向は欲求操作から願望操作になってきている、という。願望とは不安からの脱却願望である。これがその前に議論されていたトークショーの話と繋がるのかな・・・と、ここら辺も少しじっくり読めば面白そうなんだけど・・・
(2010 03/28)
第3章「時間/空間」
以下の言葉はシャロン・ズーキンの言葉の引用らしい。
「だれもどうやって他人に話していいかわからなくなった」
(p140)
「見知らぬ者」への恐怖。共同体がなくなって他人の考えが全く分からなくなる時代。資金を持っている人の究極の選択は、町を壁で囲い同じくらい資金を持っている人のみをその町に入れ、その他は壁の外に追いやって入ろうとするものは警備隊または軍隊に追いやられる。そんな町がアメリカとか南アフリカなどにはあるみたい。そんな町の中では人々は「話す必要がない」ゆえに「話す」。本当は話す必要のある「見知らぬ人々」とは話さない。
さて、情報技術の発展により(とか前提つけるのが蛇足みたいに思えるほど)空間は無力化し、ついで時間も障害ではなくなった。よって、資本は土地・設備および労働者に縛り付けられる必要がなくなり、捕まえにくくなった。こうなると労働・仕事への価値観も変わるだろう・・・ということで、次の第4章は「仕事」の章。
(2010 03/29)
第4章「仕事」
連帯や協力は生産されるものではなく、消費されるものとみなされ、それには消費物にふさわしい取り扱いがなされる。
(p212)
「仕事」の章をなんとか読み終えた。この章辺りでバウマンの姿勢というか価値観というかがみられるようになる。人間の労働契約とかその他もろもろの協力関係が「消費物」としてみられている、それに対応する人間もそのように相手をみる。そういう関係が現状でありそこに「意志の低下、社会活動への無関心」などが出てくる、というのだ。
それはそうだと自分も思う。さて、要するに人々の嗜好が生産から消費へと向かったという理由は、バウマン流「流体化」する資本が身軽になる為に労働者を切り離し、切り離された労働者も今回はそうならなかった労働者も不安を募らせて、(以前には「進歩」すべき理想像があった、と思われていた)未来にはただ不安しか感じず「今あるうちに楽しめ」、ということになった、という。それが正のフィードバックでいよいよ消費社会(生産の場においても)が加速されていく。
(2010 03/30)
第5章「共同体」
これで「リキッド・モダニティ」を読み終えたわけだが、なんだか今までの論調とは少し違わないか?
「共同体が崩れたとき、アイデンティティが発明された」
(p221)
ジョック・ヤングの言葉から、だという。昔は、個人の産まれ持った出自や、それから職業などいろいろな共同体が識別対象だったから。それが流体化した時、「自分はじつのところなんだったんだ?」という問いが生じる。しかし、実は共同体崩壊の際に(流体的資本側が個人を扱いやすいように)「個人」というアトム以外の部分を全て剥ぎ取ってしまった。だから、先のアイデンティティの問いは底なし沼で終わりのない旅に終わる。それに「個人」の側の「こんな識別子にあてがわれたくない」という浮遊したい欲望も加担する。実のところ、昔の方が「個人の差異」を理解し、保護していた世界なのかもしれない。
だいたい、アイデンティティに関わらず、何かを探したいという動きや欲求が出てくる時には、もう既にその「何か」は失われている場合が多い・・・・と思う。
組織に「樹木的」構造がなくなった結果、社会性は「爆発的」なかたちであらわれてこざるをえなくなった。組織は根をのばし、さまざまな長さの命をもつ形態を発芽させたとしてもすぐ枯れてしまう。それは組織の構成員の情熱と熱狂以外に、支えがないからである。基盤の弱さはなにかで補わねばならない。・・・(中略)・・・爆発的共同体は暴力が生まれ、暴力が存在しつづけることを必要とする。
(p249)
『樹木的」とはドゥールーズらの言葉。まあ、近代的思考枠組みとでもいえるものか。
特にコソヴォの問題を取り上げた後半部はバウマンの主眼がどこにあるのか、「流体的」近代とどこにつながるのかわからないことも多かった。「暴力の規制緩和」とそれを受け持つ「爆発的共同体」が、「固定的」近代と「流体的」近代の交点に産まれた、ということは確からしいのだが。
やはり、こうした視点が出てくるのはバウマン自身がユダヤ人だから、とも思えるのだけれど、この間の「アラブ、祈りとしての文学」読んだ身からすると、先の「壁で囲まれ、警備隊に保護された、同質的共同体」というのも、ひょっとすると「爆発的共同体」が産まれた典型的な場所というのも、実はイスラエルなのではないか。という気にもなってくる。バウマンはポーランド出国後、イスラエルに渡ってからイギリスに来た、というが、果たしてバウマンはイスラエルに何を見たのか?
(2010 03/31)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
