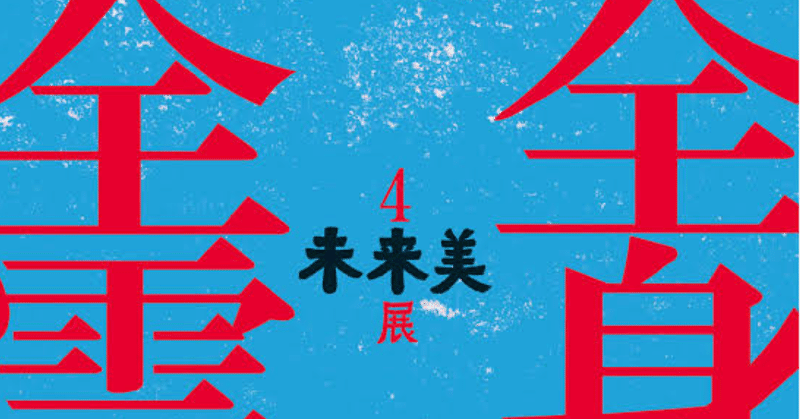
対極という火花──未来美4全身全霊
この激しい矛盾にたえる精神の在り方は、強烈に吸引し、そして反発する両極間の緊張によって発した火花のような熾烈な光景であり、また引き裂かれた傷口のように生々しい、酸鼻を極めたものなのだ。
──岡本太郎
対極主義とは、岡本太郎の作品と生涯を貫く本質的な理念である。それは、内部と外部、抽象と具象といった相対立する二極のいずれかに身を置くのではなく、またそれらの矛盾を安易に折衷させるのでもなく、矛盾や対立を強化しながら、双方のあいだを「終わりなき振幅として生き抜く」*1エートスだった。このようにして熾烈な闘争状態を生きようとした太郎の対極主義的な身ぶりは、たとえば先ごろ登録有形文化財に指定された《太陽の塔》に如実に体現されている。1970年に開催された「大阪万博」は、人類の進歩と調和を唱っていたが、これに大いに反発した太郎は、同万博の総合プロデューサーだった丹下健三が設計した大屋根を突き抜けるかたちで原始的な《太陽の塔》を立ち上げたのである。近代と古代、あるいは万博と反博。それらが妥協することなく緊張状態を保ったまま対峙した状況こそ、対極主義と形容するにふさわしい。太郎がしばしば用いた「べらぼうなもの」「いやったらしい」という独特の言葉にしても、エピグラフにある「火花」や「傷口」を生むための仕掛け、すなわち矛盾をあらわにするための対決姿勢の現われとして理解するべきだろう。
未来美術家の遠藤一郎による美学校の講座「未来美術専門学校」は、岡本太郎がかつて提唱した対極主義の今日的な実践として考えられるのではないか。「さいたま国際芸術祭2020」の中の一企画として催された「未来美4全身全霊」展は、まさしく「大阪万博」における《太陽の塔》とパラレルの関係にあると思われるからだ。「全身全霊」は「花/flower」をテーマとした国際展において明らかな異物であり、だからこそ他に類例を見ないほどの鮮烈な輝きを放っていたのである。


会場の入口付近に展示された川路智博の《ring》は、文字どおりボクシングのリングを描いた水彩画。リング上に立ち並ぶ3人の男たちが煌々としたライトに照らし出されている。スキンヘッドのアンパイアがランドセルを背負った小学生の右手を持ち上げ、勝利を告げる一方、屈強なボクサーは呆然と立ち尽くす。よく見ると、ボクサーの両手には赤いグローブが装着されているが、小学生は素手。つまりここで暗示されているのは、素人の小学生がリングの上でプロのボクサーを打ち負かしたという、現実的にはありえないが、だからこそ痛快な物語である。遠藤一郎がこの作品を会場の導入部に展示したのは、おそらく玄人に勝る素人というイメージが未来美のコンセプトと重なり合っていたからではなかったか。たしかに、著名な職業的アーティストがそろった「さいたま国際芸術祭2020」において「未来美」の素人性は否応なく際立って見える。技術的に稚拙なものも多いし、趣味的に過ぎるものも少なくない。だが、岡本太郎が的確に指摘したように、新しい価値を創り出す芸術家は本質的に批評家でもあるが、批評家の大半はじつのところ鑑定家にすぎず、「素人こそほんとうの批評眼をもっている」*2のだとすれば、「未来美」の素人性を質が低いとして単純に切って捨てることはできない。すべてとは言わないにせよ、素人が玄人を打ち倒す例がないわけではないからだ。
**
玉石混交の中でもとりわけ突出していたのが、木村奈緒の《声を探して》である。木村は、家族構成もライフスタイルも異なる2人の実在する母親の声を、ていねいに聴き出し、小冊子の形式で発表した。写真とテキストで構成されたインタビュー記事をじっくり読むと、母として期待される社会的役割とわたし自身の生き方の矛盾に苛まれるという現在進行形の問題が浮き彫りになっている。この作品がすばらしいのは、生きにくい社会と対決しているインタビュイーのたくましい生き様があらわになっているからだけではない。母として生きる彼女たちが、自分自身の欲望のありかを探し出しながら手にしていく試行錯誤の過程が、遠藤一郎が「未来美」の受講生に仕向けている欲望の発見と実行の過程と見事に重なり合っているからである。

インタビュイーのひとりは、自分自身の欲望を実現させること、平たく言い換えれば「やりたいからやる」ことを「満たし」と呼んでいるという。世間は、母親という社会的役割を担う女性が「やりたいからやる」ことを決して許さない。「母親のくせに遊んでいる」と断罪するのだ。母親である女性たち自身がそのような不条理な圧力を内面化してしまっている場合も少なくない。そのような呪いを解くための言葉が「満たし」である。「あの人は満たしの達人だな」と他人を肯定的に評価したり、家事や育児に追われるあまり「満たしをサボりすぎた」と自分を省みたり。「満たし」は、自己実現の欲望を抑圧する社会への「ささやかな抵抗」であると同時に、母親という社会的役割を担うなかで見失いがちな自分自身の輪郭を再定義するための、きわめてプラクティカルなコンセプトなのだ。
それをあえてコンセプトと呼びたいのは、木村が描き出した女性の生き方が必ずしも個人的なライフヒストリーにとどまるわけではなく、それを超えた拡がりを持ち得ていると考えられるからだ。「満たし」とは、母親として生きる女性たちだけに有効な呪文というわけではあるまい。母親でなくとも、いや、より根本的に考えるならば、女性でなくても、すべての人びとに効力を発揮する呪文ではなかったか。自分自身の欲望にいかにして忠実に生きることができるのか。じつのところ遠藤一郎が「未来美」で受講生たちに問いかけているのはこの一点であると言っても過言ではないのだが、それは、よくよく考えてみれば、男であれ女であれ、あるいは子どもを持つ者であれ持たない者であれ、何らかの社会的役割を担いながら生きるわたしたち自身の誰しもが共有しうる普遍的な問題なのだ。木村奈緒の《声を探して》がすばらしいのは、自らの作品を個人的な趣味の次元に閉じ込めるのではなく、それを社会的な地平に解き放っているからにほかならない。
***
もうひとつ、本展の中で傑出していたのが、ミラクルナビゲーターの《よみがえる伝説の縄文石棒》である。ミラクルナビゲーターとは、遠藤一郎を師と仰ぐアーティストで、スポットが当てられていないがワクワクするようなものやことを体験的に発見し、その様子や過程を自ら発行する季刊誌「ミラナビ」で発表している。本展で焦点を当てたのは石棒。縄文時代の石器のひとつで、男性器を象っているせいか、土偶や縄文土器と比べると、それほど知名度は高くない。事実、あれほど火焔土器について熱弁を振るっていた岡本太郎は、同じ縄文人が作った石棒についてはまったく言及していない。


文字どおり歴史の陰に埋もれていた石棒を掘り起こしたのがミラクルナビゲーターである。だが、どのようにして? じっさいに石棒を制作することによってである。ミラクルナビゲーターは縄文人と同じように石を石で削って石棒を作り上げた。展示された作品を見ると、円錐状の砂山の上に一本の石棒が突き立てられている。先端はわずかに赤く着色されているが、眼に飛び込んでくるのは色彩というより表面のなめらかな触感である。許しを得て触れてみると、思わず手を引っ込めてしまったほど、表面は艷やかなのだ。制作の様子を記録した動画を見ると、素材の石を道具の石でひたすら研磨する地道な作業を繰り返していたことがわかる。これに費やされた果てしない時間の長さに戦慄するとともに、まだ鉄器を持たなかった縄文人の意識と身体に思いを馳せざるを得ない。石棒を再現した彫刻家は寡聞にして知らないが、そもそも人力だけで石を石で削り出す彫刻家すら想像できないことを思えば、ミラクルナビゲーターは現代彫刻の歴史にきわめて重要な原点を刻みつけたと言えるのではないか。まさしく素人が玄人を出し抜いたのだ。
だが、それだけではない。ミラクルナビゲーターが秀逸なのは、石棒の制作に終始するだけではなく、そこから縄文人の精神史にまで到達しているからだ。そもそも人はなぜ石を立てるのか? 専門的には石棒は祭祀の道具として考えられている。だが、ミラクルナビゲーターはそこからさらに踏み込み、それは「意識の波紋の中心」だったのではないかと推測する。石棒には、どこかの誰かがそこに石を立てたという事実が残されるが、それはその石棒を見た別の者の意識にも、どれだけ時を隔てたとしても、波紋のように拡がってゆく。「波は距離や時間をとび越えぶつかり合い、響きあって大地全体を震わせ」、「それによって地球上のすべてのものが活性化する」のだ。つまり石棒とは、「地球上の生きる力を底上げする役割を担っていた」。


興味深いのは、石棒がエロスの象徴だったとしても、その使われ方はわたしたちのイメージと正反対だったのではないかとミラクルナビゲーターが推察している点である。石棒は勃起した男根のように天に向かって垂直に屹立していることが多いが、その実態は逆に先端を地中に深く突き刺していたのでないか。なぜなら大地とはあらゆるものを生み出す再生産の象徴、つまりは「母なる大地」であり、石棒はその母なるものを喜ばせる役割を担っていたにちがいないからだ。かつても今も、わたしたちは大地に働きかけることで、食べ物を収穫し、子どもを産み育て、「生きる力を底上げ」してきたのだった。石棒こそ、生=エロスの中心にあったのだ。
****
もとより、木村奈緒が描写した母として生きる現代の女性たちの輪郭と、ミラクルナビゲーターが想像した縄文人の世界観は一致しない。とりわけ「母」という役割と象徴をめぐっては大きな隔たりがあるのだろう。だが、そのような矛盾や対立を矛盾や対立のままに対決させる姿勢こそが対極主義だった。えてして職業的なキュレーターはそのような矛盾や対立を弁証法的に止揚する次元を設定しがちだが、本展における遠藤一郎の対極主義的なキュレーションはそのような安易な統合を徹底して拒否している。なぜなら遠藤が「未来美」で求める「表現」が受講生たち自身の欲望をそれぞれ忠実に体現する行為を指すならば、個別の欲望をうまい具合に調停することなど、端からありえないからだ。表現とはあくまでも個別的でなければならない。結果的に普遍的な問題や原始的な水準に到達することはあるにしても、原理的には固有性に依拠している。それらをひとつの展覧会というフレームに収めるとすれば、そのキュレーションはとうぜん火花を散らす対極主義的なものにならざるを得ないのだ。
つまり、ここでいう対極主義的な状況とは「未来美」と「さいたま国際芸術祭2020」との関係性の中だけではなく、「未来美」の中にも見出すことができる。逆に言えば、対極主義的な状況が生成してはじめて、「未来美」というプロジェクトは成功したと言えるのだ。事実、ミラクルナビゲーターの石棒に見出される垂直性のイメージは、遠藤一郎の《ほふく前進お百度参り》が醸し出す水平性のイメージとがっぷり四つで向き合っていた。弟子と師匠が抜き差しならない「火花」を散らしていたと言ってもよい。遠藤一郎が扮した「かっぱ師匠」にしても、人間ならざる存在にあえて徹することで、受講生たちの極めて人間的な営みを逆照しながら挑発していたとも考えられる。願わくは、未来美の受講生たちが今後、鮮やかな「火花」や生々しい「傷口」を生み出すことを大いに期待したい。



*1 北澤憲昭「対極の思想」、『反復する岡本太郎 あるいは「絵画のテロル」』水声社、2012年
*2 岡本太郎「日本の伝統」、『岡本太郎の宇宙3 伝統との対決』ちくま学芸文庫、2011年、pp48-49
未来美4 全身全霊
会期:2020年10月17日〜11月15日
会場:「さいたま国際芸術祭2020」アネックスサイト旧大宮図書館
参加:田中偉一郎、ミラクルナビゲーター、川路智博、YUTAKA.H、島崎桃代、濱田工望、中村るつ、チキン・コマ、横江孝治、弓矢結実乃、木村奈緒、KeyLyon、肥田将磨、川上遥か、瀧内彩里、遠藤一郎、沙江、シマカミリッカ、黒坂ひな、久保亜図美、小野美幸、松宮うらら、河童もるひね、皆藤将、永石浩幸、東村恵子、石垣真琴、町田有里、細倉一乃、新チトセ、深浦亜希
#未来美 #遠藤一郎 #岡本太郎 #美術 #アート #レビュー #福住廉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
