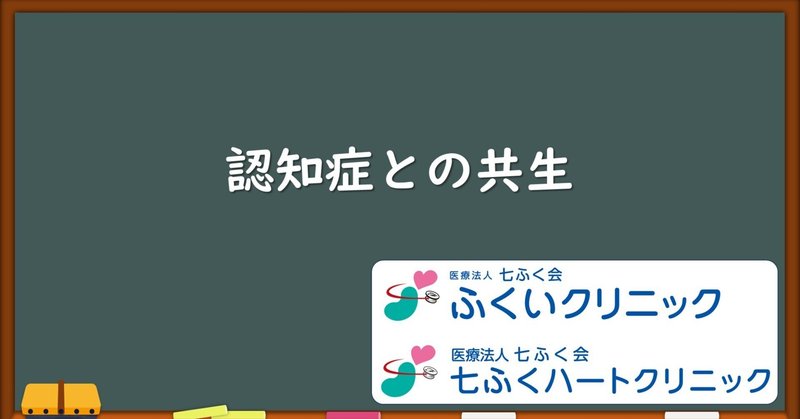
認知症との共生
5月8日に厚生労働省が『2040年には高齢者のうち、およそ3人に1人が認知症か前段階の軽度認知障害になる』と公表しました。
軽度認知障害(MCI)とは、記憶力の低下などの症状があっても、家事や買い物などの日常生活では支障が出ていない状態であり、認知症に移行していく可能性が高い状態ともいえます。もちろん認知症にも種類があるため、進行や症状は人によって異なりますが、日常生活に介助が必要かそうではないかはとても重要なラインです。軽度認知障害の段階でなんらかの介入ができれば、認知症の進行を抑制できる可能性も高くなります。
この軽度認知障害を含めた認知症患者が高齢者の3人に1人というのはやはりかなり多い数字です。
当然、認知症に限らず、病気は予防することが大切です。
認知症を予防するためのアプローチについては別の記事にまとめてありますのでそちらをご覧ください。
政府は認知症との共生を目標に掲げていますが課題は山積しています。
特に認知症の方の多くが利用する介護保険は、財政を圧迫していますし、認知症の方を介護する介護士などの人出不足の問題もあります。
当然家族への負担も大きくなり、介護のための離職という問題も出てきます。働き手不足と言われている中で、働ける人が離職するという事態はなんとももったいない状況です。
認知症に関する共生社会の実現のためには次のような課題があります。
ケアの負担
認知症患者のケアは、家族や介護者にとって大きな負担となります。症状によっては24時間監視が必要であるため、身体的・精神的なストレスが増大します。
社会的孤立
認知症患者やその家族は、周囲の理解不足や偏見により、社会的孤立を感じることがあります。友人や近隣との関係が課題です。
医療・介護体制の不足
認知症専門の医療機関や介護施設の数が限られており、必要なサポートを受けることが難しい場合があります。また、専門知識を持つ医療従事者や介護者の不足も課題となります。
経済的負担
長期にわたる介護は、家計に大きな負担をもたらします。特に施設入所や訪問介護サービスの費用は高額であり、多くの家庭で経済的な困難を伴う可能性があります。
法的・制度的課題
認知症患者の権利保護や財産管理に関する法的制度が整備されていない場合があり、悪徳業者による詐欺や財産搾取のリスクが存在します。
これらの問題点の解決策として、地域サポート体制の拡充や、地域コミュニティの活性化など、自治体によっては力を入れている場所もあり、少しずつ変化がみられています。
また医療、介護サービスでは施設の増設や専門職の育成などの対策がとられています。また最新の機器やモニタリングシステムなどの開発も進んでいます。
地域や施設によっては認知症カフェなどを実施し、患者や患者家族などの孤立や精神的負担を軽減する対策もあります。
そしてそれらに伴う法整備も進んでいます。
2023年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が可決されました。
この法律の詳細については割愛しますが、基本的な施策を紹介します。
・認知症の人への国民の理解の増進
・認知症の人の生活におけるバリアフリー化推進
・認知症の人が社会参加する機会の確保
・認知症の人の意思決定支援と権利利益の保護
・保健医療サービス・福祉サービスの提供体制の整備
・認知症の人や家族の相談体制の整備
・認知症に関わる研究等の推進
・認知症の予防に関わる取り組みの推進
すべて重要なものですが、個人的に重要だと思うものは下の2つです。
認知症に関しては、原因や治療法などがまだ十分に確立されていません。
そのため明確な治療薬がないのが現状です。
認知症に関する研究などは今後さらに必要になると思います。
予防に関してはいくつか言われているものもありますが、その認知度もまだまだ低いのが現状です。
認知症になってからどうするのかという議論も大切ですが、医療に携わるものとしては、認知症にならないためにどうするか、というものをもっと強く推し進めてもらいたいなと思います。
認知症に限らず、病気やケガなどによって仕事や生活が困難になり、介護が必要になる人は高齢化に伴い増えると予測されます。
その中で介護する側、介護される側ともに何ができるのかという点においてさまざまな場所で議論することも必要かと思います。
社会の流れや医学の進歩に注目しながら、当院としてもそのような点で情報発信ができればと思います。
当院では脳神経外科医による診察とMRI、CTなどによる画像検査を中心に、診断、治療を行っております。
認知症そのものではなく、認知症に伴う周辺症状(徘徊や暴言、無気力)などを軽減する治療が特に大切です。
現在介護を行っている方の悩みや生活安定の助けになれるよう、今後も精進してまいります。
