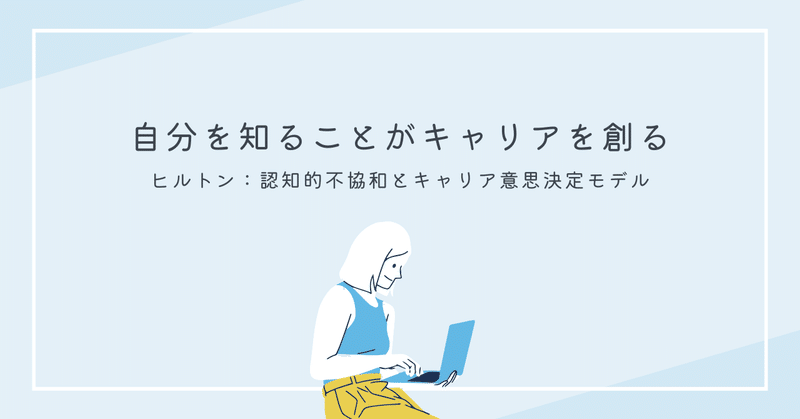
【心理学】「認知的不協和理論」と「職業選択の意思決定モデル」
こんにちは、富士山@マーケティング×キャリアの人です。このnoteは元メーカーのブランドマネージャーでありながら、いまはある広告会社の採用・教育領域の責任者をしている私が【マーケティングとキャリアを掛け算して未来を拓く】ために書いています。
今回は【キャリア・コンサルタント編】キャリア視点で見るヒルトンさんの貢献について書きます。※リスペクトのため、さんづけ呼称にしています。
1.ヒルトンさん
ヒルトンさんは、キャリア意思決定モデルを構築した心理学者です。彼は幼少期から人々の意思決定や心理的なプロセスに興味を持ち、その道を進むことを決意しました。大学で心理学を学び、異なる理論やアプローチを研究しました。
ヒルトンさんは、同じく意思決定プロセスを重視する理論家と協力し、キャリア意思決定に関する独自の理論を発展させました。彼らは、人々が自分自身のキャリアパスを選ぶ際に直面する認知的な葛藤や不協和に焦点を当てました。ヒルトンさんの代表的な理論である「認知的不協和理論」や「職業選択の意思決定モデル」を開発しました。
2.認知的不協和理論
ヒルトンさんの認知的不協和理論は、人々が自己の信念や行動と矛盾する情報に直面した際に生じる心理的な不快感を説明しています。例えば、タバコを吸うという行為は、健康への悪影響が科学的に証明されており、また周囲の人々にも迷惑をかける可能性があります。一方で、タバコを吸うことには個人的な快楽やストレスの軽減といったメリットも存在します。このような状況では、タバコを吸いたいという欲求と、健康や他人への配慮といった価値観が衝突し、認知的不協和が生じます。その際、人は不協和状態を解消する行動(正当化)をします。
→さらに知りたい人はこちら。【認知的不協和】~自分の決定が正しかったと思いたい~

キャリアコンサルティングにおいて生じる認知的不協和は、個人の職業やキャリアに関する意識や信念が矛盾している状態を指します。例えば、現在の職場やキャリアパスに不満を感じながらも、安定性や経済的な面でのメリットを考えると転職やキャリアチェンジに踏み切れない場合があります。また、自己の能力や適性に自信を持ちながらも、社会的な期待や他人の意見によって他の職業やキャリアに進むことに抵抗を感じることもあります。このような状況では、個人の内なる欲求や価値観と、外部の要素や社会の期待との間に葛藤が生じ、認知的不協和が発生します。
ヒルトンさんの推奨するキャリアコンサルティングでは、個人が自身の真の欲求や価値観を見つけ、それに基づいた職業やキャリアを選択するための支援を行うものとしています。
3.職業選択の意思決定モデル
ヒルトンさんは認知不協和理論に続き、職業選択の意思決定モデルを提唱しました。これは、個人がキャリアを選択する際に関与する要素を体系化したものです。例えば、ある人が医療業界でのキャリアを考えているとします。その場合①→⑥の流れで関与する要素を体系化していきます。
①彼は自身の能力や資質を分析します。
②彼は科学的な知識や人間関係の構築能力に長けていることに気付きます。③彼は自身の興味や情熱を考慮します。彼は人々の健康をサポートしたいという強い意欲を持っています。
④彼は自身の価値観も考慮します。彼は人々を助けることや社会貢献を重視しており、医療業界がその価値観に合致していることに気付きます。
⑤経済的な要因も考慮します。彼は医療業界が安定した収入や将来性を持っていることを認識しています。
⑥これらの要素を総合的に考慮し、彼は医療業界でのキャリアを選択することを決定します。彼は医学校に進学し、医師としての道を歩むことになります。

このように、職業選択の意思決定モデルは、個人の能力、興味、価値観、経済的な要因などを組み合わせて最適な職業を選ぶプロセスをサポートします。このモデルは、自己の能力や興味、価値観、環境などを考慮し、より良いキャリア選択をするための手法を提供します。キャリアコンサルタントは、このモデルを活用することで、クライアントの個人的な要素や環境要因を分析し、彼らが満足できるキャリアパスを見つける手助けをします。
4.まとめ
心理学者ヒルトンさんのキャリア意思決定モデルは、キャリアコンサルタントにとって貴重なツールです。認知的不協和理論を通じて、クライアントの心理的な葛藤を理解し、解決策を見つけることができます。また、職業選択の意思決定モデルは、クライアントの個人的な要素と環境要因を考慮し、より適切なキャリア選択をサポートします。これらの理論を活用することで、キャリアコンサルタントはクライアントの成功に向けたパートナーとなることができます。
今回はここまで、ほなまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
