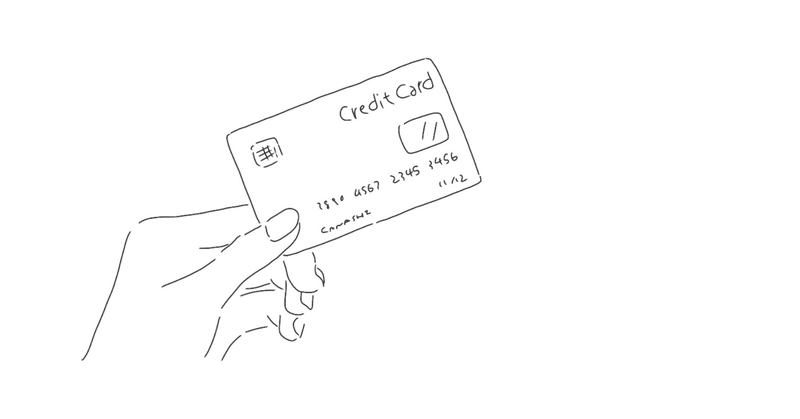
決済手数料を考える
先日、海外の企業が提供する、あるサービスの購入を検討する機会がありました。オンラインでの見積書で、「銀行振り込みではなくクレジットカード決済の場合はこちら」に進むと金額が3%上乗せされて変わり、「〇〇円+手数料3% 合計△△円」と表示が変わりました。代金の一括銀行振り込みではなくクレジットカードで決済の場合、手数料3%を課すというわけです。
5月8日の日経新聞で、「三井住友カード、中小加盟店手数料3割下げ 業界最低に」というタイトルの記事が掲載されました。一部抜粋してみます。
三井住友カードは年内に、クレジットカード決済時の中小企業向けの加盟店手数料率を一律で約3割引き下げる。現状の手数料率は2.70%で、引き下げ後は1.98%とスマートフォン決済事業者を含めた業界最低水準となる。同水準に設定するPayPayに対抗する狙いで、今後カード各社が追随する可能性もある。
カード会社が個別企業を対象とせず、一律で手数料の引き下げに踏み切るのは異例だ。
他のカード会社では中小企業向けの手数料はこれまで3%台が事実上の標準となってきた。スマホ決済大手のPayPayで店舗向けサービスを契約しないときの手数料率と並び、QRコードを使うスマホ決済事業者を含めて最安の水準となる。
三井住友カードが手数料率の引き下げに踏み切る背景には、QRコード決済の普及加速に対する危機感がある。キャッシュレス決済に占めるクレジットカードの割合はなお8割を超えるものの、2023年のクレジットカード決済の前年比の伸び率は13%だった一方、QRコードは38%増だった。手数料率の引き下げを武器に中小の加盟店数を一段と増やし、伸び率でQRコードとの差を縮めたい考えだ。
カードを中心としたキャッシュレス決済普及の壁となってきたのが高い手数料率だ。米国や欧州では中小でも3%より低い手数料が提示される例も珍しくないとされる。海外ではデビットカードが日本より普及している事情もあり、カード決済がより標準的に普及しやすい環境にあった。加盟店の審査が必要な中小向けで特に引き下げの遅れが指摘されていた。
中小の加盟店が負担する手数料率にはビザなどの国際ブランドに支払う手数料も含まれており、それを加味すると三井住友カードが打ち出す新たな料率水準は同社にとって当面、赤字になる水準とみられる。それでも引き下げに踏み切るのは加盟店数を増やす目的に加えて、収集する決済データを基にしたマーケティング事業などの収益を伸ばす狙いがある。
私たちの生活にとって買い物の決済で、日常的で高頻度なのは、小売店や飲食店です。例えばイオンのような超有力企業であっても、スーパー事業の営業利益率は2%台です。
日本全国の飲食店の平均営業利益率について、GPT-4に尋ねたところ、具体的な数値や詳細な分析については公的な資料を参照してくれという前提で、次のような回答でした。一般的には約3%~5%程度ということですが、人件費や原材料の仕入れ費が上がった影響で、さらに利益率が下がっているかもしれません。
2023年の時点で、日本全国の飲食店の平均営業利益率に関する最新の正確な数値を提供することは難しいですが、一般的に飲食業界の営業利益率は比較的低いとされています。飲食店の種類、立地、経営状態などによって大きく異なりますが、一般的には約3%から5%程度とされていることが多いです。しかし、非常に成功しているレストランや特定の業態では10%を超えることもあります。
飲食業界は、原材料費の変動、人件費、家賃などの固定費用が大きく影響し、利益率を維持、向上させることが難しい業界とされています。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響もあり、近年はより一層の経営難に直面している飲食店も少なくありません。
同記事に関連して、3点考えてみます。ひとつは、決済手数料が死活問題になりえるということです。
イオンの場合は自社グループでカードや金融事業も運営しています。(全顧客がイオンのカードを使ってくれないとしても)イオンカードの特典で決済に導くなどである程度の利益を確保することも可能なはずです。しかし、自社にそうした事業を持たない場合は、決済手数料はそのまま持ち出しになります。単純な想定として、2~3%の営業利益がそのまま決済手数料で消えてしまうということにもなりかねません。
スーパー等で時々、クレジットカード等キャッシュレスでも決済可能だがその場合は会員割引が適用されない、というやり方を見ることがあります。クレジットカードで得られる特典(ポイント還元率など)の相場を上回る会員割引の特典を設定し、現金決済に持ち込もうという算段です。3%もするような決済手数料をもっていかれるということは、それだけ小売店や飲食店にとって死活問題だというわけです。
イオンなどのように、自社グループで金融を含めた経済圏をもっている大規模事業者はよいですが、そうでない小売業等にとって決済手数料が死活問題になるということは、当事者である事業者だけではなく、消費者の立場としても取引先の立場としても知っておくとよいと思います。
2つ目は、どんな事業・ビジネスでもそのまま永続はしないということです。
かつては、クレジットカード事業は打ち出の小槌のようなビジネス領域だったかもしれません。世界中で売買の取引が起こればカードに一定の使用量が発生する。その使用料は世界経済の拡張とともに広がる。現金決済には限界があるため市場縮小はないだろう。といった具合です。
しかしながら、QRコード決済など別の手段が開発されてしまい、クレジットカードという手段は、キャッシュレス決済手段の王座から、選択肢のひとつという地位に変わってきています。私の周囲でも、店舗の買い物でクレジットカード決済からQRコード決済に変えた人をよく見かけます。
同記事を参照すると、国際ブランドに支払う手数料の影響で、三井住友カードのような横綱であってもカード事業そのものは赤字だとあります。それでも手数料率を下げなければならないぐらい、他の決済手段に顧客が流れていることが想像できます。要は、クレジットカード事業では利益がとれなくなったというわけです。
どんな事業でも外部環境の変化によって、そのままでは通じなくなる時がやってくるということを、経営・マネジメントとしては改めて考えさせられる事例だと思います。
3つ目は、正当な理由で自社の社会的持続を目指す場合の、価格転嫁に向き合うことの大切さです。
冒頭にあげた例は、「クレジットカード払いするなら、手数料は買い手のほうでもってくれ」という依頼です。私たち日本人の感覚からすると、あまり身近でないことかもしれません。
以前ある国に渡航し買い物をした経験があります。ガイドブックに「そのエリアでは値段はあってないようなもの。もともと値段を高めに設定もしている。2回は「下げろ」と言ってみましょう」と書いてあったので、その通りにやってみたところ、相手は少し考えながら渋々2回下げてきました。
それで「じゃあ買います」と言ってクレジットカードを出したところ、首を絞められかけました(もちろん、半分パフォーマンスの冗談です)。「これだけ値下げさせておいて、さらに手数料まで吹っかけてくるとは何事か」というわけです。向こうの言い分もわかるので、現金で支払いました。
こうした手数料を売り手と買い手のどちらでもつのかに、決まった正解はなく、経営判断と買い手の選択肢(買い手が払うという方針が嫌なら、その売り手から買わない)ということだと思います。そのうえで、冒頭と上記の適当な体験談からも、価格転嫁するという発想が、日本国内はあまり強くないのかもしれないと想像します。
価格転嫁しにくいことが、日本が他国に比べてこれまで物価が上がりにくかった一因とも言われています。しかしながら今後は、事業の持続性のためには、価格転嫁にも一層積極的に向き合うべきではないかと考えます。
<まとめ>
カードの決済手数料は、営業利益確保の上で死活問題になりえる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
