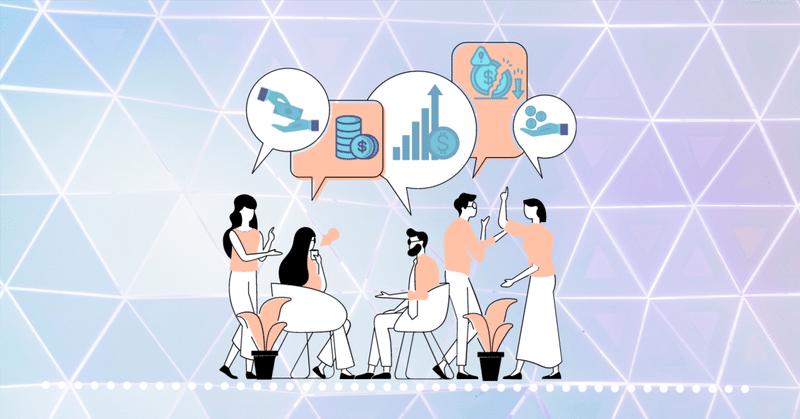
日経平均株価 過去最高値更新を考える(2)
前回は、終値で39,098円となった日経平均株価の過去最高値をテーマにしました。バブル当時よりも実態を反映した数値になっているのではないか、バブル当時とは違って今後の急激な値崩れは想定しにくいのではないか、という2点について考えました。
3つ目は、大企業を中心に、コスト削減などの合理化もさることながら、付加価値を拡大するためのさらなる投資で社会に貢献するべきではないか、ということです。
2月22日の日経新聞の記事「ホンダが5%満額回答 早期妥結、賃上げに弾み 春季労使交渉 実質賃金プラスへ中小への波及必要」を取り上げてみます。(一部抜粋)
ホンダとイオンリテールなどが21日、2024年の春季労使交渉で賃上げの労働組合の要求に満額回答した。物価上昇に直面する従業員の生活の支援や、優秀な人材の確保につなげる狙いだ。製造業と流通業を代表する企業の労使交渉の早期の事実上の決着が、他の大企業だけでなく中小企業に波及するかも注目点だ。
ホンダの初回交渉での満額回答は2年連続だ。基本給を底上げするベースアップと定期昇給の合計で前年を1000円上回る月2万円の組合要求だった。会社は満額回答したうえで、過去に労使で妥結した原資の再配分も実施し賃上げ額は2万1500円(賃上げ率は5.6%)となった。一時金は7.1カ月分の要求に満額回答した。
既にパート時給で7%の賃上げ意向を表明していたイオンは子会社6社が組合要求に満額回答して妥結した。主要子会社のイオンリテールの正社員の賃上げ率は6.39%(実額ベースで1万9751円)、パート従業員の時給も7.02%(同76.66円)の引き上げで妥結した。前年の賃上げ率は正社員が5.03%、パートは7%だった。前年より約1週間前倒しでの早期妥結だ。
早期での会社回答の背景の一つには好業績がある。東証プライム上場の3月期決算企業を一定の条件で集計したところ、全36業種のうち23業種が増益または黒字転換した。企業の賃上げ余力が増している。人手不足への対応も賃上げを後押しする。
24年春季交渉は大手企業でこれから本格化し、その後に中小企業の労使交渉が控える。今年は前年以上に注目されている。賃金が物価上昇に追いついていないためだ。厚生労働省の23年12月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所)によると、1人当たり賃金は物価変動の影響を除いた実質で前年同月比1.9%減と21カ月連続のマイナスだった。
そのため消費は振るわない。23年10~12月期の実質個人消費は前期比で3四半期連続で減った。内閣府は24年春季交渉での賃上げ加速で、名目賃金の伸びを取り戻す必要があると分析する。
大企業の賃上げ機運が高まる中で、成否を占うのは雇用の7割を占める中小企業の賃上げだ。23年春季交渉の賃上げ率は連合の集計によると全体では3.58%だったが、組合員300人未満では3.23%にとどまった。
第一生命経済研究所の永浜利広氏は、毎月勤労統計ベースでの実質賃金が24年度中にプラス圏に浮上するには、主要企業で4%程度、中小企業で3%台後半の賃上げ率が必要とみる。
ただ中小企業の賃上げ負担は重い。日本総合研究所の井上肇氏は、1人当たり人件費が3%、借り入れ平均金利が2%上昇すると、資本金1000万円未満の零細企業の経常利益は6割減るとみる。倒産件数も2割ほど増えるおそれがあるという。零細企業の従業員数は全体の2割を占め、影響は小さくない。
中小企業の賃上げを促し経済の好循環につなげるためにも、取引先の大企業による価格転嫁の促進や、中小企業自体の生産性向上を促す支援が欠かせない。
上記にある「組合員300人未満では賃上げ率3.23%」というのは、連合の調査で集計対象になる企業においてのはずです。中小零細企業では、その対象にはなっていない企業も多数あるはずですので、全国の中小零細企業の賃上げ率はもっと低いことが想定されます。そのことも含め、物価変動の影響を上回る賃上げを実現するには、昨年まで取り組まれてきた賃上げを一層底上げしていくことが求められます。
大企業が賃上げの継続的な実現を目指して、利益をねん出するためのコスト削減に走ると、下請けになっている取引先は賃上げの余力が細っていきます。全企業数の99%、全従業員数の約7割を占めると言われる中小企業による賃上げ、それを通じた消費の循環は、まわりまわって大企業の景気・業績にも波及していきます。
バブル崩壊後の長い経済低迷の一因がここにもあったはずだという観点に立ち、コスト削減もさることながら新たな付加価値の創出による売上拡大のほうが、業績好調の大企業を中心とする企業に求められる方向性ではないかと考えます。
日本の労働生産性が低いという話を時々聞きますが、今に始まったことではないようです。日本生産性本部のデータによると、G7の就業者1人当たりの労働生産性で、日本は2022年にOECD加盟国中31位だそうです。ただ、バブル経済崩壊前の90年でも13位でした。
つまりは、現実離れした物価や株価で表面的な生産性がかさ上げされていたであろう環境下で、世界第2位の経済大国と言われたバブル期であっても、1人当たりの労働生産性はG7他国より既に見劣りしていたということです。
当時は製造業を中心に、米国が産業・企業活動のモデルとして存在していました。日本企業の多くが、当時の米国のビジネスモデルに乗っかり、より良いものをより安く作る活動で成果を上げる図式が通用した、と振り返ることもできます。
1人当たり労働生産性は、生産によって生み出された付加価値を、労働者数と労働時間数の掛け合わせで割ることになります。当時は「24時間戦えますか?」も流行語となっていました。「残業代のほうが本給より多い。だから、自ら望んで来る日も来る日も残業して稼いだ」と当時を振り返っているシニア層の方もいます。
これらを重ね合わせると、「既に存在するモデルに競争で勝つための明確化された戦術に対して、サービス残業を含め時間を無限投入して頑張っていた」と言うことができるかもしれません。バブル期の人材のほうが今の人材より優秀だった、などというような種類の問題ではないように思います。
そうした、目指すべきモデルのような所与の戦術や時間の無限投入への許容が、今では存在しないのは明らかです。この観点からも、その企業ならではの強みを活かした付加価値拡大につながる投資・事業活動で、生産性の高い状態を目指していくことが求められるのだろうと考えます。
もちろん、コスト削減などの合理化も大切です。企業の置かれた環境下によっては、至上命題となることもあります。そのうえで、一定の安定した業績が見込める企業においては、合理化よりも新たな付加価値創出のための投資に注力するほうがより重要、ということが言えるのではないでしょうか。
<まとめ>
さらなる賃上げ実現のためには、付加価値拡大・生産性向上につながる投資活動が大切。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
