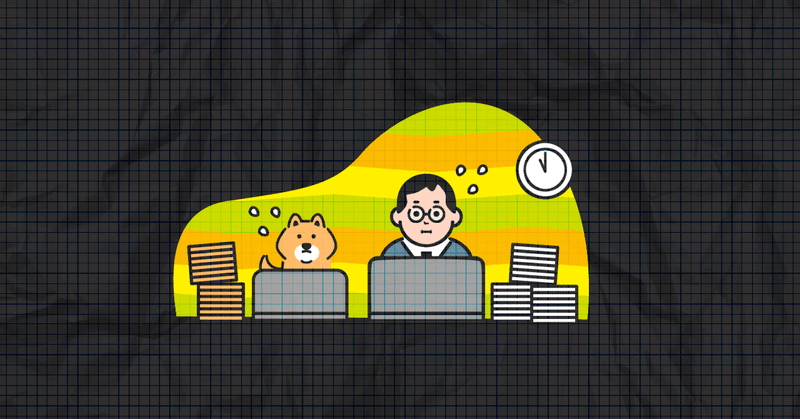
日本の労働時間を考える(2)
前回は、日本にいる留学生の7割が 「日本は労働時間が長く働きづらそう」と感じているという調査結果をテーマにしました。そのうえで、日本での労働時間は、国際比較で既に多いとは言えない状態まで減っていることを考えました。
日本は労働時間が長く働きづらそうというイメージを持たれている、もうひとつの要因は、十分な対価が得られない労働が多いこと(いわゆるサービス残業の存在)ではないかと想定します。
例えばベトナム人からは、自国から海外への就労先として、日本より韓国のほうが人気が高まっているとよく聞きます。韓国が法制面の整備含め、国をあげて国外からの就労者に魅力的な受け入れ制度を作ろうとしていること、賃金水準などの待遇面が日本を上回ってきていることなどが、その主な要因です。
前回取り上げた2019年の1人当たり年間労働時間のデータにおいて、日本1,644時間、韓国1,967時間に対して、メキシコは2,139時間となっています。
国外に留学や就労移動してまで働きたいという人は、ハードワーカーも多いものです。上記データからも、韓国は日本などよりも長労働時間が文化として根付いていることが伺えます(これはこれで、日本以上に少子化が進行しているなど、別の問題にもつながっていそうですが)。労働時間の長さ自体は、選ばれにくさの一因になる可能性があるとしても、主要因ではないのではないかということが、このことからも想定されます。
むしろ、「賃金対象にならない、サービス残業まがいのことをやらされて、割に合わないらしい」という認識をもたれていることのほうが、働きづらさのイメージにつながっているのではないかと想像します。
先日、ある中小企業のメーカーの皆さんに、ヒアリングする機会がありました。皆さんの全体的な傾向として、自分の担当する仕事自体にはやりがいを感じているものの、労働環境においては不満が感じられました。次のような事象です。
・残業をしている人のほうが評価されて、賞与なども多いイメージがある。効率的な仕事をして定時で切り上げることができても、それは評価されない。
・定時で切り上げようとすると、暇だと思われて「忙しい他部署に回って手伝ってくれ」となる。自部署に加えて他部署の仕事もできる人から優先的に手伝いに行くことになる。よって、「自部署の仕事しかできない」と思われる人のほうが、残業しないで済む。
・上司が上記のような考え方のため、自分も早く帰ろうと思わない。頑張れば早く済ませられる仕事をのばすようにしてそれなりに忙しく見せることも、時々する。
・一方で、残業や休日出勤に前向きな人もいる。どんどん仕事をしたいという動機の人もあるが、残業をして稼ぎたいという動機が背景の場合もある。その人たちは、もっと残業したいと思っている。
以前からよく指摘される、日本の就労現場でありがちな悪習です。こうした非効率的・非生産的な悪習は、取り除かなければなりません。
上記の例からも、賃金目的で長時間労働に前向きな人が、国を問わず一定数いることが分かります(もちろん、極端な長時間労働は健康上問題ですが)。しかし、非効率なことをして残業をわざわざ生み出すことや、サービス残業に対して前向きな人はいないでしょう。
日本でも、副業に取り組もうとする人が増えています。動機は人それぞれだと思いますが、中にはキャリアなどとは直接関係なく、副収入を増やすだけの目的で副業に取り組もうとする人も見られます。あえて自分から労働時間を増やしているわけです。そのようなケースの場合は、賃金がもらえる残業が職場で正当にできれば副業の必要はないと言えます。
前回から考えてきた、労働時間を自分の裁量では選びくいこと。十分な対価が得られない労働が多いこと。
法令面も絡むため難しい問題ですが、これら2つのことは、外国人はもとより、日本人労働力を今後より活用していくためにも、考えるべきことだと思います。
<まとめ>
労働時間を自分の裁量では選びくいこと、十分な対価が得られない労働が多いことが、労働時間に絡む働きづらさの要因として大きいのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
