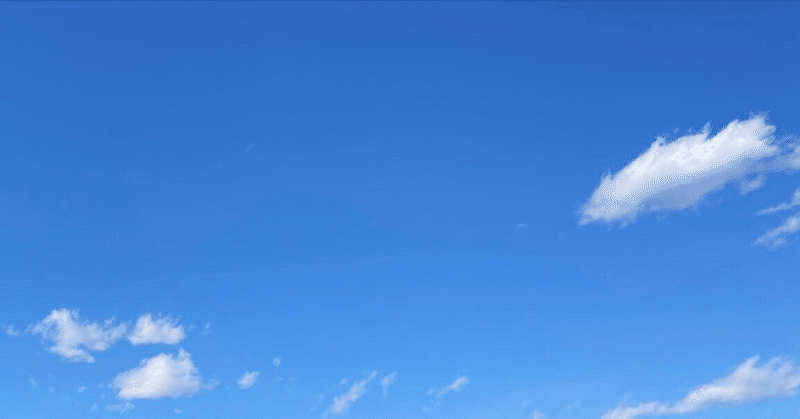
キャリアチャレンジ制度を考える
5月3日の日経新聞で、「コマツ、社員自ら異動登録 柔軟なキャリア形成支援 1.1万人対象、500の組織とマッチング」というタイトルの記事が掲載されました。希望による配置転換を可能にする制度や、多様な採用方法を推進する取り組みなどを取り上げた内容です。
同記事の一部を抜粋してみます。
コマツは全社員の約9割にあたる1万人強を対象に、希望による配置転換を可能にする「キャリアチャレンジ制度」を導入した。多様な経験を積みたい社員と500超の組織とのマッチングに生かす。退職した元社員の再雇用、従業員が知人を紹介する「リファラル採用」も今年から始めた。伝統的な人事制度を変え、柔軟なキャリア形成や離職防止につなげる。
キャリアチャレンジは新制度で、3月までに第1弾の募集を終えた。開発や生産、マーケティングなどの職種から30人超の応募があり、4月から選考や異動が始まった。社員が挑みたい部署や仕事内容をデータベースに登録し、上司の承認は不要だ。各部門が登録情報を基にオファーして、選考や面談に進む。
管理職を含め、入社4年目以降を目安にした中堅以上の正社員1万1000人を対象にする。コマツにはグループや課の単位で、500超の組織があり、約20職種がある。製造業の大企業が全社ベースでキャリアチャレンジ制度を導入するのは珍しい。
ただし、社会人としての基礎能力や所属部門での一定期間のスキル育成も重視する。そのため大卒の場合、入社3年目までの若手社員は対象外で、現在の所属部門での「在籍期間1年半以上」を応募の条件にした。会社主導の異動についても「新たな経験を積む機会」(同社)という。
リクルートが2023年に人事業務の担当者を対象に実施した調査によると、製造業のキャリアチャレンジの導入率は37%だった。全業界平均(35%)を上回るが、金融業(46%)や情報通信業(44%)よりは低い。
コマツは1月から、社外での学びを支援する制度「サバティカル休職」の募集も始めた。3月には採用方式の幅を拡大。アルムナイ(卒業生)を積極的に採用し、元社員が社外で積んだ経験を再び同社で生かすことを狙う。現役社員が知人や友人を紹介するリファラル採用も導入した。
23年3月期のコマツの自己都合離職率は1.36%と産業界の中で低い。それでも「優秀な人材の獲得競争は激しい。今後は特に少子化の日本で、より困難な状況になる」(人事部)との危機感が強まり、制度を大きく変えた。日本の製造業は特定の職種でスキルアップを重ねる傾向が強かったが、社内外での多様なアプローチからキャリアを形成しやすい環境づくりが求められている。
ここでは、同記事に関連してポイントを3つ考えてみます。ひとつは、応募の対象範囲を全社ベースとし、応募の有無を自由にしていることです。
「その行動を自らの意思で決定した」=自己決定したと思えることは、その決定内容に愛着と責任感を高め、決めたことに対して高いパフォーマンスで実行しようとすることにつながります。
例えば上記のキャリアチャレンジ制度に応募するのも自己決定ですし、応募しないと決めることも自己決定になります。引き続き今の部署での担当業務に務めるという同じ結果だとしても、他律的にそうしなければならないという気持ちで臨むのか、自ら決定したという気持ちで臨むのかでは、パフォーマンスに差が出ると想定されます。
なお、自己決定の重要性については、以前にも取り上げたことがあります。ご参照になれば幸いです。
2つ目は、応募について上司承認を不要にしていることです。
上司は、担当する部署を束ねて成果を出す責任があります。よって、部署の成果を上げてくれる優秀なメンバーを重宝します。キャリアチャレンジ制度に手をあげるようなメンバーは、概して優秀な人材であることが多いものです。自ずと、上司の利害と対立します。そうした優秀な人材を手放そうとしないのが、よくある光景です。
よって、上司承認を必要としてしまうと、その時点で立ち消えとなってしまう応募が出てくることが想定されます。承認を不要にすることで、その事象を避けることができます。
さらに上記上司の反応は、短期的な時間軸での視点と言うことができます。同制度を通じた配置再編は、メンバーの人材育成(長期的に企業にリターンをもたらすパフォーマンスの向上)、企業全体でより適材適所の実現という、長期的な時間軸での視点となります。
上司も組織運営者として、長期的な組織成果に協力しながら短期的な成果創出をすることが求められるという認識のもと、応募には協力することが必要だと思います。また、そもそもそうしたメンバーが職場環境に閉塞感をもち離職を申し出た場合は、もっと急な形で部署運営が難しくなることを認識するべきだと言えます。これらの観点からも、上司承認不要は妥当なルールだろうと考えます。
3つ目は、会社主導の異動と並行させていることです。
キャリアの自己決定に慣れていない社員、あるいは自分が望む・進みたいキャリアパスや自分の強みなどが見えていない社員も多いものと想定されます。入社3年経過していない人材を対象外としているのも、自己を客観視し判断する力は不十分だろうという判断によると想定されます。
入社3年経過した人材であっても、本人が自律的にキャリアパスや自分の強みを生かす環境を特定する準備が整っているとは限りません。その場合には、会社主導の異動による新たな経験を積む機会の提案も意義があると言えます。自身では想像しなかった・選びようがなかった機会が偶発的に得やすい環境であるということも、社員という雇用形態で仕事に取り組む意義のひとつです。
同記事では、1万1000人の対象で、30人超の応募とあります。まだ1%に満たないわずかな応募率のようですが、今後成功事例が出てくると応募も増えるものと思われます。今後の動向が期待されるところだと思います。
<まとめ>
キャリアチャレンジ制度は、キャリアの自己決定を促す仕組みとなる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
