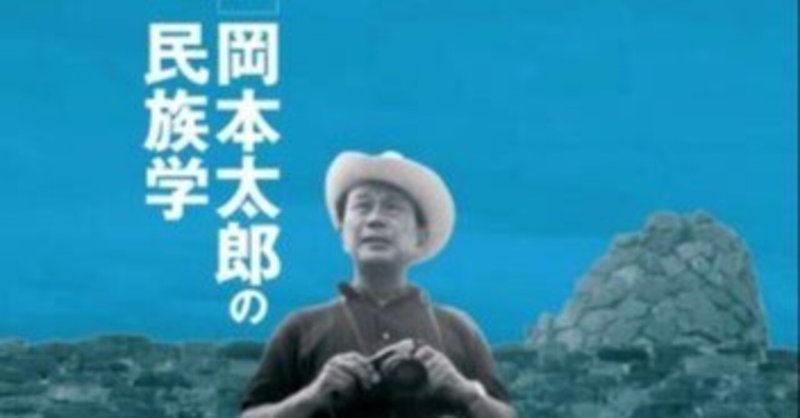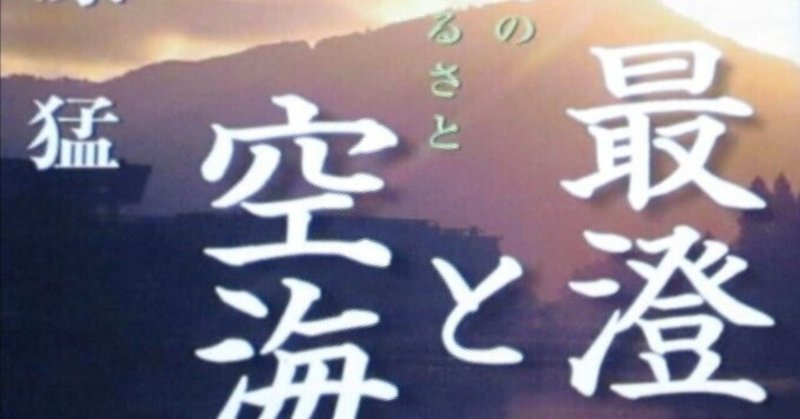記事一覧
問題意識型と地域描写型 能登半島地震で見た記者の2類型
■問題意識型と地域描写型 記者の2類型
能登半島地震がおきて、輪島の友人から尻をたたかれて2月から取材をはじめた。
そのなかで、記者には2種類いると実感した。
問題意識で切る記者か、「地域描写」をめざす記者か。
前者のほうが一般に優秀であることが多い。
珠洲原発計画のあった高屋地区と寺家地区を取材するというのは、ちょっと原発に興味がある記者ならば思いつく(はずなのに朝日と読売は書いて
能登2011-24山が崩れ9人犠牲に 珠洲・仁江を再訪
海藻の取材をした珠洲市仁江町は、能登半島地震で山が崩落し、直下にあった民家で正月をすごしていた9人が亡くなった。
2024年2月、海沿いの国道249号は寸断されているから、山のなかの小道をたどって日本海側にでた。「道の駅すず塩田村」にも、国の重要無形民俗文化財に指定された角花家の塩田にも人影がない。地震による隆起で海岸線は100メートルちかく後退している。これでは塩田に海水をくみあげるのは大変
季刊民族学165 岡本太郎の民族学
「芸術は爆発だ」というヘンなおじさん、というのがぼくらの子どものころの岡本太郎のイメージだった。
戦前にマルセル・モースに師事して民族学をまなび、帰納的で具体的な姻族学と、演繹的で抽象な芸術の双方で創的な世界をつくりあげた天才だったということがよくわかる。
太郎は戦前のパリで抽象芸術の運動にかかわる。
人間の思考、とくに芸術は、自分の主観からこうだ、と自己中心的に演繹的に決めていく。一方、ミ