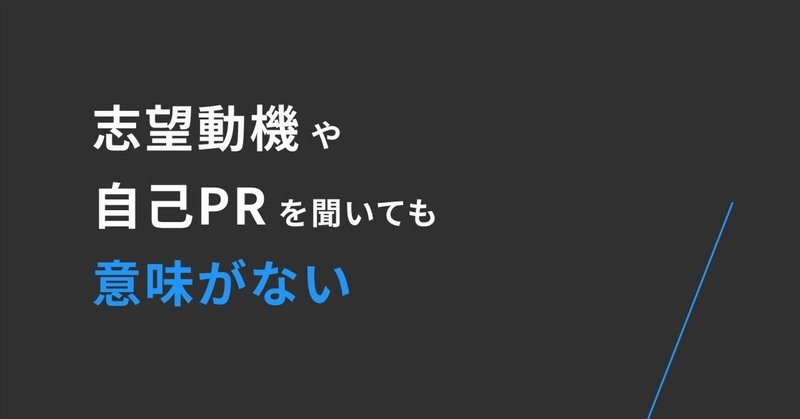
「志望動機」や「自己PR」を聞いても意味がない
フルスタックマーケティング株式会社の代表取締役CEO・清水優志(@fsm_shimizu)です。
企業のマーケティング活動を支援しています。
僕はフリーランス時代から、支援先の会社でマーケターやアナリストを採用するにときに面接に呼ばれることがよくありました。
その会社のマーケティング活動を深く理解しているので、主に技術面や能力面の見極めを期待されるのです。
その際に「志望動機」や「自己PR」を聞くことはありません。
それよりも「事実」の深掘りに時間を使います。
今日は、そんな事実の深掘りについて書きたいと思います。
なぜ「事実」を深掘りすべきなのか
そもそも、なぜ「事実」を深掘りするのが大事なのでしょうか。
この話の前提として、まず「人はすぐに嘘をつく」ということを理解する必要があります。
記憶に関する最新の研究で、特定のニューロンの「発火」により記憶が形成されることが明らかになりました。脳の中では記憶が形成されるたびにニューロンの結合が変化します。ところが記憶を思い出す際にもニューロンが発火しています。そして記憶を思い出すたびに、新しい情報と新しい記憶によって記憶が変化してしまう可能性があるのです。
記憶というのは事実に基づくものだと思いがちですが、実はそうではありません。人間の記憶は再構築され、事実と主観が入り混じります。
「嘘をつく」というと悪いことのように思えますが、要するに「記憶は必ずしも正確ではない」ということです。
マーケティングにおけるユーザーインタビューでも、ユーザーの「行動」(=事実)にフォーカスせよ、という鉄則があります。
たとえば「あなたは週に何回くらいサイトを利用しますか?」という質問には意味がありません。「あなたが前回サイトを訪問した理由を教えてください。」というのも、惜しいですが間違っています。
聞くべきは「あなたが前回サイトにアクセスしたのは◯月◯日です。このときの1日のスケジュールを教えてください。」といった質問です。

その日のスケジュールを遡って思い出していくと、なぜサイトに訪問したのか、という理由が客観的に浮き彫りになってきます。
ユーザーの主観を頼りに話を聞いてしまうと見逃してしまいがちな、重要なインサイトが手に入るのです。
こういった質問を重ねることは時間がかかりますが、その分、ユーザーの主観の余地が少ない、より精度の高いインタビューにつながります。
面接でも同じことがあてはまります。
その人自身やその人の行動の原理を深く理解しようと思ったら、事実を深掘りしなければならないのです。
事実にフォーカスするための質問
たとえば、以下のような質問には意味がありません。
あなたはなぜこの会社を志望しましたか?
あなたはこの会社でどんな仕事がしたいですか?
あなたの一番のモチベーションはなんですか?
あなたの特に優れたスキルはなんですか?
会社選びで大事にすることはなんですか?
このような質問は、いずれも事実ではなく候補者の主観を聞くものです。
候補者は真面目に、正直に、本当のことを話しているつもりでも、実際には記憶が再構築されている可能性があります。
嘘をついている(記憶が書き換わっている)ことを念頭に置いて話を聞く、というアプローチもなくはないのですが、それはそれで聞き手の判断(主観)に委ねられてしまうので良策ではありません。
本当に聞くべきは、以下のような質問です。
あなたは上司からどのように褒められ、注意されますか?
あなたがこれまでにしてしまった最悪の失敗と、それにどう対応したかを教えてください。
今までで一番テンションが上がったプロジェクトの話をしてください。
最近、仕事に関連する情報収集をしていて、最も面白いと思ったトピックについて話してください。

このような事実を深掘りしていくことで、候補者の本当の姿が明らかになっていきます。
行動原理を立体的に理解するための3段階モデル
ただし、事実を聞いただけではまだ不十分です。
環境が変われば働き方も変わりますから、新しい職場・新しいメンバー・新しい仕事でも同じことが起きる保証はありません。
つまり、事実を抽象化したうえで整理し、それが自社の環境でも再現可能なのかを検証する必要があります。
僕はこれを「行動原理を立体的に理解する」と表現しています。
そして「行動原理を立体的に理解する」うえで有効なのが「成果-行動-コンピテンシーの3段階モデル」です。

事実とは「行動」のことです。
そして、行動を通じて生み出した変化のことを「成果」と定義します。
そして、再現可能性を担保するのは、3段階のモデルを支える「コンピテンシー」です。
3段階モデルを支える「コンピテンシー」
コンピテンシーは1970年代に、ハーバード大学・心理学教授のマクレランド氏が行った調査によって生み出された概念で、「ハイパフォーマーの行動特性」を意味します。
マクレランド教授は米国国務省から依頼を受け、外交官の「採用試験の成績」と「配属後の在任中の業績」における相関関係を調査しました。調査の結果、採用試験の成績と業績の高さはそれほど相関がないと判明。また、高い成果を出す従業員にはいくつかの共通する行動特性があることが分かりました。
コンピテンシーには様々な要素が含まれますが、僕の理解では以下のように整理できます。

まず、ベースに「価値観」があります。
これは「性格」や「人間性」と表現されることもありますが、要するに「何が好きで、何が嫌いか」ということです。
これは職場によって変化することがほとんどありません。
生まれつきのもの、あるいは長年の経験の中で醸成されてきたもので、価値観が異なる人材は離職率も高くなります。
次いで「姿勢」は、仕事に取り組むうえでの態度のことです。
これは職場環境や同僚によって大きく変化します。人材配置が重要なのは、この姿勢に大きな影響を与えるからです。
その上に「知識・経験・技術」が乗ります。
これらは「知っている」「わかる」「できる」とも言いかえられます。知識があり、経験があり、技術があるから「できる」のであって、不足しているものがあればそれを補う必要があります。
これらの要素に加えて、実際に行動を起こすときに重要になるのが「動機」(モチベーション)です。

「価値観」「姿勢」「知識」「経験」「技術」が車でいうところの車体だとしたら、「動機」はガソリンです。
どんなにいい車でもガソリンがなければ走らないのと同じように、能力があってもやる気が出ない人がいます。
その理由を特定し、やる気を盛り上げるのもマネージャーの役割です。
コンピテンシーを理解するための具体的な質問例
参考までに、各コンピテンシーを理解するための質問例を記載しておきます。
価値観
あなたの最高の友人について教えてください。
今までで一番テンションあがったプロジェクトの話をしてください。
これまでのキャリアで一番楽しかった会社はどこでしたか?
「他の条件がどんなに良くても、こんな会社では働きたくない」という会社の条件はなんですか?
どんなことへの好奇心が強いですか?
姿勢
現職の上司で、最近受けたフィードバックは何ですか?そのフィードバックに対してどう思いましたか?
上司からよく受けるフィードバック(良いもの・悪いもの)はありますか?それに対してどう思いましたか?
あなたがこれまでにしてしまった最悪の失敗と、それにどう対応したかを教えてください。
知識
あなたのおすすめの本はなんですか?(あなたが最近おすすめされて読んだ本はなんですか?)
あなたの周りの、あなたより優秀な人について、なぜそう思うのかを3人教えてください。
一流の○○(職種)と、普通の人では、一番何が違うと思いますか?
最近、仕事に関連する情報収集において、特にアンテナを張っているキーワードやトピックを教えて下さい。またその理由はなんですか。
5年後の〇〇(業界やトレンド)は、現在からどのように進化していると思いますか。
経験
これまでのご自身の成功や失敗から得られた、再現性のある仕事のノウハウを教えてください。
これまでの仕事で、一度積み上げたご自身の成功体験がまったく通用しなくなったご経験はありますか?また、その状況をどのように打開することができましたか。
あなたがジョインしてから1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後の活躍イメージをそれぞれ教えてください。
弊社チームの一員になったとして、今から1年後、あなたにとってのここでの成功とはなんですか?
あなたがもし弊社に入社したとしたら、どんな課題をどのように解決すると思いますか。
「技術」に関する質問は、職種や仕事内容によって大きく異なるので省略します。
また、「動機」はこれらの質問を通じて総合的に理解されるものです。
動機の理解を深めたい方は、ぜひ以下のnoteも読んでみてください。
コンピテンシーを理解すれば、再現性の高い行動が約束される
このように、コンピテンシーを上手く理解できれば、高い再現性で「行動」を促すことができます。

マネジメントとは、メンバー各人のコンピテンシーを理解したうえで、行動を促し、成果につなげる仕事です。
したがって、採用段階でマネージャーが関与するのは、候補者が自分のチームに適したコンピテンシーを保有しているかどうかを見極めるためでもあります。
この話は採用だけでなく、自己理解・セルフマネジメントにもあてはまります。
特にフリーランスや経営者のように、セルフマネジメントが必要な働き方をしている人にとっては、「成果-行動-コンピテンシーの3段階モデル」にあてはめながら自身の行動特性を理解することは非常に重要です。
===============
もし筆者に興味を持ってくださった方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に以下のリンクより「ちょっと話してみたい」してください!
案件の相談でも、キャリアの相談でも、コンテンツの書き方でも、なんでも大歓迎です!!
Twitterアカウントはこちら
https://twitter.com/fsm_shimizu
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
