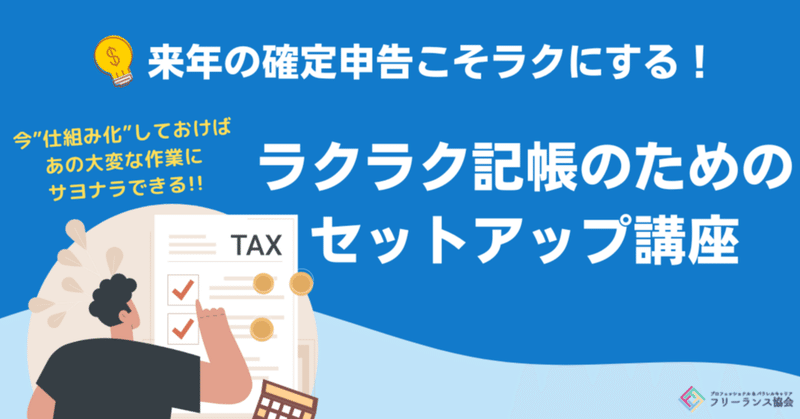
確定申告をラクにする秘策は「仕組み化」にあり! 次こそラクに申告を終わらせたい人が知っておくべきポイントを解説
個人事業主やフリーランスにとって避けて通れないのが、3月の確定申告。「書類の作成に毎年苦労している」「初めての確定申告で不安がある」という人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、確定申告の負担をグッと減らすためのテクニックをまとめてご紹介します!『フリパラ』でもおなじみの税理士・宮崎雅大さんに、ラクに記帳するための方法を伺いました。
※この記事は、フリーランス協会主催「来年の確定申告こそラクにする!ラクラク記帳のためのセットアップ講座」(2024年4月26日開催)をもとに作成しました。
トピック1 確定申告に役立つだけじゃない!定期的に記帳するメリット
日々の取引状況を把握し、記録することを「帳簿を付ける(記帳)」といいます。「定期的に帳簿を付けることで、2月や3月に駆けこみで申告書をつくるのに比べて確定申告がラクになる」と話す宮崎さん。さらに、定期的な記帳には多くのメリットがあるといいます。
■記帳は事業の定期検診と同じ
定期的な記帳は、健康診断をするのと一緒。「経営状況を把握するうえで、定期的に数字を管理するのは大切な仕事の1つです」と話す宮崎さん。
「たとえ現時点での事業規模がそれほど大きくない、または今後拡大する予定がないとしても、定期的に帳簿付けするメリットはあります。
事業は思いがけず大きくなる可能性を秘めています。言い換えると、税金を想定より多く収める可能性は誰にでもあるんです。事業規模が小さいうちから帳簿付けの習慣を付けて、売上高や支出を確認できる環境をつくっておくことが大切です」
■融資のアピールに使える
事業によっては、金融機関からの融資を受けたいと考える事業者もいるでしょう。金融機関は融資の際、申し込んだ人の自己資金や返済能力をチェックします。定期的に記帳しておくと、融資を受ける際のアピール材料になります。
「 確定申告でいいように思うかもしれませんが、融資のタイミングによっては、帳簿の効果が大きくなります。たとえば確定申告直後の2024年3月頃であれば、金融機関は確定申告の内容から事業の状況を推測できます。しかし2024年10月頃の場合は、確定申告から半年以上が経過していますから、事業の活動状況が変わっている可能性が出てきます。そのため、金融機関から『直近の帳簿を見せてください』と打診されるケースもあります。
帳簿は、金融機関が事業者の活動状況を定量的に測る材料のひとつです。『お金を貸そうかな?』と考えている立場の方からしたら、しっかり管理している人に融資したいと考えるのではないでしょうか。通帳の残高と帳簿をきちんと連動させておくことで、お金の管理ができる事業者であると、金融機関にアピールできます」
■経営判断の材料になる
適切な帳簿付けを継続することは、経営的な判断を下す材料になります。その一つは、納税額の予測です。
「1年間の売上高や支出を翌年の1月にまとめて集計すると、納税額が想定とずれるケースがあるんです。想定とずれると、資金繰りへの影響が生じる原因になります。
ですから定期的に帳簿を付けて、9月頃にある程度の帳簿付けが終わっている状態が理想的です。帳簿をもとに今年分の税金額をチェックするといいでしょう」
さらに「帳簿付けによって、売上高と支出の集計だけでは把握できない指標を管理できる」と宮崎さんは話します。
「たとえば売掛金や買掛金は、権利の発生時点で帳簿付けするルールになっています(会計用語で実現主義・発生主義といわれるルール)。売掛金の代金を回収できるのが3カ月後で、原材料費や人件費の支払いが1カ月後だとすると、代金を回収する前に支払い期限がきてしまい、一時的に資金繰りが悪化しますよね。このように定期的に帳簿を付けておくと、売上高や支出の管理だけではわからない預金残高まで集計できるんです。ここまで集計ができていると、融資を受けるかどうかなどの経営判断をする材料として役に立ちます。
また、帳簿を付けておくと、事業のためにあとどれくらい経費が使えるのかがわかります。売上高が想定よりも好調な場合は、ふるさと納税を申し込んだり、設備投資を検討したりもできる。これは、税金額の予測ができているからこそ取り組めることです。私は、定期的な帳簿付けが戦略的な投資につながるのではないかと考えています」
トピック2 できるところから帳簿付けの仕組み化を始めよう!
■仕組み化って何をすること?
宮崎さんは、帳簿付けをラクにするポイントとして「仕組み化」を挙げました。仕組み化は、大がかりで大変な作業ではなく、小さな改良の積み重ねだといいます。
「たとえば、『帳簿に入力する内容』と『入力しない内容』 を整理する作業は、仕組み化の要素に含まれます。毎月何日に入力する準備をするかを決めるのも仕組み化の1つです。仕組み化は、さまざまな作業が組み合わさって進んでいきます。
そして仕組み化に必要な作業は、事業者や業種によって異なり、『絶対こうしましょう』というルールはありません。現金商売が多い人、クレジットカードでの買い物が多い人、通帳からの入出金で取引がほとんど完結する人、さまざまなパターンがあるためです。自分に合うツールや準備を見つけることが大切です」
仕組み化するメリット
仕組み化による大きなメリットは「『何を入力すればいいのかな』から解放され、定期的な帳簿付けが楽になること」と、宮崎さんは話します。
「ひとりで申告書を作成していると、自分の作った申告書が間違っていないか心配になりますよね。
何を入力すべきかを整理して仕組み化を進めると、悩む回数が減って作業時間も短くなります。その結果、定期的に帳簿付けする心理的なハードルが下がるんです。継続して帳簿を付けるためには、作業負荷の軽減が欠かせません。来年の3月15日を余裕をもって迎えるために、一歩ずつ仕組み化を進めましょう」
■なるべく考えずにできる仕組み化をしよう
帳簿付けを仕組み化するためにおすすめの方法は次の3つです。
①事業用口座を作ること
②口座連携をできる会計システムの導入
③事業用クレジットカードの使用
「①については、ぜひ事業用口座を作って活用してほしいです。なぜなら、会計システムと連携できるからです。ただし、通帳の入出金がほとんどない場合は、プライベートと分けて現金で管理すればいいですし、事業用口座を作るメリットは少ないと思います。
②の会計システムの導入については、事業用口座と連携させることで、手間なく帳簿付けする仕組みづくりができます。一方で、事業用口座などの連携できる環境がない人は、手入力しやすい仕組みを整えることが大切です。どちらであっても、会計システムにはスマホに特化しているものやパソコンに特化したものなど、それぞれ得意分野があるので、自分の環境に合ったものを選ぶと良いでしょう」
そして、③の事業用クレジットカードについても、①の事業用口座と同じく「作っておくと会計システムに連動できて便利」と宮崎さんは語ります。
「現金払いをできるだけ少なくするために、事業用クレジットカードの作成をおすすめしています。なぜなら、現金支払いにはきちんと支払ったのかを客観的に説明できる資料がありませんが、クレジットカードで支払うと明細などが手元に残るからです。そのため、事業がフリーマーケットでの販売のように現金取引がメインであっても、自分が支払う分はクレジットカードやネットバンキングのように履歴が残るものを利用することをおすすめします。少なくとも支払った分の集計はしやすくなりますよ。
ただし、インボイス関連でマイナスする消費税額を集計する必要がある人は、クレジットカードの明細だけでは解決できないのでご注意ください」

トピック3 税理士もやっている!帳簿付けをラクにする仕組み化の実例
取引を開始すると、クレジットカードの明細や領収書などの書類が増えていきます。なかには電子データと紙が混在しているケースも。書類の管理方法をルール化しておくことで、ミスの軽減につながります。書類管理の方法について、宮崎さんが実際に取り入れている方法を例に紹介します。
「まず用意するのは100円ショップで売っているB4のファイル(下記画像内1)です。ファスナーのついている大きいタイプで、蛇腹状になっているので膨らみます。このファイルに1年分の資料を3つに分けて管理しています。

まずは、大きく『未』と書いた紙を入れたクリアファイル(画像内2)。ここには帳簿付けが済んでいない領収書やレシートを入れています。
次は『済』と書いた紙を入れたチャック付きのポリ袋(画像内3)です。入力が完了した書類はこちらで管理します。ポリ袋のなかで月ごとにまとめてクリップで留めておくと、あとで書類をチェックする際にすぐ見つけられて便利です。
最後に上記以外の書類を別のクリアファイル(画像内4)を使って管理します。生命保険料の控除証明書やふるさと納税の証明書、医療費の領収書などですね。
確定申告が終わった段階で中身を『済』の袋に移動すれば、使わなくなった書類をまとめておけます。そして、B4ファイルはずっと取っておく。個人事業主の人は、B4サイズのファイルひとつで1年分の書類を余裕をもって管理できるでしょう。100円ショップで手に入るアイテムばかりなので、毎年1セットずつ買うのがいいのではないでしょうか。わたしはこの方法で管理しているので、ぜひ参考にしてみてください」
■今できることから、少しずつ準備を
宮崎さんは、最後に「今からできる準備をすぐに始めること」と話します。
「ネットバンキングの口座やクレジットカードは、申し込んだその日からは使えません。手続きが完了するまでは、状況により何カ月もの時間がかかることもあります。便利そうと思った人は、すぐに申し込みを進めておいたほうがいいでしょう。
仕組み化は大がかりなシステム変更ではなく、小さな作業の積み重ねによって成り立っています。人は忘れる生き物です。いま何もしないままだと、あっという間に次の確定申告の時期を迎えるでしょう。できるところから少しずつ、仕組み化を進めてみてください」
教えて宮崎さん!参加者から寄せられた質問に回答
セミナーの終盤には、参加者から寄せられた質問に可能な限り回答していただきました。このレポートでは特に多くの視聴者から「聞きたい!」との声があった質問とその回答を、Q&A形式でご紹介します。
Q インボイス制度への登録にあたり、しておいたほうがいい経理作業はありますか?
A 2割特例に該当する方は、1月から12月までに発生した売上高を適切に集計することが大切です。もし、2割特例に該当せず、預かった消費税も集計しなければならない方は、売上高に加えて、レシートや領収書にインボイス番号が書いてあるか…を、ご確認ください。
Q 電子帳簿保存法の改正により「請求書や領収書を紙で保管するのはNGになった」との理解は正しいでしょうか?
A それは誤解です。紙で受け取った書類を電子化するかは任意に決められます。紙で受け取った書類は紙のまま保存しても構いません。ただし、データで受け取った請求書等は、一定のルールで保存が義務付けられています。
Q 過去の帳簿書類はずっと保存しておくほうがいいのか、それともどこかのタイミングで処分していいのか、教えてください。
A これは税理士によって見解が変わります。原則として言われているのは「7年保管」です。「5年過ぎたら一部の書類だけ残しておけばOK」と言われているので、それ以外は処分する人もいます。でも、わたしの場合は「税金以外のルールで証明しなければならない可能性があるため、10年間は保存しておいたほうがいいですよ」とお伝えしています。
Q 個人事業主2年目です。税金の支払いのためにお金を分けておく仕組みづくりのコツがあれば教えてほしいです。
A 例としては、口座振替を活用する方法があります。事業用の口座から毎月一定額を口座振替で別口座に移しておき、税金はそちらの口座から支払う方法です。もし税金用の資金管理が大変な方は、口座振替や別口座を活用する方法を検討してみてください。
教えてくれた人
宮﨑雅大(みやざき・まさひろ)
2016年10月に宮﨑雅大税理士事務所を開業。スタートアップや起業まもない顧客が多く、個人事業主からの相談も多い。クラウド会計導入など、業務効率改善に関する提案にも定評がある。確定申告・決算へ向けてゆるく帳簿を付けるもくもく会「ゆるちょぼ」を不定期で開催。
HP
書いた人
神代裕子
ライター・エディター。福岡県在住。出版社や制作会社で14年半、編集・ディレクターとして勤務。企業の広報誌やオウンドメディアの編集長などを務める。2019年に「LANKAWORKS」として独立。現在は、ビジネス系 Webメディアや企業のWebサイト・広報誌、書籍などで執筆するほか、講師としても活動中。趣味は日本酒、旅行、美容など。
@sakurakuma165
note

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
