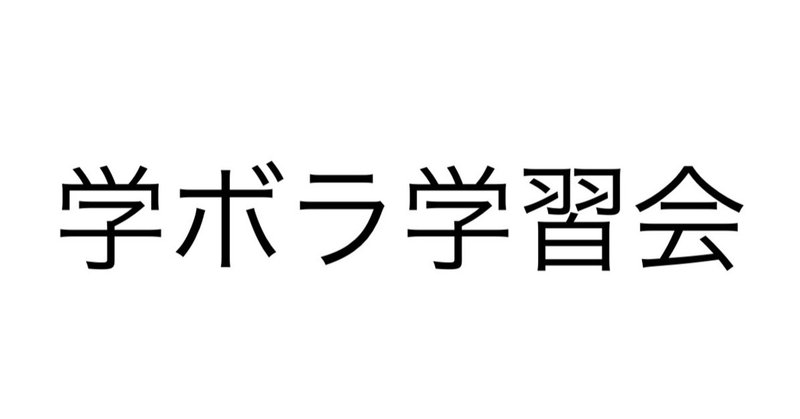
学ボラ学習会
Kacotamには学ボラという訪問型学習支援の事業があります。
参加しているメンバーのnote記事はこちら。
学ボラでは二か月に一度くらいの頻度でメンバーたちで集まり学習会をしています。
今年度はずれ込んで、ようやく年度初めての学習会開催となりました。
今回の学習会のテーマは
・社会的養護について詳しく知ろう
・学ボラってどんな存在?
・子どもとの関わり方
についてでした。
学ボラを始める前に代表との面談があり、そこでもひと通りはやる内容ではあります。特に「社会的養護」については、ずっと参加しているメンバーは何度も聞いた話かな?とも思いました。
ただ、学習会を準備するにあたっていろいろと調べていると、たくさんの「知ってほしい」に出会いました。
全国児童養護施設協議会のパンフレットのタイトルには「もっと、もっと知ってほしい」とあります。
児童養護施設出身者のYoutuber「THREE FLAGS」の動画タイトルの多くには【知ってほしい】とついていました。
どうしてこんなに「知ってほしい」のだろう?
それは、この社会の中でまだまだ社会的養護が必要な人たちが「マイノリティ」で、「自分ごと」として捉えてくれる人が少ないと感じているから、「自分ごと」になっている人を増やしたいからなんだ、と思います。
ある本にありましたが、社会的養護を必要としている人の割合って、人口の1%にも満たないそうです。
つまりとてもマイノリティなのです。
駅の改札が右利きの人に利用しやすいかたちに作られているように、社会の仕組みはまだまだそこに寄り添っていないのです。
思い出したのは自分が初めて学ボラに参加した日のことです。
代表に「どうでしたか」と尋ねられた私は、こう答えました。
「思っていたより、『ふつう』でした!」
帰った後に自分が言った言葉を振り返ってみて、
「あれ? つまり私、社会的養護を『ふつうじゃない』って思ってたってこと?」
と思いました。
もちろん「ふつう」にはいろんな意味があって、「いや、ふつうではない、いろんな大変さがあるんだよ」と思う方もたくさんいらっしゃると思うし、その通りだと思います。
ただそのときの私は、「自分の現実の延長にあると思っていなかった」と気づいた、と言いましょうか……。
自分の「ふつう」と社会的養護の「ふつう」が地続きにあると、わかっていなかったと言いますか……。
やっとそのふたつのふつうがくっついたと言うか……。
(伝われ〜〜〜〜〜)
そしてたぶん、今も気づいていない「ふつう」がきっとまだたくさんあるのかな、とも思っています。
まずは自分たちから知らなければいけない、最初はやっぱりここからだろう、とテーマを決めました。
いろいろなものを参考にしたので一部ですが、リンクを貼っておきます。
学ボラに参加していない人にも、ぜひ見てほしいなと思います!
※6/23にリンク先を追加。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
