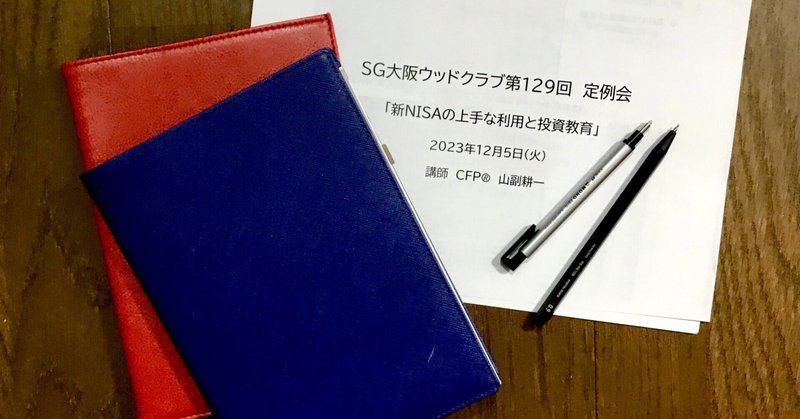
【勉強会参加】「新NISAの上手な利用と投資教育」 前編 (新NISAの上手な利用編)
今回の勉強会レポートは、2023年12月5日にSG大阪ウッドクラブで行われた、FP向けの勉強会「新NISAの上手な利用と投資教育」。
2024年4月からスタートする金融庁の「金融経済教育推進機構」に日本FP協会も参加することが決まり、「金融教育」は、これからFPの間でホットな話題になるでしょう。
今回は、日本FP協会京都支部支部長として、京都府金融広報委員会アドバイザーとして、長年、金融教育の普及に携わってきた山副耕一先生のお話をうかがいました。
前編は「新NISAの上手な利用」編です。
新NISA制度のポイント
2024年1月1日からスタートした「新NISA」は、これまでの「NISA」をもっと使いやすくして、これまで資産運用をしてこなかった人たちにも、積極的に活用してもらおうと作られた制度。
さまざまな工夫をしています。
自由度が高まった新しいNISA
新NISAの特徴をまとめてみました。
・口座開設期間の恒久化
・非課税保有期間延長:「一般NISAの成長投資枠」は5年間から無期限へ、「つみたてNISAのつみたて投資枠」が20年から無期限へ
・年間投資枠の拡大:一般NISAの「成長投資枠」が年間120万円から240万円に。「つみたて投資枠」が年間40万円から120万円へ
・これまでできなかった「一般NISAの成長投資枠」と「つみたてNISAの投資枠」との併用が可能に(合計最大年間360万円まで)
・非課税保有限度額の増額:「一般NISA」総額600万円(120万円×5年)、「つみたてNISA」の総額800万円(40万円×20年)が、全体で1,800万円(成長投資枠は1,200万円)に
・これまでできなかった「投資枠の再利用」が可能になった
要約すると「税金を取られずに運用できる金額が増えて、いつから投資を始めてもよく、長期投資で積み立てても短期投資を繰り返してもよい」ということです。
NISAをお得にする金融機関のさまざまな取り組み
金融機関も新NISA普及のために、さまざまな取り組みを続けています。
・ポイントが貯まる
・クレジットカードで積み立て投資ができる
・給与天引きでNISAが活用できる
・住宅ローン金利の優遇
・コストが安い投資信託商品の開発
・キャッシュバックキャンペーン
サービスが充実している今が、資産形成をはじめるチャンスといえるでしょう。
金融FP・山副先生の視点
「大きく儲けたい」人にとっては使い勝手の悪い制度
「新NISAは、これまでのNISAに比べると工夫されているけれども、それでも使い勝手の悪い制度です」と言われたのが衝撃的でした。
「退職金運用のような数千万単位で資産運用する人には、120万円、240万円の非課税枠では足りません」
旧NISAもそうでしたが、この制度は、資産運用をスタートする人を保護する制度で、信用取引や先物取引のような値が大きく動く商品は対象外。
「すでにある金融資産を活用して大きく儲けたい」という人には向いていません。
今すぐに新NISAをはじめなくてもいい
山副先生が、新NISAで着目されていたのが新NISAの「非課税枠復活制度」。旧NISAの非課税枠は、1年間に使える額が決まっていたのですが、新NISAで使った非課税枠は、翌年1月1日に復活する制度になりました。
ところが、この「翌年1月1日に復活」というのが曲者で、例えば、2024年1月31日に新NISAの成長投資枠240万円を使い切ってしまうと、翌年1月1日まで、成長投資枠の非課税の恩恵が受けられません。
金融市場は変動が激しいので「どのタイミングで非課税枠を使い切るのか」、その見極めが難しいところ。
「今のNISAで資産運用している人は、2024年1月1日になったからといって、わざわざ新NISAに資金を移す必要はありません。そのままNISAで資産を保有していても構わないのです。あわてずに、タイミングを見極めて運用してください」
それが金融の専門家、山副先生のアドバイスでした。
ライフのFP・FPこみなみの視点
意外にメジャーじゃなかったNISA
私が一番気になったのは「NISAを使っている人って、実際どのくらいいるのか?」でした。
私の周りには「NISAで資産運用している」という話を聞いたことがなかったからです。
日本証券業協会が発表した「NISA口座開設・利用状況調査結果(2023年9月30日現在)について」によると、18歳以下が対象のジュニアNISAを含めてNISA総口座数は1,356万口座……
2023年の日本の人口1億2330万人だから11%?
テレビや新聞、ネット広告でさんざん宣伝されているのに、実際にNISAを運用している人って、意外に少ないですね。
今は新NISAがスタートしているので、口座を開設した人も増えてきているでしょうが、普及させるには、もう一工夫必要かもしれません。
「NISA口座を作ったのに使わなかった人」の7つの理由
NISA口座を開設したのにも関わらず、資産運用していない人も意外に多いんです。
2022年6月に発表された、日本証券業協会と株式会社 日本取引所グループ「2021年度国民のNISAの利用状況等に関するアンケート調査報告書」
によると、さまざまな理由でNISAの運用をしない人がいます。
1.金融機関から熱心にすすめられたので、とりあえず口座だけ作ってみた。
2.商品が多すぎて、何を購入するべきか分からないから。
3.投資を行うつもりだが、まだ資金が貯まらない。
4.制度上の制約が多くて利用しづらい。
5.株価の相場を見て、割安な時期に投資を始めたかった。
6.口座開設の申込みから、投資ができるまでに時間がかかり、その間に意欲を失った
7.口座開設キャッシュバックなどのキャンペーンが目当だった
便利な制度ですが、まだまだ改良は必要ですね。
「NISA口座は持ってるけど使い方がわからない」と悩む人へのアドバイス
1の「とりあえず口座だけ作ってみた」という人は、気軽に積み立てから始めてみてはいかがですか。「つみたて投資枠」には、安全性を重視して
2の「商品が多すぎて何を購入するべきかわからない」人は、自分が名前を知っている、気になる商品の投資からスタートしてみるといいでしょう。
楽天証券の無料コンテンツ「トウシル」では、「資産運用入門」の連載記事や、株を保有していることで金券や食品などがもらえる「株主優待株」などの紹介記事が充実しているので、ぜひ、目を通してみてください。
3の「まだ資金が貯まらない」という人は、まとまった運用資金がなくても大丈夫。新NISAのつみたて投資枠では100円単位から積み立てられます。
4の「制度上の制約」がネックの方は、自由度の高い特定口座での運用も検討してみてください。
5の「相場を確認してから投資を始めたかった」という方。下落相場は避けましょう。1か月か3か月のチャートの流れを見て、右肩上がりになっている金融商品を選ぶとよいでしょう。
6の「途中で熱意を失った」人は、日経平均株価が高い今こそ、投資をスタートさせるチャンスです。日経平均株価が下がっていく局面では、お金を儲けるのは難しくなります。
7のキャンペーン目当てで口座を作った人も、この機会に始めてみましょう。初心者向けでは、プロに運用をお任せする投資信託などがおすすめです。
「資産形成」と「家計」のバランスが大事
「資産形成の自由度が高まったからこそ、家計について真剣に考えなければならない」と山副先生はおっしゃいました。
資産形成の自由度が高まっただけに、「いくら投資するのか」「何に投資するのか」「いつからいつまで投資するのか」「どの程度までリスクを取れるか」「家計とのバランスはどうなのか」「形成した資産をいつ使うのか」などの条件を慎重に検討する必要があります。
まず、生活に必要なお金を確保。病気や失業などの不意の出費に備えて手取り収入の6か月分の貯金して、その余裕資金で資産形成をしてください。
資産形成のために「貯金をしない」「保険を解約する」「食費を節約する」などのリスキーな行動はしないように。
「誰もが資産運用をしなければならない時代」と「金融教育」
少子高齢化による年金財源の枯渇が心配され、国も「自己責任による老後資産形成」に政策転換して、NISAやiDeCoなどの優遇制度ができましたが、どうやって資産形成するのかが問題になりました。
そこで子どものころからお金について学ぶ「金融教育」がクローズアップされてきています。
「新NISAの上手な利用と投資教育」後編は、京都で長年投資教育の普及に尽力されてきた山副先生のお話と、日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザーのFPこみなみの考察です。
お楽しみに。
*ここでは、FPこみなみ(AFP認定者)が、独自の目線で、お金に関する話題について解説しています。あくまで個人的見解で、日本FP協会の見解ではないことをご了承ください。(写真:Yuka Shimamura)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
