
もしジェイズ・バーで村上春樹の『海辺のカフカ』について語ったら
今日もジェイズ・バーで飲んでいます。村上主義の方、ぜひジェイズ・バーにお越しになって、一緒に村上春樹の小説について語りませんか?
じゃあまずはビールで。あとフライドポテトも。ビールもけっこう種類があるんですね。じゃあそのおすすめのエール、お願いします。

今日のテーマは『一番好きな村上春樹の小説』です。
いちばん好きな、というとやはり、一番多く読み返している本になるでしょうね。
みなさんのイチ押しを聞くのも楽しみです。
私は『海辺のカフカ』です。
この小説の何がそんなに好きなのか、私にとって特別なのか、今回よく考えてみました。
まず、ストーリーに出てくるナカタさん。ちょっとズレた言動、行動をするけれど、まるで聖人のようにおだやかで、ちっとも憎めない、むしろどんどん好きになってしまうキャラクター、これが本当に好きなところです。
一緒に旅をする星野さんも好きですね。昔ちょっとグレてたかもしれないけど、トラックの運転手で、ヒッチハイクをしていたナカタさんに出会い、そのまっすぐさに惹かれて、一緒に旅をすることになります。
星野さんの心の美しさや正直さが、ストーリーを通して伝わってきます。ナカタさんがこれから何をするのか気になって、その好奇心に誘われたところもあるかもしれないけれど、それだけではなく、星野さん自身の魅力と行動力で、ナカタさんと一緒に別の世界の入り口を開けることに成功しました。
この星野さんというキャラクターが、この小説にたくさんのユーモア、予想外な展開を与えていると思います。
後半で、今までズレた事ばかり言っていると思っていたナカタさんが、少しずつ重大なところに気が付いていく場面では、ページをめくる手が止まらず、毎回興奮するんですよね。
ナカタさんの影は、他の人の半分の薄さしかありません。またナカタさんいわく、ナカタさんの中には何もない、からっぽだと言うのです。
旅をする中で、ナカタさんはその事実と深刻さに気がつきます。そして身近な星野さんにそのことを打ち明けます。
星野さんはそこで「ナカタさんは自分が空っぽだと言うが、だったら自分はいったい何なのか」と自問します。
また別の重要登場人物、高知の佐伯さんもナカタさんと同じ。影が半分しかない、空っぽな存在だと私は考えます。
二人とも空っぽになるにはしっかりとした理由がありました。過去にあったあることが原因で、半分の影になってしまったのです。半分だけで生きているような、空虚な気持ち。それを抱えて生きているのです。
私はこの箇所に、強く共感しているのだと思います。それがこの小説を特に好きな理由です。
「自分には何かあるのか。それとも空っぽなのか」常に考えているわけではないけれど、人生の節目には、そのようなことをぼんやりと考えていたような気がします。ただそれを言葉にして考えていなかっただけなのです。
「自分が空っぽの場合には、影が他の人の半分しかない」
それを具体的に想像してみると、「なるほど、それはそうだろう」と思わざるをえない、むしろ考えれば考えるほど、「そうであるに違いない」と思えるのです。
影の話は、2024年現在村上春樹最新作、『街とその不確かな壁』にも出てきますよね。影と、自分の体(本体)が別々に生きている様子が、この小説にはありありと映し出されています。
影をなくした本体は、紛れもなく空っぽです。心がありません。これは村上春樹作品の中で、明らかに大きなテーマの一つであるはずです。
海辺のカフカに比べて、街と不確かな壁では、影をなくした人の空っぽさが、さらに際立つように描かれていると感じます。
これらのストーリーの中で影というのは、私達が実体のある心を持った確かな存在である、という重要な存在なのです。
私は普段影の存在など気にしません。あるかどうか、確かめてみた経験なんて、おそらく思い出せないくらい昔の、子供の頃のことでしょう。
だからナカタさんのように影が半分の薄さになっていたとしても、私はきっと気がつかないで日々を過ごすと思います。
私達は、心(影)をなくしても平然と生きていく可能性がある。
その事実に愕然としました。その可能性はいつだってあった。これからもあるのです。
ナカタさんが「自分は空っぽだ」と気がついたとき、星野さんが「じゃあ自分は?」と思ったのと同じように、私も「空っぽだったことがあるかもしれない」という想像が、止まらなくなります。
このような恐怖感、焦燥感は私にとって、小説を読むときに「面白い」と感じるエッセンスだと思います。
だって何と言ってもフィクションの小説なのだから、何が起きたって私の生活には関係ないはずです。ストーリーの中で街が爆破されようと、私の現実の街はいたって平和です。
けれど小説を読んでいるだけで「どうしよう」「怖い」と感じるということは、その小説と私の間に何か特別なものがあるではないでしょうか。
私は『海辺のカフカ』を読んで、「空っぽの自分になるのは避けたい」と切に思う。そして「いつだって私たちは空っぽになる可能性がある」という事実を思い出すのです。
それは紛れもない『体験』で、『冒険』であると言っても良いと思います。冒険には恐怖がつきもので、それは私たちにとってリアルな恐怖でなければ説得力がない。
私にとって海辺のカフカは、そんな恐怖を思い出すために、何度も読んでいるのかもしれません。
...すみません。つい熱くなってしまって。
私のそうした意見について、みなさんはどう思われますか?
空っぽの件、考えてみたことありますか?
ああ、ぜひ教えてください。じゃあ次のビールでも頼みましょうか。
じゃあ、あとチーズとナッツの盛り合わせも。
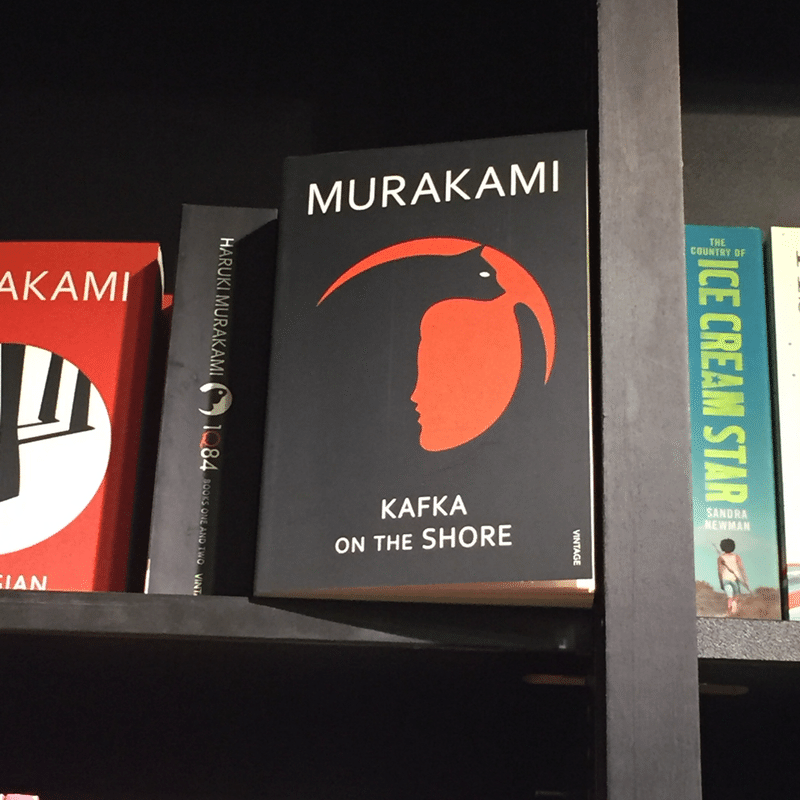
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
