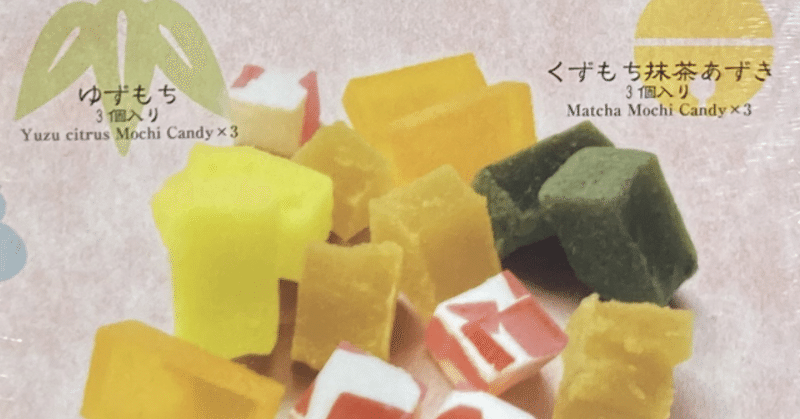
で、多様性の何がいいの?
なぜ海外の大学に進学したいのか?と聞かれた時、
「アメリカで様々なバックグラウンドを持つ人と出会い、自分の視野を広げたいと考えているから」
と高校生の私は書いた。
それから2年以上経ったわけだが、実際どうなの?「様々なバックグラウンドを持つ人と出会」って何がいいの?といったことを振り返ってみようと思う。
まずは現実を
結局似たものどうしで群れる。
似ている見た目、喋り方、テンション感、興味。
同じ授業の人とは授業の話題がメインになるし、
仲良くしてくれる人はやっぱり日本のことをある程度知ってくれている人が多い。
大学の日本人も、日本国内の雰囲気が合わないからアメリカに来てアメリカに溶け込む人たちが多い。
じゃあせっかく大学が「多様性」のあるコミュニティを用意しても、結局似たものどうしの各々のコンフォートゾーンがひしめき合っているだけで意味ないじゃん、と思ったこともあった。
じゃあ何が良かったの
結局あまりにも共通点がなさすぎる人と近しい関係になることはできない。
人間の性質的に仕方のないことである。
だが、私がアメリカに来た意味は「アメリカ国内のどこのコミュニティにも属さない外部の人間として来たこと」にあるのかなと思っている。
もちろん私の見た目や乏しい言語能力だけで判断して切り捨てる人たちもいるのだが、たまに私がどこにも属していないことを見兼ねて仲間に入れてくれたり、彼らの考えを教えてくれたりする優しい人たちがいる。
そして、そういう時に彼らが話すことはだいたい本音に近いような気がする。
私が彼らの所属するコミュニティに全く関係がないからこそ、こちらがどう思うかに気を使って嘘をつかなくてもよくなるのかもしれない。
私はどうせ、that’s so interesting、としか言わないので。(だって本当にinterestingなんだもん。)
自分なんにも知らないじゃん
そうやって色んな人の興味を興味深いねぇって頷きつつ、いかに自分が無知だったかをいつも痛感する。
今まで日本では、いかにコミュニティ内の嫌な感じの人と上手くやっていくかとか、いかに仲間外れにされないかとか、いかにテストで点数をとるかとか、そういうことにばかり脳のリソースを割いていた。
こちらの大学に来て、一旦そういう狭めの話題から物理的に自分を遠ざけることで、新しいことに対して興味を持つ脳みその余裕ができて来た気がするし、今まで思いもしなかった考え方を人から学んだりする。
自分の生きてた世界って狭かったんだなぁと思うと同時に、じゃあ自分はどんな世界で生きていきたいんだろう?と迷子になることもよくある。
似たものどうしでわいわい楽しくやっている日本の大学生が羨ましくなることだってある。
だって自分の価値観を集団に委ねる方が基本は楽だもの。
自分はどうなりたいか
世界には色々なレンズがあることを知った上で、やっぱり自分軸を持っていたいな、と思う。
それは、私はこの道に進むから他は知らない!といったことじゃなくて、
他人と関わる時や物事を選択する時に「私は自分がそうしたいと思っているから今そうしている」といったような、自分の行動に責任を持つことかなと思う。
そうすればきっと期待通りに行かなくても人のせいにしないだろうし、嫌な人に出会ってもダメージを負わなくて済む。
そういった自分を応援してくれる人とはお互いの成長のために仲良くしたいし、受け入れてくれない人に対してはにこっと微笑んで立ち去りたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
