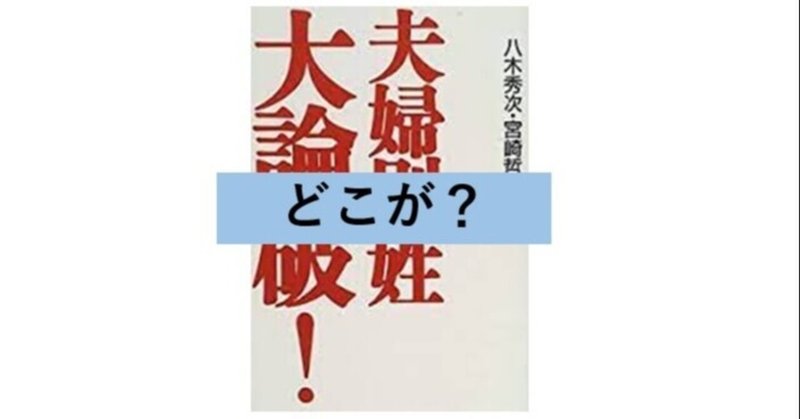
【選択的夫婦別姓】反対派の絶対国防圏「戸籍崩壊論」…本当は誰の責任なのか(3・完)「バグ」はなぜわざわざ残されているのか
〔写真〕反対派のバイブル本を茶化そうとして、5分くらいで作りました。三流の本には三流の対応で十分。
【前記事】
差別的な戸籍制度の当事者が問い直す
前記事では、下記の本をご紹介しながら、戸籍制度が想定する「夫婦と未婚の子」という婚姻家族規範は、その機能が失われつつある現実を説明してきました。
しかし、このまま自壊に任せるわけにはいきません。
なぜなら、この硬直した戸籍制度の歪みで、本来受けられるべき教育・社会保障制度を受けられない人が大勢いるからです。
その数は、1万人以上と推計されます。
著者の井戸まさえ氏は、東京女子大学卒業後、ジャーナリストを経て県議会議員、衆議院議員を務め、現在はNPO法人の代表として無戸籍問題に取り組んでいます。
そして、著者自身も差別的な戸籍制度の当事者でした。
無戸籍者は一体どんな目にあうのか
本書で紹介されていますが、著者は3人の子どもを産んだものの離婚、現在の夫と再婚した際に4人目の子どもを授かったにもかかわらず、その子どもが「無戸籍」に落ち込んでしまいます。
原因は、法の欠陥。(法律上、欠缺(けんけつ)といいます)
まず、離婚調停に大幅な時間がかかったこと。
婚姻関係が破綻した後に、現在の夫と結ばれたことは明らかであるにもかかわらず、早産となったため、民法772条の嫡出子推定に引っかかってしまったのです。
<参考>民法772条
①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
②婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
そのため、最初の市役所の指導は、「前夫を父とした出生届を出して戸籍を作る」でした。ところが、出生届に異議を出され、子どもが無戸籍になってしまいます。
納得のいかない著者は、ありとあらゆるところに働きかけを行い、偶然、法務省民事局長に直談判する機会を得ます。
家事事件(家庭内の紛争などの家庭に関する事件)の判例をいろいろ調べていたら、現夫を相手取った認知調停を起こして、子どもを認知させるという「認知調停」という方法があることが分かった。前夫の子どもでないことと、現夫の子であることの立証が必要となるが、この方法なら、少なくとも前夫は調停・裁判の当事者にはならなくてすむ。
前夫が刑務所うにいたとか海外にいたというような事情がある場合の措置である。しかし私の場合は、現夫が自ら市役所に出生届を出している以上、それ自体が認知行為とみなされるため、私が現夫を訴える利益がなく、認知調停を起こせるかどうか、それすらわからなかった。
私は民事局長に向かって、率直に自分が最後の手段として考えついた実の父親に対する、しかも否定をしていない者に対して「認知調停」という形がとれるものか聞いた。
局長は法務省の官僚たちに「君たちできると思うか?」と聞いた。
官僚たちの手にはそれぞれ分厚い六法全書があった。局長の号令に、凄まじい勢いで一斉に六法をめくる。ページがめくれる音が収まった瞬間、局長は再び聞いた。
「君たち、できると思うか?」
全員、答えは同じだった。「できます」。
(P.17~18)
こうしたお墨付きを得たにもかかわらず、家庭裁判所の調停は不成立となります。
前例がないため、裁判手続きに移行する必要があったためです。
こうして「勝訴」に至ったのだが、敗訴側も喜ぶ、そして誰もが納得する奇妙な瞬間だった。
(P.18)
しかも、この奇矯ともいうべき新判例は、その後大幅に利用が進むものの、家庭裁判所によって手続きや審議過程にかなりのばらつきがあり、ほとんえど同じような事実関係の事案にもかかわらず、担当裁判官によって判断が分かれるなど、かなりの違いが生じているのが実態のようです。(P.19~20)
無戸籍であることは様々な社会保障上の差別を生み出しています。
たとえば、国民健康保険。実は、無戸籍であっても加入する門戸が開かれるよう、当時の厚生省が1959年に出した通達があるにもかかわらず、自治体窓口に周知されず形骸化し、長年無戸籍者が排除されてきました。
児童手当や就学、生活保護などにおいても同様で、国からはその度に通達で無戸籍者でも利用できるよう門戸が開かれているにもかかわらず、十分に現場に浸透していない実態が、本書では詳しく紹介されています。
唖然とするのは選挙権であり、実は、著者が支援した無戸籍者のほとんどは、選挙権(被選挙権)も行使できるようになったのです。
国民の登録簿であるはずの戸籍がないにもかかわらず、法律上は日本国民として選挙ができるが法理論上は可能です。
もはや、戸籍は一体何のためにあるのか?という思いがします。
民法はもはやあらゆる意味で時代遅れ
こうした奇妙な法制度が頑なに維持されるのは、戸籍と民法が密着した連動性を持っているからです。
例えば、上記の民法772条などがそうですが、第2項で前夫の子と推定されながら、実際には前夫の子ではない場合、前夫が否認したら、その子は簡単に無戸籍に落ち込んでしまいます。
再婚待期期間や離婚後300日の嫡出推定規定など、民法の第四編親族、第五編相続の規定は、明治民法の残滓を引きずった、現在では非科学的な規定が数多く存在しています。
そのたびに、上記に紹介した認知調停や各種の行政通達で、また、2007年には法務省が医師の診断書があれば嫡出子推定を外すといった新しい通達、弥縫策を積み重ねて、どうにか維持しているというのが現状なのです。
その点、現在進行している選択的夫婦別姓を求める4つの違憲訴訟は、いかに現在の戸籍制度や民法が時代遅れの産物となっているか、滑稽なほど的確な検討素材を提供しているように思えます。
これは選択的夫婦別姓だけの問題ではなく、今、検討が進められている離婚後共同親権問題にもいえます。
たとえば、前夫のDVから逃れた女性が、子の存在を知られることをおそれ、懐胎したケースといった場合、子どもはやはり無戸籍者になってしまます。
前夫が死亡し、晴れて父子関係不存在の訴えを起こし、勝訴しても、その子供は「出生時の母親の籍」、つまり前夫と同じ籍に入らなければいけなくなってしまいます。
悲劇的なほど無意味な戸籍制度です。
日本人が目を背けてきた戦後の清算
本書の白眉ともいえる箇所は、第4章「消えた戸籍を追って」という章です。
戦争、移民、災害。。。戦前の棄民的な移民政策や、アジア太平洋戦争の過程で見捨ててきた大勢の日本人と、それによって失われた戸籍。
彼らが戦後日本で生きなおす際に立ちはだかったのが、「失われた戸籍」の問題でした。
戦後補償をできるだけ極小化しようという官僚たち、歴史の負の側面を決して認めようとしない保守政治家と、あまりにも長すぎた保守長期政権。
冷戦後の歴史修正主義の台頭で、愛国的で自画自賛的な言説の中で狙い撃ちにあった選択的夫婦別姓制度。
その実現性が失われていく過程の中で、こうした人々が人間として尊厳を回復する機会も失われていったのです。
選択的夫婦別姓制度、戸籍、そして歴史修正主義(ネット右翼問題)は、地続きの社会的問題だと改めて痛感します。
正しい日本人論に抵抗しなかった蓮舫氏への評価
また、この本の執筆当時、最も政治的な話題の1つであった、当時民進党代表であった蓮舫氏の戸籍公開問題にも紙数を割いて触れています。
戸籍法と国籍法、婚姻家族思想と血統主義の国籍論は、保守・ネトウヨ思想には車の両輪であり、リベラルな思想を長年にわたって排撃する言説として機能してきました。
著者は、そもそも二重国籍を違法視する現行法の問題を指摘しつつ、次のように述べます。
内容云々より「戸籍を開示する」という行為自体に意味があり、「戸籍を貴ぶ保守派の人々を納得させるため」もしくは「正統な日本人と認められることでこの問題の幕引きを図った」ともとられなかねないことに思いが至らなかったことは非常に残念である。
(P.171)
しかし、むしろ私は、蓮舫氏の普段の言動、伊勢神宮に参拝することを積極的にPRしたりする姿勢などを考えると、「正統な日本人」であると認定されることを彼女は強く望んでいたフシが大きいように思います。
背景に強大な社会の偏見がたちはだかる問題で、蓮舫氏ばかりを責めることはフェアではありませんが、私は、彼女がマイノリティを徹底的に守ろうと覚悟があったのか、今でも疑問に思っています。
「バグの中に邪気がある」という至言
ここまでの制度疲労を起こしている戸籍制度を、なぜ終わらせられないのか。
著者は本書の終盤で、こんな言い方をしています。
構造的なバグはわかった段階で、当然ながら取り除いて改善されるものだろう。しかし、この一五年の無戸籍支援活動の中で私が悟ったのは、バグの中にこそ戸籍制度を神格化しようという邪気が宿っているということである。バグは実はバグではなく、「わざわざ残している」ものなのだ。
(P.240)
至言、だと思います。
この視点は、民法750条という硬直化した家族観の条文1つ、なぜ削除に到らないのか、という問題と通底していると思います。
サイボウズ社長・青野慶久氏のような合理主義者には、全く理解しがたい現実でしょうが、バグはわざと残されているのです。
保守・ネトウヨ思想の神格化のためにです。
そこが、「ニュー選択的夫婦別姓」訴訟において、青野氏や代理人弁護士の作花知志氏が最も見誤った点、保守・ネトウヨ思想の邪な政治的思惑なのです。
その点、著者の井戸まさえ氏の「ニュー選択的夫婦別姓」批判は、彼らの肯綮を的確に突いたと評価せざるを得ません。
個人的な考えですが、選択的夫婦別姓を導入するにあたって、必ずしも戸籍制度の大幅な改革や、硬直的な婚姻家族思想の打破までを目指すことは必要ないと思います。
戸籍制度や家族思想は、「それはそれ」の個別の問題であります。本来。
だが、こうも思います。
著者の井戸まさえ氏が示唆するように、邪気を取り除くことなくバグを取り除くことはおそらく不可能なのではないか、と。
最新のがん治療のように、病変部分だけを摘出するようには、おそらくできないのではないか、と。
(この連載終了)
【連載一覧】
【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。
