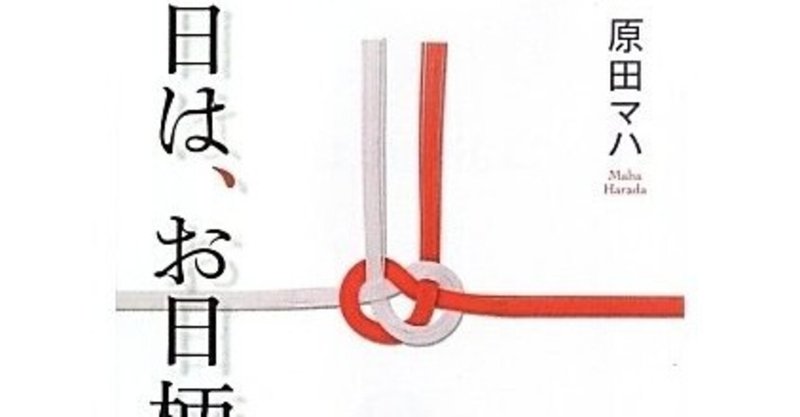
【ブックレビュー】「本日は、お日柄もよく」―”言葉の力を信じる”とはどういうことなのか
あらすじ
OL二ノ宮こと葉は、片思いをしていた幼馴染の披露宴である大失態を犯してしまう。
ところが、それが縁で出会った"伝説のスピーチライター"・久遠久美のスピーチに感激し、勢いのままに弟子入り。
後日、同僚の披露宴で見事なスピーチをやってのけます。
スピーチライターとしての才能を久美に見抜かれたこと葉。
久美の仕事を手伝いながら、政権交代を目指す民衆党の立候補者のスピーチライターを担当することに。
ところが、政権与党・進展党の立候補者のスピーチライターを担当したのは、大手広告代理店が派遣した天才スピーチライター。
果たして、「言葉の力」で政権交代は実現できるのかー。
時代を反映した選挙お仕事小説
本作は、かつて徳間書店が発行していた文芸誌「本とも」に2008年11月~2010年6月に連載していたものを単行本にしたものです。
読後の第一印象は、ずいぶんとミーハーな小説だなぁ、と思ったこと。
書影から受ける印象に反し、本作の中盤以降は、2009年に起きた、日本の政権交代選挙を題材とした話が占めていますが、同時並行して、2008年のアメリカ大統領選挙でのバラク・オバマのスピーチが影響を与えています。
つまり、本作は実質的には選挙お仕事小説です。
「(当時の)流行りに乗って小説書いちゃったんじゃないの?」と勘ぐっていたのですが、読後、著者の原田マハさんのインタビューを調べてみたところ、マスコミに騒がれる前からバラク・オバマを知っていたと、のことでした。
とすると、おそらく、2004年の民主党党大会でのオバマの演説を知っていたのでしょう。
ずいぶんとリベラルにお詳しい。
本作執筆のきっかけになったのは、オバマのスピーチライターに28歳の若者がいたこと。
主人公・こと葉や主要登場人物の年齢に近いというわけです。
20代の若者たち(これがしょーもない軽薄なガキンチョぞろいなわけですが)が社会を変えられるのか。
久遠久美はこと葉にこのように示唆します。
「もしかすると、世界か彼(オバマ)に教えられるかもしれないわよ?スピーチで世界が変わるってことを」(P.117)
見逃された主人公の疑問
だが、2021年、惨々たる選挙結果の現場当事者であった私からすると、すんなりとは受け入れられない言葉です。
フェイクニュースが溢れ、なけなしの批判能力すら喪失したマスメディア。
「公平」の名のもとに行われた、消極的な選挙報道。
憲政史上最短の選挙日程を組むという、与党の愚劣な選挙戦術。
100年後、日本史の教科書にどのように書かれるだろうかと、今から頭が痛くなる思いがします。
こうした現状を、おそらく有権者の多くは知っているが、彼らに現状を変える気概はない。
憂さ晴らしに維新の党に入れるのがせいぜい。
政府の失政で新型コロナウイルスの蔓延し、夥しい死者が出ているにもかかわらず、です。
作中、久美は、こうした選挙民を「したたか」と評しますが、どうだかね。
操作されることに慣れ切っているだけじゃないのか。
作中、衆議院の解散目前、党首討論のシーンが登場します。
怒号が飛び交う議場の傍聴席で、こと葉は「これじゃなんにも聞こえないよ」とこぼすのですが、傍らにいた幼馴染の厚志は「いや、聞こえる」とはっきり言い切っています。(P.219)
2021年、こんな有権者は少ない。
いや、もともと少なかったことに気づくのが遅かっただけじゃないのか。
作中、こと葉は久美に疑問をぶつけます。
終わってみれば、「郵政民営化」など、実は国民にとってはさして切迫した問題ではなかったような気がする。国民は、結局、与党内で小早川総裁が自作自演で起こした嵐に巻きこまれてしまったに過ぎない。同時に、国民は知ったのだった。政治家の言葉には、ときに人を動かす力があるものなのだ、ということを。そして、選挙のときに各党の政策をちゃんと聞いておかないと、あとで自分たちが彼らを審判できないのだ、ということも。
さきの総選挙のとき、小早川総裁の勢いを誰も止められなかったことを引き合いに出し、久美さんは言った。
「あのなんだかよくわからない『郵政民営化選挙』をやられて、国民は、しまった、って思っているのよ。もうだまされないぞ。今度こそちゃんと話を聞いてやろう。それで、よりおもしろいほうに一票を投じてやろう、って気分になっている。」
「よりおもしろいほう、なんですか?よりよい政策とかじゃなくて?」
なんだか不安になってきた。政策の内容じゃなくて、気分で支持政党が決められてしまうなんて、この国は本当に大丈夫なんだろうか。
「気分が向かなきゃ投票所に足も向かないでしょ。おもしろそうだからこの政党に一票入れてみるか、って。まずはその気にさせなくちゃ始まらないの」
久美さんは力強く言った。
(P.307~308)
この後に続く、久美の浮動票を動かす、投票率を上げるという戦術にこと葉は納得していますが、「気分」で動いた有権者の投票がいかに浮薄なものか。本作では結局、語られることはありません。
現実には、2021年10月、維新の党の「躍進」という結果で、こと葉の不安は的中してしまうのですが。
本作で見落とされた日米の有権者の行動力
本作では"言葉の力"で社会を変えることについて、素朴で、牧歌的で、底意地の悪い言い方をすれば能天気に、そのポジティブなイメージが語られていますが、本作で決して取り上げられていないポイントが2つあります。
1つは、実際のバラク・オバマの演説。
本作では大きな影響を与え、終盤、それが久遠久美の行動に影響すら及ぼしているのですが、一行たりも出てこない。
まあ、邪推なんですが、本作に出てくるスピーチのいずれも、オバマのスピーチを超える内容がなかったから。。。ではないかと。
もう1つ描かれなかったのは、日米の有権者の「行動力」の違いです。
なぜ、かの国ではいまだに「言葉の力」が社会を動かすのか。
それは、2008年に脆弱な組織力しか持っていなかったオバマを応援するため、大勢のボランティアがはせ参じたこと。
2020年、米国政治史上最も醜悪な大統領であるドナルド・トランプを倒すために、トランプに投じた6500万人をはるかに凌駕する、7300万人を超える有権者がジョー・バイデンに投じるため投票所に向かったこと。
その行動力。そして、自分たちが社会の主役なのだという、圧倒的な自覚の差です。
それはラシュモア山を下から眺めることと頂上まで登って上から眺めてみることが違うくらい、巨大な差がある。
"夢の一本"は本当はどこにあるのか
作中、久遠久美は「夢の一本」となるスピーチ原稿を書きたいと、こと葉に打ち明けています。
その想いは、久美の最終盤のある行動へつながっていきます。
夢の一本ねぇ。。。
言葉の力が社会を変える、ということを僕も信じたいです。
本作発表後の10年は、腐敗、不信、失望の連続でした。
一方、この10年、社会を変えるような名セリフが出てきたか、というと、全く思いつかない。
安倍晋三も菅義偉も、言葉の力で世論を動かすというより、側近たちを動かして、いかにメディア・言論チャンネルを操作することに腐心してきたことか。
夢の一本は全く必要とされなかった。
対抗するリベラル勢も、2015年、SEALDsの「民主主義ってなんだ?」は問いかけで終わっているし、2018年、枝野幸男の大演説は話題になりましたが、次にはつながらなかった。(大演説は1回で止めちゃだめだよ。)
何より、2009年より2021年の方が、社会をより良い方向へ動かしていくことが、格段に難しくなっている。
では、"夢の一本"へ続く道はどこにあるのか?
本作では、こんなシーンが出てきます。
まっすぐに
「・・・・・これは・・・・・」
小山田党首がつぶやいて、久美さんを見た。久美さんは、ゆっくりとうなずいて見せた。
「宿題の、答えです。」
(中略)
「民衆党の次の選挙のキーワードよ...」
(P.204~205)
この「まっすぐに」というキーワード、劇的な登場を見せますが、その後、久美の選挙戦術の変更で切り捨てられてしまいます。
こと葉は久美に、次のように疑問をぶつけます。
「『いますぐ、まっすぐに』はどうなんですか?」と訊いてみた。選挙を闘うフレーズとして、久美さんが最初に掲げたキャッチコピーは使わないんだろうか。
「『政権交代』よりも新鮮で強いフレーズはないでしょ。このさきは、『政権交代』一本でいくから」
あっさりと取り下げられた。より耳新しく、記憶に残るフレーズ一本に絞り込む。余計なものはばっさりと切り捨てる潔さがプロフェッショナルには必要なんだな、と感じ入った。
(P.303)
本作では、こと葉は久美から素質を見抜かれていますが、作中、いくつも本質的な疑問を投げかけています。その度久美に諭されて得心してしまう素直さが大変もどかしい。
こと葉は自分の素直な疑問をもっと大切にするべきでしたね。
対する久美も、"夢の一本"にたどり着きたいならば、もっと自分がやってきたことを大切にするべきだったんじゃないでしょうかね。
2021年の現実に生きる私たちも例外ではない。
動かない、動こうとしない、拒もうとすらする世論を動かす奇跡を起こすのに、おそらく魔法の杖はない。
技巧的な修辞はいらない。
まっすぐしかないんじゃないでしょうか。
(了)
おまけ
本作は恋愛小説なんですが、最後まではまらなかった。
わりとはまる方なんですけどね。
【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。
