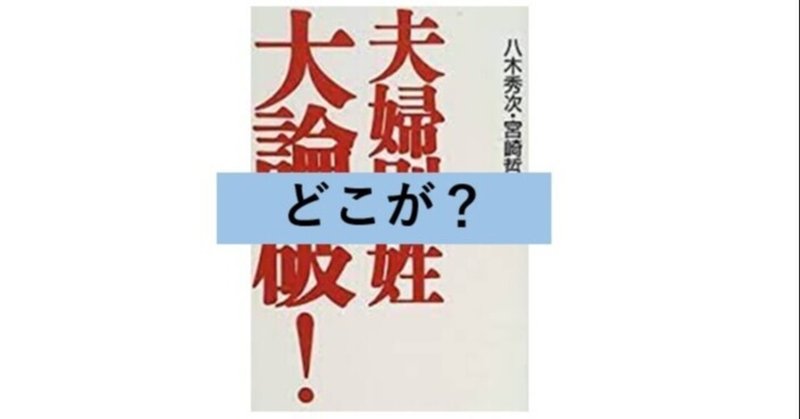
【選択的夫婦別姓】反対派の絶対国防圏「戸籍崩壊論」…本当は誰の責任なのか(2)砂上の楼閣となった「婚姻家族」思想
〔写真〕反対派のバイブル本を茶化そうとして、5分くらいで作りました。三流の本には三流の対応で十分。
【前記事】
前記事で、下記の本を引用しつつ、戸籍の社会的役割が終わりつつある経緯を明らかにしてきました。
今回は、新たにこの本をご紹介して、戸籍制度はそんなに立派なものなのか?という点を一緒に考えていきたいと思います。
著者の下夷美幸氏は、お茶の水女子大学大学院修了後、放送大学教授。これまで養育費に関する研究書を出すなど、家族政策を主に研究されています。
本の冒頭、興味深いデータが紹介されています。
戸籍抄本・戸籍謄本の請求数の推移です。
1952年は約1300万件ほどでしたが、1972年には4000万件を突破し、いったんピークを迎えます。
ところが、1976年の戸籍法改正で請求に規制がかけられたため、いったん2500万件に激減。しかし、また徐々に増え始め、近年は3500万件で推移しています。
その使い道がまた興味深い。
2017年の統計を調べてみると、請求件数約3500万件のうち、900万件が手数料が無料の手続きでした。これは、主に手数料無料となる社会保障関係であることが推測されます。残り約2600万件は不明です。
また、法務省の委託調査による研究では、東京都のある自治体の交付請求書を調べたところ、全体の33.9%が相続関係、9.5%が社会保障関係、5.2%が旅券関係でした。
相続関係は、全体では相当な割合を占めることが予想されます。なぜなら、ご経験のある方はご存知でしょうが、相続手続で相続人を確定するため、亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本を出生から死亡まで追跡しなければならず、複数の戸籍謄本請求が行われることが一般的だからです。(P.1~6)
こうしてみると、戸籍は、ライフステージの中で、非常に偏った、限定的な目的のみで利用されていることが分かります。
戦後改正が残してきた硬直的な「婚姻家族」規範
前回記事でご紹介したように、本来、戸籍は、徴兵や納税のための住民登録としての機能を果たしつつ、国民統合のイデオロギーを浸透させるツールでありました。
しかし、人々の往来が激しくなると、住民登録として機能しなくなり、身分登録としての役割だけが残っていきます。冒頭でご紹介したように、相続を中心とした利用法になってしまったのは、こうした経緯からです。(P.10)
戦後、国民統合のイデオロギーである家制度は廃止されましたが、戸籍の編製単位は、「家」から「夫婦と未婚の子」へ改められました。
「一夫婦一夫婦の原則」「三代戸籍の禁止の原則」「同氏同籍の原則」は、戦前の家制度とかなり本質的な変更ではあるにもかかわらず、国民の間には家制度に類似した家族規範的なイデオロギーは残されました。
著者は次のように問題提起します。
日本では明治以来、戸籍が親族単位で編製されてきたが、著者はこの親族単位の戸籍が日本の家族のあり方の通底をなしてきた、と考えている。つまり、民法(家族法)と戸籍法が一体的に運用される仕組みのもと、事実上、親族単位の戸籍が日本社会のあるべき姿を作り上げてきた、という味方である。そしてそれが、現代の家族が抱える問題にも通底しているのではないか、とみている。(P.18)
著者は、本書の中で、婚姻届けを出した夫婦とその間に生まれた子のみからなる家族を「婚姻家族」と定義し、これこそが正当な家族であり、あるべき家族であるとみなす考え方を「婚姻家族」規範と定義しています。
そのうえで、「戸籍を基盤とするこの規範が、ひとり親家族やステップファミリー(子連れ再婚家庭)など、「婚姻家族」とは異なる構成の家族に生きづらさをもたらしてきたのではないか。さらに政策も「婚姻家族」を前提に策定され、そこから外れる家族の問題に十分に対処してこなかったのではないか。」(P.18)と問題提起をしています。
機能が失われつつある戸籍法擁護論の現実
この本の1つの読みどころは、P.18~27に展開されている戸籍のあり方を巡る専門家の議論です。戦後の戸籍法改正を是とする家族単位論と、個人の尊厳という憲法的価値の実現の徹底化を企図する個人単位論の議論を明快に整理されています。
家族単位論の擁護は、イデオロギー的な価値というより技術的側面(身分関係の検索性の良さ)を重視したもので、従来、戸籍行政に携わってきた官僚たちが主張してきましたが、1980年代になると、官僚の中からも批判的な見解が出されてきます。
個人単位論は民法学者や女性法律家が中心に主張してきましたが、その決定打ともいえるのが、現在、白鴎大学で教鞭を取る水野紀子東北大学名誉教授です。1992年からはじまる一連の論文の中で、民法の主要判例を引用しつつ、除籍や転籍によって戸籍の検索機能が大幅に失われており、家族単位論の技術的限界を明快に指摘しています。
また、本来、家族の保護法であるべき民法(家族法)が、戸籍法の桎梏から逃れ、真の家族法への脱皮を図るため、個人単位での戸籍法改正を主張しています。
※水野教授の論考については以下の記事で紹介しています。
「婚姻家族」規範は誰を幸せにしているのか
この本の一番の読みどころといえるのが、新聞に掲載された「身の上相談」欄の研究です。
1950年から2014年に、読売新聞「人生案内」に掲載された記事から、その時代の人々に共有されている戸籍や家族に関する認識や規範を浮き彫りにしようという試みです。
ここで登場するのが「戸籍が汚れる」という思想。
戦前の戸籍法は、虚偽の出生届を簡単に出すことができましたが、戦後改正により、医師らが作成する出生証明書の添付が義務付けられたため、各段に困難となります。
しかし、実際には、婚外子を嫡出子とするため、虚偽の出生届が相当数行われたという研究が紹介されています。
著者は、1950年から1989年にかけて虚偽の出生届が出されたことに関する、女性たちの相談事例を取り上げていますが(P.125~P.137)、虚偽の出生届を出された、産んでいない子を嫡出子として届けられたにもかかわらず、世間体から現状を隠蔽しようとしたり、はてまた「戸籍が汚された」と激怒したり、生々しい悩みが描写されます。
驚くべきは、こうした「戸籍が汚れる」という思想は80年代の若い女性から語られることもあったのです。
戸籍制度が、道徳律として、「夫婦と未婚の子」で構成される小家族の純潔性を権威付けていたかが分かります。
また、虚偽の出生届が、後日の親族間の争いになったり、出された当事者が心理的な圧迫を受けたりと、父親たちの無責任な不節操が、硬直的な制度の狭間で苦しむ当事者たちを浮き彫りにしています。(P.125~144)
また、私生児として届けられなかった無戸籍児という問題が、長年、日本社会に影を落としていた事例も紹介されています。(P.149~150)
驚くべきは、認知、準正、特別養子縁組といった法制度が、こうした婚外子を救済するため、換言すれば、「戸籍を汚さない」という「婚姻家族」思想から落ちこぼれた当事者を救済・懐柔する制度として機能していた、ということです。
単なる弥縫策だったのです。
そのほか、離婚前の出生子に対する嫡出推定や、離婚後300日以内に出生した子、親子関係不存在確認訴訟の問題など、嫡出子になるか非嫡出子になるか、連れ子同士の再婚、戸籍が汚れるか汚れないかをめぐって、当事者たちが延々と不毛な争いを繰り広げている様子が描かれます。
そして、家庭裁判所もこの「婚姻家族」規範を強化してきました。例えば、認知された子が父親の戸籍に入る場合、子の氏の変更の許可を家庭裁判所で得る必要がありますが、家族間の紛争を防止するため、運用上、母親の意向を非常に尊重していたことがわかっています。(P.240~241)
極めつけは、結婚24年目にして夫の前婚の子が戸籍に残ってしまった妻の相談のケースです。
彼女には夫のほか、子どもが2人いましたが、仮に、夫に先立たれ、子どもが2人とも婚姻したならば、戸籍には家族関係の実態がない、彼女と前婚の子だけが残ってしまう、という可能性があります。
そう考えると、家族単位という戸籍制度の無意味さを問わずにはいられない、と著者は指摘します。(P.231)
個人戸籍への改革は本当に非現実的なのか
本書では指摘されていませんが、実際には、「夫婦(初婚)と未婚の子」という”正しい結婚のかたち”は、統計上、少子化や晩婚化、非婚化といった問題を背景に、減少の一途を辿っています。
著者は、「身分関係という公証ツールという視点から改めて戸籍をみると、もはや家族単位が有していた機能は失われ、むしろその弊害が拡大している」と指摘しています。(P.261)
立ち枯れていく「婚姻家族」思想と日本社会は無理心中を図ろうとしている、というのが私の読後の感想です。
筆者は、その処方箋として「失われた視点の回復」を改めて提言し、忘れられた立法関係者や法学者の意見を再発掘しています。(P.33~124)
こうした政策立案は官僚側から出されていた時期もあり、個人戸籍への改革は決して非現実的なものではないことを指摘します。
長期にわたった保守政権の終わりの始まりが見えてきた今、バックラッシュで失われてきた、「リベラルの本筋」を回復する機会のように思われます。
(この連載続く)
【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。
