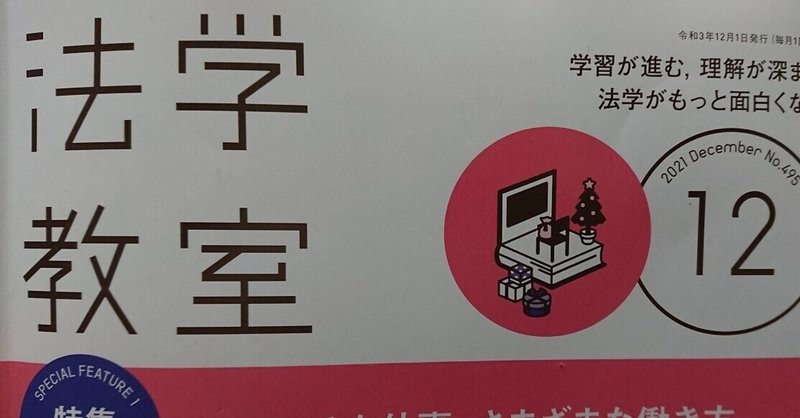
【選択的夫婦別姓】民法学(家族法学)の第一人者による最新解説
【関連記事一覧】
再論
昨年6月、最高裁判所は、婚姻にあたり夫婦の氏を同一とすることを定めた民法750条について、2015年の最高裁判所判決に続き、改めて憲法に違反しない旨の判断を下しました。
私が発行しているニュースレターでも、昨年10月、最高裁判所の判断についての判例評釈をご紹介しております。 ※読者限定記事
そして昨年末、民法学の第一人者である、水野紀子白鷗大学教授による最新解説が、「法学教室」2021年12月号(有斐閣)に掲載されました。
今回はこちらをご紹介したいと思います。
<参考文献①>
水野紀子「日本家族法を考える 第8回 夫婦の氏を考える」法学教室495号(2021年12月)(有斐閣)86-92頁
※以下、断りのない限り、こちらの文献を「本記事」としてご紹介します。
実は、水野教授は、選択的夫婦別姓について、金字塔ともいる有名な論文があります。
今回の論考はいわば再論です。
<参照文献②>
水野紀子「夫婦の氏」戸籍時報428号(1993年)6頁以下
http://www.law.tohoku.ac.jp/~parenoir/uji.html
感情的な反発
本記事の冒頭、水野教授は、昨年2月にNHKで放送されたドキュメンタリー番組に触れます。
昨年末、再放送されてtwitterで再び話題になったので、ご記憶の方も多いかと思います。
私(foresight1974)は、「ああ、ご覧になっていたのか」と思いました。
ご心中いかばかりだったろうか。
というのも、20年以上前、水野教授には似たような体験がありました。
情念の問題はおくとしても、いずれにせよこの問題は感情的な対立を呼び込んできた。別氏選択制への強い感情的な反発は、法制審議会民法部会身分法小委員会が1996年の民法改正要綱を策定していた時代から体感していた。この身分法小委員会の幹事として30代の5年間を費やした私は、委員会メンバーの数少ない生き残りの一人である。当時、講師として出席した自民党国会議員の勉強会の記憶は鮮烈である。改正賛成派と反対派の講師が呼ばれており、私は賛成派の立場から氏の歴史や比較法の話したが、反対派の講師は、「夫婦別氏が通ると日本は革命直後のソ連のようになり、婦女強姦魔と非嫡出子が増えて、家庭が崩壊し、オウム真理教がはびこる」というものであった。そして彼の話が「先生の言われる通りだ」と議員たちの拍手を浴びたのである。その後の質問の時間では、ある議員から私に、「私の選挙区ではまだ夫の親を介護している孝行な嫁がいる。夫婦別姓が通るとそういう高校な嫁が村八分にあってしまう。いかがお考えか」と訊かれた。この質問は、ケア労働を主婦に委ねる戦後の軽量社会保障体制がもたらした「常識」からは自然だったものだったのかもしれないが、愕然呆然としたまま、気の利いた臨機応変な対応ができなかった私は、つくづく自分にはジャーナリストや政治家の素質がないと自覚した。
(<参照文献①>P.86~87)
しかし、時代は変わりつつあります。
水野教授は、世論調査の結果は、選択的夫婦別姓に賛成する人が増加する傾向を示しており、立法の機運が高まっていることを指摘されています。
氏の機能
まず、水野教授は、氏の機能として次の4つを挙げています。
①血統に基づく所有権的理解
②国家が国民である個人を直接識別する機能(個人識別機能)
③国家が家族の秩序維持機能(家族秩序維持機能)
④氏を個人の側から自己を表象する存在として捉える理解(人格権的理解)
水野教授によれば、選択的夫婦別姓に関連する訴訟として頻繁に取り上げられる、NHK日本語読み訴訟最高裁判決(最判昭和63年2月16日)は、④の捉え方を認めたものと評価されています。
氏の比較法
その上で、水野教授は、氏の法的規律について、各国法を概観していきます。
<英米法>
氏の取得変更は、個人の自由に委ねるのがコモンローの原則。
アメリカ法では同氏強制が行われていたが、現在では同氏強制を採用している州法はない。
英米法においては、所有権的理解が法制度として確立する前に氏決定の自由が慣習法として成立してしまい、上記④にほぼ直行した。
<ドイツ>
民法立法の段階で、家族秩序維持機能を形式的にも実質的にも整備したが、徐々に改正している。もともとは夫の氏を称するものであったが、
1957年 二重氏の導入
1976年 婚氏選択制
1993年 選択的別氏制導入
<フランス>
氏はフランス法の伝統では家族の所有。もともと氏名不変の原則があった。
子は父の氏を継承するのが原則。(母は命を与え、父は名を与える)
1985年法 母の氏を二重氏として追加可能
2005年法 母の氏を継承可能
2013年法 二重氏にして子が自分で決定可能
※水野教授のまとめ
氏についてのある側面を原則化することがそれぞれの国で行われ、いったんその国で確立した氏の原則は、慣行として大きな力を持つ。しかし個人の尊重と男女の平等は、あらがい難い流れとして、それに抵触する氏の原則は崩さずにおかない。二重氏の可能な国では、その技術が過渡的に活用される。そして、各国の法改正の動きは明らかに、氏に対する人格権的理解の方向に向かっている。
(同P.89)
<東洋法>
西欧法と比較すると、東洋法である中国や朝鮮の氏は、所有権的機能がもっとよくその形態をとどめている。伝統的な中国や韓国の宗教文化では、氏は「人の根源的なアイデンティティの徵表」(渡辺浩)であった。『中日大辞典』が「『我要撒謊 、我改姓』に『わたしがうそをついたら首をやるよ』という訳を与えているのは、日中両文化の対照を示して象徴的である」。韓国においても、「姓を変えるようなやつ」というのは、「もっとも相手を侮辱する悪口」なのである。日韓併合当時、姓を「人の根源的なアイデンティティの徵表」と考える民族の人々に、日本人は、創氏改名政策を実行した。この政策が朝鮮の人々にとってどれほどの屈辱的な政策と受け取られうるのかについて自覚がなかったとしたら、当時の日本人の貧困さに驚きを禁じ得ない。
(同上)
「朝鮮半島では父系血統主義の考え方が強いため、血は100パーセント父親から受け継ぐ(母親からは一滴も受け継がない)」とされている」そうである。
(同上)
韓国と同様に中国社会も、男系の血統集団である宗族が基礎集団となる社会であるが、現在の中国では氏の創設を含めて、法的には氏の自由化が定められている。
(同上)
日本法の評価
続いて、水野教授は日本法を次のように分析しています。
東洋法圏にある日本であるが、宗族と異なる「家」の伝統により、女性も氏を継承できる点で、中国や韓国よりも自由な氏の継承文化をもってきた。
(同上)
<近世日本>
家職国家。「家」は家族であり同時に企業体。
家職を継ぐために、男性も改氏は行われ、恥ではなく、他人養子を確立した慣行としていた。
<明治期>
識別機能の確立の必要性から、氏の秩序が一気に形成される。
戸籍制度を同時に整備。
近世日本の慣習が瞬く間に失われていく。
当初の戸籍実務では、氏の東洋法の伝統(血統による所有権的理解)に従って、夫婦別氏とされていた。しかし個人の名としてより屋号としての氏の意識が実際にはかなり強かったから、戸籍実務の夫婦別氏へは自然発生的違和感が存在した。明治民法jにおける夫婦同氏制度の立法は、起草者たちによる西欧法の継受と、この自然発生的違和感が合流したものであったように思われる。
(P.90)
そして、水野教授は、日本社会において、男性が改姓しなくなった経緯を次のように分析されます。
明治民法の「家」制度は、戸籍と氏が合体して、氏を家名とした。「家」制度の創設によって、家族秩序維持の観点からの氏の規制力が一挙に、しかも比類ないほどに強まった。やがて時代が下って、日本の産業構造が近代化すると、自営業を営む実体としての家は崩壊していき、それに従って婚姻にあたって男性が氏を変更する率は著しく減少していった。その結果、日本人の男性の多くは、自分の結婚を機に自分が改氏を強制される可能性があることへの想像力を瞬く間に失っていったように思われる。
(同上)
水野教授の主張
これらを踏まえた上での水野教授の主張は、バランス感覚に富んだものになっています。
家族秩序維持の観点から、同氏強制制度が婚姻共同体の象徴として夫婦とその子によって構成される家族の一体感を確保する価値が指摘されてきた。たしかに夫婦が子を育てる家庭の安定性について、家族法は十分に配慮する必要がある。現在の日本家族法は、この配慮が非常に不十分であることに問題がある。家族法は、絶対的弱者である未成熟子を保護するばかりではなく、そのケア負担を負う者の保護法でもある必要がある。そのために、離婚過程への介入や家族の住居を保護する制度や家事債務の確実な履行確保制度などの立法が急がれ、家庭の安定性や一体感はこれらの制度で実質的に担保されるべきである。同氏強制制度が家庭の安定性に寄与するかという点について私は大いに懐疑的であるが、かりに寄与するところがあるとしても、同氏強制によって家庭の安定が図られるべきではない。その寄与は、意思に反して改氏を強いられる被害とは、比較にならないからである。
現実には氏はさまざまな性格を内包するものとして存在している。氏の自由と自己決定権を貫けば、コモンローのように自己が名乗りたいと考える氏がその者の正式な氏であるとする制度に行き着くが、日本法においては、たとえ氏の将来像としてもそのような制度を考えることは現実的ではない。日本における氏の社会秩序維持的な機能は、個人識別機能はもちろんのこと、家族秩序維持機能も重要な機能として肯定的に受け入れられてきた。また氏が子孫に受け継がれることへの要求は、明治民法では「家」の永続性の要請のうちに含めて構成されていたが、この氏の存続に対する要請の根底には、氏の原初的・本能的捉え方ともいうべき所有権的理解があったと思われ、「家」の永続性は否定されても、氏から所有権的機能の要素そのものを否定することは無理であった。
しかし地縁社会や家族からの個人の独立が進むにつれて、氏の個人の表象としての性格は強くなる。ある家族の一員であることが、その個人にとって最も主要な存在の特徴であった時代は遠くなって久しい。またそもそも氏名は、その人間を象徴するものとして個人の人格を深く関連した存在である。今後の氏の規制の在り方は、人格権的要素をできるだけ重視した方向で進めなければならないであろう。
(同P.90~91)
最高裁判例への評価
この水野教授の見解からみた、2つの最高裁判例(最大判平成27年12月16日・最大決令和3年6月23日)については、簡単に3点にまとめられています。
(1)民法750条の位置づけ
令和3年決定の補足意見は民法750条の制約を間接的な制約と評価し、確かに、外国で結婚した日本人夫婦について、事実上別氏で婚姻したことを認定した判例(東京地判令和3年4月12日)も存在する。
しかし、日本国内で日本人が結婚する場合、民法750条は婚姻の権利と氏名を変更されない権利の二者択一を迫るものであり、間接的制約とはいえない。
(2)選択的夫婦別姓(別氏)は婚姻の多様化か
令和3年決定の補足意見のように、夫婦別氏を維持したければ事実婚にすればいいという結論になりかねないため、水野教授は、この考えに反対です。
「婚姻自体は、国家が提供するサービスではなく、両当事者間の終生的共同生活を目的とする結合として社会に自生的に成立し一定の方式を伴って社会的に認められた人間の営みであり、私たちは、原則として、憲法24条1項の婚姻はその意味と解すべきである。」と述べる宮崎・宇賀反対意見の方が、婚姻制度の本来の在り方を正しく指摘していると評価されます。
(3)令和3年決定の評価
令和3年決定は、夫婦の氏に対してどのような制度を採るのかという立法政策と、憲法24条の適合性との問題は、次元を異にすると述べている。
これは国会にボールを投げたものと評価しています。
一方で、「氏を強制的に変更させるという著しい人格権侵害を放置しないことが、人権の守り手である最高裁判所にとって期待される役割であろう。」と批判されています。
立法政策の難題―子の氏の決定方法について―
水野教授は、この問題を難題と捉えており、私見ながら、選択的夫婦別姓賛成の当事者の皆さんと、この問題点の温度差が大きいように思います。
(理由)
(1)婚姻要件を増やす
婚姻時に子の氏を決定しなければならないとすると、自分の氏を子に伝えられない決断を婚姻時に求める(婚姻の要件)とすることになり、婚姻の自由と衝突する。
(2)子の意思の尊重
子に両方の氏を継承できる可能性を開いておく必要がある。
(3)日本社会の慣習
氏の原初的・伝統的捉え方である所有権的理解からの要請を無視すべきではない。氏の継承を封じると、祖父母の養子になるという便法が考えられるが、それでは両親が親権者でなくなってしまう。
<水野教授の提案>
少なくとも、複数の子どもたちの氏を同一にするとしても、出生後に他方の氏に変更できることを認めることで、事実上、両親それぞれの氏を子に伝える権利を確保したと近い結果が得られる。
先行論文との異同
水野教授が本記事の脚注で触れていますが、本記事は、28年前の論文<参照文献②>と重なる点が多いです。
基本的に、水野先生は長年の研究の中で、自己の学説を改めたことがほとんどありません。30年前に確立したご自身の理論を深化させるタイプの研究者です。
<先行研究との異同点>
(1)ご自身の立ち位置について
<参照文献②>では、選択的夫婦別姓をめぐる"思想的対立"(本記事の冒頭で感情的対立とされている)について、「そしてこの対立が平行線をたどることによって不毛な議論に陥ることをおそれる「現実的」な改正派が、少数者の自由をてこにして改正を実現しようとしているという構図が、現状ではないであろうか。」と述べておられますが、基本的には、同様の立ち位置を維持されています。
(2)氏の機能について
本記事でご紹介した氏の機能面の分析は、<参照文献②>とほぼ同じです。
(3)氏の比較法について
28年前から現在までの改正法を新たに追記し、<参照文献②>にはみられない、東洋法の分析も試みておられますが、海外法が人格権的理解に氏の機能を変遷させているという基本的な分析は同じです。
(4)日本法の評価
紙数の関係もあり、日本法の沿革に関する考察は、<参照文献②>の方が具体的で詳細です。特に戦後改正による戸籍との矛盾・弊害が具体的に述べられており、選択的夫婦別姓と戸籍の関係についてお調べになりたい方は、<参照文献②>を参照されることをお勧めします。
水野教授の分析の骨格には変更はありません。
(5)選択的夫婦別姓を擁護する法的構成
<参照文献②>では執筆当時、憲法上の人格権という概念が新しく登場したばかりのため、それが憲法上保障されるかについて、アメリカの判例を引用しながら、かなり具体的に論じられています。
・氏の機能を人格権的理解に寄せていくこと
・現行法の改氏の被害は、氏の統一が寄与するものと比較にならないこと
・家庭の安定性や一体性は社会政策によるべきこと
といった主張の骨格に変更はありません。
(6)立法政策上の課題
<参照文献②>では、本記事でも挙げた選択的夫婦別姓導入時の難題となる、子の氏の決定方法の規律は詳細に述べられており、また、本記事では簡単に触れられているにとどまっている戸籍編製の弊害除去方法についても、詳細に論じられています。
主張の骨格に変更はありません。
【補足】判例の評価について
<参照文献②>の当時は、まだ最高裁判例がないため、何ら論じられてしませんが、2015年(平成27年)判決後、水野教授は、判例評釈を一本執筆されています。
<参照文献③>
水野紀子「夫婦同氏を定める民法750条についての憲法13条、14条1項、24条の適合性」家庭の法と裁判6号(2016年)15頁以下
昨年6月、令和3年決定の直前に、こちらのニュースレターで概要をご紹介しました。 ※読者限定記事
「現実的改正論者」を自認されながら、最高裁判決や保守派の思想的背景に果敢に切り込み、その思想を痛烈に批判した内容となっています。
本記事ではあまり触れられていない、男女差別の問題、復古主義的なイデオロギーや最高裁判所の陥穽を鋭く突いている内容なので、詳細は<参照文献③>をご覧いただければと思います。
私見 ―水野教授の「現実論」の限界―
(1)憲法論について
水野教授は、家族法を、単に西欧法の人権基準で理解するのではなく、「明治以来十分に理解されないままできた西欧の家族法・家族観を見直し、それと意識的・無意識的に存在する家族法観とを対比して、今後の家族法を考える基礎を確立する立場」(星野英一)という西欧法対比説に立たれています。
そのため、選択的夫婦別姓に関する、憲法学者の人権論構成や「家族の多様化」といったイデオロギーに、簡単には乗ってこない。あくまで、「氏の人格権的理解」「不当な婚姻障碍の除去」といった、実際的理由に基づく賛成論です。
そのため、違憲訴訟を戦う当事者に、鋭利な武器(法的論理)を提供しているものではありません。上記にご紹介したように、最高裁判例を批判はされますが、では、どのような違憲審査基準、憲法適合性判断のアプローチをとるべきか、人格権の憲法上の位置づけ(13条、14条、24条いずれで保障されるのか?)といった点にほとんど触れていません。また、最高裁判所の憲法判断の論理を厳密に論じ、論駁するといったこともほぼありません。
その結果、民法750条が合憲か違憲かの結論は示されていません(論理的には違憲と結論されるはずですが。。。)。
そもそも、人格権的理解について、「海外法は人格権的理解に変遷してきた」⇒「日本法も同様に理解するべき」という論理となっていますが、日本法を相対的に評価することを明言しながら、なぜ上記論理が必然的となるかについて、明快な説明はありません。憲法学的には、人権の普遍性から説明可能な論理ですが、水野教授は、人格権的理解にも「家」の所有権的理解にも一定の配慮を示しており、憲法上の人格権保障がどこまで徹底されたいのか不明確なままとなっています。
(2)反対派への"説得の論理"
論文では、現実的改正論者として、細部に行き届いた実際的な改正構想を提示される点は、さすがは家族法学の第一人者といっていいと思います。
しかし、現実的改正論者だが、感情的な反発を続ける、反対派への「説得の論理」は、これまた提供されていません。比較法や日本法の解説は大変興味深い内容ではありますが。これが反対派の気が変えるポイントがあるように思えない。
一方、賛成派がより増えるような、賛否明らかでない中間派を引き付けるような、明快な論理も提示されていません。
要するに、玄人受けする内容であるだけなのです。
最後に
「アカデミズムとしてはそれでいいかもしれないが。。。」
というのが、残念ながら読後感です。
研究者としては、本分をまっとうした、といえると思います。
しかし、本記事でも触れられているように、立法論に舞台が移行している以上、地方議会で陳情活動を続ける市民の皆さん、さらなる違憲訴訟を準備される実務法律家の皆さんに、武器としての法律論を提供する、せめてその思想的バックボーンを提供するのも、アカデミズムの役割であろうと思うのですが。
(了)
【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。
