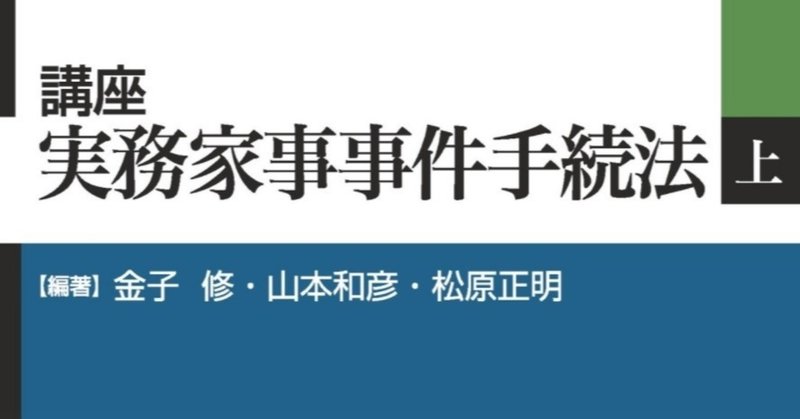
【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(3・完)立法趣旨なき家事事件手続法65条の”漂流”
※前記事
これまでの連載で、法律上の子の意思の反映させる制度として、家庭裁判所調査官の調査、子どもの手続代理人制度をご紹介してきましたが、いまいち、な印象を持たれたのではなかろうかと存じます。
その背景は、家事事件手続法の考え方にあります。
以下にご紹介する文献に沿って解説していきます。
窪田充見「子に対する手続保障」(所収「講座実務家事事件手続法」(日本加除出版)P.441~P.455)
※神戸大学大学院法学研究科教授
1、子の意思を把握するための家事事件手続法の規定
総則的な規定は、65条ですが、家事事件手続法では、以下に挙げるように、各所で子の陳述を聴くことを定めています。
<65条>
家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
<152条2項>
家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
<169条2項>
家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
<258条1項>
...第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について...て準用する。
窪田教授によれば、「これらの規定における「子の意思」が何を意味するのか、また、「考慮する」というのは具体的にどのような形で実現されるのか等、必ずしも明確ではない部分が残されている」と指摘されています。
65条の制定の背景にあたって、窪田教授は次の2つの点が指摘されている、といいます。
①従前の実務においても、家庭裁判所調査官による調査など、適切な方法によって、子の意思を把握することが行われてきた。
②児童の権利に関する条約
児童の権利に関する条約12条1項
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
同12条2項
このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
2、”立法趣旨”が定まらなかった法制審議会の議論
ところが、窪田教授によると、法制審議会の議論では次のような結果になったといいます。
家事事件手続法65条の成立過程の議論に照らすと、そうした基本的な方向については了解があるとしても、そこで、「子の意思」とは何なのか、「子の意思」を把握し、考慮するということが具体的に何を意味しているのかという点については、必ずしも明確な一致があったわけではない。むしろ、最も基本的なレベルでの見解の対立があり、その点の対立は必ずしも完全には解消されないまま、成立に至ったといわざるを得ないように思われる。(P.444)
条文解釈の根拠となる、条文の目的や役割のことを立法趣旨といい、裁判官が条文を解釈し、事案に適用するうえでの指針となるものです。
以前の立法では、立法趣旨は裁判官の解釈の裁量に任せられてきましたが、近年の立法においては、趣旨規定を置いたり、審議会で立法趣旨を明確化し、公開したりすることが行われてきたため、このような基本的事項において、立法趣旨が明確化しなかった、というのは大変珍しいことといえます。
窪田教授によれば、法制審議会の議論において、大きく2つの立場が存在した、とされています。
A.子の意思決定権、子の意見表明権という観点から説明しようという立場
児童の権利条約との親和性をはかる立場であり、判断主体としての子の意思を尊重しようという立場です。
ところが、窪田教授によれば、この立場には「最後まで、消極的な、あるいは慎重な意見が大勢」であった、ということです。
特に、子に意見表明をさせるということ自体に伴うリスクや問題は、多くの委員から指摘されていたところである。すなわち、親権者の決定において、子に親を選ばせるといったことについては、そうした選択をさせること自体が残酷であり、避けるべきであるということが、繰り返し、多くの委員から指摘されている。(P.445)
一方、子の意見表明権という観点から、この制度を位置づけようという委員からも、次のような見解が示された、といいます。
子の意見が常に正しいというわけでもないし、子ども手続代理人の立場で、この子の意見はこうだけれども、実際の子の最善の利益は別のところにあるという主張をすることができる(増田勝久弁護士)
これは、子の意見表明権を代行するというより、より後見主義的な色彩の強いものと位置付けることができます。
窪田教授はどのように考えていたのでしょうか。
私的自治が民法の原則であることは確かだが、そうした私的自治は、例外なくすべての場合に妥当しているわけではない。実際には、判断能力の程度や判断すべき対象に応じて、さまざまな調整がなされている。(中略)年齢についてまったく言及されていない家事事件手続法65条の「子の意思」を、こうした私的自治からの観点からのみ説明するということは十分ではなく、また、すでに指摘されている具体的な問題にも照らせば、適当ともいえないだろう。(P.446)
B.民法全体を通じた理念とされている「子の福祉」の実現と考える立場
重視される子の意思は、子の福祉を実現することに向けた判断材料の一つに過ぎない、とする立場です。そのため、児童の権利に関する条約が定める「子の意見表明権」「子の意思決定権」から説明されるものではない、という立場です。
3、残された問題
これらの議論の結果、窪田教授によれば、以下のような問題が残された、と指摘されています。
①家事事件手続法65条の規定の不明確さ
上記Aの立場は主流とはならなかったものの、文言上は解釈の余地を残すことが可能となりました。
そのため、弁護士の中には、子どもの意見表明権の”実質的保障”を実現するための制度と説明する見解もあります。(池田清貴「子どもの意思の代弁~家事事件手続法における子どもの手続代理人」二宮周平=渡辺惺之偏『離婚紛争の合意による解決と子の意思の尊重』(日本加除出版)P.65)
②子の福祉の観点から基礎づける「子の意思」の不明確さ
前記Bの説によった場合、では判断材料の子の意思って何?という議論の結論は示されませんでした。
また、「子の福祉」を論じるならば、ほかにも多くの環境要因を考慮すべきところ、なぜ「子の意思」だけ独立して明文で規定されたのか、という理論的問題も解消されていません。
窪田教授は、このように懸念を示しています。
子の意思を把握することについて法律上の手がかりが得られたことは、実際の家事事件手続において意義を有するとしても、「子の意思」という言葉は、場合によってはミスリーディングなニュアンスを有するリスクが否定できないように思われる。(P.448)
窪田教授は続けて、「子の意思」について「法律上の「意思」とは異質な、子の精神状態や漠然とした希望や気持ちをふまえて、子の福祉にかなうような判断を行うことが期待されている」という見解を示しています。
4、的中した窪田教授の懸念
しかし、家事事件手続法制定後の家庭裁判所の運用は、残念ながら、窪田教授が指摘した「ミスリーディング」をなぞるような、一方的・一面的な法運用が横行するようになります。
特に、悪評が集中しているのが、いわゆる「面会交流原則的実施論」にみられるような画一的運用であり、その弊害は次のマガジンで現在まとめているところです。
※記事は随時追加中です。
その時に、「子の意思」を良いように濫用する、家庭裁判所調査官の弊害を指摘した記事はこちらです。
こうしてみると、前記B説にみられるように、「子の意思」を裁判所実務関係者の広汎な裁量にゆだね過ぎてしまった結果、実際の子の意思が置き去りにされている現状が浮かび上がってきます。
5、再び問い直すべき家事事件手続法65条の解釈論ー子どもに意見を表明させることは本当に残酷なのか?
2013年に家事事件手続法が施行されてから、8年目となり、問題点も出尽くした印象があります。
実務の議論動向を幅広く調査してきましたが、本条の規定をどのように解釈するか、というより、各事件の場面における適切な実務運用をどうするべきか、という点に議論のフォーカスが当たりすぎているように思います。
ですが、今日の子の意思が置き去りにされた遠因は、法制審議会で本条の立法趣旨が未解決のまま立法にいたり、それを関係が手前勝手に良いように運用しているから、ではないでしょうか。
一連の資料を読み直して思ったのですが、そもそも子の意思というものを表明させることは「本当に残酷」なのでしょうか?
私が日ごろ接している、シングルマザーのtwitterアカウントの皆さんに見られる子どもの気持ちは、存外明確であり、思慮に富んでいるように思います。
子どもには子どもなりに人生を背負い、困難な問題に決断する能力がある、というこをもっと尊重するべきなのではないでしょうか?
そうだとするならば、共同親権推進派が主張するような空疎な子どもの気持ち論や、独善的な家庭裁判所調査官の調査運用は、根本的に見直すべきもののにように思われます。
とすると、現在下火になっている家事事件手続法65条の解釈論を再論することは、理論的には避けられない、というのが私の本連載の結論です。
(了)
【お知らせ】
2021年4月から、新しいニュースレターを発行します。
今までと変わらない、正確で信頼性の高い法律情報をタイムリーにお届けいたします。
【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。
