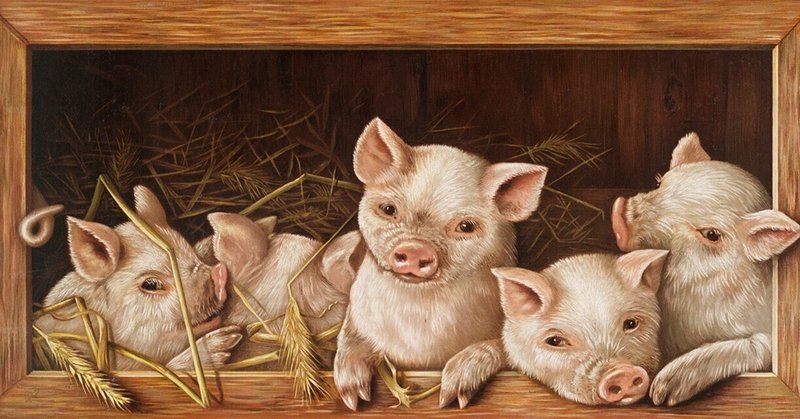
バカの言語学:「バカ」の語源(1) 外来語由来説
「「バカ」の語誌(2)」で述べましたように、「バカ」という言葉がどのようにして生まれたのかははっきりしていません。漢字で「馬鹿」と書くのも当て字で、かつては「母嫁」「馬嫁」「破家」など、複数の当て字が存在しました。
ですから、当然のことながら「バカ」の元になる言葉、つまり語源もわかっていません。諸説ありますが、特に有力といえる説はないようです。そこでとりあえず、その諸説を「外来語由来説」と「和語由来説」に分けて、見ていきたいと思います。
まずは外来語由来説です。これはさらに梵語(サンスクリット語)由来説と漢語由来説に分けることができます。もっとも、梵語由来説も中国経由で漢字表記の形で日本に伝わっていますので、広い意味ではどちらも漢語由来説といえるかもしれません。
Ⅰ 梵語(サンスクリット語)由来説
①「痴」を表すमोह(moha/慕何)
「「バカ」の語義(1)」で見たように、『広辞苑』で取り上げられているのがこの説です。『広辞苑』だけでなく、『言海』以来の多くの国語辞典がこの説を採っています。
『広辞苑』の編者である新村出は「馬鹿考」という文章を書いていますが、これによれば、最初にこの説を試みたのは江戸時代の国学者である天野信景だそうです。彼の随筆集『塩尻』にはこう記されています。
按ずるに、胡語慕何といふを譯して癡といふ、翻譯名義に見えたり。之はバカの音に近し。然れば元と佛者よりいひ初たる言にや。されども此を以て決する事なかれ。若我言の附會たる事あらば博學の士改めよ。
「翻訳名義」というのは、12世紀に南宋時代の中国で編纂された梵漢辞典『翻訳名義集』のことで、日本の僧侶たちもこれを利用していたようです。この辞書の中で「慕何(मोह)」という梵語が「癡」と訳されていて、この "मोह" の音訳である「慕何」が発音的に「バカ」と近いので、これが語源なのではないか、と天野信景はいっています。
もっとも「此を以て決する事なかれ。若我言の附會たる事あらば博學の士改めよ」と付け加えていますから、そんなに自信をもってこの説を唱えているわけではないようです。
"मोह" は "moha" と読みますが、これがなぜ「慕何」なのでしょう。
「慕」は、現在では音読みでは「ボ」としか読みませんが、「幕」「母」など、呉音でマ行、漢音でバ行の読みになる(「幕切れ」と「幕府」、「雲母」と「父母」)漢字はよくあります。
また、「何」については、「上海」の「海」が「ハイ」という発音になっていることを思えば、ハ行とカ行の入れ替わりも十分に起こりえます。
ですから、"moha" が「ボカ」になることは確かにありえます。ただ、「ボ」が「バ」に変わっているのがちょっと引っ掛かります。私が最初にこの説を知ったときは、この母音の変化がどうも不自然に感じられて、疑わしいなあと思いました。
しかし「「バカ」の語誌(6)」で見たように、抄物の『碧巌鈔』や『四河入海』では「バカ」が「痴(漢)」の訳語として使われています。つまり、「バカ」=「痴」という認識が抄物の著者である禅僧たちには共有されていたはずです。そうだとすれば、この「慕何」説はかなり有力に思えてきます。
仏教では人間の煩悩のうち、根本的な3つを「貪」(貪欲)、「瞋」(憎悪)、「痴」(愚昧)とし、これを「三毒」と呼んでいます(それぞれを鶏・蛇・豚に例えることもあるようです)。
"मोह (moha)" は、三毒のうちの「痴」の原語ですので、その音訳である「慕何」が僧侶たちに親しまれていたというのも十分ありうることです。『広辞苑』は「僧侶」の隠語と記していますが、師の説法を理解できなかったり、お経をなかなか覚えられなかったりする修行僧がいると「あいつは慕何だぜ」などと陰口を言っていた、ということなのでしょう。
それなら、もう「バカ」の語源は「慕何」で決まりじゃないか……。しかしこの説を批判した有名な学者がいます。民俗学者の柳田国男です。
彼は「鳴滸の文学」という文章の中で、「しかしこの説などは、隠語の顕語となる条件を知っていての説でないのみか、文語と口語との区別すらも、心得ていたかどうかが怪しいもの」と、かなり厳しいことを言っています。「隠語の顕語となる条件」が何なのかぜひ知りたいところですが、残念ながら柳田国男はそこまで書いてはいません。
柳田国男の考えはともかくとしても、「慕何」説に何ら難点がないわけではありません。それは「「バカ」の語誌(2)」で見たように、室町時代に書かれた『文明本節用集』などで「バカ」の意味が「狼藉」とされていることです。
蘇軾の詩の注釈書である抄物『四河入海』は16世紀に、『文明本節用集』は15世紀に書かれています。ですから、「バカ」を「痴」の訳語としている『四河入海』より1世紀前に「バカ」は「狼藉」を意味するとされていたことになります(蘇軾の詩にある「癡」(=「痴」)に「狼藉」の意味はありません)。となると、『碧巌鈔』や『四河入海』において「痴」の訳語として「バカ」が使われていたからといって、それが「バカ」の語源であるとはいえません。
ちなみに、「「バカ」の語義(1)」でも触れたように、「バカ」の当て字として大正以降に文学作品などでは「莫迦」もよく用いられましたが、これも「慕何」と同じく "moha" の音訳です。
そのことから、「バカ」は「莫迦」と書くほうが正しいのだ、と思ってこちらを使っていた人もいたようなのですが、 "moha" 説に否定的な柳田国男は「今でもえらい人に限って、わざわざ「莫迦」という字を書いてバカと読ませようとしておられる」とぼやいています。
②「老弱」を表すमहल्लिका(mahallaka/摩訶羅・莫喝洛迦)
国語辞典や語源辞典などでは、「慕何」説と並記されていることが多い説です。
天野信景はこの説に触れていませんが、太田全斎らが著した17世紀末ごろの俗語辞典『俚言集覧』には、「慕何」説とともにこの「摩訶羅」説も(否定的にですが)紹介されています。また新村出は「馬鹿考」の中で、「摩訶羅」が「老弱とか羸弱とかいう本義だけれども、転じてボケた義、老耄の意となったとすれば、それからバカという語が出てくるはずだ」と書いています。
新村出はさらに「摩訶という略音形もバカと読める」とも言っています。また『俚言集覧』にも「摩訶」を「バカ」と読む事例があると書かれています。あるというのならそれを信じるしかありませんが、こちらの説は「慕何」説に比べるとどうも説得力に欠ける気がします。
③「青鷺」を表すबक(baka)
こちらは上田万年らが編纂した『日本外来語辞典』(三省堂、1915年)の「ばか」の項で取り上げられています。
梵語ニテbakaハ「痴漢」「無頼漢」「偽善家」等ヲ意味スル語ナレバ,此語ヨリ来レルナルベシ.bakaハ原「青鷺」ト云ヘル義ニシテ,印度ニテハ「青鷺」ヲ馬鹿ノ標準トシテ恒ニ痴漢ヲ呼ブニ此名ヲ以テセリ.baka-murkha「鷺ノ愚」ト云ヘル語モ存セリ.故ニ,bakaヲ秘語トシテ用ヒ,遂ニ通語トナリシモノナルベシ.(J・T)
ちなみに、最後に「(J・T)」とあるのは、編纂者の一人、高楠順次郎が執筆したということのようです。
新村出は、この "baka" 説に対して、「印度語のバカの本義は、むしろ青鷺の周視眈々たる状や欺瞞性偽善性をさしたもので、直ちにその語を痴愚の意とするはいかがなものであろうか」と批判しています(ただしこの直後に「私は梵語については知識はなはだ貧しい者であるから断言は憚る」と付け加えていますが)。また、やはり上田万年が編纂に携わった『大日本国語辞典』も語源の欄に「梵 Baka(慕何)痴漢また無頼漢の義 」としていますが、これについても新村出は、「慕何」の原語を "baka" としているのは明らかに間違いだ、と指摘しています。
私もサンスクリット語の知識なんてまるっきりありませんし、インドの文化についても大して知りませんので、この説についての妥当性を判断することはできません。
ただ、釈迦の前世でのエピソードを集めた説話集「ジャータカ」の中に、まだ菩薩だった釈迦が、魚たちを騙しては食い殺していたアオサギが蟹も騙そうとして逆に首をちょん切られた、という喩え話で人を欺くことを戒めた、という話が載っています。ですから、"baka" という語が新村出の言うとおり「青鷺の周視眈々たる状や欺瞞性偽善性をさした」のだろうとは思います。
Ⅱ 漢語由来説
①『史記』に出てくる故事「鹿を謂ひて馬と為す」
これは『史記』の「秦始皇本紀」に記されているエピソードが語源になっているという説で、「指鹿為馬」という成句もあります。元の話は古くからよく知られていて、『源氏物語』の「須磨」にも「かの鹿を馬と言ひけむ人のひがめるやうに追従する」と喩えに使われています。
秦の時代に趙高という非常に権力欲の強い政治家がいて、始皇帝亡き後、その末っ子だった胡亥を謀略によって2代目の皇帝に即位させると、自らは丞相(今でいえば首相にあたる地位)に就任します。そして胡亥を政治の蚊帳の外に置き、実権を握ったのですが、彼の強権的な政治によって国は疲弊し、劉邦ら率いる反乱軍や項羽率いる楚軍に攻め込まれてしまいます。追い詰められた趙高は、責任逃れのために……、
八月己亥、趙高、乱を為さんと欲す。羣臣の聴かざらんことを恐れ、乃ち先づ験を設け、鹿を持ちて二世に献じて曰く、馬なり、と。二世笑ひて曰く、丞相誤れるか。鹿を謂ひて馬と為す、と。左右に問ふ。左右或は黙し、或は馬と言ひ、以て趙高に阿り順ふ。或は鹿と言ふ〔者あり〕。高因りて陰に諸々の鹿と言ひし者に中つるに法を以てす。後羣臣皆高を畏る。
つまり趙高は胡亥暗殺を謀るわけです。そのためにまず家臣たちが自分についてくるかを試そうと考えて、ある日のこと、彼は皆の前で胡亥に「馬でございます」と言っておきながら鹿を献上します。胡亥が笑いながら「おかしなことを言うなあ、鹿なのに馬だなんて」と言って周りの家臣に同意を求めますが、ある者は黙り込み、ある者は馬でございますと言って趙高のおもねります。中には空気が読めず、それは鹿でございますと答えた者もいたのですが、趙高は法を濫用してそういう連中を次々と粛清してしまい、その結果、家臣たちはますます趙高を恐れるようになってしまった――。
「「バカ」の語誌(2)」でも触れましたが、16世紀に編纂された『運歩色葉集』という辞書には、「馬鹿」の項に「指鹿曰馬之意」とありますので、上記の『史記』のエピソードを「バカ」の語源とする説は室町時代からあったことになります。その後も江戸時代まで、この説はしばしば文献に登場します。
しかし上のエピソードは愚かさを表すものとは考えにくいように思います。「指鹿為馬」という成句も、道理に合わないことを押し通すという意味であって、「バカ」には通じません。
そのためこの説を否定する人も多く、「「バカ」の語義(4)」で見たように、『言海』では「妄ナラム」と一蹴しています。
また『言海』では、「湯桶読ナルモ拙シ」、つまり「馬鹿」という熟語が湯桶読みになっているのもおかしい、と指摘しています(もっとも実際は「馬」が音読みで「鹿」が訓読みですから重箱読みなのですが、「湯桶読」は両者の総称だったのかもしれません)。確かに中国由来の言葉なら、両方音読みで「ばろく」と読まないとおかしいはずです。したがって「馬鹿」はあくまでも当て字であって、趙高の話とは関係ないはずです。
となると、この説は却下してもよさそうに思えます。しかし、「バカ」の語源ではないとしても、「馬鹿」という当て字の起源だというのなら、可能性はあると思います。
冒頭でも触れましたように、かつては「馬嫁」「破家」などいろいろな当て字が「バカ」にはありましたが、江戸時代以降はほとんど「馬鹿」しか使われなくなりました。これは「鹿を謂ひて馬と為す」が「バカ」の語源と信じられたためかもしれません。
根拠なく民間で信じられている語源説のことを「通俗語源説」とか「語源俗解」などといいます。通俗語源説は正しい語源ではないにせよ、これが流布することで言葉の意味や形が変わってしまうことがあるそうです。「鹿を謂ひて馬と為す」説も「馬鹿」という当て字を決定づけた通俗語源説なのかもしれません。
しかしそれが正しいとしても、この「馬鹿」という当て字は『史記』に由来する通俗語源説だけが原因で現在まで残っているのでしょうか。これはあくまで私個人の考えですが、「馬」も「鹿」も動物の名前である、ということも影響したのではないでしょうか。
古今東西どこにおいても人を動物に見立てることは、場合によっては差別と結びつきますし、差別までいかなくても人を愚弄するのによく使わます。ですから「馬」「鹿」と2種類も動物が並んでいるのが「バカ」のイメージにぴったりだと多くの人が感じてきたために、現在でも私たちは「馬鹿」という当て字を使っているのかもしれません。
②白居易の詩に出てくる「馬家の宅」
これは朝日放送の「探偵! ナイトスクープ」の初代プロデューサーだった松本修が、同番組での企画を元に書いた、バカ学にとっては先駆的な名著といえる『全国アホ・バカ分布考』(以下『アホ・バカ』)の中で唱えている説です。同書については「「バカ」の語誌」でも何度か取り上げましたし、「バカ」の方言について考える際にも重用するつもりでおりますが、ここでは松本氏独自の語源説を取り上げます。
「探偵! ナイトスクープ」の「全国アホ・バカ分布図の完成」編でギャラクシー賞などの各賞を受賞し、取材やら何やらに追われていたのがようやく一段落した1991年7月の半ば、松本プロデューサー(当時)は構成作家と連れ立って大阪の天神祭に出かけ、大阪天満宮にお詣りしたそうです。すると道真公のご利益でしょうか、その数日後、仕事を終えて一息入れようと梅田の某書店に入りますと、岩波書店の『中國詩人選集』がずらりと並んでいるのが目に留まります。ふと気になって、松本氏が何気に手に取ったのが「総索引」の巻でした。つい最近までかかりっきりだった仕事が頭をよぎったのか「ハ」の項を引きますと、「馬家の宅」なる一句が目に飛び込んでくる――。
ちょっと話ができすぎの感もなくはありません。もしかするとテレビ業界人ならではのサービス精神かもしれません。
それはともかく「馬家の宅」という言葉ですが、これは唐代の大詩人、白居易(白楽天ともいいます)の「杏を梁と為す」と「宅を傷む」という2つの詩に出てきます。一時の栄華を誇って立派な屋敷を建てても、いずれは身を落とし屋敷は朽ち果てるだろう、だからどんなに出世しようが奢りを抱いてはならない、というような意味の「諷諭詩」といわれるもので、どちらの詩も終盤に「あの馬家の家だって、今では奉誠園になってしまったではないか」と訴えかけています。「宅を傷む」の最後の2行を引用しましょう。
不見馬家宅
今作奉誠園
(見ずや 馬家の宅の、今や奉誠園と作りたるを)
『新釈漢文大系 白氏文集 一』でこの詩の「馬家宅」についての説明を見ると、唐代の将軍だった馬燧が長安の繁華街に大邸宅を建て、息子の馬暢がそれを継いだのですが、「宦官などからのさまざまな言いがかりによって徐々に横取りされ、最後は皇帝に献上して「奉誠園」」と名付けられるに至った」とされています。白居易と同時代の詩人である元稹は「奉誠園」という詩で「秋来の古巷人の掃く無く、樹は空牆に満ちて戟門を閉ざす」と、馬家宅の跡が廃墟になった様子を描いています。他にも晩唐の詩人杜牧の「田家宅を過る」に、奉誠園の荒れ地となったさまが描かれています。
こんなふうに複数の有名な詩人に取り上げられているのですから、確かに昔の中国で広く知られていた話だったのでしょう。
『アホ・バカ』では、この「馬家」が漢詩に親しむ日本の教養人たちの間に広まり、「バカ」の語源になったのではないかと推測されています。「馬」と「家」は漢音で読めば「バ」「カ」なので、発音的にもおかしくないといいます。
私はこの説を批判するだけの素養を持ち合わせていませんが、一つ思うのは、人気の高い白居易の詩から「バカ」という言葉が生まれたのなら、そのことに触れた文献があってもよさそうだ、ということです。古代から中世にかけての文章には中国の古典からの引用が頻繁に行われていますから、「白居易の馬家のように愚かな」みたいなことを誰かが書いていそうなものじゃないかと思います。
この「宅を傷む」の別の一節に依拠しているらしい文が『源氏物語』の「胡蝶」にあるようなのですが、それならなおさら愚か者の例えとして「馬家の宅」を引用した文献がありそうなものです。今後そういう文献が見つかれば、この説はかなり有力になってくるかもしれません。
ところで『アホ・バカ』ではこの「馬家の宅」説が、『文明本節用集』において「バカ」の語義が「狼藉」とされていたこととも結びつけられています。
同じ白居易の「草茫々」という詩に「奢者狼藉倹者安」という一節があるのですが、通常は「奢れる者は狼藉にせられ倹なる者は安し」と読み下されて「ぜいたくな墓は掘り返してとりちらかされるが、つつましい墓は安全だ」と訳されています。しかし松本氏は、この一節が日本では「奢れる者は狼藉なり」と読まれるようになり、それが独り歩きして「奢り」=「狼藉」=「バカ」と結びつくようになったのではないか、としています。
しかし「「バカ」の語誌」を通して見てきたように、室町時代においても「バカ」は「狼藉」の意味のみで用いられていたわけではありません。そのことはおくとしても、私には上記の推論はちょっとこじつけの感があると思われます(ちなみに「こじつけ」の語源は「故事付け」です)。元禄以前に書かれたとされる「草茫々」に対する注釈書で、上記の一節を「ヲコレルモノハラウセキナリ」と読み下しているものが一つあるらしく、これをもって松本氏は説の裏付けとしているのですが、それだけではちょっとどうなのかなあ、という気がします。
③「破家」
「バカ」に「破家」という字を当てる例は『文明本節用集』にもすでに見えますが、「破家」を単なる当て字ではなく語源と見なす説があります。これは国語学者の佐藤喜代治が唱えた説らしいのですが、具体的にどう論じているかは調べがつきませんでした。
「破家」は現在でも中国で使われている言葉で(もちろん「バカ」と発音しませんが)、「家庭が崩壊すること」「家や財産を失うこと」といった意味になります。「亡国破家」という言い方が『史記』などによく出てきます。
日本では仏教、とりわけ禅宗でこの言葉が使われたようです。特に「破家散宅」という言葉があって、これは「無一物になる」ということから「悟りを得る」という肯定的な意味で用いられることもあります。
ですから、もしも「破家」説が正しいとすれば、禅宗の僧侶から伝わったのかもしれません。また語源ではないとしても、「破家」という当て字は仏教についての知識をもった人が使っていた可能性はあります。
④『大智度論』『三教指帰』に出てくる「術婆伽」
こちらは「「バカ」の語誌(2)」ですでに取り上げていますが、室町時代後期(戦国時代)の明経道の学者である清原宣賢が編纂した『塵芥』という辞書に見られるものです。
婆伽 三教指帰、ハカ狼藉ト云
語釈には空海(弘法大師)の若き日の著作である『三教指帰』の書名が記されているだけで、この本にある「術婆伽」が語源である、と言っているわけではありません。しかし当て字を「婆伽」としていますから、そう取るのがいちばん自然かと思います。
「術婆伽」の伝説についても「「バカ」の語誌(2)」で詳しく説明しましたが、つまりインドの龍樹が書いて鳩摩羅什が漢訳した『大智度論』に記されている話で、術婆伽という漁師が美しい王女に一目惚れし、あまりの想いの強さに、恋い焦がれるという言葉のとおり、体から火を発して焼け死んでしまうという話です。
重要なのは、『大智度論』ではこの話は女の誘惑の恐ろしさを表しているとされているのに対し、『三教指帰』では男性の情欲が彼を愚か者にしてしまう話だとしていることです。ですから愚か者の喩えとして術婆伽の名が使われるのはありうることだと思います。もしもこの説が正しければ僧侶、特に真言僧が「バカ」という言葉を使い始めたと考えられます。
「婆伽」を「バカ」の当て字とする例は、「「バカ」の語誌(4)」で見た『太平記』の古活字本(1603年刊行)の巻十六にあります。『太平記』には術婆伽の話に触れた箇所もあります(ただし、文脈的には愚かさとあまり関係がないようです)。もっとも、先に見た "moha" の音訳として「婆伽」が使われることもあったそうなので、『太平記』の古活字本の「婆伽」が術婆伽を指しているとは限りません。
この説もやはり術婆伽を愚か者の例えとしている文献が『三教指帰』以外にもっとあれば有力になってきそうなのですが、実際のところどうなのかわかりません。また「術婆伽」を「バカ」の語源とする説も『塵芥』以外では取り上げられていないようです。『日本国語大辞典』でも「バカ」の語源説の中にこの説を含めていません。
◎参考・引用文献
天野信景『随筆 塩尻』 帝国書院、1907年 ウェブサイト「国会図書館デジタルコレクション」にて閲覧 https://dl.ndl.go.jp/pid/991407
新村出「馬鹿考」『語源をさぐる』 講談社文芸文庫、1995年
柳田国男「嗚滸の文学」『不幸なる芸術・笑の本願』 岩波文庫、1979年
上田万年ほか編『日本外来語辞典』 三省堂、1915年/復刻版 名著普及会、1984年
上田万年・松井簡治著『大日本国語辞典』 冨山房、1929年 国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1136397
吉田賢抗『新釈漢文大系 史記 一(本紀)』 明治書院、1973年
フランク・B・ギブニー編『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 第2版改訂』 TBSブリタニカ、1993年
松本修『全国アホ・バカ分布考』 太田出版、1993年/新潮文庫、1996年
岡村繁『新釈漢文大系 白氏文集 一』 明治書院、2017年
「馬鹿」 「ウィキペディア 日本語版」 https://ja.wikipedia.org/wiki/馬鹿
清原宣賢『塵芥』 室町時代後期 ウェブサイト「京都大学貴重資料デジタルアーカイブ」にて閲覧 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00007911
その他、多数のウェブサイトを参考にしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
