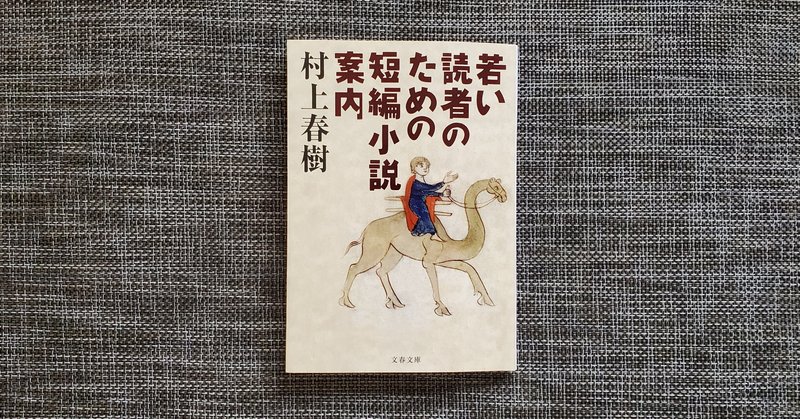
村上春樹『若い読者のための短編小説案内』を改めて読む① ~短編と読む視点~
村上春樹の新作短編集『一人称単数』を尻目に、むかーしの『若い読者のための短編小説案内』を改めて読んでいる。単行本は1997年に出ているから、もう23年も前の「案内」だ。当時は(若かったけれど)、春樹氏が書いた文章であれば何でも読みたいというミーハーなファンだったので、そこで取り上げられた作家の作品自体は1つも読んでいない。
そこで今回は(若くはないけれど)ちゃんと、取り上げられている作家達の作品を読み、その上で、春樹氏の読み解きを楽しんでいこうと思っている。取り上げられている作品は6つ。
吉行淳之介「水の畔り」
小島信夫「馬」
安岡章太郎「ガラスの靴」
庄野潤三「静物」
丸谷才一「樹影譚」
長谷川四郎「阿久正の話」
吉行氏の本は絶版なので図書館で予約をし、長谷川氏の本は中古本でも高額なので古い全集を注文。他は一応、全部手元に揃えた。これらは春樹氏が、1991年~93年にかけてアメリカのプリンストン大学の大学院で受け持った授業で取り上げた作品だという。
本書の「文庫本のための序文」では、氏にとっての「短編」について述べられている。氏は「短編小説をひとつの実験の場として、可能性を試すための場として」使っているという。短編で発展性があるかどうかを試してみて、発展性があるとしたら、「長編小説の始動モーターとして」取り込まれていく。『ノルウェイの森』にとっての「蛍」、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』にとっての「街と、その不確かな壁」のように。
そんな発展の可能性を試すことに加えて、
僕は長編小説にはうまく収まりきらない題材を、短編小説に使うことがよくあります。ある情景のスケッチ、断片的なエピソード、消え残っている記憶、ふとした会話、ある種の仮説のようなもの(たとえば激しい雨が二十日間も降り続けたら、僕らの生活はどんなことになるだろう?)、言葉遊び、そういうものを思いつくままに短い物語のかたちにしてみます。
ふとした、断片的な、思考の試行のようなことも短編上で行うという。
それは画家にとってのデッサンのようなものだと言えるかもしれません。正確で巧みなデッサンをする力がなければ、大きな油絵を描き切ることはできません。僕は短編小説を書くことによって、またほかの作家の優れた短編小説を読むことによって、あるいは翻訳することによって、作家としての勉強をしてきました。
自分自身も、最近はもっぱら短編ばかりを読んでいる。それは「書き方を学ぶため」であり、その作家の「クセ(いわゆる文体、スタイルというようなもの)を知りたい」からだ。長編を読むと、物語に飲み込まれてしまう。客観的に文章をとらえることができなくなる。簡単にいうとただ単に物語の世界に没頭しちゃうということなんだけど。
本書は、村上春樹氏が小説を書くという自身の体験を通して得た「創作本能」を横糸に、それぞれの作家が自分の自我(エゴ)と自己(セルフ)の関係をどのように位置づけているかを縦糸にして、作品を読んでいくという。「それ(エゴとセルフの位置づけ)はある意味では僕自身の創作上の大きな命題でもあったから」だと。
とにかくそこでは僕は、その作家のはいていた靴に自分の足を入れていきます。そしてその作家の目で、そこにあるものを見てみようとしています。
というように、本書は6つの作品について、「そのテキストを書くという作家の営為を意識の中心において読み進め」られていく。
今回自分は、書き方を学ぶというよりも「作品の読み方を知りたい」と思ってこの本を再度手にとっている。「読み方」というのは、どんな視点を持って作品を読みこんでいくかということだ。自分がいつも読んでいるようにただ読んでいると、自分の反応と推測しか起こらない。それはとても狭くて浅くて奥行きがないものに思える。それ以上の、見えていない何かを知りたい。そうやって「読む」を奥に進んでいくと、書くことにも還元されていくと思っている。おまけに、春樹氏の新作『一人称単数』の短編のそれぞれも、より作者の意図などが深く味わえるんではないか、とも。
このまま続けて1作品目について書こうとしたが、ひたすら長くなりそうなので、今日は前書きだけ。1作品ずつ投稿していけたらと思う。
サポートいただけたら跳ねて喜びます!そしてその分は、喜びの連鎖が続くように他のクリエイターのサポートに使わせていただきます!
