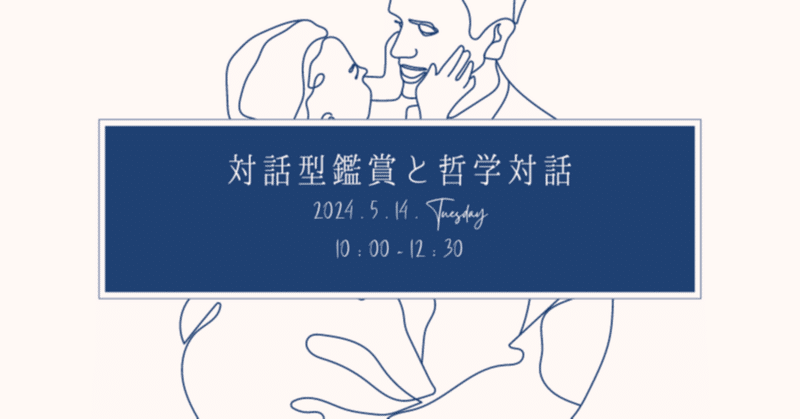
対話型鑑賞と哲学対話#8 開催レポート
8回目の対話型鑑賞と哲学対話を実施しました。
前半は2つの作品を鑑賞し、発見したことや考えたことを出し合いました。
後半は、前半で出てきたやり取りをふまえて問いを出し合い、1つの問いを選んで哲学対話をしました。
チェックイン
いつものように、お互いの声がちゃんと聞こえるかの確認も含めて、今の気分や体調をお1人ずつ簡単にお話していただきました。
対話型鑑賞
今回は2作品を見ることにしました。
鑑賞した作品はカンディンスキーのものとロバート・ブルームのもの。
そこから様々な発見や解釈が生まれました。対話型鑑賞の際には、進行役から「どこからそう思いましたか?」と「そこからどう思いましたか?」の質問を重ねていきます。このやり取りが実は、哲学対話で対話をしていく下地のようなものになります。
根拠とともに自分の感じたこと考えたことを言う。
シンプルだけととても大切なことです。
また、他の人の発見や洞察を聞いていると、なるほどそういう風にも見えるねと、同じ絵が違って見えてくることも不思議です。人がどれだけ自分の基準というメガネで世界を見ているかということをありありと実感します。
問い出し
1時間ほど鑑賞をしたあとは、休憩を挟んで、前半の話をふまえて問いを出し合いました。
1.リアリティを感じるための条件は何か?
2.リアルとは何か?
3.非現実な物語の必要性とは何か?
4.絵を見るとなぜ物語を感じ取ろうとするのか?
5.知的好奇心は何で生まれてくるんだろう?
6.同じものを見ているのにどうして違う印象が生じるのか?
投票と話し合いの結果、選ばれたのは「絵を見るとなぜ物語を感じ取ろうとするのか?」という問いです。
絵を通してやり取りした内容から、興味深い哲学対話の問いが立ちました。
哲学対話
※個人が特定されない範囲で出された意見をご紹介します。メモをもとに書いているため、進行役の解釈が入っていますのでご了承ください。
●絵を見るとなぜ物語を感じ取ろうとするのか?
・作品名や作者を知らずに絵と対面したときに、感覚的なものだけ受け取るということもできるけれど、人物や背景の関係性を読み取ろうとしている自分がいた。
・じっくり見るというのは、物語、そこにある意味を読み取ろうとすること。人は物事を時間軸で捉えて意味づける。なのでこの問いに対しての答えとしては、人が生きているからとなる。あとは風景画でも同じように物語を読み取ろうとするか?そこに人間が描かれているから物語を読み取ろうとするのではないか。
・物語を感じ取ろうとするのは不安定を解消したいからではないか。何を意味しているか分からない状態は不安定なので、物語を推測して安心感を得たいのではないか。また意味を見出そうとするときに、頭のなかだけで考えるのではなくて、最初に絵を見て感じたものをもとにして考える方が的確に意味がつかめそうな気がする。
・人それぞれ持っている想像力が働くからではないか。同じ絵を見ても、これまでの人生や経験によって受け取り方は様々で、受け取って、想像力が反応して物語が広がっていくのではないか。
・作品であるということは、それを創った作者がいるので、そこに何かしらメッセージがあると思う。そのメッセージを見つけたいという衝動からくるのではないか。見つけたときにうれしいという気持ちを感じられるから余計に求めるのではないか。
・美術館などは作者も作品名もわかっている状態で観るので、その作者の一生の物語のなかで個別の作品のテクニックや細部を観たりする。個別の作品のなかの物語は、注目させるフックになると思った。
・子どもが書いた絵やアール・ブリュットの絵などは、作者の意図があるかないかわからない。それでもつい反射的に意図を感じようとするのはなぜなんだろう?ないかもしれないのに、あると思って理解をしようとする。理解できなくてもいいのに反射的にやってしまう。
⇒理解できなくてもいいというのはどういうこと?
⇒自分の範疇の理解を当てはめなくてもいいのではないかということ。説明はどうせできない。決めつけになる可能性もある。
・NHKの「no art, no life」という番組で、精神障害のある人の作品が紹介されている。それを見る時、意味はあまり考えていない。その人がどんな風に考えているかが不思議と絵を通してわかる。精神の中をそのまま書いている感じがする。
・そもそもわからないものはわかりたいという欲求を持っている。わからなくてもわかろうとしたい。だから風景画であっても、そこに時間を感じ取ろうとすると思う。自分がわかろうとしても、わからない、わかれないということもわかりたい。だからこそ、自分にない考えを知りたい。他の人の意見を聴いて、自分の見方がガラッと変わったとき、感動したりもやもやしたりする。わかろうとする先に新たなわからないが出てくる。
・読み取れる物語は1つではない。美術館の作品紹介も1つの物語だけど、見る人によって違うものを読み取れる。わかりたい、知りたい、絵と仲良くなりたい、絵に近づきたいということが物語を読み取ろうとする根底にあるのではないか。
進行役コメント
今回は哲学対話のスタート地点で、「思いついたことを言うというよりも、問いについて自分の答えを言ってみるということを意識してみてください」とお伝えしたので、もしかしたら少し窮屈に感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
それでも、普段の哲学対話でどんどん問いが展開していくのに対して、今回はみなさんが最初の問いに向き合い続けてくださったので、ぐーっと深めていけそうな観点がいろいろ出てきたなと思います。
私自身は、作品のなかの物語を読み取ろうとしているのか、それとも作品を通して自分のなかに物語を立ち上げているのかという疑問が浮かんできていました。自分のフィルターを通してその作品を意味づけるということは、その作品のなかに見出す物語は自分のなかにあるものから構成しているはずです。対話の時間が続いていたら、そんなことを投げかけてみたいなと思いました。
次回の開催
次回は6/20(木)です。
平日午前ですが、ご都合つく方はぜひ!
サポートいただけたら跳ねて喜びます!そしてその分は、喜びの連鎖が続くように他のクリエイターのサポートに使わせていただきます!
