
花贈りにロマンを込めて~花ことばとメッセージ~
1.序文
「花ことば」はどう使う?
本ではよく目にする言葉でも、
花束に添えるメッセージには、あまり使わないかもしれません。
さまざまな芸術作品で花が引用されたり、
花ことばの意味を暗示的に使うことはあっても、
その言葉のまま使うことは少なそう。
それでも、花ことばが存在するのはなぜか……。
その理由を考えてみました。
2.花ことばとは(エリンジウム)
花ことばというと、「どこか空想的で詩的な世界」
と感じる方もいるかもしれません。
実際、花ことばは、どんな理由でつけられているのでしょうか。
例えば、エリンジウムの花。

メタリックブルーのシャープな姿が凛々しい。
銀白色の光を帯びたトゲトゲした葉は、どこか神々しくもあります。
(品種によって白色や緑色もあります)
エリンジウムの花言葉は
光を求める、秘密の愛、秘めた思い
その理由は、
花や葉の姿が、何者をもよせつけず、
秘密を守っているように見えるから。
また、他の本では、「秘密の恋」など、
言葉のニュアンスが違ったり、本の掲載基準によって
「代表的なものだけ抜粋する」「ネガティブなもの載せない」など、
その記載内容に少し違いがあるようです。

エリンジウムの花ことばは、
花の特徴や見た目の印象がもとになっているので、
うんうん、分かる!とすんなり受け入れられる。
芸術作品でも、比喩として使えそうですね。
一方で、花贈りのメッセージに使うのは、ハードルが高そうです。
無理に使えば、本当に伝えたい想いとズレてしまったり、
相手が「?」となるような、恥ずかしい結末を想像せずにはいられません。花ことばの意味から花を選ぶとしても、
「季節の花じゃない」「贈りたい花じゃない」かもしれません。
でも実際、花ことばは、
花贈りのメッセージとして、コミュニケーションの手段として、
使われていた歴史もあります。

3.花ことばの由来
花ことばはどこから生まれたのでしょうか?
諸説ありますが、オスマントルコのセラム(selam)という風習が
起源だったと言われています。
当時、様々な植物(色、花、雑草、果実、ハーブ、小石や羽毛など)に
詩句がつけられ、手紙や文書として送りあう風習がありました。
それは、花ことばそのものでなく、
その言葉と同じ韻をふむ他の言葉を暗示するための表現でした。
例)セラムの品(洋梨)トルコ語で「armoude」
→同じ韻を踏む(希望)「omoude」ということばを連想
慣用表現:「私にいくらか希望を与えてください」
(参考:著:樋口康夫 花ことば-起源と歴史を探る-八坂書房)
その後、18世紀初頭に、トルコ大使夫人が書簡につづった
トルコ流恋文(セラム)がヨーロッパへ伝わり、
セラムに用いられる品物から花だけを取りだして、
恋愛に関わる意味を花に込める作業が行われました。
花ことばの意味の由来は、花の特徴や性質だけでなく、
神話や逸話、聖書、文学からと様々。
花の品種、色、本数によっても、別の言葉がつけられていたりします。
19世紀初頭に、花ことばに関する本がフランスで著作され、
その後、イギリス、アメリカへ。
各国の文化や商業事情にあわせて編纂され、広まっていきました。
日本には明治維新後の西洋化の流れの中で、洋花とともに伝わりました。
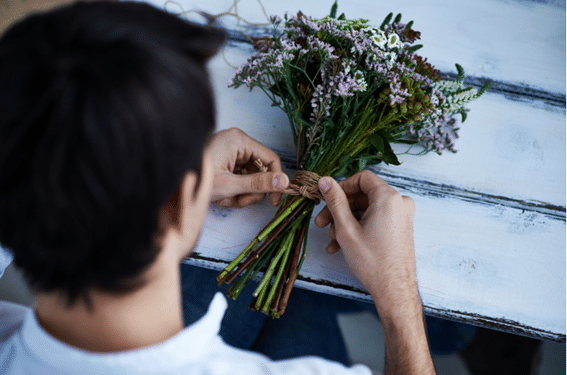
4.花ことばと花贈り
花ことばは当初、どのように使われていたのでしょうか?
花ことばには、恋愛にまつわるものが多く、
上流階級の男性の教養とされていましたが、
やがて中流階級の女性の嗜みになっていきます。
フランスの貴族婦人たちは、花束を持ち歩いたり、
頭や腰などに飾りつけ、魔除けやお守りにしたり、
体臭をカモフラージュするためのエチケットにも使っていました。
そして、その小さな花束を手紙の代わりに、
フィアンセや恋人に贈り、愛を伝える手段としても使っていました。
ヴィクトリア朝時代のイギリスでは、貴族たちは、
花ことばを学び、花に特別な意味やメッセージ(花ことば)を与え
それを束ねた小さな花束(Posy Bouquet:数種の花を組み合わせたもの)を、愛する女性に贈る習慣がありました。
(参照:著 Jennifer Davies, Saying It With Flowers, Headline Book Pub Ltd)
やがて、花ことばは大衆へと広まり、
19世紀後半頃には、その流行は衰退していきます。
花ことばは、歴史的には西洋で発展した流れを受けたもので、
時代や国ごとに異なる価値観によって変化してきました。
その意味に、科学的な根拠はありません。
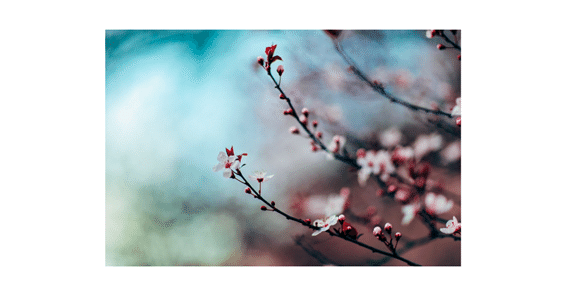
5.花言葉とメッセージ
それでも、花ことばが誕生する前(古代)から、人々は花を求め、
花を敬愛する文化を築いてきました。
花の絵画、花飾り、庭園づくり、造花など。
西洋でも東洋でも、花を慈しみ、味わう習慣がありました。
また、国花、紋章、文学や芸術作品への引用など。
そこに、「メッセージ性」を見出してきました。
日本では、皇室や家紋のモチーフにも花が使われていますが、
万葉集(和歌)や源氏物語など、文学作品の中でよく目にしますね。
控えめで感情表現が乏しいと思われがちな日本人でも、
平安~江戸時代にかけて、恋文や懸想文という習慣はあって、
花は、比喩としてよく使われていたのです。
今はインターネットの時代。
もう、そんなやりとりは、求められなくなってしまったのでしょうか。
個人的には「眠っているだけ」のように思います。

会社員時代のこと。
バレンタインデーがたまたま祝日と重なり、
「今年は、チョコ買わなでいいよね」と女性同士で約束し、
何食わぬ顔で一カ月過ごしていました。
すると、上司から、ホワイトデーのお返しが……。
それを「催促」のように感じ、慌てふためいた私たちは、
急いでデパートに買いはしり、後づけで「すみません」と言って、
お返しのお返しをすることに。
その時は、(催促のつもりなんて微塵もなかった)
上司のキャラクターもあいまって、
面白い、かわいい!と思ってしまったのですが。
「義理チョコ」という、形だけのやりとりに、
すれ違う心、それに思い煩うこともよくありました。
それが、令和の時代にかけて、ガラッと変わったように思います。
むしろ、そんな形だけのやりとりに少し冷めた目で見ることが多くなった。社会、環境、その大きな流れにあわせて、
賢く生きなくては……。無駄を省こう。
まじめに忠実に生きる人なら、なおさらそう考える。
心までデジタル&スマートな時代となりました。
でも、そのどちらにも、
心の奥では「オブラートに包むしかない寂しさ」があったりする。
「酸っぱいぶどう」の物語のきつねのように……。
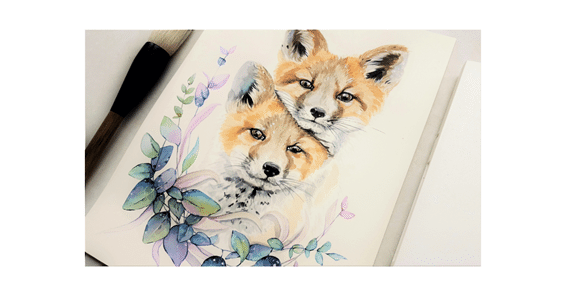
6.花言葉のまとめ
花は、言葉にできないあいまいな気持ち、感覚、
ストレートに伝えにくい情熱、恋心など、
目に見えないものまで、豊かに表現してくれます。
花ことばは、花の豊かなメッセージ性を言葉にして、
体系化、汎用化しようとした歴史の結晶ともいえます。
その歴史に思いを馳せれば、私たちが共感できて、
花のイメージを広げてくれる言葉もたくさんありますね。
そんな人々の花への願いや情熱は、
いつの時代も生き続けています。
「花のように美しく、幸せに生きたい」
「美しくもはかなく散る花に、感謝したい」
そして、花を見て満たされれば、
「この幸せを、あの人にも届けたい!」と、
その心は、リレーのようにつながっていく……。
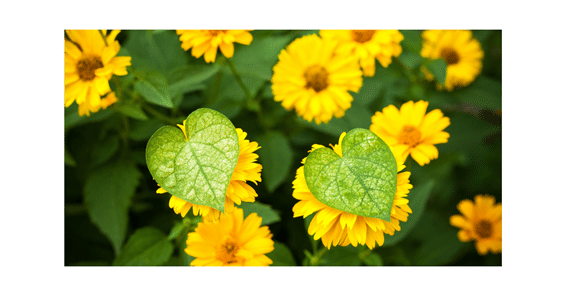
日常に追われていると、そんな幸せな心もついつい眠ってしまいがち。
時には、それを抑えて行動すべきときもあります。
でも、心が「酸っぱいぶどう」のわなに陥らないように。
たまには、時計の針をあわせて、
自分の心の中の「花ことば」をリセットしたいものです。
花ことばの本には、
素直な心を取り戻すヒントが、たくさんつまっています。
ぜひ、参考にしてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
