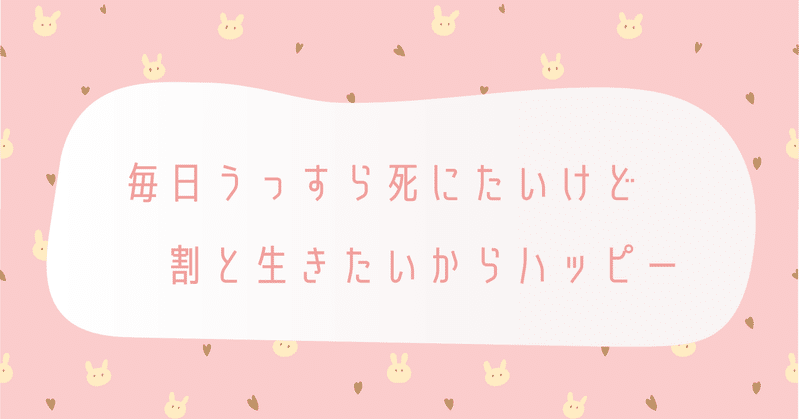
14.あれは近眼大学生のためのアプリだ。
9月に入り、少しずつ涼しくなっていく……かと思えば、そんなことはまったくなく、クソ暑い毎日が続いている。駅前の道を行き交う人々もいまだ半袖のままで、残暑どころか暑中まっただなかである。
しかしそんな暑い日でも長袖を着こむのが私のポリシーで、今日も今日とて薄手のブラウスとスカートに黒いタイツを合わせて外に出た。そして帽子も忘れない。
どこへ出かけるときでも、基本帽子は被っていく。これは顔を隠したいからとか、日焼けしたくないからとかではなく、純粋に帽子が好きだからだ。アイデンティティの一部なのである。帽子をかぶっていない日は元気が出ない。さながら水にぬれた某国民的ヒーローのように。あるいはしわくちゃの某世界的モンスターのように。
私にとって帽子はファッションアイテムでありながら必須品なのだ。眼鏡と同じである。
眼鏡と、同じ。
駅の階段に足をかけてハタと気づく。端に寄って鞄の中を漁った。そして疑惑は確信に変わる。
眼鏡、忘れた。
私は衆目の中くるりと踵を返して、もと来た道を引き返した。見られている気がして非常に恥ずかしかったが、眼鏡を忘れたまま美術館に行くわけにはいかない。虚無を見ることになる。
美術館。アートを鑑賞する場所である。展示されるアートは多岐に渡り、近年では手で触れ、耳で聴き、鼻でかぐタイプのものもある。しかしやはりいまだにアートの主戦場は視覚であり、目が見えないことには美術館の価値は半減するのである。
「え、みけこ、どうしたの」
みぃが言った。しかしこんな人中でみぃの質問に答えるわけにはいかなかったから、私は無言で帰路を急いだ。
駅から家まで徒歩十分。決して遠い道のりではない。けれど往復すればニ十分。さらにもう一度駅まで行くから三十分。ちょっと徒歩の許容範囲を超えている距離である。己の未熟さが身に染みた。
「ねえみけこ、なんか忘れ物?」
私はうなずく。するとみぃは静かになった。私たちはひたすら徒歩十分の道を歩いた。
そもそも私は眼鏡というものがそんなに好きじゃない。似合わないからだ。だから家では眼鏡をかけて過ごすけれど、出かけるときは眼鏡ケースに入れて持ち運ぶ。そうして必要なときだけかけるのだ。すると今日のように眼鏡を忘れるということも、割とよくある。もう十年以上眼鏡をかけているのにも関わらず。
小中高のころは眼鏡を忘れればなす術がなかったけれど、大学に入れば「スマホのカメラでズームして黒板を読む」という術を身につけた。ついでにそのままカメラで撮影してしまえばノートも楽に写せる。
そういうときに便利なのがカメラアプリのSNOWやSODAで、シャッター音が鳴らないから厳しい教授の講義でもばれずに板書を撮影することができる。盛れると言うが講義でも大活躍なのだ。というか板書撮影以外の用途でSNOWを使ったことがない。あれは近眼大学生のためのアプリだ。
などと無駄な回想にふけりながらわが家へと到着する。玄関の扉を開け、靴を脱ぎ、リビングへ入った。まず、いつも眼鏡を置くダイニングテーブルの上を探す。
しかし、どこにも眼鏡はない。
おかしい、と思って本棚を見る。ときどき私はリビングの本棚に眼鏡を置きっぱなしにするのだ。
本棚にも眼鏡はない。おかしい。
じゃあ自分の部屋だ。きっと机に置いたままにしたのだろう。そう考えてドアを開くも、やはりそこにも眼鏡はない。そういえば洗面所で顔を洗うときに眼鏡を取ってそのままかも。洗面所へ急ぐ。しかし眼鏡はない。
ない。眼鏡が、どこにも。
「ねえみけこ、なに探してるの」
みぃが不安げに言う。私も不安になって、弱々しい声で「眼鏡」と言った。
「は?」
「だから、眼鏡」
眼鏡は決して安い買い物ではない。なくせばそれなりのダメージだ。そもそも私は無職なのだ。収入源がない。つまり眼鏡をなくせば、母か父に眼鏡代を出してもらうしかないということだ。親の脛をかじって生きる人間のゴミのような私が、その上「眼鏡をなくしたのでお金を出してください」など言えるはずがない。もうどうしていいのかわからない。つらい。死にたい。
「いや、眼鏡って」
みぃが私の顔に手を伸ばした。
「かけてるじゃん」
ん?
顔に手を当てる。すると指先に触れる硬い感触。混乱しつつ洗面所の鏡を見た。
そこには、眼鏡をかけた私の姿があった。
「嘘ぉ……」
そんな馬鹿なことが。言われてみればこの視界は眼鏡をかけた視界以外の何者でもない。それなのに私は眼鏡をかけていることに気づかず……こんな……。
十分以上を無駄にし、体力も無駄にし、何より自分の尊厳的な何かをズタボロにし、眼鏡を探し回ってしまった。とぼけているどころの話ではない。これはキツイ。へこむ。
けれど。
「ぶっ……あっはっは! みけこ! おばあちゃんじゃないんだから!」
みぃはお腹を抱えて大爆笑している。この子どもに笑われるのは不満だった。けれど同時に、こいつが笑っているならそれでいいか、とも思うのだった。
どうせ毎日500歩程度しか歩いていないのだ。今日くらい5,000歩でも10,000歩でも歩いてやろう。そう考えると、無駄な忘れ物もそう悪い気はしなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
