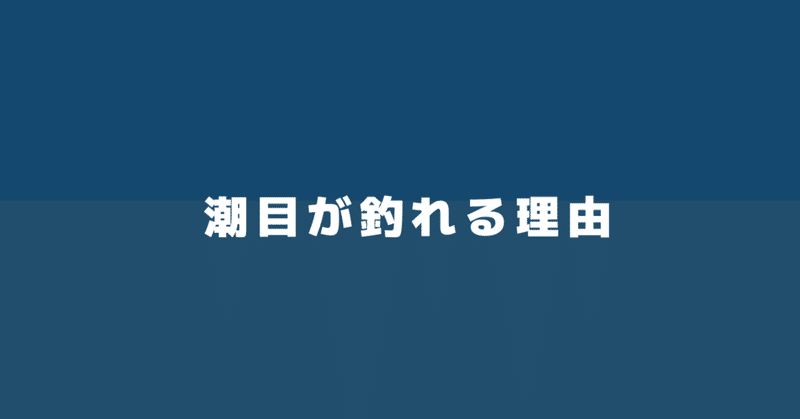
潮目が釣れる理由。
こんばんは、カツオです。
今回は、潮目が釣れる理由について
ご紹介いたします。
潮目とは異なる海流が発生するものです。
たとえば
------------------------------------------------
水温が高い海流と低い海流
水がきれいな海流と汚い海流
------------------------------------------------
などで、潮目が発生しています。
黒潮(暖流)と親潮(寒流)がぶつかってできる
宮城県沖の潮目が有名どころでしょう。

では、なぜ異なる海流がぶつかっただけで
魚は釣れるのか?
その理由は3つあります。
------------------------------------------------------
水温が違うから
酸素の量が多いから
プランクトン(エサ)が豊富だから
------------------------------------------------------
水温が違うから
魚には活動できる適水温があります。
たとえば
------------------------------------
アジ:15℃〜25℃
イワシ:16℃〜22℃
ヒラメ:10℃〜20℃
マゴチ:15℃〜25℃
--------------------------------------
と一部、論文によって異なりますが
魚の適水温は、いろいろな研究でわかっています。

潮目は異なる海流がぶつかって発生するものなので
水温が高い海流と水温が低い海流がぶつかって、潮目ができます。
よって、水温が高い海流には
高い水温を好む魚(マグロ・マゴチ)がいて
水温が低い海流には
低い水温を好む魚(ヒラメ・イワシ)がいるということになります。
なので、これら一箇所に集まる潮目には
いろいろな魚が集まります。

つまり、潮目は高い水温を好む魚と
低い水温を好む魚が行き交う、交差点のような場所なのです。
さまざまな魚種が行き交うことは
それだけエサが豊富ですし、魚の活性が高くなりやすいので
結果、釣れやすくなります。
酸素の量が多いから
潮目は海流が激しく流れるため
水がかき回されます。
すると、水中に溶けている酸素量が多くなり
酸素の泉が完成するのです。
魚は酸素を必要とする生き物ですので
酸素量が多くなっている潮目には
多くの魚が集まり
結果、釣れやすくなります。
プランクトン(エサ)が豊富だから
潮目では、海流のぶつかり合いによって
プランクトンや水中の栄養分が巻き上げられます。
プランクトンは小魚のエサとなり
その小魚は、大型のエサになるので
潮目には多くの魚が集まります。

魚にとって、潮目は
地元の人気食堂ようなものです。
魚たちは思う存分食事ができ
大きく成長することができるので
潮目という名の食堂に行くのです。
まとめ
潮目があるからといって
絶対に、もう100%釣れるみたいなことはありませんが
少なくとも、釣果に期待できるものと言えます。
潮目は、魚にとって
------------------------------------
豊かなエサ場
元気に暮らせる場所
いろいろな魚種が集まる場所
------------------------------------------------
です。
これらの理由で潮目は魚が釣れやすいとされています。
もし釣りに行かれる際には
潮目の存在を気にして、釣りをしてみてはどうでしょうか?
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
