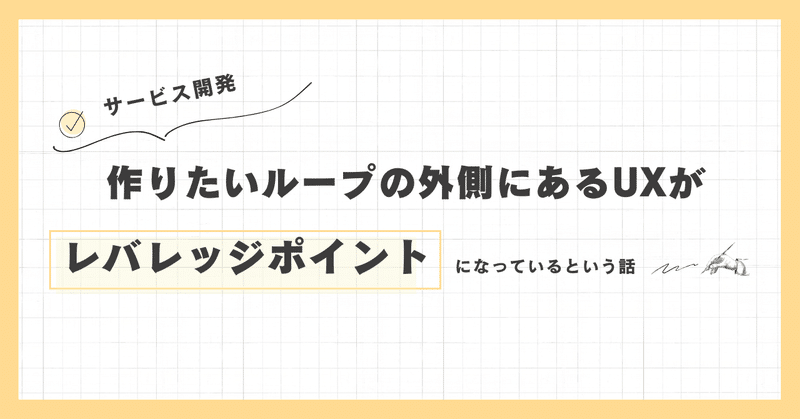
作りたいループの外側にあるUXがレバレッジポイントになっているという話
先日システム思考の本を読みました。養殖の生産管理サービス(業務システム)を企画・設計をするときにも、このシステム思考の思考フレームを持っておけると結構面白いかなと思ったので、そんなことをつらつらと書いてみます。読んだのはこの本。結構面白かったです。オススメです。
生産管理とは何か
餌の記録を付けたら、増肉係数(1kg魚を太らせるのに何kgの餌が必要か)がわかるとか、原価がわかるというのが生産管理のベーシックな構造です。もうちょっと一般化すると、「データをためていくと欲しいアウトプットが得られる仕組み・ワークフロー」という感じですかね。

アウトプットが価値の本質
生産管理サービスを作っていると、「使いやすいシステム」そのものに価値があるかのように錯覚しそうになることがありますが、そんなことはなく当然価値の本質はアウトプットにあります。「データいれて、で、何なの?」の答えに価値が宿ります。先ほどの例だと増肉係数や原価がそれですね。

データのストックには時間がかかる
ここで大きな問題があることに気づきます。欲しいデータをアウトプットを手に入れるまでには時間がかかるということです。3日間の給餌データだけでは大した分析はできないのです。浴槽に水を溜めるのと同じです。お風呂を楽しみたいなら、浴槽に水が溜まるのを待つしかありません。

以上の基本的な枠組みを図式化しておきましょう。
生産活動をすると記録すべきデータが生まれ、このデータを溜めていくと分析結果が得られます。データと分析結果の間に「//」が入っているのは時間的遅れがあるという意味です。生産活動の量が多ければ(生簀数が多い・作業量が多いなど)、データ量も多くなり、分析結果も多くなります。

データ分析と意思決定
この分析結果はそれはそれで有用ではあるのですが、大切なことは何かしらの意思決定の精度・品質を上げ、よりよい意思決定を下せるようにすることです。経験と勘にデータ分析の観点を加えるということですね。結果的に利益が増えれば、生産活動を継続・拡大できます。図に書き込むとこんな感じになります。

このループは正の方向でも負の方向でもぐるぐる回る自己強化型のループです。負の方向だとこんな感じ。
十分な分析ができない→意思決定の品質が下がる→利益が出ない→生産規模が縮小→生産活動が減少→データが減少→十分な分析ができない→…
生産管理のゴールはこの自己強化型ループを正の方向に切り替え、強化することであるともいえます。
人は怠惰な生き物
さて、分析結果が得られるまでループが回しきれればあとはループが回り続けるわけですが、問題が1つあります。人間は怠惰な生き物だということです。「ダイエットする!」と意気込んでジムに入会したけど行ったのは3回だけ…「資格試験を取るぞ!」と思って参考書を買った時がやる気のピーク…誰しも経験があるのではないでしょうか。
生産管理も例にもれず「三日坊主」の人間心理にどう抗うかが問題となります。基本的には「記録する」というのは「面倒くさい」行為だからです。ゆえに記録は簡単に溜まります。

記録すべきデータがたまれば、モチベーションが下がります。モチベーションが下がると、データはより溜まりやすくなります。データがたまりすぎるともはやリカバリは不可能です。紙の野帳に逆戻りです。この「めんどくさい」ループを図に書き込んでおきます。ちなみに緑の矢印は正、赤の矢印は負の方向にそれぞれ作用することを意味しています。

モチベーションの低下に抗う
このモチベーションの低下に抗う方法が3つあります。
1.強制力
2.期待形成
3.UX
図に書き込んでみるとこんな感じですかね。それぞれ書いてみます。

1.強制力
超簡単にいうと「無理やりやらせる」です。生産管理は業務ツールです。経営者が「やれ」ということで現場に「やらせる」構造を作ったり、業務の枠組みとして組み込んで標準化させたりすることはできるでしょう。ただ、日本の養殖業界に限ると、ここに頼るのは微妙です。家族経営のような中小規模の会社が多いので、経営者自身がデータを記録するみたいな構造になりやすいのです。現場と経営がほぼ一体のため、強制力だけでドライブさせるのはやや厳しい印象があります。
2.期待形成
分析結果が出せなくても、その結果を使って何ができるかの夢やビジョンをベースに期待値だけ先に作ってしまって、意思の力でドライブさせることはできます。たとえば僕は「生簀ごとの原価」を重要な指標に設定しています。なぜなら、養殖は生簀単位で群管理するからです。各生簀で原価を把握して利益が残るように生産・販売をコントロールできれば、事業上利益は必ず残せます。利益を計算するには、原価把握が必要不可欠です。原価をゴールにすると、分析結果を利用するまでの時間的遅れを短縮できるのもメリットです。2~3年の飼育期間が終わるまで待つ必要はありません。
3.UX
システムに人が合わせるのではなく、人が使いやすいシステムを作るというのがUXの役割です。簡単、自動、サクサク、手軽、楽…みたいなキーワードがUXで先立つのはこの「めんどくさい」ループに抗おうとしているからです。要らない機能を引き算したり、使いやすい機能群に見直したりするのもこのループを意識しているからです。
レバレッジポイントはUXにある
強制力はあまり期待できませんし、セールスが成立した時点である程度期待形成による効果も織り込んでしまっています。活用時の「めんどくさい」ループを突破するレバレッジポイントはどこにあるかというと、UX以外にありません。

記録を溜めたくなるUX
すでに書いた通りで、簡単、手軽みたいな方向でのUX改善も1つの答えです。それ以外にも「ついやりたくなる」「やらないと気持ち悪い」みたいな方向でUXを考えることもできます。
データを記録するという行動そのものに対してユーザにフィードバックを返し、行動履歴を蓄積させることでその履歴の継続性を失いたくないという損失回避の心理を使って習慣を作ります。

簡単にいうとスマホゲームのログインボーナスです。「7日間連続でログインしたからXXXをプレゼントするよ!明日はXXXXがもらえるよ!」みたいなやつですね。
この視点で作ったのが「記録履歴」の機能です。(githubの草にヒントをもらっています)

これは日々の記録状況を見える化するための機能です。1日1セルです。投与記録や斃死記録といった各飼育記録を入力していくと白から濃青に段階的に色が変わります。
9月、10月はあえて虫食いのデータにしていますが、「なんか気持ち悪い」とは思わないでしょうか。今まで使ってきた時間や積み上げてきたものが途切れたり、失われたりするのは誰もが嫌なはずです。人はリスクや失敗、損失、後悔にとにかく敏感です。何かを得るよりも何かを失うことの方を過大に評価する傾向があります。
だから過去の枠の色を変えることはできないというルールにあえてしています。サボッた記録は明確な「白枠」として残り続けます。これは「ちゃんとやればよかった」という後悔を目に見える形で残すためです。積み上げてきた濃青の「青枠」によって記録を頑張ってきた行動量や努力にポジティブなフィードバックを返すためです。
記録した内容ではなく、記録したという行動そのものを評価する機能をホームの一番上という一番いい導線に置いているのは理由があります。魚の成長や効率に向き合う前に、我々は人の弱さやモチベーションに向き合うべきだよねという意思と哲学がそこにはあるわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
