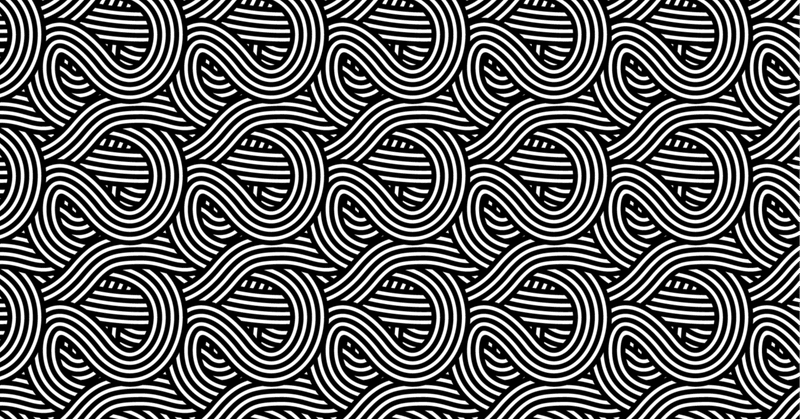
書く人が通る道
2024年5月15日(水)朝の6:00になりました。
孤独な者よ、君は創造者の道を行く。
どうも、高倉大希です。
毎朝投稿をはじめて、今日でちょうど501日目になりました。
レギュラーストレートの、デニムと同じ数字です。
note をはじめる前は、べつの媒体で毎朝投稿をしていました。
そのときは、400日くらい継続したかと思います。
これだけ書いていると、文体も変わります。
昔の文章を読み返すと、とても恥ずかしい気持ちになります。
「どんな仕事でも、とにかく毎日、一〇年やったらモノになる」と言いましたが、一〇年以上やっている人は、まず、「自己評価が正確である」と言えるんです。これはもう、前提にしたいと思います。「自己評価が正確でありさえすれば、ちゃんと仕事として成り立ちますよ」とも言えるし、一〇年以上やった人なら、思い込みをしたって、自己評価は、あんまり狂わないと思うんです。
ものを書く人は大抵、ちょっと詩的な表現に憧れを抱きます。
体言止めを多用してみたり、意味ありげな言葉で締め括ってみたりします。
ものを書く人は大抵、ちょっと昔の表現に憧れを抱きます。
徒然なるままに書いてみたり、男もすなる日記といふものを女もしてみたりします。
うまく言ってやろうという意図が丸見えで、読む側が目を背けたくなります。
すべて、自分の話です。
自分で「うまいこと言えた」と思える箇所ほど、読者を興醒めさせる贅肉だったりするものだ。ためらことなく削ぎ落としていこう。そして、まずはレシピどおりにつくる地力をつけること。隠し味を加えるのは、そのあとで十分である。
ものを書く人は大抵、読み手に訴えかけようとします。
疑問文を多用してみたり、同調を求めてみたりします。
ものを書く人は大抵、読み手の役に立とうとします。
苦しかった経験を赤裸々に語ってみたり、エールを送ってみたりします。
そもそも誰も興味をもっていないという事実が、すっぽりと抜け落ちています。
すべて、自分の話です。
ぼくが最初に教えるのは「お前の書いたことは誰も読みたくない」ということ。いまは書く機会がいっぱいあるから「書けば誰かが読んでくれて感動するはずだ」とか「すばらしい!と言ってくれるはずだ」と思ってしまう。実際は誰も読まない。
ものを書く人は大抵、人生のような大きなものを語りたがります。
ものを書く人は大抵、自分だけが気づいているという勘違いをします。
ものを書く人は大抵、賢いと思ってほしそうです。
ものを書く人は大抵、書けば伝わると思い込みがちです。
書く人が通る道。
まだまだ、道半ばです。
毎朝6時に更新します。読みましょう。 https://t.co/rAu7K1rUO8
— 高倉大希|インク (@firesign_ink) January 1, 2023
サポートしたあなたには幸せが訪れます。

