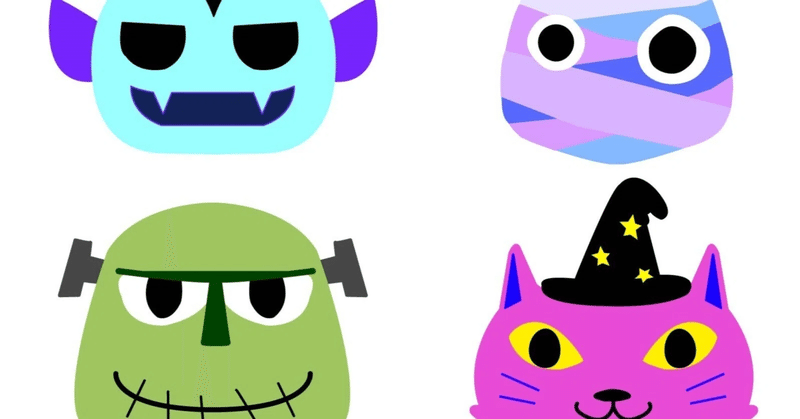
4種の法人比較(6)~意思決定方法による比較~
法人の重要な意思決定はどのように行われるか
今回は株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人の意思決定がどのように行われるかについて考えてみます。
大雑把には、以下のように整理できます。

まず、法人における重要な意思決定はいろいろとありますが、法人の根本的なルールである定款を変更したい場合を例に考えてみましょう。
株式会社の場合
会社法では定款変更については重要な意思決定であるため、特別決議として分類し、普通決議よりも重い決議要件を定めています。
株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない
本稿で焦点を当てたいのは、他の法人と比較して、「議決権」が出資額に応じて与えられているという点です。
つまり、大雑把には、株式を67%保有していれば、株主総会での特別決議を単独で可決できる権力をもっていることになります。
このように、株式会社は出資額に応じて権力を集中させることができる法人形態と言えます。
有限会社の場合
有限会社の場合、一般的な株式会社よりも定款変更決議に必要な要件が加重されています。
総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この規定の読み方としては、前段部分により、「総株主の半数以上」という要件があるため、出資額に関わらず、株主人数の半数以上が決議に賛成しつつ、かつ、株式数(出資額)における比率が75%以上の賛成必要だ、ということです。
本稿におけるポイントは、単純に出資額によって権力を集中させることなく、少額の出資者も尊重している、という点です。
例えばAが800万出資し、BとCがそれぞれ100万ずつ出資してそれに応じた株式を保有している場合、株式会社であればA単独で定款を変更できますが、有限会社の場合はA単独では定款を変更できない(総株主3名のうち半数以上にならないため)ので、BかCのどちらかの賛成が必要になるのです。
合同会社の場合
合同会社の場合はさらに重い要件が課されています。
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
先の例と同じく、例えばAが800万出資し、BとCがそれぞれ100万ずつ出資している場合、合同会社では原則としてABCの全員の同意がなければ定款を変更できないことになります。
これは、所有と経営が分離していない持分会社においては出資者相互の結び付きが強いことが想定されているため、出資額の比重に関係なく全員の同意を求めているのです。
裏を返すと法人内での意見の対立は権力の集中によって解決するべきではなく、話し合いによって解決すべきだというメッセージです。
理念は理解できるのですが、これは壮大なトラブルの種になり得ます。
例えば、設立費用が安いことに魅力を感じ、Aさんが300万円出資して個人事業主から合同会社へ法人成りしたとします。
その後Aさんは、順調に会社も大きくなり、頑張ってくれている従業員のBさんにも経営に関与してほしいと思い、株式会社でいうところの取締役相当の役職に就いてほしいほしいと考えます。
しかし、合同会社は所有と経営が分離していないため、Bさんに取締役相当、合同会社でいうところの業務執行社員になってもらうためには出資もしてもらわなければなりません。
とはいえ従業員を役員に登用するのにあまり多額の出資をしてもらうわけにもいかず、10万円だけ出資してもらい、Bさんは晴れて業務執行社員になってもらったとします。
このような事例はいくらでもありそうですが、今後、AさんとBさんの意見が対立した場合、会社の重要な意思決定ができない状態になります。
出資額は300万対10万の比率であるにも関わらず、Aさんに権力が集中しないのです。
これを防ぐためにはBさんが業務執行社員に加わる際に、定款の規定を見直して出資額に応じた議決権の概念を導入し、Aさん単独でも重要な意思決定ができるように定款の整備をすべきでした。
しかし、小規模な事業者にそのような法律知識を求めるのはあまりにも酷です。
Bさんとの話し合いが上手くいかず対立が解消されなければ会社の経営は座礁しかねません。
「法の不知は許さない」というのが法治国家の前提ですが、さらにその前提として、法が優れたものである必要があるのではないでしょうか。
一般社団法人の場合
一般社団法人の定款変更決議の要件は以下の通りです。
総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
前段部分については有限会社と同様の規定です。
しかし、前提として、一般社団法人の社員は出資を必要とせず、1人1議決権を原則としている点が大きな違いです。
また、一般社団法人の場合、出資を必要としない分、多様な人が社員(会員)となり、その数も多数になり易いという特徴があります。
言い方を変えると民主主義なわけです。
これは、社員(会員)の管理を間違えると途端に意思決定ができなくなることを意味します。
出資を必要としない分、執行部と人間関係の薄い方も社員となり得ます。
そうなってくると、当初はコミュニケーションが取れたけれども、熱が冷めると団体と距離を置き始める会員が増えてくるという現象が当然のように起こります。
想像してみてください。全会員の3分の2以上をアクティブな状態に保てますか?
また、各会員にしてみると、法人の活動に生活(収入)が依存していないことが多くなってきます。
これは、執行部の意見に表立って反対する心理的なハードルが低いことを意味します。
そして反対意見の波は同じ論理によって多数の会員に伝播するかもしれません。
一般社団法人の運営では将来的にこのようなリスクがあることを踏まえ、適切な会員管理を行うことがとても重要になってきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
