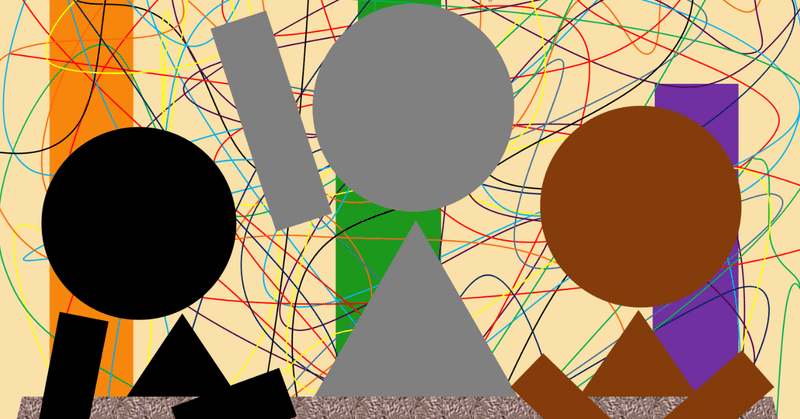
雑記5 最近観たホラー映画5ーー「CUBE」「ヘルレイザー」ーー
「CUBE」はわりと面白いし、なかなか独創的である。7点くらい。施設に閉じ込められ、機械の罠を避けつつ脱出を目指すというネタはポー「陥穽と振子」に見られる着想だが、「CUBE」はそれにパズル要素を加えた点が新しく、テレビゲーム的である。スラッシャーやモンスター、幽霊、悪魔がホラー映画の主流であるため、機械による恐怖というのは珍しい趣向だろう。ストレスフルな状況で目まぐるしく変化する人間関係も見どころの一つで、キャラによっては序盤と終盤で印象が百八十度異なる。ところで、罠の有無を見抜くために三桁の因数分解をしなくてはならない、というような字幕があったが、あれは素因数分解の間違いではないのか? それともアメリカないし数学界では、因数分解という語で素因数分解を意味するのが普通なのだろうか? また因数と罠の対応関係について明確に語られていないが、レヴンはいつ、どのような経緯で気がついたのだろう? wikiによれば因数を一つだけ持つ数が紛れている場合に罠があるらしいが、話の展開からでは、そんなことは分からない。今まで通ってきた部屋の数字と罠の有無を彼女が全部覚えていた、というのが筋の通った推理だろうが、果たして。キューブの移動ルールも不明瞭だ。彼女は正確に移動規則を導き出していたが、どう計算したのか? 導出前に一度だけ、箱の動作を見るシーンがあるので、そこから求めたのだろうか? 確かに四つの扉に記された数字を全部覚え、移動前後で比較すればその時の移動量は出せるが、二回目、三回目と同じ動きをする保証はない。もう少し複雑なルールで動いている可能性もあるのだ。まあ、作中でそんな細かい話をできないのはわかっているから、これは嫌味な指摘である。話は変わるが、アメリカ・ホラーにはおぞましき場所(Terrible Place)がしばしば登場しており、「CUBE」もその一種と言える。おぞましき場所とは、踏み入れると災厄に見舞われる場所のことで、「悪魔のいけにえ」、「シャイニング」、「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」、「パラノーマル・アクティビティ」、「死霊館」、「インシディアス」、「ゲットアウト」、「ウィッチ」等々、類例には事欠かない。多くの作品で恐怖を与える主体が判明し、大抵は殺人鬼か悪魔である。また殆どの場合、登場人物は自分の意思でその場所に踏み込んでいるため、恐ろしい目に遭うのは、多少なりとも自業自得な面がある。一方、「CUBE」では機械を操っている人物、つまり恐怖を与える者が誰なのか最後まで分からない上、キャラクターは無理矢理キューブへ連れて来られている。これら二点は他作品にはない本作独自の要素で、不明ゆえの恐怖を描いていると言えるだろう。
セノバイトの縦横無尽な暴虐を期待して観始めた「ヘル・レイザー」だったが、一作目はあまり活躍の場面がなく、拍子抜けしてしまった。筋は整っているのだが、正直セノバイトがいなくても話が成立するため、何のためにパズルボックスの設定があったのかよくわからない。6点くらい。ただ、セノバイトやパズルボックスのビジュアルは秀逸で、これだけで高く評価してあげたい気にもなる。どうやら2と3にはセノバイトの大立ち回りがあるようなので、暇を見つけて鑑賞したい。強烈なインパクトを残すセノバイトだが、本作における悪役は彼らではなく、ヒロイン、カースティの伯父フランクである。地獄の門を開いてセノバイトを呼び出した彼は魔界へ引きずり込まれたものの、人の姿を失いながらも帰還を果たし、人の生き血を啜ることで徐々に元の姿を取り戻す。人血が復活のキーとなる作品といえば「血塗られた墓標」が有名だが、この作品のアーサーが血を吸った瞬間、生来の美貌を取り戻すのに対し、フランクは人体模型のような姿を経てから戻るため、よりグロテスクだ。他には『墓場鬼太郎』に出てくる妖怪・夜叉も血を得たことで長き眠りから覚め、催眠術で人を操って獲物を捕らえようとする。「ヘル・レイザー」に登場するパズルボックスの元ネタは恐らくパンドラの箱で、双方とも開けたら不幸が引き起こされる。パンドラの方では、開封と同時に数多の厄災が飛び出すが、パズルボックスから出てくるのは究極の快楽であり、やや設定が異なる。とはいえ、本作の快楽というのはセノバイト視点の認識であり、普通の人間にとっては苦痛でしかないのだから同じといえば同じか。余談だが、ピンヘッドは『HUNTER×HUNTER』に出てくるイルミの元ネタらしい。まあ、イルミというか、彼の変装していたギタラクルの元ネタだろうが。そういえば「Fate」シリーズのギルガメッシュは鎖を召喚して操作する能力を持っていたが、ピンヘッドにインスパイアされたのだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
