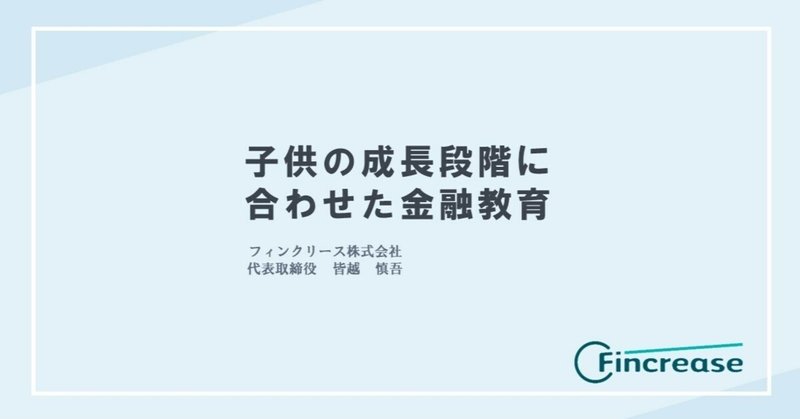
子供の成長段階に合わせた金融教育
みなさん、こんにちは共同代表の皆越です。これから定期的にブログを更新していくので、見て頂けると嬉しいです!
まずは、当社について少し紹介させていただきます。当社は、「従来にないIFA法人」を目指して創業しました。その核心には、「伴走型の資産運用モデル」があります。このモデルでは、資産を増やしていくことはもちろん、資産が次世代に継承される相続まで、生涯にわたるサポートを目指しています。
この道のりの中で、多くの方が直面する課題の一つが「子どもの教育」です。この大切なテーマに光を当て、深掘りしていきたいと考えています。特に、富裕層や成功を収めている方々が自分の子どもたちにどのような教育を施しているのか、参考にしている教育方法は何か、という点は多くの方が気になるはずです。
そこで、自身が学んだことを中心に「子育て論や教育論に関しては、当ブログを参照してほしい」と言われるよう、教育に特化した情報発信を行っていきます。もちろん、教育に関する価値観や思想は多岐にわたりますが、当ブログを一つの情報源として楽しんでいただければ幸いです。
そして、今回がその第1回目の投稿となります。今回は、当社のビジネスの中心である「資産運用」と「マネーリテラシー」にスポットを当てお伝えします。
今回は全体像の把握として「子供の成長段階に合わせた金融教育のアイディア」をご紹介します。金融教育は、ただお金を貯める術を教えるだけでなく、生活における賢い選択をする力を育むことにもつながります。それでは、年齢別に見ていきましょう。
幼稚園:遊びを通じて学ぶお金の基本
モノを大切にする
お子様におもちゃを限られた数だけ与え、それぞれの価値を理解させましょう。また、おもちゃの交換会を開くことで、所有するものの価値を再認識することが期待できます。「欲しいものリスト」作り
一緒に欲しいものをリストアップし、それに対する優先順位を話し合います。優先順位を考えることで、自分の意思で選択する力が育まれることや我慢を学ぶ良い機会になります。
幼稚園や保育園の時期は、遊びを通じて学ぶのに最適な時期ですよ。この段階でお金について直接教え込むのはなかなか難しいです・・・なんならクレジットやPayPayを出せば全てのモノが手に入る感覚でいるかもしれません。その中で物を大切にする心や、欲しいものが手に入らないときの感情の扱い方を学ぶのが大切になります。
我が家では、野菜を一緒に育てて収穫するまでの苦労や喜びを通じて、努力して得られる成果の価値を共に学びました。このことについても具体的にお伝えしていければと思います。
小学校低学年:身近な経済活動を理解する
お買い物ゲーム
実際のお買い物を模擬体験できるゲームを用意し、お金の使い方と計算スキルを養います。
私が過去開いたイベントでは塗り絵を販売してイベント内の通貨でやり取りして他の塗り絵を買う企画をしましたが
「自分が作ったモノに価値が生まれてお金と交換する。そのお金を自分が選んだ価値あるモノと交換できる」という学びになったことを覚えています。

家族での貯金プロジェクト
特定の目標に向けて家族で貯金をする活動は、共有目標に向かう喜びと貯蓄の大切さを学べます。旅行貯金なんかは大人もワクワクしながらできるのでいいですよね。
小学校に入学すると、子どもたちは数字に対する理解が深まります。この時期に、「お金」という概念を導入するのに適しています。シンプルな家計簿をつけさせたり、小銭を使った計算問題を出したりすることで、お金の基本が身に付きます。また、地域内での小さな買い物を任せることで、実際のお金の流れが体験できますよ!
小学校中学年:社会とのかかわりを深める
地域の職業人、経営者インタビュー
地域のさまざまな職業人を訪ね、仕事とお金の関係について学びます。また、知り合いに経営者がいる場合は子供にインタビューさせ大人との関わりを広げる機会にもなりますね。自分のビジネスプランを作成
レモネードスタンドなど、シンプルなビジネスを計画させ、実際に運営することで稼ぐことについて考えるようになります。
この段階で子どもたちは、自分の行動が家族や地域の経済活動にどのように関わっているかを理解し始めます。地域の企業を訪問したり、家族経営のお店を手伝ったりすることで、働くことの意味やお金を稼ぐプロセスを学びます。また、クラスでの模擬店や市場を通じて、供給と需要の概念を楽しみながら理解していく年代です。
小学校高学年:経済の仕組みと生活設計
ライフプランニングの基礎
将来の夢を描き、それを実現するための貯蓄や学習が必要な理由を話し合います。投資シミュレーションゲーム
バーチャルな投資ゲームを通じて、資産運用の基本を学びます。興味がある分野の企業について2週間毎に株価を追い「株価が動いた理由」を一緒に探るといいでしょう。正解を見つけるというよりは仮説をたてる楽しさや、ニュースによってどんな動きをするのかを感覚的に知ることが大切になります。
この時期になると、子どもたちはより複雑な概念を理解できるようになります。お小遣い帳の管理をさせ、自分の収入(お小遣い)内でどうやって欲しい物を手に入れるか、計画的な消費の重要性が分かる時期です。また、簡単な投資ゲームを通じて、お金を増やす方法とリスクについて学び始める良い機会となります。
中学校:実生活での金融知識の応用
契約と借金の勉強
サブスクリプションやスマホの契約など、日常生活で出会う契約の概念と借金について伝えることや、決済するさいは一緒に立ち会うことで自分毎になります。家計簿アプリの利用
家計簿アプリを使って、実際に自分の支出を管理させることで、収支のバランスを理解させます。マネーフォワードやZaimがオススメです!
中学になると、子どもたちはさらに自分の周りの世界に興味を持ち始めます。この好奇心を利用して、銀行口座の開設や、簡単な株式投資のシミュレーションなど、現実の金融活動に近い体験と知識が実生活で役立つようになります。
高校生:将来に向けた経済的自立へ
ライフプランニング
将来の職業選択や生活設計をテーマに親子で話し合い未来について深く考える時期です。税制と社会保障の勉強
大人になってから直面する税金や社会保障について伝え、社会の一員としての自覚を育みます。
高校生になると、子どもたちは将来について真剣に考え始めます。大学の学費や将来の職業について話し合う中で、金融計画の重要性に気づいていきます。また、実際の投資方法や、保険、税金など、成人になってから直面する金融の問題について、基本的な知識を一緒に学びながら備えるといいでしょう。
まとめ
金融リテラシーはみなさまご存知の通り一朝一夕に身につくものではありません。子どもたちが成長する各段階で、理解度に合わせて知識を深め、経験を積ませることが重要です。このプロセスを通じて、子どもたちは自分と社会の関わりを理解し、将来的に経済的に自立し、社会で生きる力を養うことができます。
子どもたちが自分の価値観を大切に選択し大人へと成長する姿を見るのは、親にとって何物にも代えがたい喜びですよね。家族で一緒に、この大切な学びの時間を楽しみましょう!
おわりに
子どもの教育に関しては、「正解」というものが存在しないと私は考えています。皆さんとの交流を通じて、少しでもお子さんの未来に役立つ気づきやインスピレーションを提供できれば幸いです。
もっと詳細に聞きたい!なんなら語りたい!
そんな方はX(旧Twitter)やFacebookから連絡ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
