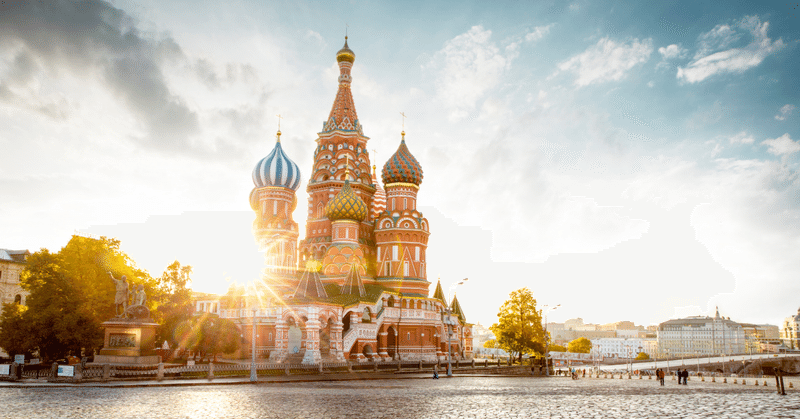
『ロシア語だけの青春』
さいきんロシア語のことをnoteに書くことが増えてきました。
そろそろ「ロシア語」で新たにマガジンを作ってまとめておこうかと思います。
以前から著書を何冊か読んだことがある、黒田さんの本。
今回も図書館で借りてきました。
何がきっかけで知ったんだっけな…(すでに記憶にない)
『ロシア語だけの青春』
黒田 龍之助 (著)
この本では、筆者がロシア語を学ぶために高校生のときに出会った「ミール・ロシア語研究所」でロシア語を学んできた過程を詳しく描写されている。
なぜロシア語を選んだのか。
ドイツ語やフランス語、中国語ではなくロシア語だったのか。
わたしにも思い当たる部分があって、なんだか嬉しくなった。
大学の第二外国語を選ぶとき、メジャーどころではなくマイナーなロシア語を選んだ理由。基本的に「みんなと同じ」は選びたくないという気持ちがあったから。
わたしには2学年上の姉がいて、姉はなんでもわたしより一歩先をゆく存在で、小中学校のときは常に全ての面においてわたしは姉に勝てないことを悔しくおもっていた。
英語にかんしては、わたしのほうが一歩先にエイやっと国外にでてイギリスで10ヶ月すごしたおかげで、英語だけは負けてない(勝ち負けではないのだけれども)というある種の優越感みたいなものはあったが、大学で英文科に進んだ姉と英語で勝負するのは控えようと思っていた。
もっとも、わたしは高校2年でイギリスへ、姉はその直後に大学生でアメリカ(オレゴン)へ短期留学をしたので、同じ英語でもちょっと違うよね、という感じ。同じ「英語」というくくりでも、わたしはアメリカの英語がいちいち下を巻く感じがいやらしくて聞きとりづらいと感じていたし、姉はイギリス英語がスパッスパッとしていて聞きとるのが難しいと言っていたと思う。
大学生になっていた姉は第二外国語でドイツ語を選んでいて、わたしにはちっともわからないドイツ語を家でもぶつぶつと発音練習していたのを覚えている。と同じくらいの時期に、父は中国語の勉強をしていた。仕事で必要だったのだと思うけど、家にいてもラジオで中国語講座を聴いていたのがわたしの耳にも聞こえていた。四声の「マー」「マァ」「マー」「マァ」を何度聞かされたことか…
そんなこともあって、わたしはこれらの外国語は選ばないことにした。
身近にすでに学んでいる人がいるなら、分からないことがあったら教えてもらえるじゃん、ではなく、身近な人だからこそいちいち口出しされたくないという気持ちの方が大きかった。
どうせなら全然だれもやっていない言語がいい、なんて思うわたしはひねくれてるかなと思ったけど、この本の著者である黒田さんも同じようなことを考えていたと知ってなんだか嬉しくなった。
身近に学習している人がいない言語がいい、というのは子どもの頃の苦い経験から。
小学生の頃から、学校の勉強で分からないことを親に教えてもらおうと思ったことなどなかった。でもやむを得ず、ということもあって、夏休みの宿題かなにかで音楽の課題で「短調と長調の違い」とか「『半音』と『全音』とはどういうこと?」って分からなくて母親に聞いたことがあった。母はピアノを使って教えてくれたのだけれど、学校で教えてもらうのとは全く違う説明をされたわたしは余計に混乱してしまった。分からないんだけど…という反応をしたら「どうしてそんなことも分からないの」みたいな言い方をされたのが、癪にさわったのだった。母は純粋に自分の得意分野だから、教えてあげるね、という気持ちだったんだろうけど、わたしは自分が分からないことが悔しかったんだろう。
身近な親だからこそ、反発してしまうモノだと思う。
分からないことは先生に聞くのが一番、だと思った。
ちょっと話がそれてしまった。
外国語のはなし。
なぜそんなに外国語に興味を持ったのか、は定かではない。けれども、海外の映画をみたり本を読んだりしているうちに、わたしもわかるようになりたい、と思ったのは確かだ。
大きかったのは、小学生のころから好きだった体操の影響だと思う。強い国といえば、中国、ソ連、女子ならルーマニア。憧れのあの選手が話している言葉を理解したい、と思ったのだ。そうなるとやっぱり、ロシア語か。あの不思議な文字も読めるようになりたい、と思ってきた・
大学進学の際に、第二外国語が選べることを知った。
先に書いたとおり、ドイツ語、中国語は却下。この二つのほかに、フランス語を選ぶこともできたが、ロシア語を選んだ。理由は単純で、マイナーであろうロシア語を選ぶことに魅力を感じたことと、フランス語ならこの先何かしらの方法で勉強するチャンスがありそうだと思ったから。
じっさい、大学在学中にわたしは公文式の通信教育でフランス語をしばらく勉強した。特に何かを成し遂げたかったわけではなくて、英語を勉強しているうちに、これはフランス語からきてるね、みたいな単語がたくさんあったから英語の親戚みたいなものだと思っていて、興味を持ったから。またそのうち機会があれば勉強してみたいとは思っている。
大学に入ってから、やはりロシア語を選ぶ人は少数派だと知って嬉しくなった。教師の目が行き届くからサボれないと思う人もいただろうけど、わたしはそうではなかった。これはみっちり分からないことも聞けるしラッキー、と思っていた。そしてわたしと同じようにロシア語を選ぶ学生というのは、ちょっと個性的な人が多かったみたいだ。
1回生の時は第二外国語は必修科目で、2回生以降は選択科目になったがわたしは迷わず選択した。人数もそこでグッと減って、上回生で選択科目になってからは教室ではなく、教授の部屋で授業が行われていたんじゃなかったっけ。
などなど、この本を読んでいたらいろいろと思い出して懐かしくなった。
ロシア語に限らず、だとはおもうけど外国語の習得は難しい。
英語と同じアルファベットを使う言語だったとしても、難しい。とはいえ、全く別のアルファベットが出てくる言語はもっと難しく感じた。でも、難しいからこそ、わかったときの喜びもひとしお、なのだ。
・・・
なんてことをこの本を読みながら再確認した。
本当はもっともっと感じたことはあるけれど、長くなりそうなので今日はこの辺で止めておこうと思う。
でも最後に…
姉に負けたくない、という一心でマイナーな外国語であるロシア語を選んだんだけど、もし姉が先にロシア語を選んでいたらどうなっていたんだろう、とふと思った。
姉もわたしも一緒に体操教室に通っていて、体操大好きだったからなぁ。
とはいえ、体操マニア度はわたしのほうが上だったかも知れない。それに、日の当たらないところを好むわたしとは対照的に、姉はもっと日の当たるところに出ていく傾向がありそうなので、そもそもロシア語は眼中になかったのかも知れないなぁ、なんて思った。そんな姉は最近は熱心に中国語の勉強をしているらしい。仕事で使うんだとか。父と同じだね。父と中国語の話で盛り上がるんだろうか。共通の話題があるというのは、いいことだ。
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
