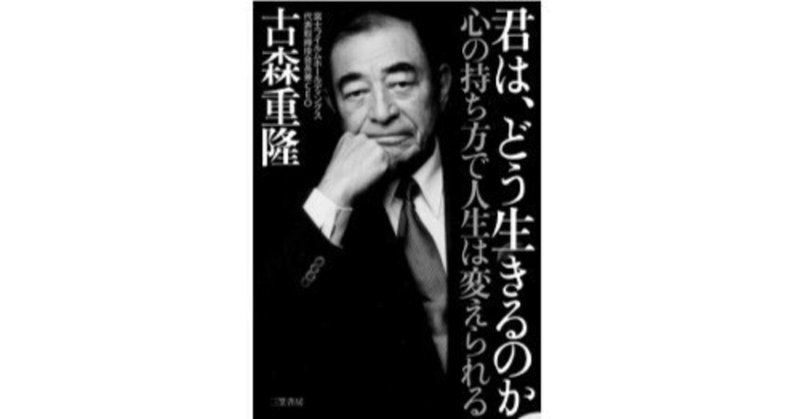
古森重隆著(2014)『君は、どう生きるのか』株式会社三笠書房
トップの考え方を知ることができる本
以前一度読んだことはあるのですが、やはり今日の日本は、現代への転換が上手くできなかったのかと思うと、再度、当時のフィルムカメラがデジカメの台頭で衰退していく中にあって、どう企業を存続していくのかという点での考え方というのを学ぶ必要があるのだろうと思い再読した。
富士フィルムの事業転換は経営学では今でも注目されていますが、その転換点にいた経営者の考えを知る上では、本書は大変参考になると思う。
その都度ベストを尽くせば、それなりに自分に返ってくると説いているが、昨今の従業員はベストを尽くす以前に、単に仕事を消化しているだけのようにわたしも感じている。努力は裏切らないと著者も書いているが、まさに努力無しには成果が期待できない。
本書のエピソードで、著者は営業出身であり、自社製品が売れないのは製品が悪いといわば人のせいにしていたとのこと、そこで当時の社長に「ただ、君はそのために何をしたのかね?」と聞かれ、お客様のニーズをしっかりと研究や工場の技術者に伝え、また技術者を実際に利用者に会わせるなど、著者が自分でできる部分でベストを尽くすという能動的な行動で、変化を与えるという点で「実際に行動にうつす」ことの重要性というのを早期に理解していった点は著者の行動として根付いていったのだろう…
そしてなりより「自分の頭で考え抜く」というのを実践していることは素晴らしい。また家庭環境として両親から「曲がったことはするな」「卑怯な真似はするな」「正直であれ」「嘘をつくな」「負けて泣くな」「弱い者いじめをするな」「人様に迷惑をかけるな」「姿勢を正しくせよ」などは、著者に限らず日本の多くのご家庭では耳にタコができるくらい聞かされると思うのだが、それを愚直に守ること、すなわち行動として実証することができる人は意外と少ない。わたしも40年、社会人として生きてきたけど、これらが守られない人を多く見てきた… 人間は自分のこととなると他人を蹴落としても優位に立とうとする輩が多く、なかには専門職倫理すらまもれないで平然としている人も多いのが現状。その意味では頭では理解しても、それが行動に出るか出ないかが人間としての質の違いになるのだろう…
著者が文学作品を読み、ニーチェで開放感を感じたとのこと。やはり読書は人を育てるのかも知れない。世の中最大の敵は「自分自身」であることは多くの経営者の自伝でも語られている共通項だと思う。本書では人間力のシグマ(総和)という表現が出てくる。あらゆる人間の知覚から情報を受け取りそれを自分で考え抜くことが重要と説いている。それらの情報というのは、変化を敏感に感じ取る「鼻」、事実を見逃さない「目」、聞き取る「耳」等、全てを働かせるということ。何処か身体論にも似た考えだが、それらの総合という考えが付け加わった点が面白い。その人間力のシグマが決断力の土台になるという理解。リーダーとはそれを備えているということにほかならない。
本書は、さらに健康に関する記述もあるが、本書でわたしが重要に思うことは、日本企業が抱えている課題として、キャッチアップ型のビジネスモデルから抜け出せていないという点。わたしも未だに抜け出せていないと思う。自分たちで道を切り開いていこうとする意欲が希薄である。著者が言う「新しいものを創り出す想像力」「未知のものに果敢に挑戦していく冒険心」まさに日本にとって欠けている部分である。なかなか現代にも通じる視座があり勉強になった。
さて、本書を読もうと思ったきっかけの企業存続における事業転換についてですが、本書を読むとその事前準備がなされていたことがよく理解できる。事前に未来を読み、それに備える手法を施しておくことができる経営者は強い。この部分は、ぜひ実際に読んでみて各々感じてほしいので、あえて記載をしないことにする。今でも入社したての社会人からベテランまで、一読していて損はしない本だと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
