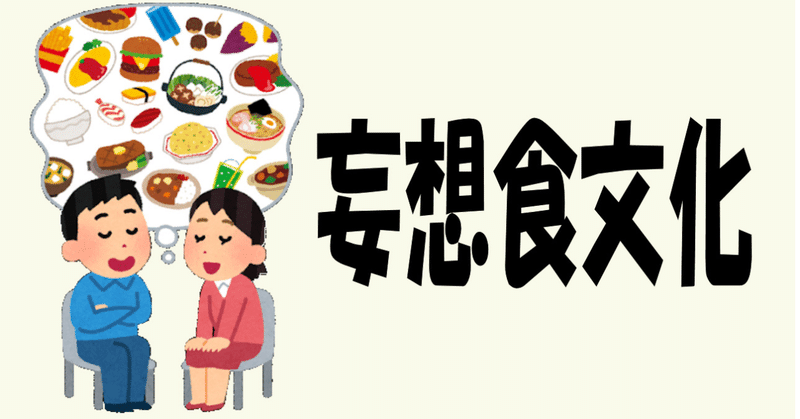
ぬく寿司は冬のご馳走

寿司と言えば日本中で握り寿司全盛ですが、家庭で作る寿司は関東では「ちらし寿司」、関西では「ばら寿司」ですね。世間では「ちらし寿司」と「ばら寿司」は呼び方の違いだと認識されているようですが、「ちらし寿司」と「ばら寿司」は違うものです。
関東はちらし寿司
ちらし寿司は寿司飯の上に様々な魚介類の切り身を乗せた「乗せ寿司」です。たくさんの寿司ネタが乗っていてとても豪華です。握り寿司から派生したので、本来は赤酢の酢飯です。

関西は「ばら寿司」
「ちらし寿司」は上に具をちらすので「ちらし寿司」なのですが、「ばら寿司」はなぜ「ばら寿司」なのか?
伝承料理研究家の奥村彪生氏によると、昔は酢飯に味付けした具を混ぜ合わせ、重しをしてしばらく味をなじませてから、木じゃくしで起こし、ばらして食べたから「ばら寿司」だそうです。ちらし寿司との違いは作り方だけではありません。混ぜ込む具はちらし寿司のような生の魚は使わず、錦糸玉子・干椎茸の煮つけ・かんぴょう・酢蓮根・茹でた海老・焼穴子等を混ぜ(錦糸玉子は混ぜ込まずに乗せる場合もあります)込みます。種類としては魚介類よりも野菜の方が多くなります。押し寿司から派生したので、酢飯は押し寿司と同じく、色をつけない甘めです。
祭り寿司
「ちらし寿司」と「ばら寿司」は違うものだと分かっていただけたと思いますが、さらに第三の寿司があります。岡山県の祭り寿司です。祭り寿司は具を混ぜた寿司飯にさらに魚の切り身などの具を乗せる「ばらちらし」です。この豪華なお寿司の誕生は江戸時代初期にまで遡ります。
時の岡山藩主である池田光政公が「おまえら贅沢過ぎじゃー!
そげんことじゃあ、おえまーが」「めしとおかずと汁がひとつずつでえーんじゃー!」と言ったことがきっかけです。これに反発した岡山の町民達は、魚や野菜を酢飯の中に混ぜ、さらに上にも乗せてしまいました。「これでめしとおかずがひとつじゃー!」「もんくありゃせんじゃろー!」「まだ汁がくえるでー」
祭り寿司誕生秘話でありました。
ぬく寿司
最後に、京都と大阪の冬の御馳走を紹介します。それは「ぬく寿司(一般的には蒸し寿司と呼ぶ)」です。ばら寿司を蒸したもので、湯気がたっている温々をいただきます。蒸すことで酢の風味が優しく、まろやかになります。筆者が子どものころは、繁華街の寿司屋さんの店先にはシューシューと水蒸気を吹き上げる大きな蒸籠があり、店先を通ると甘酸っぱい香りがしました。風が冷たい町を歩いて帰る時に「ちょっと小腹がすいたさかい、ぬく寿司でも食べていこか」なんて祖父が言うてくれたら飛び上がって喜んだもんです。このごろは店先の蒸籠なんか滅多にお目にかかりまへんけど、ぬく寿司を食べたら祖父母の顔を思い出しますなぁ。あれ、なんや大
阪弁がでてしもた…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
