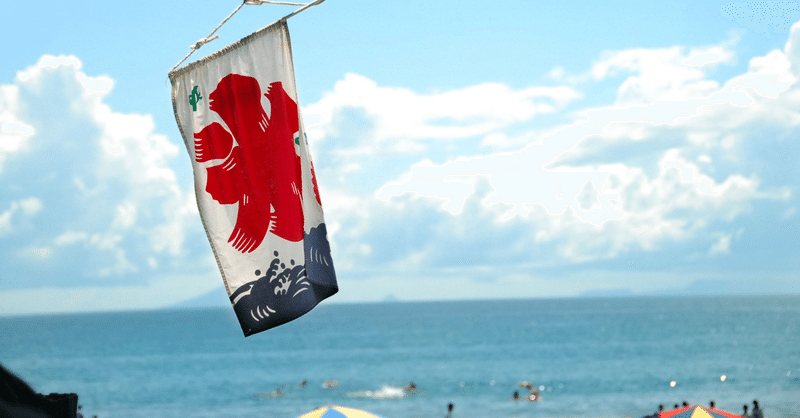
第六十一話 わだつみの宮
昼食は海の家で食べることにした。おにぎりは一人一、二個しか行き渡らず、海水浴場の近くには飲食店もコンビニもない。海水浴場は西側を川に阻まれた道的な行き詰まりで、こんな立地で成り立つ店は、海の家くらいしかない。まだ美緒が海から上がっていなかったが、真帆曰く、車の中に食べ物があるから大丈夫、とのこと。
海の家の前には、貸しボート、貸しイカダ、三色パラソル、サマーベッドなどがごちゃごちゃと並べられ、骨董市のようだ。「ブギーボード」 とダンボールの札に書かれたスポンジ素材の板は、ボディボードとビート板の中間みたいな見た目で、素人にも扱いやすそう。入り口の鉄柱の袂に置かれた水色の樽は足洗い用。座敷利用者は樽の水で足の砂を落として、砂の通路の両側に並べられたすのこの上を歩くらしい。
浜辺の少ない人出のわりには、店内はそこそこ混んでいた。辺鄙な土地であることが、かえって海の家に幸いしたようだ。
四、五分待たされて席につくと、西脇がセルフサービスの水を汲みに行った。真一はぐるっと周りを見回す。天井を見上げると、鉄骨の梁にパステルカラーの丸提灯がいくつも吊り下がり、ビアガーデンのような雰囲気。木製のテーブルとイスは手作りで、安っぽい花柄のビニールクロスが掛けられてある。厨房の窓口の上には、生ビールと冷やし中華のポスター。手書きのメニューを目で辿っていくと、ラーメン、カレーライス、焼きそば、おでん、イカ焼き、焼きはまぐり――そばやうどんがないのに、カツ丼があるところが不思議だ。おしゃれな海の家が増えてきた今日この頃だが、海の家 「わだつみの宮」 は、時代の流れを一顧だにせず、昔ながらのスタイルを貫いている。
しばらくして、真っ黒に日焼けして、鶏ガラみたいに痩せた老人が注文を取りにきた。どこの親戚が駆り出されてきたのか、ランニングシャツにステテコという、およそ客商売をやる人間としてあり得ない格好。七人分の注文を一気に告げようとした久寿彦に、ボールペンでクリップボードをぺしりと叩き、もっとゆっくりしゃべれ、と荒っぽい土地の言葉で叱りつける。これまた客商売をやる人間にあり得ない言動だ。久寿彦は謝るしかない。世間の常識を軽く超越したこのお方こそ、わだつみの宮の龍王様ではあるまいか、と真一は思ってしまった。
しかし、真一を含む何人かが頼んだラーメンは、予想に反しておいしかった。スープを一口含んで広がった味は、素朴ながら未体験のもので、みんな顔を見合わせたが、最初に久寿彦が煮干しの味だと気づいた。カツ丼に付いてくるみそ汁ならまだしも、ラーメンのスープで煮干し出汁というのは意外で、気づくのに時間がかかってしまった。
◇◇◇
「あんなラーメン、初めて食べた」
梅雨入り前の暗い空を、物悲しいセッカの声が横切っていく。真一は短くなった煙草を、ベンチの脚にくくり付けられた空き缶の吸い殻入れに放り捨てた。木柵の先の水面にぽつぽつと広がる波紋が目に留まり、雨が降り出したかと思ったが、アメンボが作る波紋だった。
「俺は一度食べた記憶がある。ずいぶん前のことだから、どこで食べたかはっきりと思い出せないけど。でも、スープが絶妙でうまかったな」
「あのラーメンと比べたら?」
「それはちょっと……どうかな……」
久寿彦は苦笑いして、何かをごまかすように顎をさする。
まあ、そうだろう。真一も 「わだつみの宮」 のラーメンを街なかで食べたら、さして美味しいとは思わないだろう。あのラーメンが美味しかったのは、海というロケーションと泳いだあとという状況があったからだ。あっさりしたスープは冷えた体に優しく染み渡り、内側から体を温めてくれた。ただ、そうした事情を抜きにして評価すれば、味は平凡でこれといって褒められる点はない。煮干し出汁という発想だけに驚かされた。
「近くに煮干し工場があったし、知り合いの伝手か何かで安く仕入れられるのかもね」
ちなみに、煮干し出汁のラーメンは青森にもあるようだ。団地に住んでいた頃、同じ棟に青森出身のおばさんがいて、雪国出身の両親と仲が良かった。よく部屋に遊びに来て母親とお茶を飲んでいたが、その人が珍しいラーメンの話をしていたことを覚えている。
◇◇◇
帰りも大陸的な一本道をひた走った。田んぼは西日を浴びて黄金色に輝き、ぼんやり反射した光が疲れた体を心地よく包み込んでいた。バンのステアリングを握っていたのは益田。行きに高速の区間を運転した真一はお役御免で、ゆったり車に揺られていた。道の両側はずっと田んぼだけが広がっていたわけではなく、トウモロコシ畑の中を突っ切る区間もあった。青々とした畑の真ん中に直売所の掘っ立て小屋を見つけ、空き地に車を停めて、焼きトウモロコシを買って食べた。海の家のラーメンもそうだったが、泳いだあとの冷えた体には、スイカやかき氷などよりも、熱いトウモロコシのほうが嬉しかった。みりん醤油の香ばしい匂いに食欲を刺激され、真一はつい二本も買ってしまった。
空き地に溢れるキリギリスの声が、本格的な夏の到来を告げていた。空は梅雨の名残か、少しだけ紫灰に濁っていた。トウモロコシ畑がどこか懐かしい、青臭い匂いを放っていたことを思い出す。真一は空の青と畑の緑しかない景色を見渡しながら、今年の夏はどんな夏になるのだろう、と期待に胸を膨らませた。
◇◇◇
「あれから地元に辿り着くまでの間の記憶がまったくない」
「お前、帰り道で爆睡してたもんな」
紺色の店のバンに乗って、空き地から道路に出たところまでは覚えている。だが、そこから先の記憶がぶっつり途切れている。トウモロコシ畑を抜けたら、また田んぼの景色が延々と続くはずだったのだが……。
「あんなに深く眠ったのは何年ぶりかな」
寝苦しい夏場は夢を見ることも多い真一だが、あの時は夢の断片すら覚えていなかった。
「五秒くらい眠ったと思ったら、もう水場前の駐車場に着いてて。トウモロコシ畑からワープしたかと思ったよ」
「五秒は言い過ぎだろ」
「いや、ホントだって」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
