
家族志向のケアの概要と実践@東京北医療センター
10月1日に東京北医療センターにてワークショップを行いました。
東京北医療センターは東京北区赤羽にある地域医療支援病院です。
https://www.tokyokita-jadecom.jp/
地域医療振興協会の基幹病院でもあり、多くの医療スタッフを日本の各地(特に僻地)へ医療支援として派遣されています。また、教育病院としても有名で、多くの優秀な研修医・専攻医が日々切磋琢磨しながら勉強しております。
今回は「家族志向のケアの基本から実践まで」と題し、レクチャーに加えグループワークやロールプレイも交えた3時間ばかりのワークショップを行いましたので報告いたします。

ワークショップ内容
主に家族志向のケアの概要と目標、家族アセスメント、家族カウンセリングの3つを扱いました。
①家族志向のケアの概要と目標
家族志向のケアをより深く理解するには、元の概念である家族療法とシステム理論について知る必要があります。
システム理論を臨床に応用したのが家族療法であり、家族志向のケアは『個人システムと家族システムの相互作用を医療に活かし、患者の健康と幸福感を高めること』を目標にしているということができます。
それでは、システム理論では「家族」をどのように見ているでしょうか。
飲酒のことで言い合う夫婦の会話を元に「問題を維持する相互作用に着目」「円環的思考」「システムとしてのルール」についてお話ししました。
また、システム理論・家族療法の独特な言い回しにスケープ・ゴートやIPという言葉があります。
スケープゴート:「身代わり」「生贄」などの意味合いを持つ聖書由来の用語で、「贖罪(しょくざい)の山羊」等と訳されます。家族療法では、集団や家族が抱える問題が特定の個人に身代わりとして押しつけられ、結果個人の症状や問題として見えることを指します。
IP(Identified patietnt):家族療法では、被治療者を「患者」や「クライエント」ではなく「Identified Patient(患者とみなされる人)」と呼びます。個人の症状や問題は集団や家族のシステムの不調和にあるとみなし、その中でたまたま患者になってしまったという意味があります。

②家族アセスメント/グループワーク
家族アセスメントの「構造」「機能」「発達」の3つの側面をそれぞれお話しました。
家族のアセスメントツールは様々ありますが、臨床家が時間をかけて家族の情報を集めるに勝るアセスメント方法はありません。通常のアセスメントと同じく、仮説の設定・賢所湯の繰り返しが大切です。
レクチャーの後は、パニック障害の診断となった52歳女性の架空の事例について家族図を描きながら、グループに分かれ家族アセスメントを考えていただきました。

③家族カウンセリング/ロールプレイ
家族カウンセリングとして、感情面への介入として「共感的応答」「多方向肩入れ」、認知面への介入として「一般化」「リフレーミング」「外在化」、そして「家族カンファレンス」について扱いました。
家族カウンセリングといっても、必ずしも家族の同伴が必要なものではありません。システムの特徴として、個人が変化することで家族全体が変化するという「さざなみ効果」を意識することが大切で、個人の患者にも家族志向型の面談を行うことも大切です。
レクチャーの後は、先ほどの事例の家族カンファレンスについて準備したシナリオを役割に分かれて読み上げるロールプレイ演習をしました。ロールプレイをすることで支援者の言葉の選び方を学んだり、患者・家族の感情体験をすることができます。
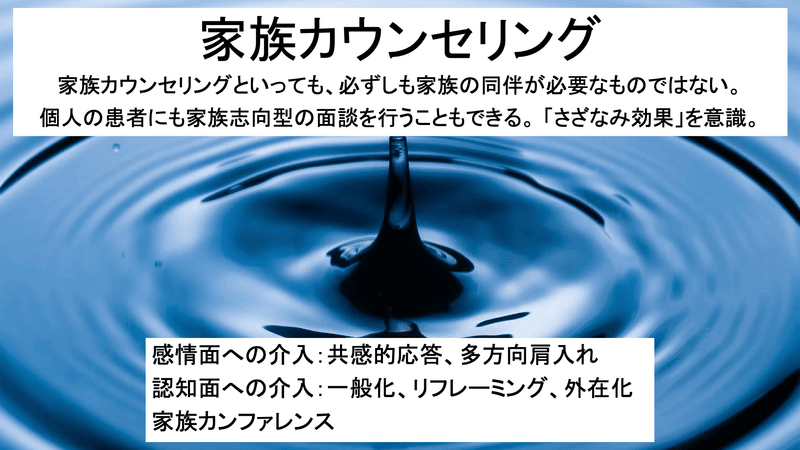
質疑応答
ワークショップの間にたくさんの質問をいただきました。回答含め紹介いたします。
Q)普段の臨床でシステム理論や家族療法はどのように意識しているか。
システム理論や家族療法で重要な点に「円環性」と「関係性」がある。
「円環性」を意識するには、アセスメントに患者や家族の誰かの視点だけを盛り込むだけでは不十分で、流れ全体で掴む。例えば、夫からの心理的虐待を訴える妻の主張があった時に、夫にどのように言われただけではなく、どのように妻が応答するかについてまで確認することが重要。
関係性を意識するには、個々の問題に焦点を当てるだけでなく、誰と誰の関係が問題となっているのかに着目する。例えば、受診に来られたのは本人でも本当に困っているのは本人と家族の関係であることがある。また、主治医との関係に困り、別の医者の元に「症状を利用して」助けを求めに来るケースもある。さらには、本当に問題なのは支援者間の関係でありそこに挟まれた本人や家族が相談に来るケースも稀にある。
受診の背後に、様々な関係性の衝突がある可能性を意識し、「本当に困っているのは誰か」を意識することが大事である。
Q)家族志向のケアを限られた診療時間や家族面接の機会しかないような急性期病院でどのように活かせばよいのか?
個人のみの場合、家族が同伴する場合、家族カンファレンスを開催する場合に分けて述べる。
個人のみが来られた時にもその背後に日常的に存在する家族を意識することは、患者本人の問題の本質を理解しやすくなる。また、個人に対しても家族志向の面談の技法を行うことは有用である。特に、一般化やリフレーミングといった家族への認知面を変化させるような関わりは、一対一であっても家族の関係も変化させる可能性があり利用しやすい。
家族が同伴する場合には、それぞれが捉える問題はそれぞれの視点や観点があり、語る様相はあくまでその人の見方からみた状況であることを理解することで双方の信頼関係を得やすくなる。また、様々な視点があるということを踏まえることで、巻き込まれることは減る。また、同伴した家族に円環的な質問(ex. 本人についてどう考えていますか?)をすることで関係性を探ることができる。
病院では家族カンファレンスを目的に家族を集めるということはハードルも高いが、病状説明や関係者会議などで家族が集まる場面はある。その場面を「家族カンファレンス」と捉え意識することで、幅広い理解や多様な療プランの選択肢を得やすくなる。何よりも患者・家族の関係性にも気をつけることで、医療者が巻き込まれることが少なくなり、さらにカンファレンス自体が患者・家族の葛藤の軽減につながることもある。
Q)面接の中で関係性を築く段階から変化や介入する段階に「ギアを入れる」タイミングは?何かを提案する際に気をつけるのはどうゆうことか?
家族志向のケアというよりは、「コーチング」や「動機付け面接」の手法が有用。
まずは面接において関係性を築くことが大切である。関係性を築く際にはラポールマーカーに着目するとよい。ラポールマーカーとは相手が自分に心を開いているサインである。うなずきといった非言語的なサインや「そうなんです」「そうそう」といった言語的なサインがあり、それを面接の初めに多く導き出すことが大切である。
関係性が築くことができてもすぐに提案はせず、「どう考えますか?」「どうされますか?」といったように相手から答えを引き出す「誘導的関わり」をまずはすることが大切。それでも難しい場合に提案をする。
提案する際も一方的かつ断定的な提案は避ける。提案したことに対して「どう思うか?」や「難しいかもしれないが」と枕詞をつけながら提案することで、より相手に受け入れてもらいやすくなる。
Q)会話の運びを間違って変な空気になったらどうするか?例えば、リフレーミングをして気分を害してしまった際など。
コミュニケーションをとっている中で、返答が的外れであることや場合によっては気分を害する可能性は十分にある。感じた際は話を続けず、まずは一旦立ち止まって、何が違うのか、どう感じたのかなどを聞き、早いうちにリカバリーすることが大切である。逆に、聞き返すことは患者さんをより理解することにもつながる。
的外れになってしまうことを気にしすぎず、積極的に反映・一般化・リフレーミングを活用していくことが大切であるし、練習する中で的外れになることは減っていく。
Q)介護問題など目の前の問題と、長期的な家族の関係の課題をどのように診療の中で扱っていけばよいのか。
関係性の変化を望んで来院しているのであれば扱うことが必要だが、大抵の場合は目の前の問題をどうにかしたくて来院しているケースが多いだろう。その際は、関係が気になったとしてもあえてそのテーマは扱わず、目の前の問題を中心に扱う方がシンプルである。ただ、目の前の問題を家族で一緒に考え、向き合う中で結果的に関係性が変わることはありうり、それだけで関係性が好転することはしばしば経験する。
短期的にまずは目の前の問題を扱い、その後希望があれば長期的な家族関係まで扱うのが良いだろう。
Q)家族図で関係性を書く際に意見が分かれた場合はどのように関係を描けば良いのか。また、患者や家族と家族図を書く際に、関係の不仲も一緒に目の前で書くのは気まずくないか。
一対一であれば目の前の人と話し合いながら引く線を決めれば良いし、本人の申告で他の家族との関係性が悪いと言われる場合は、それを自覚しているため関係性の描き方で迷うことはないだろう。
問題となるのは、家族メンバー間で意見が異なる場合であろう。意見が異なる際も何かしらの関係性の評価が第三者からできるので、その評価を記載すれば良い。またその際は記載にこだわらず、相違があることに焦点をあて、各々が二者間で感じていることや考えていることを共有することの方が大切である。
また、関係が不仲の場合にそれを記載することでの反対や違和感が一方が話す場合は、やはり記載にこだわらず、各々が感じていることや考えていることを共有することの方が大切かもしれない。
Q)コミュニケーションを学ぶ際にロールプレイを行う理由。効果的なロールプレイ学習はどのようなものか。
ロールプレイを行うことで、支援者の言動を学ぶこともできるだけでなく、患者や家族の役割を演じてもらうことで、支援者の言動でどのような考えや感情になるかも体感することができるため、コミュニケーションを学ぶには非常に良い方法である。
参加者からの感想
参加者の皆様からお寄せいただいた感想を一部紹介させていただきます。
・用語の説明から丁寧にしてくださって、理解が深まった。
・家族志向のケアについて深いところまで理解することができた。
・日本における具体例で、用語を説明してくださったのわかりやすかった。
・具体的な面談方法について学べた。
・ロールプレイをすることで、患者・家族の気持ちを追体験することができた。
・家族カンファレンスの手法が急性期病院における病状説明や関係者会議に使えるというのが目からウロコだった。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後もファミラボでは様々なセミナー、勉強会を企画していきます。こんな勉強会してほしいなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
●最新情報はこちらからお知らせします。
Facebook:https://www.facebook.com/familabo113rd/
Twitter:https://twitter.com/familabo_113rd
●オンライングループページ運営しています。(医師限定・無料)
詳細こちら:https://note.com/familabo_113rd/n/nd829c2550aa7
●お問い合わせ:https://forms.gle/SoRrCeCswAqv4dxf6
執筆:宮本侑達(ひまわりクリニック)
編集:田中道徳(岡山家庭医療センター)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
