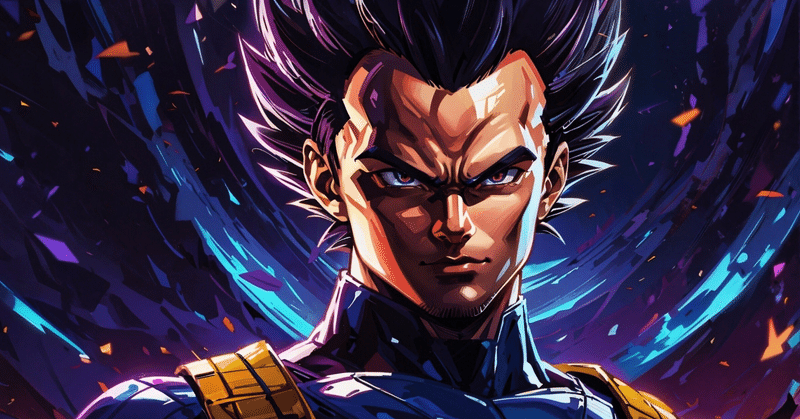
第一章 第十話 リュウガの思惑
リュウガはレガに命令を下すと、
急ぎ足で階段を駆け上り、再び館の外へ出た。
愛馬であるツヤの綺麗な漆黒の毛のアニーは
近づいてきたが、アレックス王から譲り受けた
駿馬だけあって、まるで人の言葉を知っている
かのような瞳をした、漆黒の毛並みの愛馬であった。
「すぐに戻るから、もう少しだけ待ってて欲しい」
彼は人に語りかけるように言葉をかけた。
首元をさすってあげると、気持ちよさそうにして、
主の顏を舐めてきた。
「もう少しだけだから」と言って、彼は寂しそうに
するアニーを横目に木に対して、縦に駆け上がると、
高き所からなら、あのライオンの化け物を探すのは
容易だと思い、先ほどまでいた場所を頼りにして
木から木へと軽々と飛び跳ねながら、先ほどまでいた
場所に巨大な体を低くして、コシローが手懐けている
のを目にした。
リュウガは音を消して、その場に降り立つと、ライオン
のバケモノは威嚇するように、その大きな体を二足で
立ち上がった。
「またお前か。一体何の用できた?」
弟に殺気は無いように見えたが、そもそもコイツは
身体のエネルギーに満ち溢れているのを、留めずに
おくことで、いつでも動ける状態なのだと理解した。
髪はその象徴とも言うべきか、逆立ったままだった。
「お前は知らんかもしれんが、そのライオンを見れば
分かると思うが、天使と悪魔の戦いが始まった。
そのお前の力はまだまだ上がっていく事になるだろう」
コシローは言葉を聞いて、太い木に対して
力任せに殴りつけた。
何十年か何百年かの木の幹は、鋭さは無いが、
ライオンの化け物以上の威力が木に伝わるように、
拳の何十倍もの波動のようなものが当たった感じで、
弾け飛んだ。木はそのまま倒れていき、コシローは
満足そうな笑みを浮かべていた。
「コイツはすげーな! それでお前の用はなんだ?
何しに来た?」
「俺は自分の配下を連れてここを出る。二度と戻る
つもりはないが、用が出来たら来る事になるかも
しれんが、お前には用はない。あるとすれば本だけだ」
「だから襲うなと言いたいのか? 一体どうした?
騙し合いはいつもの事だろう。気でも狂ったのか?」
気は狂ってはいないが、弟の言う事は正論だった。
血族による命さえも奪い合う騙し合いは、
長きに渡り続いていた。
弟の反論に対して、リュウガは言葉が出なくなった。
弟が一歩前に歩んできた。
「お前を殺るつもりは無い」
そう言いながら兄は一歩後退した。
「じゃあ何しに来たんだ?」
リュウガは一定に距離を保ちながら話していた。
「父母は残る事になることを伝えに来た」
「何のためにだ? まさか手を出すなと言うつもりか?」
「そのつもりは無い。俺は奴等とは手を切った。
ここから今日中に出て行くつもりだ。俺が再び来たのは、
これからはお前が領主だと伝えに来た」
リュウガはコシローの言動は読みにくい事から、
定義を出すことにより、考えた上での言葉を求めた。
予想通り、明らかに考えている様子を見せていた。
リュウガ本人としては、答えにそれほど興味は無かった。
コシローとはいずれ戦いになる可能性が高いと見て、
どう動くつもりなのかを探る目的で問いかけた。
この地を離れる可能性があるのであれば、この力を
利用しない手は無いと考えていた。一番の目的は
イストリア方面へ来させないようにすることが、
何よりも大事だとしていた。
リュウガとコシローの力は、まるで競う合うように、
強さの基本とも呼べる身体エネルギーが上昇している
のを実兄は感じていたからだった。
自分の力は出すまでは分からないが、いつも好戦的な
実弟ならば、闘気も力も隠さず見える
事によって、自分の力を知ろうとしていた。
「分かった。だがお前は何か企む癖がある。本は全て
持って行け。そして二度とこの地に入るな。俺はここ
の領主として奴等どもを敵として喰らい
尽くしてやる」
この時、リュウガは天使も悪魔も喰えないものだと
知っていた。仮に食えるほどの相手ならば相当な強さ
を持つものでない限り、ただのエネルギーの塊である
事から、人間と同化した相手なら食えるが、それは
相当ヤバい強さの天魔になるので、リュウガは敵と
しては避けるつもりでいた。
その答えは、エルドール王国の最初の建国者であった
ロバートⅠ世の本から容易に理解できた。
至大な大きさを持つモノたちは大勢いた。
しかし、天魔の戦いが終わると、そのものたちまで
消えて行った。それは他のどこかに行ったのでは無く、
神の遺伝子が通わなくなったので、衰弱していった
だけであるため、本来ならば死しても残る巨大な骨等が
見つからないのは、元の姿に戻っただけである事を
リュウガは知っていたが、それをコシローに伝えなかった。
上手く行けば邪魔な勢力同士の戦いになることを期待
していたからだった。
特にコシローには大きな期待を寄せていた。
遥かに大きな獣の王の変異体ですら、その強さに
屈伏しているのであれば、他にも仲間を増やす可能性は
充分にあった。
実際、このライオンの化け物は食わずに配下としている
事から、仲間を増やすつもりなのだと悟った。
滅びる事の無い肉体のような頑強さと、どんなに痛手を
食らっても、痛みを感じないようにすぐに立ち上がる
者など見た事は無かった。
リュウガは多くは語らず、要点だけをコシローに
伝えて、二度とこの地には戻らない為に本を移動
させなければと考えていた。
「エルドール王国の者たちも1人残らず連れていく。
お前の領土として扱ってもいい。だが、俺たちが
ぶつかるのは避けたい。俺たちはエルドール王国より
西には行かない。そこで領域の区切りとして欲しい」
滅多に頼み事などしない実兄を見て、気分が良くなった
のか、コシローは了承した。しかし、一歩でも踏み込めば
東に攻めるとも断言した。
リュウガはそれを承諾して話はまとまった。
エルドール王国まで与えたのには理由があった。
広大に広がる緑豊かなベガル平原ではあるが、
天使や悪魔に関しては問題無かったが、ベガル平原
の遊牧民の中には力をつけた者も多いと考えていた。
一致団結はしていないが、遊牧民の数はどの国よりも
大勢いて、狩りに長けた者たちは大勢いた。
つまりは能力に目覚めた場合、戦闘タイプになる
可能性が非常に高いものだと悟っていた。
それに第三勢力の者たちまで蘇るとすれば、
如何にも誰かが居そうな巨大な防壁は、敵を呼ぶ餌に
なるとふんでいた。
コシローは少しの刺激を与えられただけでも、
怒りは最大限にまで一気に上がる短気な男だった。
仮に攻めるような行為をすれば、
敵は殲滅するはずだと思っていた。
敵同士が戦っている間に、能力が発動する事に期待を
寄せていた。実際に身につけないと分からない事が
多すぎるからだった。
しかし、身体能力の上昇が止まれば、そこから鍛練
して力を増す事が可能なのか? とも考えていた。
可能ならば底力を上げる事によって、能力を更に
強める可能性は高いものであったが、その辺りの事に
関しては、まだ知り得ない情報であり、
理想としては底上げが可能ならば、能力にも大きな
影響を与えるであろうと熟慮していた。
コシローは美食家では無い事も、リュウガたちにとって
より良い事だった。食べる量は多いものの味に関しては
無頓着で、人の数倍は食べるだけに留まっていた。
酒も肉も民と同じようなものを食べていた。
そして、今やライオンとの戦いで見たのは、生肉さえ
食っていた。
彼が人間を食べたという噂は聞かなかったが、
仮に口に合えばと思うだけで、悪魔より質が悪いと
頭を過っていた。
だからこそなるべく、お互いに接触する事は無い
ものであると、話をつけに来ていた。
そのせいもあり、イストリア王国に来る意味が無い
事が功を奏していた。この会話からドークス帝国に
自然と攻め込むように言葉には出さずとも、誘導
していった。
「では二度と会う事は無いだろうが、せいぜい
頑張りな。じゃあな、弟よ」
この時、コシローには絶対に見えないように消える
ために、体内のエネルギーを足元に集めていた。
この布石により、コシローは嫌でも兄を警戒する
ようにするためには、必要な事であった。
リュウガは全力で野原を駆けながら、
とんでもない程までに自分の力が増している事に
気づかされていた。
来る時にはもっと時間がかかったはずなのに、
あっという間に館まで着いていた。
レガが丁度、館の中から出てきて、リュウガの姿が
目に留まり、近づいてきた。
「これから行かれるのですか?」
若者は難しそうな顏をして、首を横に軽く振った。
「もう行ってきた。お前が勘違いするほどまでに、
俺の身体能力は上がり続けている。
事の恐ろしさを俺はどうやら見誤っていたようだ。
今は時間の方が惜しいから、後でまた話すとしよう。
それよりも書物庫にある本を全て運び出してくれ」
「若が、弟君に会いに行かれた時に、最悪の事態に
備えて、勝手ながら全ての書を積み込んでおきました」
「それは助かった。では予定通りレガは先陣として
側近を新たに二名選んで先陣部隊としてエルドール王
には会わずに、そのまま一直線に関所を抜けて、
最速でイストリア王国に辿り着くように進め。
あの地は空からの攻撃には無力だからな。俺が直接
ロバート王に会って話を通す」
「分かりました。それでは先陣にはラベール・トリシア、
ハヤト・レジートの二名に行かせます。二人とも現在も
尚、身体能力が上がり続けている者たちです」
「なら大丈夫だろうが、先に家族や荷台を行かせるのに
対して、ラベールとハヤトはあくまでも先陣の隊長として、
50名ほどの防衛隊を作らせて隙の無いように隊を組ませろ」
「分かりました。では王に従うものたち以外は、全員
連れていきます」
「ああ。任せた。俺はこれからすぐにロバート王に
会って事情を説明して、エルドール王国の全ての者を
イストリア王国行かせるよう話した後、アレックス王
に会って、頼んで来る」
「間に合いますか?」
「問題ない。お前たちとはイストリアで会う事に
なるだろうが、悪魔どもが怪しい動きを見せていたら
俺が向かう」
リュウガは指から口笛を鳴らした。アニーはすぐに反応
を示して飛び出してきた。彼は背中や胴の部分に手を当てて、
何かに納得したように頷いていた。
「ではエルドール王に話してくる。敵はいないと思うが
警戒だけはしておけ」
「はい。抜かりなく、犠牲者は1人として出しませんので、
お任せください」
リュウガはアニーの背に乗ると、
「レガ、それでは任せたぞ。アレックス王と話しを
つけ次第、俺は空から見張る」
レガは深く頷いて見せた。
「アニー。お前の力を見せてくれ」
彼は耳に届くよう、頭を撫でながらそう伝えた。
その場で突然、砂埃が起こり、
馬体から翼を広げて上昇し始めた。
夜空の明かりは小さくなっていて、悪魔たちが未だに
優勢である事を知った。と言うよりも、天使は何かを
待っているように思えた。
一定までは悪魔が攻めているが、防衛ラインがあるように、
そこから先へは優勢でありながらも、ずっと進めずに
いたからだった。
だが、今はすべき事が他にあった事から、
すぐにエルドール王国の方へと下降していき、
闇の中に漆黒の馬は消えて行った。
「エルドール王! リュウガ様が火急の用にて、
王に急ぎ取り次ぐよう参っております。
如何致しましょうか?」
「ようやく来たか、すぐにお通ししろ」
「はッ」
「ロバート王。火急の用につき、失礼を承知で参りました」
ロバートはベッドの上で横になりながら、流威の本の複製
したものを読んでいる途中だった。
「今か今かと待ちわびておったぞ。若き勇者よ。
|其方が来たと言うことは、
あの《・・》戦いは紛れも無く本物であるのだな?」
「話が速くて助かります。ええ、戦いは始まりました。
私に従う者たちはイストリアに向かわせました。
エルドール王国の民や兵士たちも、かの地に向かわせる
べきかとお伝えに参りました」
「長年守ってきたこの地を捨てて逃げ出せと言うのか?」
「その通りです。王の役目は民を守ることであって、
領土を守ることは最良の手ではありません。
この地は、空からの攻撃に対して、余りにも無防備すぎます。
今はまだ下級の天使と悪魔が争っています。
この機を利用して、守るべき者たちを守るのが王の務めと
言えましょう」
ロバート王は若き男の眼を見て、何度か頷いた。
「誰かおらぬか?」
「はッ。ここに控えておりました」
「ならば話は早い。急ぎ皆に必要最低限のものだけ持って、
移動の準備をさせよ。誰一人として残ることは許すな。
命を第一として、守りの固いイストリア王国に向かうことを
全ての騎士、民たちに告げよ!」
「はッ! 分かりましてございまする」
それからすぐに高台にある鐘の音が、王国全土に間隔を空けて、
三度鳴り響いた。それは緊急を要する時にのみ使われる
非常事態宣言の告知であった。
「護衛は我らにお任せを。誰一人として犠牲者は出ない
ように、手配しますのでご安心ください」
「其方がいて、心から心強く思う」
「私はこれからアレックス王に私の配下と、エルドール王国の
国民から兵士たちまでの居場所の確保を願いに行ってきます。
今の私なら駆けてたとしても、それほど時間を要しませんが、
アニーが覚醒して天馬になりましたので、
私が全力疾走するよりも早く着きますのでご安心を」
「其方は我々が知らない事の多くを知っておるようだが、
それは偶然か? それとも運命を感じたのか?」
リュウガは笑みを浮かべただけで答えなかった。
問われて初めて、そうなのか? と思ったからだった。
「それは分かりませんが、我らの力は奴等にも通用する
ことだけは確かだと言えます。護衛には元父王の側近で
あったギデオンと、その配下である69名をつけます」
その意味は尋ねなくてもロバートは理解できた。
しかし、それはそれほど問題にならなかった事も悟った。
ギデオンと言えば、文武両道の義を重んじる男だとは
知っていたからであった。
「それでは後ほどお会いしましょう。では」
リュウガはそう告げると、再び闇の中に姿が消えて行った。
次回予告 第一章 第十一話 リュウガ対王子カミーユ部隊との戦い
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
