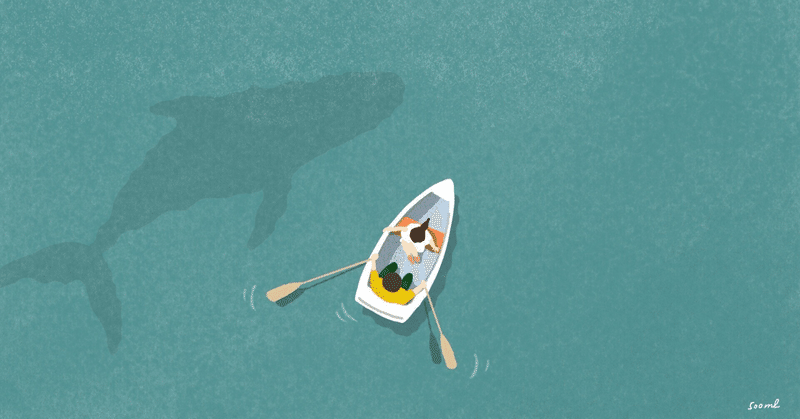
【キャリア】咲くのは「置かれた場所」で良いのか?
先日、「置かれた場所で咲きなさい」はうそではなく、結論は正しいという話を記事にあげた。
ただし、これには続きがある。
「正しい」のは、キャリア形成の上で一定のフェーズに限定されるということ。
「置かれた」はある意味かなり受動的なので、能動的に選択できる際には、この考え方は当てはまらないと考えている。
実際、現在の自分は「置かれた場所」で咲いていない。「咲けない」と判断し、そのカテゴリでは勝負しない選択をした。
これは私自身の感覚的なものからそういう道を選んだのだろうけど、改めて振り返ってみて、言語化に挑戦してみたい気になった。
アラフォーとは、そういう世代。
1 勝てないと悟った
私には同期が同科目で13名いる(内、すでに数名が退職)。
最初の研修で、ちょっとだけ肩身が狭くなった事実が判明する。
・3分の2が院卒(修士課程修了)
・半分が留学経験者
この2点。
教員だから免許が取得できれば問題ないという安易な考えで単なる学部卒私には、こんなに修士の方々がいるとは予想していなかった。
しかも、院卒ストレート合格だとしても、大学を卒業してすぐモラトリアムで数年遊んでしまった私よりも若い。
もう、これだけで劣等生感が自分を包む。
さらに、
田舎育ちの私には留学するとかしないとかという視点は全くなかって。
都内の私立大に通っていた割にはちょくちょく地元に戻ってきていたし、積極的に外を視る姿勢を持てていなかった。
いわゆる、お上りさん。
ファッションやらヘアスタイルやらには都会のエッセンスを存分に取り入れてたくせに、肝心の「学生として」できることをおざなりにしていた過去の私。
実際、もし私が「留学したいんだけど」なんて親に当時言っていたとしても、想定外のことに余裕資金はきっとなかっただろうし、私の卒業と同時に大学入学を控えた4歳下の弟は、学資ローンを使ってどうたらこうたらと両親が話していたもんだから、どっちにしても無理だったと思う。
と、他責思考満載だけど、本当に留学したければ、親を頼らずアルバイトで貯めたお金を足しにするとか、奨学金を堅実に使って残りを留学資金に充てるとか、そんなこと容易に思いついたはずだけど。
繰り返すけど、いろいろおざなりにしていた若かりし頃の私。
高校教員は中学校教員同様、「教科」での採用となる。「教育者」として素晴らしいかどうかの採用基準は、面接や集団討論などで一部判断されているんだろうけど、一次を通るためにはやはり教科のレベルが試される。
私だって一次は結構な高得点で学科試験を通過したはずなのだ(自己採点では)。
でも合格者が出揃えば、結局のところ、点数云々よりも各々のスペックがものを言う。
私が彼らに対抗できたものは…
残念ながら特になかった。
情熱とか使命感とかっていう可視化できないものを挙げたとしても、実績も何もない状況でのそれらからは何の価値も生み出せなかった。
2 最初の5年は「置かれた場所」で
導入でもふれたが、前回あげた記事の内容が教員人生がスタートした最初の5年間の有り様。
自分が課された使命を全うした、というような美しい心持ちでいたわけではなくて、よくわからないうちに毎日すごいことが起きる学校だったから、目の前のことをとにかくこなしていくことに専念した。
スキルは持ち合わせてなかったから、このときは嘘偽りなく、本当に誠実に仕事に向き合ったと思う。
働き方改革も何もない時代。
土日も部活、平日は夜が更けるまで。
疲れて帰ってきて、玄関で気を失い、その場で寝たことも。
お供は栄養ドリンクだった。明らかに過剰摂取だった。
3 キーパーソンとの出逢い
そんな状況だったけど、愚痴を吐くにはさすがに気が引けた。
みんな大変だということが分かっていたから。
ただ、教員になってすぐに担任を仰せつかった身としては、校外にもアドバイザーが欲しかった私。
研修を担当していた指導主事に相談し、状況を説明し、助言を求めた。
指導主事
学校の営む教育活動自体の適正・活発な進行を促進するため、校長及び教員に助言と指導を与えることを職務として教育委員会事務局に置かれる職。教育課程、学習指導、生徒指導、教材、学校の組織編制その他学校教育の専門的事項の指導に関する職務を行う。
当時担当していた指導主事は、たまたま同じ教科の専門でもあったため、クラス経営や生徒指導だけではなく、教科指導に関してもアドバイスをくださったO先生。
一度信用すると、その人にどっぷり浸かるタイプのAB型な私は、自分が実践したことのあれこれを、振り返りと共に逐一、O先生に報告することに。
O先生は、私のクラス経営を細かいところまでなんでも知っている人のひとりとなった。
そして無事に1年目が終わり、2年目に移って2ヶ月後、校長に一本の電話が入る。
研修において、実践発表の登壇依頼である。
青天の霹靂だった。
研修受講者は、前年度の自分と同じ立場の初任者。
発表内容は、「充実したホームルーム経営を目指して」(うろ覚え)。
依頼をいただいた際、そう言えば自分も研修でその講座があったな、と思い出した。
その時は、5年目くらいの体育会系男性教員が担っていたと記憶している。
2年目の私が、大丈夫か??
と非常に不安になったが、O先生がきちんとフォローするという約束があり、お受けすることに。
発表内容は、当然のことながら理論は話せる立場ではない。
理論はO先生が事前に講義し、私がその後、実践発表をする。
つまり、O先生の教えを実践してきた私は、発表した内容のほぼ全てが、講義の理論と往還していることになる。
O先生にとっても、教示した理論を実践者が成果と共に発表してくれるというメリット。
意図せずとも、私が説得性を上げる役割を担えたのだ。
当時の私は難しいプレゼンができないので、スライドもシンプルに、そして撮りためた写真と動画をこれでもかと使用した。
クラスの雰囲気は十分に伝わったと思う。
詳しいことは割愛するが、いろいろあって、その後、4年間連続でこの依頼を受けることになる。
O先生が初任者向け研修を担っていた5年間のうちの4年間である。
後にも先にも、こんなに継続してその役を務めたのは私だけらしい。
毎年アップデートし、理論を意識しながら実践を積めたことを発表でき、私自身も成長できたと感じている。
O先生との出逢いに感謝。
4 キーパーソンはつながっていく
不思議なもので、O先生との出逢いがきっかけとなり、別のキーパーソンとの出逢いが訪れる。
その方も指導主事で、別の分野を担当していた。
O先生ともともと親交のあったS先生。
S先生は、私がどういう人物かをO先生から聞いており、その方の陰謀(?)で、またまた校長に電話が入る。
ある教育活動の推進委員への推薦である。
教員5年目のことだった。
正直、その委員会の実態がわからない。
分からなくても行け、と命じられ、よく分からないまま最初の委員会の場へ。
メンバーを見て目が飛び出てしまった。
20代は私ひとり、30代の女性教員がひとり。
その他は、数名の40〜50代の経験を積んだ先生方。
一番びっくりしたのは、教育長と大学教授が座っていたこと。他にも、教育委員会で何番手の誰さん的なポジションの人たち。スーツが見たことない高級生地な感じがしたのが20代の私にも容易に分かった。
借りてきた猫の私。
どうやら、ある教材を作成する上で、若手教員の意見や考えを反映させたいという狙いがあったようで。
S先生がご推薦くださり、なぜか私が委員のひとりになってしまった。
その後、授業研究や立証などをメンバーや大学の先生と実践し、教材作成にあたった。
5年間を務め、もっと居てほしい旨を何度もいただいたが、妊娠してつわりが始まりそれどころではなく、年度切り替えで除名させていただくことになった。
5 登壇の機会に恵まれる
それを機に、さまざまな研修の場に呼ばれるようになった。
何度もこなしていけば緊張も全くしなくなるのだが、実はさすがに緊張した実践発表が2回ほどある。
1つは、某大学のとある講座での発表。
こちらは発表の様子を某新聞社から取材していただき、当時の新聞にも掲載していただいた。
もう1つは、他県の研修での実践発表。
実は先に述べた某大学講座を受講していた方が、その県の指導主事で、私を指名してくださったのだった。
その県で他県の教員が発表するのは、当時異例中の異例だったらしく、課長を説得するのに大変だったんだよ、と告白されたときには何と返していいか分からなかった。
完全アウェーの登壇。
目の前には150名の他県の受講者。
同業者ではあっても、こちらに向けられた厳しい目が刺さる。
課長だけじゃなくて、受講者も私にアンチだった。
けれど、特別なことは発表しない。
自分がしてきたことを伝えたのみ。
基本スタンス通り、写真と動画をたっぷりと。
授業の様子を伝えるには動画が最適。
終わった後には盛大な拍手をいただいた。
第一印象にフィルターがかかっていただけに(何処の馬の骨)、これには助けられた。
6 育休明けという「置かれた場所」
お分かりだと思うが、ここまで私はとりあえず置かれた場所でどうにかこうにか小さな花の蕾をつけてきた。
30代半ばに差し掛かり、自分のキャリア形成やライフプランを考える余裕が出てくる。
当時すでに結婚はしていたものの子どもはおらず、年齢的にもそろそろ妊活を始めるか、という気にようやくなって、不妊治療の門を叩くことにした。
それから35才で妊娠出産、キャリアを一度中断する。
1年半の産育休を経て復帰した私は、今まで努力してきたことで得てきたある種の称号的なもの諸々が、自分から失われてしまったことに気づかされる。
つまり、実績はあっても、それは過去のこと。
そして「育休明けの働き方に制限がある人」という雰囲気が拭えない世間一般的な配慮を受け、自分の存在価値への問いと勝手に向き合う日々がスタートする。
なるほど、出産を機にキャリアを中断すると、こういうことになるのか。
なんとなく分かっていたことだけど、最小限で済むように、育休期間も人の半分しか取らなかった(それでも、当時の校長からは「もう少し休んだ」と促され、予定より半年延ばしたのだが)し、復職後もほぼ全員が取得する時短勤務は申し出なかった。
権利を放棄するなんてもったいない!と言われたこともあったし、彼女なら取らないよねという、あの人に言っても無駄的な視線を向けたれたのにも気づいた。
自分で選択することなのだから、他人にとやかく言われる筋合いはないと割り切ったけれど、肝心な「自分の強みを活かした実績」は、これからまた積み上げていかないといけないのだなと悟り、ちょっと途方に暮れた。
女性がキャリアを中断せねばならないことのデメリットに対して言いたいことは山ほどあるが、ここでは趣旨から外れるので割愛。
とにかく私はこのネガティブな状況にのまれたら出てこれないかもという恐怖心に打ち勝つため、視点を変えて、新しいことを始められる好機だと捉えることにした。
7 「置かれそうな場所」を意識的に脱出する
まず、育休明けという身分なため、適度に仕事の配分に配慮がされていたため少々手持ち無沙汰になっていた私。
何かやりたくて疼く。
身バレ防止のため詳細は避けるが、産前から興味があったけれど出来なかったこと2点をここで始められないか検討し始める。
1つは、自分を含めて数名のフォロワーがいれば成り立つことだったので、さっさと実行に移した。
誰に声を掛けるかの目利きがポイントで、学校のことは大概のことが立場や配属分掌などが関係する業務だけれど、この案件は自分の研鑽も含めた「やっても良いことだけど、大半の人が面倒くさくて絶対にやらないこと」だったため、協働するメンツに制限はない。
興味関心や教育観のベクトルが似ているある人に声を掛け、見事数ヶ月で達成。自分の(そして彼にも!)大きな自信になった。
もう1つは、結構な困難があった。
規模でいうと、上述の取り組みよりも大きく、自分の所属分掌のYESがもらえないと進められないことであったので、諦めようかと思ったことが何度も訪れた。
とりあえず、面倒なことを言い出すなという周囲の顔つきには、さすがの後天的鈍感さを身に付けた私もめげた。
一旦諦めたけれど、待っていたわけでもなく、ただこのタイミングではなかったのだなと腹落ちさせて過ごした数ヶ月になぜか神風が吹く。
その後はトントン拍子に進み、どうにかこうにか形になる。
そしてそれを土台に、次年度はアップグレードさせた同取り組みを計画的に実行し、それが結構な話題になった(なんと、各種メディアにも!)。
そこからそれが自分の売りになり、「あの人はこれの人」というイメージが固定化した。以前、ガンガン石を投げつけてきた人からだって、賞賛の言葉をいただけるなんて日が来るものだから、逆手のひら返し。
この一連における私の考察は、2つの「置かれそうな場所」から抜け出したという点を強調しておきたい。
1.一定期間訪れるであろう、マミートラックを避けたい
2.産前までに積み上げたものは崩壊したので、新規参入の方向へ
1に関しては、育休中に読んだブログなどで話題にあがっていたことだったけれど、教育職の自分にはそんなことはあるまいと軽く考えていた。
けれど実際は、配慮じゃない配慮がそこら中に舞っていて、役に立ちたい欲が強い自分にはいささか居心地が悪い環境だった。
育児に支障がない程度に、自分を忙しくさせたいなと思った。
2に関して。この気持ちの切り替えが結構難しくて、上記1があったおかげもあって、どうにか2に気持ちを振り切れたと思う。
もし、育休明けだけどたんまり仕事してねーっていう雰囲気だったら、2みたいな気持ちは湧かなかったかもしれないし、こういうパラドックスのおかげで自分の身の振り方を見直させてもらったという不思議な経験だった。
8 意識的に「身を置いた場所」が「自分」を後押し
私自身、「自分って何者」論が脳内につきまとう面倒な奴なんだけど、ここから回避できる安心材料の1つが、自分についたイメージなのだと思っている。
もしあのまま育休明けに受け身で過ごしていたら・・・と思うとおぞましい。
でも、これは自分の職業観や、教職を続けていく上での倫理に沿って自分で選択したことは確かだから、別の人だったら当然違った選択をしているはずだし、何が正解なのかとか、いらん議論はしたくない。
私の働き方にあれこれ言う人だって実際はいるだろうし(その最たる例が夫という異常さ)、社会的同スペックの人と比較することだって時には必要かもしれない。
でも、愉しく仕事したいのである。
戦略的に動いたつもりは毛頭ないが、動物的嗅覚が優れていた当時の自分のことは褒めてやりたい。
9 まとめ
この場に停留するのか、別の場へ移動するのか。
その時その環境における、自分の条件や持っている資源をもとに吟味して選択する覚悟。
少し経ってから、「レッドオーシャン」という言葉を知った。
ビジネスシーン用語で、競争相手が非常に多く、企業同士の争いが激化している既存市場のことを指すらしい。
教育の場は、きれいごと的な視点で言えば、教育従事者みんなで児童生徒を育てていくわけだから、教師はみんな同じレベルで同じ方向を向いて指導にあたることが望ましいのかもしれないけれど。
教育の質を保証する上では、そういう側面ももちろん必要で。
でも、そもそも教師だって人間だから。
いろいろな人がいて当然だし、そもそも、多様な人と関わることで児童生徒が感じることや得られることに緩急がつくのであって。
あの分野はあの先生が得意だから、あの先生について行こう!
でも、こっちの分野だったらこの先生だよね!
みたいなのは普通のこと。
採用されるときに既に持ち得た特性だけが許されて、教師になってから努力で得た何か特別なことが、他人の嫉妬によって穿った見方をされて活用されたいのは甚だおかしい。
という側面と、
教師だってみんな、職業として教師をしている。
教師である前に、1人の人間だ。
であれば、承認欲求があってもよいはずだ。
と言うか、普通の人間であれば、誰かに認められたり求められたりすることで、自分の価値を確認したり、他者に何かをしてあげたいと思ったりするものだと思う。
それが、「幸せ」を言語化する上では重要ではないかと私は考えている。
※流行りの「ウェルビーイング」ってやつ
であれば、自分が自分として認められるための手段として、レッドオーシャンから抜け出し、なるべく競争相手がいない海を求めて移動することは、生存戦略としてあながち間違っていないはず。
他人の成功や成果についてあれこれと文句をつけたい人は、こういう視点を持っているといいのになって思っちゃう。
(私だって嫉妬心は人並みに持ってはいるけれど、向けられる嫉妬の方がはるかに多い。そして自分が甘んじて受けた嫉妬と同類の嫉妬心を持ったことがないので、こういうことに関して本当によく分からない。ただただ、苦しい。)
・
・
・
ちょっと考えてみたので、まとめてみた。
打っていて、咲くなら野原なのに、最後の頃は海になっていて、だったら咲かずに泳ぐだよなぁ、とカナヅチの戯言を最後に残しておく。
暑かったり寒かったりと、不安定な気持ちをどうにか抑えてくれるのが、ランニングだったりする。
病は気からって本当。
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
では、また!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
