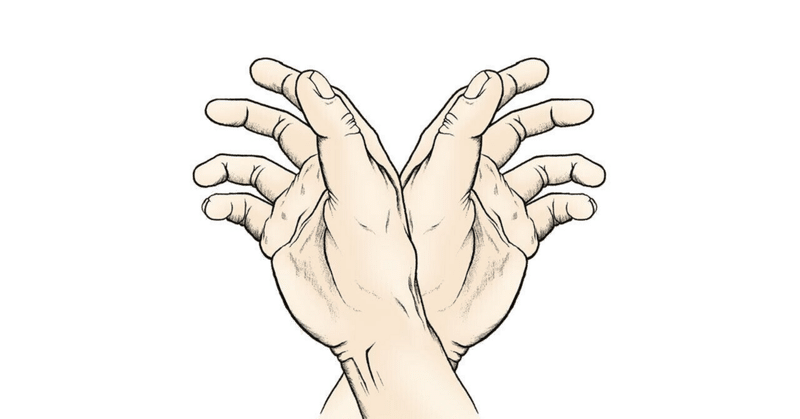
【マインド】支援すりゃ良いってもんじゃないから。
誰かに欠けているところがもしあるなら。
それを補えるものがあったらいいよね。
誰かが特別な何かを必要とするなら。
周りの人が支えてあげないとね。
社会には昔から互助の文化があった。
地域やコミュニティで、お互いの存在を認め合い、困っている人がいれば助け合う。
返報性の原理よろしく、前にあの人に助けてもらったから今後はこちらが支えてあげるんだ、って。
そうやって、人との関わりの中で集団の結束を高めたり心理的安全性を担保したりして、安定した営みを送るための支えにしてきたのだと思う。
時代が進み、社会も成熟して、ダイバーシティの考えが色濃く出るようになってきた。
個の特性が決して特別ではないことを受け入れる風潮が加速したり、マイノリティやかつて生きづらさを感じていた人たちも過ごしやすい社会の在り方が見直されたりと、望ましい方向へ世の中が進んでいくことは良いこと。
「そう在る」ことがスタンダードであることは、社会全体が流れを作ったことで確かになっていきつつあるのは事実。
でもさ、
舵取りが難しいって感じちゃうんだよ。
多様性を受け入れなきゃね、
違うことは悪くないよ、
みんな特別、みんな一緒、
それが前提で、
そう在るべきだってみんなが思うし、
それが正当であることは紛れもないことだけど、
実際はその大きなフィルターバブルの中で絶対的な正解に苛まれている場合もあるってことに気づいているのに気づかないふりをしなきゃいけない人も結構いるんじゃないかって。
少なくとも私はそれに気づいてしまった。
「ここが欠けている」
それを補おうとする。
めいっぱい。
時には大袈裟に。
時には過保護に。
対象者が望んでいるから?
それとも社会が「そう在るべき」だから?
我々がそうしたいから?
それはちゃんとした利他主義?
そもそも我々はそちら側の人間?
社会は「そう在るべき」なのに、
一歩外へ出た別の社会では、「そうではなかった」なんてことは実はよくあることなんじゃないの。
在るべき形で精一杯のサポートがあった場所(あるいは段階)から、それがないことが前提の場所(あるいは段階)へ移動・移行した際、どう感じるんだろう。
私はどちら側の人間なんだろう。
こんなこと考えている時点で、いかにも「与える側」であることが当然かのような視点でいる気がする。
マジョリティ側でいることが自分の考えのデフォルトみたいな気がして急に嫌気が刺したのだけれど、ふと、息子が生まれて少し経った時のことを思い出した。
ショッピングモールでのトイレにて。
人が列を成してトイレの順番を待っている。
初めて息子を連れてのモールでのトイレ。
少し前にウンチをしたのに気づいた私は、トイレに駆け込み、人の列にうろたえる。
そこでなぜか私は「すいません、息子がウンチしてるんです。順番を譲っていただけませんか?」と前の方に伝え、先に使わせてもらったのだ。
恥ずかしくて思い出したくもなかったけれど、このときは早くオムツ替えをしなきゃという気持ちで頭がいっぱいだったから、かなりナチュラルにこの言葉を発していた。
でも今考えれば、
子育て中なら配慮してもらって当然だって気持ちとか、
オムツを替えないといけない私の立場を知ってほしい気持ちとか、
そんな感情が潜在的にあったんじゃないかなって思ってる。
だけど、
息子がウンチをしてようが、
子育て中で大変だろうが、
トイレを使う順番に対して優劣はとくにないのだし、そこに基準は設けるべきでもないのだし。
仮に誰かが「お先どうぞ」なんて言ってくれていたら、感謝の気持ちでいっぱいになりながらありがたく使わせてもらってたのだろうか。
はたまた、「当然だ」とも思いながら、横柄に使っていたんだろうか。
それとも、「結構ですよ、ちゃんと待ちます」という選択をしたのだろうか。
社会がマイノリティに優しくて、
それがスタンダードとして確立してて、
当然だと受け入れることに慣れていって、
でも実はそうでもない場面に出会して、
そのときの気持ちの拠り所が見つからなくて、
それを社会のせいにしたりして、
でも実際は単なる捉え様だけの問題で、
で、
で、
で、、、
「そう在るわけでない」社会への順応を全ての人に強いるのには是非が生じるのだけど、でも事実そういう社会が存在し得ることは確かで、その事実に遭遇したときに面食らわないようにする努力は双方に必要な気がしている。
支援する側もされる側も、「そう在るわけでない」社会にスムーズに身を置けるよう、グラデーションな支援の在り方があって良いと思う。
ささやかな声かけや、
言葉を使わない見守りだって、
立派な支援の1つ。
仕組みを整えて過ぎてガッチガチの支援だけが良いわけではない。
やってますよ感が満載の支援が正解なわけではない。
人は変わるものだから。
社会も変わるものだから。
支援だってそれに合わせて変えていいものであって。
その人や社会の成長に合わせて都度決めれば良いのであって。
そういえば臨月で電車に乗ったとき、ある青年が席を譲ろうと声を掛けてくれた。
私はそれを断った。
彼の気持ちを汲めなかったことに今でも悔いているのだけど、でもなぜ私はその支援を受け入れることができなかったんだろう。
しばし空いたままの席は、次の駅で乗車した人によってすぐに埋められた。目の前の私に一瞥することもなく。
自分自身の中でも、ダブルスタンダードがある矛盾。
支援にも、施す側・受ける側相互間に感情のマッチングがあるだなんて思いたくないけれど、「欠けてるから補う」だけの単純なものではないってことだけは分かった。
仕組みを作れば良いってもんじゃないことも分かった。
もっと温かいものであって欲しいと思った。
決して、「支援して満足」で終わるものではない。
っていうことを、ある出来事をきっかけに考えてしまったので、戯言を述べてみた。
取り止めのない文章をお読みいただき、ありがとうございました。
言語化するって難しい。
では、また!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
