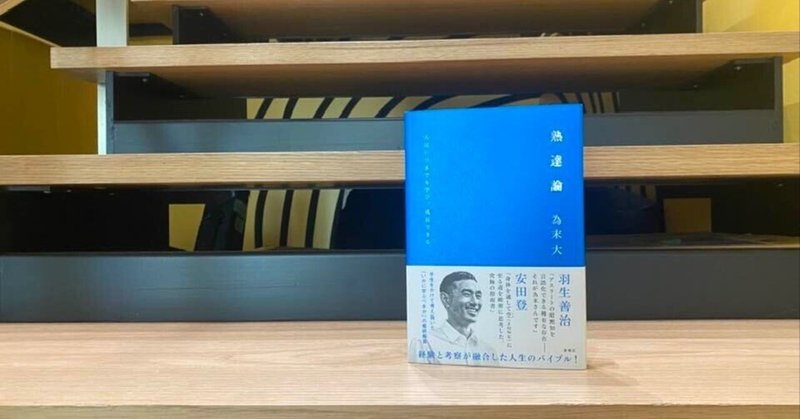
為末大さんは『熟達論』をいかに書き上げたか
7月13日に発売された為末大さんの『熟達論』。ご自身が「これまでの集大成」と言う本はいかに生まれたか。プロデューサーとしてその執筆を間近に見ていた立場から、この本の出版プロセスを書いてみたい。
「現代の『五輪書』を書いてみたい」
出版プロジェクトはひょんなことから始まった。
その日は中目黒のブルーボトルコーヒーで、為末さんとお会いしていた。仕事の合間にいろんな話しをしていたが、じっくり話すのはこれが初めてである。
いつも通り、為末さんは自ら自分の語るというより、いろんな問いかけをする。それらの問いが、ちょうどいい塩梅の難易度で、問われて言語化してみたくなるものばかりだ。「新しいメディアを作るなら、どんなものがいいか?」など。また、こちらの問いに対しても、面白がってくれて、それをなんとか言語化しようとされる。そこから生まれる言葉がまた面白い。
そんな中で為末さんから意外な話が出てきた。陸上選手を引退してちょうど10年になる。引退後は、いろんな場で話したり、異なる分野の第一人者と対話する機会にも恵まれた。同時に会社を経営したりビジネスの領域にも進出した。ただし、これからは軸足を変えてみようと思っている、と。すでにこれまでの仕事を減らしつつあるそうだ。
「これからどんな活動をされる予定ですか」と伺うと、
「まだ具体的には決まっていないんです。ただ、自分の言葉をもっと発信していきたい」と。
これまでも十分にご自身の意見を発信していたという印象だったので、これは意外だった。テレビやネットのメディアでも多く拝見するし、書籍も随分出されている。すっかり「陸上の人」から「言葉の人」に変わりつつあるのかと思っていたら、ご本人の認識は違ったようだ。
「どんなことを発信しようと思ってます?」と伺うと、
「いろいろあるんですけどね。いつか将来は、『五輪書』のようなものを書いてみたいとは思っています」
さすが、かつて「侍ハードラー」という異名をとっただけある。それにしても、喩えが『五輪書』とはこちらの想像を遥かに超えていた。為末さん曰く、『五輪書』は剣術の本でありながら、分野を超えて通貫する熟達の方法論になっている。自分も陸上競技を通して感じ、そして引退後に他分野の第一人者と語り合ってきたことを抽象レベルで統合して、どんな分野でも通用する普遍的な方法論を言葉にしてみたいということであった。壮大な構想だなというのが第一印象だったが、確かにこれは言語化する力に卓越した為末さんならではの本かもしれない。
では、為末さんが「いつか」と言っている将来は、どんな条件が整ったあとなのだろうかと、単純に興味が沸いた。現代の『五輪書』を書くのに、まだ何が足りないと考えいのか?やはりそれだけのものを書こうとすると、まだ何かが熟していないと思っているのか?
そんなことを考えて聞いてみた。
「それは今ではダメなんですね?」
どうやら、為末さんはこれを「今書いたらどうですか?」という意味に受け取ったようだ。
こうして、ゼロからこのプロジェクトが始まった。もうこの時点で書名は『熟達論』と半ば決まっていた。そして僕は、為末さんの過去の著作と同時に、宮本武蔵の『五輪書』を購入した。
雑談のような打ち合わせ
「書きたい」といった為末さんだが、それは「いつか」だったので具体的なアイデアがあるわけではない。打ち合わせは、毎回ほぼ都内のカフェだったが、側から見ると雑談をしているようにしか見えなかっただろう。お互いにパソコンを出すわけでも、ノートに書くこともない。
最初の頃は、ひたすら熟達とは何か、なぜ人は熟達を目指すのか、そんな話ばかりしていた。為末さんのご自身の体験も語られ、その具体的な話の面白さもあるが、それを抽象化するとどういうことなのかを二人で話してみる。時に話は脱線するが、1時間あるいは2時間と対話していくと、具体的な何かは見えなくても大きな方向性はすこしずつ見え始める。
ただ、為末さんは具体的な書くイメージは一向に湧かないようだった。「とりあえず、何か書いてみます」といっても次回お会いしたら一向に進んでいない。「毎日2時間、書く時間を作っているのですが」。
この頃、為末さんは苦悩していたのか。実は僕はそのことをほとんど気にしていなかった。というのも、為末さんの書く意欲がまったく下がっていないように見えたからだ。
そういえば、為末さんといえば現役時代にコーチをつけなかった選手として知られている。コーチの存在とは、自分を客観的に観察してアドバイスすること、そして本人だけでは頓挫する計画を立て、それを遂行するパートナーであるとともに、選手を励ましモチベーションを維持する上でも大きな役割を果たすものではないか。そんなコーチの存在を置かなかった為末さん。確かに自分のことを客観視する力は人並み以上である。それ以上に感じたのは、この人は自分のモチベーションを、他人の力を借りなくても自分でコントロールできる人ではないか、というものだった。どんなタイミングでお会いしても淡々とされている。
書けないからといって気合を入れるわけでもなく、為末さんはいろんな試行錯誤をし始める。書籍という長文を書くために、noteなどの数千字の文章を書くのをやめてみる。書く時間や場所も変えているようだ。
そんな数ヶ月を経て、徐々に構成が決まってきた。熟達をプロセスで表現できそうであると。そして、最初の段階は「遊ぶ」であり、最後の段階は「自分がなくなる」(本書では「空」となった)であることは、為末さんの頭の中で最初から描かれていた。こうして、熟達の5段階の概念が固まりだしてから、執筆は少しずつ進むようになった。
「これまでの本より20 倍、大変です」
為末さんはこれまで単著だけでも10冊ほど著書がある。しかし今回は過去のプロセスとはまるで違う。これまでの本は、出版社からの依頼で始まったものばかりであった。為末さんが過去に話たり書いたり話したりした内容を出版社の人が整理してくれて、原稿の土台を用意してもらうことが多かったという。今回は違う。誰かから依頼されたわけではなく、為末さん自らの発案なのだ。事実、この段階では出版社は決まっていなかった。原稿も過去に書いたものを持ち出すのではなく、ゼロからご自身で書かなくてはならない。最もプリミティブな形で「本を書く」ということに挑戦するのだ。
一見、自分で自由に書くのは簡単なことのように思えるが、人から頼まれて枠組みを決めてもらった中を埋める方が遥かに難易度は低い。本当に書きたいことは何か、それをどうすれば1つのテーマのなかに納められるか。自由度の高さは無限の選択肢の中で泳ぐようなものだ。書きたいことはあるし、その熱意も十二分にあるが、白紙の紙を前にして、本当に何もない中から始めるプロジェクトである。初めてのこのプロセスを為末さんは「これまでの本より20倍大変です」と笑って話す。
とはいえ、僕にとっては原稿をもらうのが僕にとっては楽しみだった。砂の中に眠る宝物の形がどんどん浮き彫りになってくるかのようだった。荒さもあるが輪郭がしっかりと浮き彫りになる。僕は登山に喩え「五合目まできましたね」「8合目まで来ました!」と口にしていた。
同時に、この段階になって為末さんとどの出版社にお願いするかを相談した。ここまで出版社を決めなかったのは、書く内容に集中してもらいたかったからだ。為末さんが本当に書きたいことをまとめたら、引き受けてくれる出版社が見つからないはずはない。そう確信していた。そこで実際に出版社を決める際、ビジネス書を得意としている版元じゃないところにしようと思った。引退後の10年ですっかりビジネス界でも大きな存在となっていた。過去の書籍も広い意味でビジネス書系の版元から出されている。だが、この本はこれまでの為末さんの著作とは明らかに違う。自ら為末さんが生涯書きたかったテーマに取り組んだものであり、その内容はビジネスの分野を超え普遍的な「学び」につながるものである。人間の思考や活動そのものに直結するものだ。さらに言うと、為末さんの今後の軸足である「言葉の発信」に相応しい出版社にしたいと思った。
そこで思いついたのが新潮社だった。信頼する編集者・足立真穂さんもいる。早速、足立さんに相談しこれまでの経緯を話すと、見事に、為末さんの意図を汲み取ってくれて快諾してくれた。こうして出版プロジェクトは後半を迎える。
鬼コーチ、現る
足立さんは、過去に養老孟司さんや独立研究者の森田真生さんなどの書籍を手がけられ、僕も尊敬する編集者の一人である。表情が柔らかく、どんな相手にも丁寧に接する方だ。早速為末さんの原稿を読んで、「これはすごい本になりますね」と言って引き継いでくれた。
「今回は為末さんが、一から全て自分で書いた本なんです」という僕の言葉を受け、足立さんは、為末さんの原稿を一字一句直さないと決めていたようだ。違和感があるところを直すのではなく、為末さんに再考を促す。どんな小さな点に関しても、足立さんは直さずに指摘するのだ。しかもあの柔らい表情とは裏腹に、指摘箇所の数が半端ない。
全体の大きな流れに変更はなかったものに、細部に関しては、ほぼ全面書き換えに近い作業になった。足立さんに持っていく前に、僕は為末さんに「もう9合目まで行きました!」と言っていたのだが、そこから山の麓まで振り出しに戻ったようで、為末さんには申し訳なかった。
足立さんの指摘は厳しいが、実に的確かつ丁寧である。ワードファイルで仕上げた為末さんの原稿に、ファイル上で修正するのではなく、それを紙に印刷してすべて手書きで問題点を指摘する。これは膨大な作業なのではないか。しかも、それが3回、4回と続く。その膨大なダメ出しはまるで「千本ノックのよう」と為末さんは称し、僕らは足立さんのことを「鬼コーチ」と呼んでいた。だか、これが本書の完成においては画期的なプロセスとなった。原稿のクオリティは段違いに高まり、為末さんは足立さんにとても感謝されることになる。
なぜ本書が集大成なのか?
足立さんの厳しいフィードバック、それに応える為末さん。原稿はますます磨きがかかってきた。まもなく完成である。僕も何度も通しで読んできたが、最後の最後に読む際はとても感慨深かった。この一年近くの作業がようやく終わる。
本書の最後は、熟達の最後である「空」(くう)の段階について書かれている。ここには、為末さんの現役時代に体験したゾーン体験が生々しく書かれている。それは、2001年カナダのエドモントンでの世界選手権。集中が最大限高まる中で静寂の時が訪れ、何かに導かれたかのように走る為末さん。この記述は何度読んでも感動的であり、本書の醍醐味の一つだろう。そういえば、この場面、動画で見れないだろうか?Youtubeを検索したら、すぐに見つけることができた。下記の動画である。
僕が知る為末さんとは明らかに別人である。物静かな哲学者、あるいは思想家、言葉を丁寧に穏やかに語る為末さんではなく、動画に映るその人はまるで何かを狙う野獣だ。体内のエネルギーを全て表出させたかのように、殺気を感じるほどである。その野獣は一点を見つめスタートに備える。ピストルの音で飛び出す。ハードルも軽やかに超え、コーナーをスムーズに走り抜ける。ゴール前に漲るエネルギーを1ミリも残さず放出させたかのようにゴールする。日本人トラック競技で初の世界大会3位。その歴史的な瞬間を実況するアナウンサーは興奮し声が裏返る。為末さんの表情は、物事に全霊で取り組み、あらゆる可能性に挑んで極めた人のみに許されるもの、そんな表情である。これが熟達の究極的な喜びなのかもしれない。
本書で静かな筆致で書かれたその現場は、こんなエネルギーの燃え滾ったギラギラした世界だったのだ。そんな極限まで熱い世界を通過して訪れるのが、「熟達の境地」という静かな世界なのだ。
為末さんは、本書をご自身の「これまでの集大成」と呼ぶ。あとがきでは「死ぬまでに書きたかった本」と書かれた。この映像に映る為末さんの表情を見て、「本書が集大成」と語る為末さんの深層が理解できた。
本書は、技能を向上と自分を磨くための方法論であり、また本物を突き詰めた人が得られる世界を知ることができる本である。そして、ある領域でとことん自分と向き合い至福の経験をした熟達者が、その世界の尊さを言語化したものだ。どうか、一人でも多くの人に読んでもらいたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
