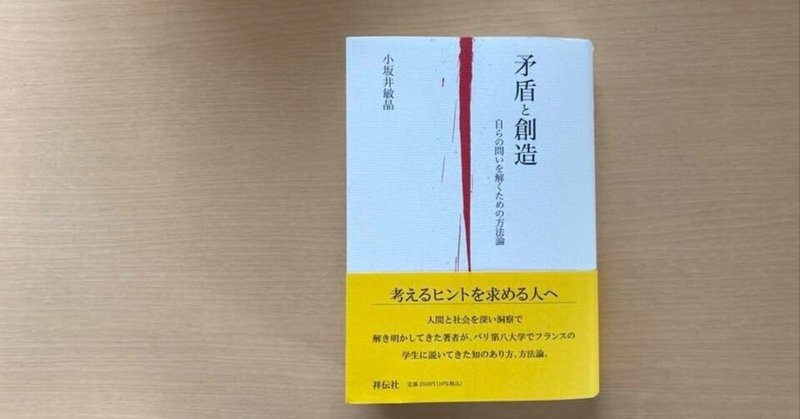
本は頭で書くのか、心で書くのか?――『矛盾と創造』を読んで
どの著書にも手抜きが感じられない著者
読んだ本の面白さは、書き手ではなく内容が全てである。ただ、読む本を決めるとき、書き手がどんな人なのかは大きな影響を及ぼす。僕には「この人の書いたものなら無条件に読む」という著者がいる。社会心理学者の小坂井敏晶さんがその一人だ。
10年ほど前に最初に読んだ『責任という虚構』で、「当たり前を疑う」その深さに感服した。責任の所在を追及する本書では、社会が捏造した「虚構」であると言い切る。責任が虚構であるなら、その裏返しにある自由とは何か?我々が人権を尊重する、その核である「自由」の存在を揺さぶってくる。その後『社会心理学講義』、『答えのない世界を生きる』、『格差という虚構』を読んだが、どの本も自分の頭にあった「常識」を揺さぶられる。
得てして本を複数出す人は、それらに濃淡が出るものである。渾身の一冊もあれば、その時々に書いた文章をまとめたものもある。自分の専門分野とエッセイとを明らかに書き分ける人もいる。しかし、小坂井さんの本に、その濃淡を感じたことがない。
そんな小坂井さんの新刊『矛盾と創造』が発売された。本書も過去に読んだ本と寸分違わぬ濃さだ。似ているのは『答えのない世界を生きる』であろうか。それは、一つのテーマを追及するというより、著者の思索の変遷を綴ったところである。その意味で「アナザーストーリー」と名付けられるものに属するが、そこに軽さは微塵もない。裏話を知るお楽しみに価値があるのではなく、思索の格闘の記録にその凄みがある。選び抜かれた言葉が並んでいるのだ。
本を書くとは、自らと格闘すること
400頁を超える本書は、まさに著者の格闘の歴史である。その格闘の積み重ねが、これまでの書籍を生み出してきたのは容易に想像できると書きたいところだが、「容易に想像」という言葉があまりに軽い。想像を超えた格闘を読むことで、過去の書籍の背景を伺い知ることができるのだ。
その格闘が生々しい。特に印象的だったのは「第5章 躊躇と覚醒」である。この章の最初に次のような言葉が書かれている。
頭が出した結論を心が拒む。論理には捉えられない真理がある。拙書はどれもそんな経緯を経てできあがった。
そして、
論理だけでなく、書く動機が感情の次元で支えられないと魂の入った分析はできない。
という。
「考える」という行為において感情の置き場所をどうするか。人は自分の願う方向になんとか論理的な整合性を求めがちだ。自分に都合のいい事実や論理は受け入れやすいし、自らもその動機で考えがちである。しかし、小坂井さんは冷徹なまでに論理の構造に自らの感情を入り込むことを拒否する。同時に、「書く動機」に感情の存在の大きさも自覚されている。論理と感情の間に溝を作ることで、あえて格闘の次元を高めているのではないかとさえ思える。
ここから、『格差という虚構』を書かれた時の葛藤について書かれている。同書では、『責任という虚構』と同様、格差も虚構であることを主張していたのが、そこに至るまでの道のりは容易いものではなかったのだ。
自由意志という虚構が責任を正当化する仕組みを見れば、能力という虚構が格差を正当化する理屈と同じなのは明白だ。それでも常識に邪魔され、背後に隠れる論理が見えなかった。自由意志を能力に、責任を格差に置き換えるだけの簡単なことなのに、それができなかった。
常識はしぶとい。中でも最も執拗なのが感情を揺さぶる倫理観だ。
同書『格差という虚構』を読んだ人の中には、『責任という虚構』と同じ論理だったと感想を言う人がいる。同じ道具を使って別のものを作った、と。しかし、上記
を読むと、目の前の道具が使えることに気づかなかったほど、著者にとっては異なる課題だったということがわかる。そして、責任と格差との違いとは何か、邪魔された「常識」の正体とは何か。
責任と格差の意味が私にとって違う。(中略)虚構であっても責任を解体したいとは思わない。必要悪として責任を認めている。他方、格差には怒りを覚える。絶対に格差はなくならないと承知しても、だから格差を放置すべきだとは思わない。必要悪としても認めたくない。
なぜ人は本を書くのか
僕自身、本を作る仕事をしているので、よく著者にとって「本を書く動機」はなんだろうと考える。社会に自分の考えや経験を公表すること。それは同時に、見知らぬ誰かからの批判を受け入れる覚悟が要求される。それでも、書きたいことがある、言葉にしたいことがある。小坂井さんは橋本治氏についての文章を引用した後、次のように続ける。
私も同じ気持ちで書く。読者に説く以前に、自分自身が納得するために。
本は読者に向けて書くものと、安易に決めてはいけない。所詮、読者という他人が知りたいことなど知る由もない。そんなあやふやな対象ではなく、書く対象を自分自身に向ける。そうやって生まれた文章が、読者という他者に響く。それは自分自身を納得させ切った言葉が積まれているからだろう。そんな言葉が400頁にわたって並ぶ本書は、正面から読む読者に刺さるものがないはずがない。
最後に、これまでの小坂井さんの著書を読んで気になっていたことが一つ解けた。それは主体を否定される小坂井さんが、人それぞれの「個性」の存在をどう捉えているのか、という疑問だ。これについて本書で触れており、「一貫して私は主体を否認する。だが、同時に個性を大切にし、自らの問いだけを追えと説く」(p.284)と書かれて、これについて「説明する術」がまだ見つからないとも書き添えておられる。
この箇所を含め、本書を読んで改めて思った。小坂井さんは「分類されたくない人」ではないか。社会心理学者という括りも、ましては海外で活動する学者という括りも、さらに言えば、日本人やアジア人という括りに入れられることも窮屈さを感じる。どこまでも小坂井敏晶という存在のみであることが心地いい人なのではないか。だから時に天邪鬼にも映り、そこが共感できるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
