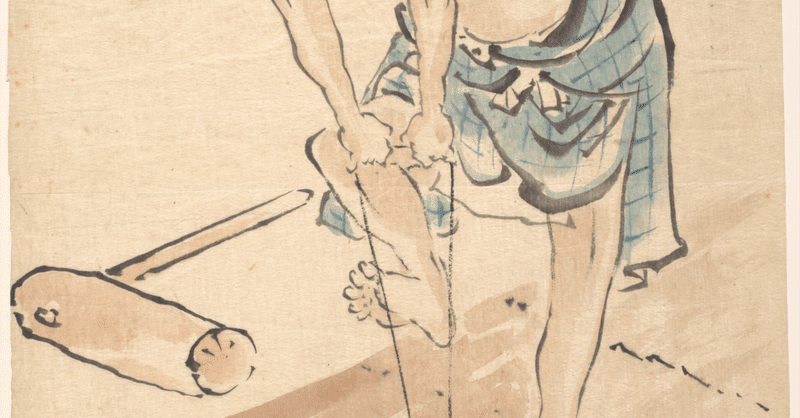
756 インターネット、ソフトウェア、OS、ハードウェア市場・産業などについてゴールデンウィークに調べてみたら・・・。
ソフトウェア業界
目次
ソフトウェア業界とは
「ソフトウェア」とは、コンピュータ上でさまざまな処理を行うプログラムのこと。パソコンにインストールして使用する文字入力ソフトや図表作成ソフト、法人向けの経営管理ソフトなどのほか、家電製品や自動車といったハードウェアとソフトウェアが一体となった製品の開発など、ユーザーのニーズに合った機能や役割を持つさまざまなソフトウェアを開発しているのがソフトウェア業界だ。
ソフトウェア業界の仕組み
ソフトウェアには、パソコンやスマートフォンなどを動かす基本のソフトである「OS(Operating Systemの略。オペレーティングシステム)」と、特定の作業を行うために使用される「アプリケーションソフト」がある。
OSとアプリケーションソフトの関係は密接で、基本となるOSごとにアプリケーションソフトは開発される。個人用には文字入力や図表作成のオフィスソフトやゲームソフト、セキュリティソフトなどのアプリケーションソフトがある。また、法人向けには、オフィスソフトやセキュリティソフトに加え、経営管理ソフト、勤怠管理ソフト、在庫管理ソフトなどがある。顧客のニーズの多様化・高度化を受けて、次々と新しいアプリケーションソフトが開発されている。
ソフトウェアの開発には顧客のニーズに応じてイチからソフトを開発する「受託開発」と、ユーザーのニーズなどを捉えて自社でパッケージ品を開発して販売する「パッケージ開発」の2つがある。
ソフトウェア業界の現状
経済産業省の「平成30年特定サービス産業実態調査」によると、ソフトウェア業の事業所数は2万1953事業所(前年比2.9%減)、従事する人は70万7600人(前年比0.9%増)、年間売上高は14兆8401億円(前年比5.2%増)。今後はAIやIoT(後述)、ビッグデータ、セキュリティ対策などの分野で需要増加が続くとみられる。
ソフトウェア業界の今後の展望
ソフトウェアの導入を通じ、企業が自身のビジネスの進め方を変革していくような取り組みが、今後増えていきそうだ。
例えば、顧客情報を一元管理し分析するCRM(Customer Relationship Managementの略。顧客との関係を構築・管理するシステム・戦略のこと)に関するソフトウェアでは、
AIやビッグデータに関連した技術の発達よって、今までよりも膨大なデータ(検索やアクセス履歴、購入履歴など)を解析することで、顧客ごとに適切な情報提供や営業提案が可能になってきている。また、ソフトウェアにより、従来の企業のマーケティングや営業を効率化するだけではなく、今までは行ってこなかったような打ち手を実現することが可能なシーンも増えてきている。
IoTへの対応など、企業のIT投資は積極的で、ソフトウェア開発のニーズは高い。また、クラウド(後述)を活用してソフトウェアを取引先に提供するサービスへの転換も進んでいる。
こうした中、情報の適切な利用は今まで以上に厳正な管理が求められる。個人情報の流出は、企業の信用を大きく失墜させることになり、企業の存続にもかかわるような影響を及ぼしかねない。顧客の個人情報管理のための安全性の強化や、サイバー攻撃への備えなどセキュリティ対策は、各企業にとってますます重要になり、費やす予算は増加傾向にある。セキュリティソフト市場は今後さらに成長が予想されている。
個人向けソフトウェアの提供では、モバイル端末、特にスマートフォンを意識していくことがますます重要になっていく。総務省の「平成30年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、スマートフォンの利用率は87.0%となっている。スマートフォン用のアプリケーションソフトやゲームソフトが今後個人向けソフトウェア開発分野をけん引するだろう。
ソフトウェア業界の最新動向
IoTの普及
Internet of Thingsの略。「モノのインターネット化」とも呼ばれ、これまでインターネットと縁遠いと考えられていたモノに通信機能を持たせ、遠くからでも位置確認や操作、情報のやりとりができるようにする技術のことだ。最近では、高齢化社会のニーズに対応するために、腕時計型の端末で高齢者の健康状態を管理することで、使用者に何か異変があった場合は、警備会社に連絡がいくようにシステムを組む、といった事例もある。
クラウド化
インターネットを経由してソフトウェアをダウンロードし利用するケースが増えている。このようなソフトウェアの提供方法の変更を「クラウド化」と呼ぶ。クラウド化されると、利用者は常に最新版のソフトウェアの利用が可能になる、異なる端末から利用してもデータを共通化できるなどといったメリットがあり、市場規模は年々拡大している。
BI
Business Intelligence(ビジネスインテリジェンス)の略。企業に蓄積されたさまざまな情報を収集し、整理することで、経営の意思決定に活用する手法をビジネスインテリジェンスという。組織のあちこちに散らばっているデータを集約・分析してわかりやすく表示し、経営管理や売り上げのシミュレーションなどに役立てるBIツールとしてのソフト開発が盛んだ。
MA
Marketing Automation(マーケティングオートメーション)の略。これまで人が行ってきたマーケティング活動をシステムで自動化することで、効率化を図るツールだ。購入客や見込み客への新サービスの案内の自動送信、メールを開く、リンクをクリックするなど顧客ごとに異なるレスポンスを情報として管理・分類し業務を最適化することで、一人ひとりに合ったマーケティング、One to Oneマーケティングの実現が可能になる。
ソフトウェア業界に関連する業界
家電メーカー
エアコンが人のいる場所に合わせて冷風を送ったり、冷蔵庫がドアの開閉に合わせて温度調整したりする、洗濯機が洗濯物の量に合わせてすすぎの回数や乾燥時間まで自動で設定するなど、多くの家電製品にソフトウェアが組み込まれている。
ゲームメーカー
アプリケーションソフトをダウンロードすればいつでもどこでも遊べる手軽さから、スマートフォン向けのソフトが急成長している。
IT関連業界
IT関連業界には、企業の情報システムを構築・運用する情報処理系の企業があり、その業務の一部として、ソフトウェア開発が委託されるケースが多い。
株式会社Works Human Intelligence
海外「なぜ日本はハードウェアの時代と同じようにソフトウェアに秀でることができない?」
最終更新日 2022年05月26日投稿日 2021年01月30日
Why doesn’t Japan excel in software as they did in hardware? (なぜ日本はハードウェアの時代と同じようにソフトウェアに秀でることができない?) という英語Quoraのやり取り、分析が興味深かったので、まとめ。
仮説1: 日本は完璧を求める
10人のエンジニアのソフトウェア開発会社を経営しているフランス人の友人が、ルイ・ヴィトン日本支社のコンピュータシステムのマネージャーと同意した話:ソフトウェアはハードウェアではなく、産業用でもない。50年間同じトヨタカローラのように構築され、洗練され、完成されたものではありません。ゼロバグでそれを「完璧」にすることは不可能であり、したがって、「ゼロデフォルト」という、総合的な品質、継続的な改善を求める日本人の精神に反するものです。
日本は職人の国であり、漢字を書いたり、折り紙を折ったりする技術を身につけ、料理や機械工など、どんな芸術でも完璧に仕上げることはできる。しかし、これはソフトウェア開発にとって逆効果である:人は完璧にソフトウェアを磨くことはないし、競争相手であるマイクロソフトは、それよりも先に製品を市場に投入してしまう。
パレートの法則:「最後の20%の時間に80%の時間が費やされる」。日本人がカローラのような古いDOSソフトの改良に80%の時間を費やすのに対し、アメリカ人はテスラのような新しいデザインのWindows ntに80%の時間を投資する。カローラがどうであれ、テスラが勝つということ。どんなDOSソフトより、windowsアプリの勝ち。ソニー/panasonic/京セラ/シャープ/カシオ/...の「ケータイ」が何であれ、AndroidやiOSのようなタッチスマホが勝つ。
日本人は伝統的な階層教育や仕事に縛られている。
マイクロソフト、アップル、グーグル、フェイスブック、それらはすべて天才たちによって作られたもので、ほとんど、大学の中で作られている。日本の大学では、アメリカの大学のように、学生が自分たちのシステムで「遊ぶ」ことを許さないだろうし、日本人の学生には、ビル・ゲイツの基本的なアルゴリズムやグーグルの最初のアルゴリズムを作ったような「副業」をする時間もなければ、大学の「フェイスブック」のような派手な仕事をするという考えもない。
ソフトウェアには非常に高速なイノベーションが必要で、しかしハードウェアよりもはるかに安いので、アップルやマイクロソフトのような小さな企業でもIBMを脅かすことができる。イノベーションにはリスクがある。日本は、最高の学生は、大企業をターゲットにしてしまう。さらに悲しいことに、彼らの頭脳は、大企業で十分に活用されていない。
ソフトウェアは無駄がなく、速く、革新的で、アジャイルな小さなチームで行われる必要がある。これは決して日本の文化ではなく、まさにアメリカの文化。かのヨーロッパの小さな冒険者が古いヨーロッパを飛び去って構築したスピリッツ。
一方中国に関しては:孔子や共産主義が日本と同じように彼らの文化を妨げたり、形成したりしたかもしれないが、彼らは小規模なファミリーの国であり、彼らは、小さなソフトウェア会社を構築し、巨大な市場で十分に販売することができる大きな可能性はある。かつ、中国人は日本のように総合的な品質を求めていない。日本の企業がソフトウェア時代よりも前に、機械産業やその他の伝統的な産業が存在し、優秀なエンジニアを吸収していっていたのに対し、中国の現代産業は後からスタートしたため、伝統的な機械産業よりもソフトウェア産業をスタートさせるのが簡単だった。そういったタイミングの問題もあるかもしれない。
仮説2: 日本のソフトウェア開発職は他の技術職と同じではない
日本では、毎年、大卒の新入生が数千人規模の巨大なキャリアフェアで仕事を探しながら行進する習慣がある。これを私は「ペンギンの行進」と呼んでいる。彼らは皆、新品の黒のスーツに真っ白なシャツを着ている。
企業は履歴書を受け取り、面接を行い、おそらく次の面接への招待状を出す。これらの企業の誰もが、あなたが何を勉強したか、何に情熱を持っているかについて気にしていない。一流の学校(東大、慶応、早稲田、東工大など)の出身であることを聞くことで、企業は興奮するのかもしれない。
仕事をする上で知っておくべきことはすべて教えてもらえる。
メルカリや楽天(日本のeBayとAmazon)のような国際的企業で働いている人たちは、これがテック企業の採用方法ではないと言うだろう。しかし悲しいことに、彼らは無知な新卒者を雇って訓練し、もっと国際的な企業できちんとしたソフトウェア開発者に育てろと言われてもできない。それに耐えられるだけの外国人は十分にいるが、ソフトウェア開発会社の大多数はそのようには動いていない。
結果当然のことながら、日本のソフトウェア開発会社の多くは、質の低いエンジニアリングチームを抱える。ソフトウェア開発は、経理、秘書、プロジェクト管理、経営分析など、数ヶ月から1年で習得できるスキルとして見られているのである。
仮説3: 英語が話せない
当然のことながら、英語が読めない、話せない場合、ソフトウェア開発に使うツールや開発方法は、ドキュメントや記事の翻訳にボランティアで時間を割いてくれる人たちによって、英語のソースからどうにか移入してきたものになります。
日本のソフトウェア開発の最先端は、世界に比べて半年から7年も遅れている。ソフトウェア開発が逆ピラミッド方式である。
ほとんどの技術コンサルティング会社は、実際には開発者を持っていないか、あるいは手元に一握りしかいない。彼らは、順番に少ない会社に彼らの仕事をサブあるいはもっと契約するトーテムポールのような企業に彼らの仕事を契約する。製品に取り組んでいる実際の開発者は、5次下請け契約レベルである可能性がある。ビジネス要件の変更を管理することができない。契約書をやりとりする人々は、それらを提案するものと同じように技術的には知識がない。
消費者も非常に保守的な嗜好を持っている。日本企業が今でも採用している絶対的に前衛的なウェブサイトのデザインを見たことがあるだろうか。日本最大のオンライン旅行代理店サイト: www.jalan.net。 日本のウェブサイトが「ゴミ」のように見えるのは、デザイナーがこうしたいと思ったからではない。日本のオーディエンスがこのようなサイトを好むからである。彼らは、巨大で気が散るように点滅するバナーが好きなのだ。圧倒的な量のテキストが好きなのだ。彼らは、あなたや私がウェブサイトのコンテンツを装った粗雑で洗練されていない広告と呼ぶものが好きなのだ。
それゆえ、国際的な注目を集めながらも、国内のユーザーを疎外するようなモダンなデザインを作るか、何十年も前からやっているように既存の顧客にサービスを提供するかという究極の選択、どちらかになってしまう。後者を選ぶことが自明。
仮説4: 国際標準との互換性
1984年に、私はSORDという日本の会社で働いていましたが、ビジネスウィークに「日本のアップル」と書かれていました。この会社は日本で最も急成長している会社で、独自のパソコン、独自のオペレーティングシステム、表計算ソフトを開発しています。
ほぼ同時期に、IBMが独自のパソコンを開発し、アップルがリサを開発していた。Macが出てこようとしていた。SORDの社長は私をアメリカに派遣して市場調査をさせた。私の報告では、アメリカではIBMのPCが話題になっていて、互換性のない日本のコンピュータには誰も興味を示さないようであった。SORDは、アプリケーションはすべて自社で開発しようという方針で、IBM PC用にサードパーティが開発したソフトウェアにはついていけない。
私は社長に、自分のコンピュータをIBM互換にしない限り、米国市場に参入しようとしないようにアドバイスした。しかし社長は動揺し、自分が持っていたもので米国市場に参入しようと、他の人を雇った。結局失敗し、SORDは東芝に買収され、社長は買収されたお金を持ってIBM互換のパソコンメーカーを立ち上げた。
その後、シャープ、NEC、エプソンなどがIBM互換だが日本語で使えるパソコンを作り始めたが、貴重な時間が失われている。IBM互換のソフトウェアのドキュメントは英語から始まり、日本語になるのはかなり後になってからである。そのため、ソフトウェアエンジニアはドキュメントを見ながら作業を進めることはできるが、かなりの労力が必要になる。
おわりに
我々の業界を内から見るのとは異なり、外から、さらに海外の目線からどのように分析されているのか、共感する部分があったりと非常に興味深い議論です。辛辣なコメントも垣間見られます。日本のソフトウェア開発者として、どのような感想を抱くでしょうか。
2021.05.31 追記
その後こんな話も、という記事を参考までリンク。
2021.08.28 追記
2021.09.29 コメントいただき追記
【KNN特約】ネットエイジへ続け!--数億円で事業を売却した新タイプのベンチャー成功術
1999年04月12日 00時00分更新
文● KandaNewsNetowork、神田敏晶
お気に入り
'99年4月5日、渋谷のインターネットベンチャー、(株)ネットエイジを巡る動きに、日本のベンチャービジネス関係者が沸いた。ネットエイジの運営するオンライン新車見積り取り次ぎサービス“ネットディーラーズ”が、ソフトバンクグループに売却されるという発表があったからだ。しかも売却額は数億円。日本のインターネットベンチャーの新しいビジネスモデルが誕生した。
自動車販売仲介サービスをソフトバンクに売却
売却先は、4月末に設立されるカーポイント(株)である。これは、 ソフトバンク(株)が50パーセント、米マイクロソフト社が40パーセント、ヤフー(株)が10パーセントずつ出資して設立される合弁会社。マイクロソフトが米国で運営する“カーポイント”と同様のサービスを、日本でも11月に事業化する。インターネットを利用して、自動車販売仲介サービスを提供するというものである。
ソフトバンクへの売却を発表したネットエイジの“ネットディーラーズ”事業部門のロゴ
ネットエイジ代表取締役社長の西川潔(にしかわ・きよし)氏は、コンサルティング会社、AOLジャパン(株)を経て、'98年の2月にネットエイジの設立に臨んだ。現在、日本のインターネットのベンチャーの多くが、ウェブサイト制作、サーバーホスティング、インターネット広告というクライアント依存型ビジネスを目指している。その中で同社は自らが事業を創造していこうとする創造型インターネット事業のスタイルを確立した。
宴会場検索システムの “スペースファインダー”に始まり、“Yahoo自動車”への情報提供サービスの立ち上げ、そして今回の“ネットディーラーズ”と、この1年間に意欲的なチャレンジを繰り返してきた。
・スペースファインダー
http://www.spacefinder.net/
・Yahoo自動車
http://autos.yahoo.co.jp/
・ネットディーラーズ
http://www.netdealers.co.jp/
すべてに共通する点は、探したい人の立場に立ち、しかも情報をインターネットで提供するという手法だ。インターネットビジネスで成功した米国企業300社以上の事例を綿密に調査することで、西川氏が得た答えなのだろう。同氏は脳裏で、自社に適しているビジネスモデルを、常に模索していたに違いない。
売却は計画的犯行?
今回のソフトバンクグループへの売却について、西川氏に「計画的犯行では?」と意地悪な質問を投げかけてみた。
(株)ネットエイジ 西川潔代表取締役
「計画的犯行だなんて、めっそうもありません」と西川氏は即座に否定した。売却のタイミングについて次のように続ける。「ただ、EXIT(創業者が経営の前面からは退いて運営型の人物にバトンを渡す)の方法として、いつか事業売却もあるだろうな--というのは、最初から意識していました。米国ではごく当たり前ですから。今回は、たまたまネットディーラーズがヤフーさんと提携してやっていたことと、孫さんとビル・ゲイツ氏との約束の分野が自動車だったことの、2つの幸運が重なりました」--。
ヤフーとの提携がすべてのチャンスのきっかけになった、と西川氏は言う。実際に米ヤフー社も、創業時には、米ネットスケープ社に間借りしながら成功のチャンスをつかんだという経緯がある。双方の企業にメリットがあれば、ヤフーは“Yahooブランド”を利用した事業に積極的である。
日本の場合、大企業が提携するとなると、実現するまでてんやわんやの大騒ぎである。しかし、米国の場合、事業提携が非常にスピーディーだ。そして決断も速ければ、結果が出るのも速い。それは“失敗したら提携をやめればいいだけ”と考えているからだ。インターネットビジネスでは、スピードが成功の最大の秘訣。先にブランドを浸透させてしまえば、はるか彼方にまで飛べることをみんな知っている。
スタートダッシュと情報装置産業
西川氏によれば、“Yahoo自動車”に提供するためのコンテンツの収集は、当初、予想以上に難航した。自動車メーカーも、どこの馬の骨かわからない企業に、車種のリストをおいそれと渡しはしない。ある時は雑誌、ある時は電話、そしてある時は、客をよそおい、車種のカタログを集め回った。西川氏に勝算があったからこそできた行動だ。
そして、そのリストのデータベースがあるからこそ、次のネットディーラーズの事業へと結び付く。今度は利用者が知りたい情報を持っているカーディーラーの開拓だ。西川氏は、ディーラーへの説明会のため、東へ西へと奔走し、靴底を減らした。
データベースには、装置産業のような性格がある。網羅型のデータベースは、いくら追い掛けたところで、先行した企業と同じものになるのがせいぜいである。とすれば、スタート時にダッシュして、コストの回収を早く始めた先行企業の方が有利になる。
こうしたインターネットの論理に、早くから気付いていたという点でも、西川氏は突出している。そして、それを実践した数少ない日本人の1人でもある。請負型のインターネットビジネスの限界を知っているからこそ、創造型のインターネットビジネスを推進できたのだろう。
サービス分野でのナンバーワンを目指すソフトバンク
そんな彼に注目したのが、ソフトバンク代表取締役の孫正義氏だ。ヤフーの大株主でもある。株価の高値で、自社以上の規模の企業を買収したのである。孫氏はインターネットビジネスを、「インフラの時代、サービスの時代、コンテンツの時代」とセグメント化する。「インターネットは、ようやくサービスの時代へと向かっている最中。まだまだコンテンツの時代ではない」とも語る。
また、同氏は「インターネット前史のシステム時代を代表したのはIBM。しかし、インターネット時代のサービスではヤフーだ。今後サービスの分野でソフトバンクグループはナンバーワンになる」と豪語する。
孫氏の手法は、米国ではインターネット時代の“ケイレツ”と称されている。ソフトバンクは他社に類をみないような資本投下による系列化で、インターネットのギガサイトともいえる“ネット系列”を完成しつつある。この系列が完成してしまえば、新規参入のチャンスは皆無になってしまうはずだ。
売却はベンチャー企業の1つのゴール
今回、事業を売却、そして買収された立場であるネットエイジでは、やんやの大賑わいであった。ベンチャー企業の成功理想形の1つなのである。日本流の“買収された”というネガティブなイメージはまったくない。「継続するか売り時か?」という合理的な判断の結果、売却という答えを出した。
かといって売り逃げではない。カーポイントの立ち上げに向けて、今後も協力していく。返済の必要のない潤沢な資金を、銀行でもなく、またベンチャーキャピタルでもない、自分たちの事業によって得た。新規の事業にさらに投資できる体力を身に着けたのである。
このことは、事業部門の1つのゴールとも言えるだろう。その規模が数億円で、孫氏のお年玉が含まれていたとしても、日本のインターネットベンチャーにカンフル剤を与えたことに違いはない。
西川氏は、また、新たなインターネットビジネスのインキュベーターでありたいとも明言する。ソフトバンクの“ネット系列”をもフルに活用する勝算があるのだろう。
苗木で売るから庭は要らず、鉢だけで済む
ネットエイジのビジネスモデルの目標は、ソフト的なインキュベーター、米idealab! である。カリフォルニア州パサデナに本拠を置き、インターネット上でアイデアのあるベンチャーに対してのみ投資する。米GoTo.com社や米Free-PC社をインキュベートした実績を誇る。
米GoTo.com社が運営する検索サイトは、有料広告を優先して露出するという、マーケティング主導による検索システム。また、米Free-PC社は、ディスプレーに広告を強制的に表示させることで、ユーザーに無料でパソコンを提供する企業だ。出資者は種をまき、苗木になるまで育てる。そこまできたら、他力利用で成長させ、投資を一気に回収する--というビジネスモデルだ。
このように、今までにないソフト型のインキュベーションの図式が、すでに米国では構築されている。アイデアのあるベンチャーと、それを支援するインキュベーターとで構成される。株式公開まで付き合うという、従来のベンチャーキャピタルに多いパターンとは違ったサポートの形である。
ハード設備を重視したインキュベート施設とは意味がまったく違う。ハード重視の姿勢には、不景気の時代の空きビル対策といった、本末転倒ともいえる思惑まで隠れていた。アイデア先行の時代には、広々としたフロアも豪華なキューブも不要だ。ましてや高価なハード機器は、インターネットベンチャーには無用の長物となりつつある。
・米GoTo.com社
http://www.goto.com
・米Free-PC社にリンク
http://www.free-pc.com/
・米idealab!にリンク
http://www.idealab.com/
車小屋か兎小屋か
ネットエイジの拠点は、東京・渋谷の繁華街に入ってすぐのところにある。狭い階段をのぼった2階の2LDKの中古マンションには、ひしめきあうように人が詰めている。西川氏は「この狭さがベンチャーなんですよ」と言うが、本当に窮屈である。オフィス環境は決してお世辞にもいいとはいえないが、この凝縮した空間には、ベンチャーの活気が満ちあふれていた。
ふすまを開ければ会議室へとつながるのも和室ならでは。ドアではこうはいかない
シリコンバレーの会社のスタートアップが、ガレージカンパニーといわれるのは、自宅の中で比較的スペースを自由にできるのが、ガレージぐらいしかなかったからである。基本的にガレージはどの家にもある。日本では、それがマンションカンパニーとなる。
道路を隔てた別室の開発チームの面々。道路を隔てていてもインターネットラインは届いているから不思議だ
全景を入れるとこうなる
風呂や押し入れを改造して、少しでもオフィスニーズに合う形を作る。そんなマンションカンパニーでは、大声を出せば一気に情報が共有できる。電話で喋る声だけで営業結果がわかるメリットもある。またシリコンバレーでは、朝夕のラッシュ時に身動きができなくなるが、日本では、その心配もない。公共交通機関で1日に何社も訪問し、打ち合わせをいくつも持つことができる。
来客が多いと玄関のドアが靴で締まらない。ここまで集まることは珍しい。ともかく、渋谷の立地を活かし、いつも誰かとコンタクトがとれる
トイレの壁と溜まり場とサーバーとの共通点
西川氏は、ネットエイジのビジネス以外にも、渋谷を日本のシリコンバレーにしようという“Bit Valley構想を提唱している。bitは、“bitter”(苦み、渋み、渋谷の渋)にもつながっているらしい。
・“Bit Valley構想”
http://www.netage.co.jp/html/nacr/30.shtml
“Bit Valley構想”は、まさにそんな渋谷エリアを中心とした、ネット系ベンチャーのコミュニティーの呼称である。ネットエイジは、その旗手ともいえる。サービス開始からわずか2ヵ月、準備を含めても1年に満たない期間で数億円もの資金をゲットしたネットエイジのチャレンジ。
トイレの壁は情報共有のクリッピングボード。ゆっくりと情報を共有できる場所は、もはやここにしかない。渋谷でbit valley、厠で踏ん張り、人が集まる、便がよい
しかしそれは、海の向こうの話ではない。超リアル感をもって日本のネット系のベンチャーを、十分刺激したことであろう。日本のインターネットベンチャーが、創造型インターネットサービスへ知恵と勇気を注ぎ込むことに期待したい。「ネットエイジへ続け!」と。
インド株ETF〜注目されている3つの理由とは?おすすめランキング5選も大公開
急速な経済発展を遂げているインドETFに注目が集まっているおすすめインドETFは5種類
メリットは値上がりが期待でき、分散投資がしやすいこと
デメリットは新興市場ならではの不透明性
「今インドETFがおすすめされているって本当?」
「どのインドETFに投資すればいいかわからない」
ここ最近、その驚異的な経済成長と多様な投資商品、さらにはリスク分散が可能なことで、インドETFは注目の的となっています。
この記事では、注目のインドETFについて、その魅力からおすすめの銘柄、そして投資の方法まで詳しく解説します。
記事を読むことで、インドETFへの疑問を解消し、投資戦略を明確に描けるようになるでしょう。
※この記事は2023年7月時点の情報をもとに作成しています。
インド株ETFに投資できるおすすめ証券会社
【楽天証券】
⇒ 楽天ポイントが使えるので自己資金を抑えられる!各種キャンペーンが充実!
口座開設(公式サイト)はこちら
【松井証券】
⇒ 大手ネット証券の安心感!専門スタッフに投資判断を相談できる!
口座開設(公式サイト)はこちら
【SBI証券】
⇒ 株式取引シェアNo.1!住信SBIネット銀行と連携して為替手数料を削減可能!
口座開設(公式サイト)はこちら
【マネックス証券】
⇒ 米国株投資が強みで買付時の為替手数料は無料!インドADR 9銘柄!
口座開設(公式サイト)はこちら
【IG証券】
⇒ 日本・米国株、世界のETFをCFDでレバレッジ取引可能
口座開設(公式サイト)はこちら
目次 - Contents [非表示 - hide]
インド株ETFが注目されている理由
最近、急速に成長を遂げているインドの株式市場。その中でも特にインド株ETFが投資家から広く注目を集めています。
その理由は、著しい経済成長と多様な投資商品の存在、そして投資リスクの分散が可能な点にあります。
このセクションでは、それらの魅力を詳しく掘り下げ、なぜインド株ETFが注目されているのかを理解していきましょう。
急速な経済成長:2023年に世界1位の人口水準

インドの経済成長の躍進は、圧倒的なスピードで進行しています。
IMF(国際通貨基金)によると、来年度のインドの実質GDP成長率は6.3%と予想され、新興国の中でも特に顕著な高成長を遂げています。
これは、中国の4.5%という数値を大きく上回るもので、インドの経済活動の活発さを象徴しているといえるでしょう。
さらに、世界のGDPランキングを見ても、インドの成長は明らかです。
2050年には、インドは米国を抜き、中国に次ぐ世界で第2位の経済大国になると予想されています。これは、人口増加に伴う巨大な市場の存在と、それを支える労働力の増加が大きく寄与した結果でしょう。
このような急速な経済成長がもたらす投資チャンスは無限大で、インド株ETFの魅力を一層高めています。
投資家ならば、世界1位の人口水準を持つインドの経済成長には、つねに目を光らせておきたいところでしょう。
多様な投資商品:IT分野を筆頭に様々な分野が成長
インドの経済市場は、その多様性から多岐にわたる投資機会を提供しています。中でも注目すべきは、急成長を続けるIT分野です。
経済全体のデジタル化が進む中、インドのIT企業はその需要に応える形で急速に拡大しています。大手IT企業の出現やスタートアップの活況は、新たな価値を生み出し、国内外からの投資を引き寄せています。
IT分野を筆頭に、製造業、小売業、サービス業といった多様な業種も、インド市場で成長を遂げている最中です。これらの業種も、インド株ETFのバスケットに広く含まれ、投資家に多角的な投資の場を設けています。
このように、インド株ETFは多様な成長産業を網羅し、投資家に対して幅広い選択肢を提供しています。
それぞれの分野の動向を見つつ、効率的に成長市場に投資できるのが、インド株ETFの大きな利点といえるでしょう。
<各分野ごとの代表的なETF投資商品>
分野ETF名称概要ITiShares India 50 ETFインドの主要50社(IT企業を含む)をカバーするインドETF銀行・金融WisdomTree India Earnings Fundインドの収益性の高い企業を対象としたETFで、銀行と金融分野が主体エネルギーInvesco India ETFインドのエネルギー、天然資源、インフラ企業に投資するETF製造業VanEck Vectors India Small-Cap Index ETFインドの製造業を中心に、小型株を対象としたETFヘルスケアMSCI India Health Care Index Fundインドのヘルスケア、製薬分野に焦点を当てたETF
リスクの分散:ポートフォリオを地理的に分散可能
インド株ETFへの投資は、賢明なリスク管理戦略の一環となります。特に地理的なリスクの分散に対して効果的です。
それは、インドという特定の国に投資することで、他の地域における経済の揺れ動きから一定程度遮断されるためです。
具体的には、アメリカやヨーロッパのような先進国に起こる経済の変動とインドの経済動向が必ずしも連動しないことから、インド株ETFをポートフォリオに組み入れることで、先進国中心の投資から生じる地理的なリスクを軽減することが可能となります。
インドは未だ発展途上の経済を持つ大国であり、その成長は内部要因に強く依存しています。このことが、投資リターンを先進国とは異なる方向に導く可能性をもたらし、投資家のポートフォリオ全体のリスク分散に寄与します。
したがって、一部の資金をインド株ETFに振り向けることで、特定の地域や市場の変動リスクから身を守りつつ、全体の投資リスクを効果的に管理することが可能となります。
この機能性は、インド株ETFが投資家にとって魅力的な選択肢である理由の一つです。
信託報酬重視!インド株ETFのおすすめランキングTOP5
ETF名信託報酬ベンチマーク運用会社資産総額 (百万USD)iシェアーズ・コア S&P BSE SENSEX インディアETF (02836)0.64%インド・センセックス・インデックスBlackRock91.028ウィズダムツリー インド株収益ファンド (EPI)0.84%ウィズダムツリーインド収益指数WisdomTree913.590ヴァンエック・ベクトル・インド小型株ETF (GLIN)0.94%マーケット・ベクトル・インド小型株インデックスVanEck54.515NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 (1678)1.045%インドルピーベースのNifty50指数Nomura Asset Management191.6Direxion デイリー MSCI インド株 ブル2倍 ETF (INDL)1.31%MSCI インディア・インデックスの2倍の投資成果を目指すDirexion58.118
※2023年6月27日時点
インドへの投資を検討する中で、コスト効率性を重視するなら信託報酬が低いETFがおすすめ。
ここでは、信託報酬を重視し、インド株ETFの選択肢を5つご紹介します。各ETFの特性やメリットを詳しく解説し、投資戦略に最適な選択をする一助としてください。
iシェアーズ・コア S&P BSE SENSEX インディアETF

「iシェアーズ・コア S&P BSE SENSEX インディアETF」は、世界最大級の資産運用会社であるBlackRockが運用するETFです。信託報酬は0.64%と、インド株に投資可能なETFの中では抑えられています。
このETFの特徴は何と言ってもそのベンチマークである「S&P BSE SENSEX」への追従です。
この指数は、インドのボンベイ証券取引所で取引される上位30社を対象としており、インド経済の動向を反映した投資が可能となっています。
投資適性については、インドの大手企業への投資を希望し、かつ地理的なリスク分散を行いたい投資家に向いていそうです。
大手企業に重点を置くことで、インド経済全体のリスクを分散させることが可能となります。
しかし、同時にリスクとしては、インド経済の動向に大きく影響を受けることや、企業の業績や政策変動による価格変動のリスクが存在します。
投資を検討する際には、自身のリスク許容度と合わせて、これらの点を考慮しましょう。
ウィズダムツリー インド株収益ファンド (EPI)

次にご紹介するのは「ウィズダムツリー インド株収益ファンド (EPI)」です。このETFの信託報酬は0.84%と、やや高めですが、その理由は特有の戦略にあります。
EPIはウィズダムツリーインド収益指数を追跡しています。
この指数は、インド市場における収益性の高い企業を中心に構築されており、そのため一部の高配当銘柄に投資する機会が増えます。
これにより、ポートフォリオに恒常的に一定のインカムをもたらす可能性があります。
このETFの特徴は、成長性と安定した収益性を両立したインド市場へのアクセスを提供する点です。一方、特定の業種に偏りが出る可能性や、高配当銘柄の価格変動によるリスクがあることも認識しておく必要があります。
したがって、EPIは一定のインカムを求め、同時にインド市場の成長に参加したい投資家に適していそうです。
ただし、特定の業種への投資には、景気変動によるリスクもついて回ることは覚えておきましょう。
ヴァンエック・ベクトル・インド小型株ETF (GLIN)

次にご紹介するのは「ヴァンエック・ベクトル・インド小型株ETF (GLIN)」です。信託報酬は0.94%となっています。
GLINはマーケット・ベクトル・インド小型株インデックスを追跡し、その組み合わせにより、インドの小型株市場に広範なエクスポージャーを提供します。
こうした小型株は、大型株とは異なるパフォーマンスを発揮する可能性があり、ポートフォリオの多様化を図ることが可能です。
特に、このETFはインドの経済成長と市場の底上げを期待する投資家に向いていそうです。
小型株は一般的に大型株よりも高いリスクを伴いますが、それと同時に高いリターンの潜在能力もあります。
さらに、インドの小型株市場は多様な業種から成るため、広範なセクターへのアクセスが可能です。
その一方で、小型株は市場の揺れに対する感応性が高いため、市場の波乱要素や短期的な価格変動に耐えられる投資家にとって最適な選択肢となります。
成長を追求し、かつ高いリスク許容度を持つ投資家にとっては魅力的なETFといえるでしょう。
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信

次のETFは、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信」。信託報酬は1.045%となります。
この投信はインドの代表的な株価指数であるNifty 50指数をベンチマークとしています。
Nifty 50指数は、インドの主要な上場企業50社の株価で構成されており、インド経済の様々な業種をカバーしており、インド経済全体の動きを捉えられます。
このETFは、インド経済の成長に対する期待を持つ投資家に適しているといえるでしょう。
特に、インド市場へのダイレクトなエクスポージャーを求める投資家や、既存のポートフォリオに新興市場の多様性を加えたい投資家にとって有益な選択肢となりえます。
しかし、新興市場は先進市場と比較してリスクが高いため、投資前には自身のリスク許容度を評価することが重要です。
また、為替リスクも考慮する必要があります。ドルや円といった他の通貨と比較して、インドルピーは揺れが大きい傾向にあるので、この点はしっかりと頭に入れておきましょう。
Direxion デイリー MSCI インド株 ブル2倍 ETF (INDL)

最後にご紹介するETFは「Direxion デイリー MSCI インド株 ブル2倍 ETF (INDL)」で、信託報酬は1.31%となります。
特筆すべきは、このETFがレバレッジ型のETFであるという点です。
このETFは、MSCIインディア指数の2倍の値動きを目指しています。つまり、ベンチマークとなる指数が1%上昇すると、ETFの価値は約2%上昇することを目指しています。
この効果は「レバレッジ」と呼ばれ、投資の世界では自己資金を膨らませて投資を行う手法を指します。
しかし、その一方で、リスクも2倍になることを覚えておくことが重要です。つまり、指数が1%下落した場合、このETFは約2%の価値を失う可能性があります。
また、レバレッジETFは基本的に短期的な取引を目指すもので、長期保有を前提とした商品ではありません。これは、レバレッジETFが日々のリセットを行うため、長期間保有すると期待したリターンと異なる結果を招く可能性があるからです。
結論として、Direxion デイリー MSCI インド株 ブル2倍 ETF (INDL)は、高リスク高リターンを求める経験豊富な投資家や、短期的な取引を行うデイトレーダーにとって魅力的な選択肢といえるでしょう。
インド株ETFに投資するメリット
インド株ETFに投資をすることは、経済が安定していない新興市場に投資する一種の冒険のように見られがちです。
しかし、それは決して無謀な挑戦ではありません。そこには様々なメリットが存在しています。
新興市場特有の急速な経済成長、豊富な投資選択肢、そして効率的なコスト管理など、インド株ETFは投資家に対して多くのメリットが存在します。
このセクションでは、インド株ETFに投資をするメリットを詳しく解説します。
急成長する新興市場ならではの値上がりが期待できる
分散投資がしやすい
他の新興市場と比較してアクセスしやすい
コスト効率が良い
セクター特化型ポートフォリオが組みやすい
これらのメリットについて、一つ一つ詳しく見ていきましょう。
メリット① 急成長する新興市場ならではの値上がりが期待できる

経済指標を見ると、インドは急速に成長している新興市場であり、これはインド株ETFへの投資にも大きな意味を持ちます。
例えば、2023年の1-3月期のインドの実質GDP成長率は前年同期比+6.1%となり、前期の+4.5%から上昇しました。これは、市場予想の+5.0%を上回る数値で、インドの経済が健全に成長を続けていることを示しています。
成長の要因を見ても、内需が堅調に推移しています。
民間消費は前年同期比で+2.8%と上昇し、総固定資本形成は+8.9%という成長を達成。これは企業の投資活動が活発であることを示し、これが企業の収益増加や株価上昇につながります。
外需面でも、輸出が前年同期比で+11.9%と大幅に増加しています。
これはインドの製品やサービスへの国際的な需要が高まっている証拠であり、インドの企業にとっては追加の収益源となります。
また、産業部門別に見ると、第三次産業の成長が特に顕著で、前年同期比で+6.9%の成長を達成しました。
特に貿易・ホテル・交通・通信は+9.1%、金融・不動産は+7.1%という成長率を示し、このセクターに投資している企業の収益も増える可能性があります。
これらの成長指標は、インド株ETFの将来的な価格上昇を見込む強力な理由となります。
もちろん、必ずしも株価上昇を保証するわけではありませんが、経済全体の成長は通常、企業の収益増加や株価上昇と密接に関連しています。
メリット② 分散投資がしやすい
投資の基本的な原則として「リスクを分散させる」という原則があります。
つまり、一つの企業や一つの市場だけに投資を集中させるのではなく、複数の異なる資産に投資を行い、リスクを分散する必要があるということです。
ここで、インド株ETFが大きなメリットを発揮します。
インド株ETFは、インドの株式市場全体を代表する幅広い企業群を包含しています。
これにより、一つのETFを購入するだけで、インドの多様な業界や企業への投資が可能となり、資産の分散が容易になります。
具体的には、インドの情報通信業、金融業、製造業など、様々な産業への投資を一度に行うことが可能です。
そのため、一つの業界や企業が経済的に困難な状況に遭遇したとしても、他の業界や企業の好調さがそれを補い、全体のリスクを軽減します。
これは、個別のインド株を選択して投資を行うのとは異なり、選択の難しさやリスクを軽減しながらインド市場に投資する効果的な方法です。また、その過程でインド経済の広範な成長を享受することが可能となります。
このように、分散投資が容易になるという点が、インド株ETFに投資する大きなメリットの一つです。
メリット③ 他の新興市場と比較してアクセスしやすい
新興市場への投資は、高い成長潜在性と共に一定のリスクを伴います。その中で、インド株ETFは他の新興市場に比べて「アクセスのしやすさ」が特徴的です。
新興市場に直接投資する場合、その国の言語、法律、証券取引所のルールなどを理解し、対応する必要があります。これは、投資家にとって高度な知識と経験、そして時間を必要とする場合が多く、難易度が高いといえます。
しかし、インド株ETFの場合、これらの問題は大幅に軽減されます。
ETFは各国の主要な証券取引所で取引されるため、投資家は自国の取引所やオンラインブローカーを通じて容易に投資を行うことができます。
また、ETFは一般的に広範な企業をカバーしており、特定の企業や業界のリスクを受けにくいという特性も持っています。
さらに、インドの証券市場は透明性が高く、国際的な規範に準拠しているため、他の新興市場と比較すると投資家が投資情報を得やすく、投資判断を行いやすいという利点もあります。
メリット④ コスト効率が良い
投資における重要な要素の一つがコストです。より少ない費用で効果的な投資をできれば、利益率は自然と高まります。
ETF(Exchange Traded Fund)はその構造上、管理コストを抑えられるメリットがあります。これは、投資信託に比べて運用コストが大幅に削減できるためです。
具体的には、ETFは証券取引所で取引され、売買が直接行われるため、投信と比べて取引コストが低く抑えられます。
また、インド株ETFはインドの多様な企業群を包括的にカバーしています。これにより、一つのETFを購入するだけで、多数のインド企業へ投資することができます。
もし個別の株式を直接購入する場合、手数料が各取引ごとに発生しますが、ETFを通じてインドの株式に投資することで、これらの取引コストを大幅に削減することが可能です。
このように、インド株ETFは、他の投資手段と比較してコスト効率に優れています。
メリット⑤ セクター特化型ポートフォリオが組みやすい
投資において、特定のセクターに注力することは、その分野が持つ成長の潜在力を最大限に引き出す手段となります。そして、インド株ETFは、特化型のポートフォリオを組む上での優れた方法となり得ます。
インド経済は、その多様な産業と急速な成長により、多数の投資機会が選択できます。
特に、ITや製造業などの急成長セクターにおいては、インドの優れた労働力と高い成長率が相まって、大きなポテンシャルがあります。
また、セクター特化型のETFを使用することにより、個々の銘柄を一つ一つ選ぶ手間を省くことが可能となります。これは、特に外国の市場について詳しくない投資家にとっては、時間と手間を大幅に節約することにつながります。
さらに、セクター特化型のインド株ETFを組み合わせることで、自分だけのカスタマイズされたポートフォリオを作ることも。
例えば、IT分野に重点を置きつつ、製造業や消費者分野へのリスク分散を図るといった具体的な戦略が容易に実現できます。
このように、インド株ETFを用いれば、特定の成長セクターへの集中投資と、全体としてのリスクの分散という、二つの投資戦略を同時に実現することが可能となります。
インド株ETFに投資するデメリット
投資はリスクとリターンがセットになっています。インド株ETFへの投資も例外ではありません。
ここまで、インド株ETFの魅力について説明してきましたが、一方で無視できないデメリットも存在します。
これらは慎重に考慮するべき重要な要素であり、意識せずに投資を進めると、思わぬ損失を被る可能性があります。
政治的不安定要素に左右されやすい
新興市場のため情報をキャッチアップしにくい
ボラティリティが高い傾向にある
これらのポイントを頭に入れて、投資の検討を進めていきましょう。一つ一つの要素については、次のセクションで詳しく説明します。
デメリット① 政治的不安定要素に左右されやすい
インドは急速な経済成長を遂げており、2014年のモディ大統領の就任以降、アジア3位の経済大国にまで昇り詰めています。
しかし、その経済の底流には依然として不確定要素が存在します。その一つが政治的不安定性です。
一次産業への依存が未だ続いており、経済の安定化にはインフラ整備や不良債権問題の解消などが必要とされています。
新興国投資には、一般に「カントリーリスク」がつきものです。
インドの場合、政治的な状況の変動や予期せぬ自然災害などがこのリスク要因となり得ます。これらはインド国内の経済活動を直撃し、それが結果としてインド株ETFのパフォーマンスにも影響を及ぼします。
インド株ETFに投資する場合、これらのリスク要素は必ずしも予測可能なものではないと認識することが重要です。
投資を進める上で、日本ではなかなか見ることのないこれらのカントリーリスクを理解し、投資戦略に反映させていくことが求められます。
デメリット② 新興市場のため情報をキャッチアップしにくい
新興市場であるインド株市場に投資する際の一つの課題となるのが、情報の入手難易度です。成熟した市場、例えば米国株や日本株に比べて、インド株についての情報は少なく、かつ流れてくる情報の速度や量も十分とはいえません。
情報収集が困難であると、投資判断に必要な情報の非対称性が生まれ、市場の透明性が低下し、投資を困難にする恐れがあります。
具体的な対策としては、インド現地のニュースサイトや新聞などから直接情報を得ることが有効です。また、証券会社が提供するレポートや分析情報も役立つでしょう。
さらに、SNSを活用する手もあります。Twitterにはインド株に関する情報を配信しているアカウントも存在しますが、SNSの情報は必ずしも真実とは限らないため、信頼性の裏付けは必須です。
以上のような事実を考慮に入れ、インド株ETFに投資する際は、情報収集に向けた適切な戦略を立てることが重要となります。
デメリット③ ボラティリティが高い傾向にある
新興市場特有の特徴として、インド株ETFのボラティリティ、つまり価格の変動率が高いという点を理解しておくことが重要です。
一般的に、成熟市場に比べて新興市場の株価は大きく揺れやすく、その結果、インド株ETFも一定のリスクを孕んでいます。
この高いボラティリティは、大きなリターンのチャンスを提供する一方、同時に潜在的損失のリスクも伴います。例えば、インドの経済が急速に成長すれば、それに伴ってETFの価格も上昇する可能性があります。
しかし逆に、経済的・政治的な不安定性から株価が大きく下落すると、投資家は大きな損失を被る可能性もあります。
したがって、インド株ETFに投資する際には、そのボラティリティの高さを理解し、自身のリスク許容度に合わせた資産配分を慎重に考えることが必要です。
また、定期的なポートフォリオの見直しやバランス調整も、このリスクを管理する上で重要な手段となります。
インド株ETFに投資するには?
インド株ETFへの投資は、投資家がインドの急速な経済成長を活用し、ポートフォリオを多様化するための一つの方法です。
ここからは、具体的にインド株ETFに投資するためのステップと手順を解説します。
また、インド株ETFを取り扱う証券会社も紹介するので、投資初心者でも簡単にETFの買い方が理解できるようになります。
インド株ETFを取り扱っている証券会社一覧表
日本国内でインド株ETFに投資するためには、以下の証券会社がおすすめです。
証券会社名取扱商品数特徴サポート内容

公式サイトヘインドETF
8本楽天ポイントが使えるため、自己資金を抑えた投資が可能楽天ポイント連携
各種キャンペーン

公式サイトヘインドETF
9種類使い勝手が良い取引アプリとロボアドバイザーによる運用サポートが特徴米国株サポート
ロボアドバイザーによる運用サポート

公式サイトへインドADR
8銘柄株式取引シェアNo.1。
住信SBIネット銀行と連携して為替手数料を削減可能Tポイント連携
住信SBIネット銀行との連携

公式サイトヘインドADR
9銘柄米国株投資が強みで、買付時の為替手数料は無料米国株投資サポート

公式サイトヘインドETF
11銘柄CFD取引が強みで、無料のオリジナル学習コンテンツ「IGアカデミー」が利用可能CFD取引サポート
オリジナル学習コンテンツ「IGアカデミー」提供
※各社のロゴを選択すると公式サイトへ遷移します
それぞれの証券会社の特徴、サポート内容、そして取扱商品数を参照して、自分の投資スタイルに合った証券会社を選びましょう。
【ワンポイント】ADRとは?
ADR(American Depositary Receipt)は、米国以外の企業が発行する株式を米国の証券市場で取引するための証券。これにより、投資家は外国の企業株式を、自国の市場と同じ方法で取引することが可能になります。
初心者でもわかるインド株ETFの買い方手順
投資は難しく感じるかもしれませんが、手順を一つずつ追っていくことで、あなたが思っているよりも簡単にインド株ETを購入できます。
以下に、口座の開設からETFの選択、購入注文の発行までを具体的に説明します。ここではSBI証券を例に解説していますが、その他の証券会社でも手順はほとんど同じなので、ぜひ参考にしてください。
STEP1.証券会社の選択と口座開設
Apple年次報告書から推察〜ジョブズとスカリーの関係2
私の手元にある1983年と1985年のApple決算報告書を元に当時のAppleがどのような状況にあり、スティーブ・ジョブズおよびジョン・スカリーの関係がどう変化していったかを追ってみた第2弾である。先般ティム・クック体勢が始まって以来の大きな人事異動が発表されたが、1985年にジョブズが退職するに至る当時のニュースは桁違いに我々を驚愕させ不安にさせたものだ。
前回ご紹介した1983年の年次報告書に続いて今回は1985年の四半期決算報告書をご覧いただくが、こちらは “First Quarter Report 1985” と記されているように対象期間は1984年10月から12月までの四半期決算を年が明けた1985年早々に報告書としてまとめたものとなる。
※Apple “First Quarter Report 1985” 表紙
まずこれらの報告書は株主に対して当該四半期の業績を報告すると共に自社の優位性や次期への展望などを示し、株主らに理解と支持を得るための資料であるが、この1985年第4四半期報告書は四半期のものだという点を考慮に入れてもページ数が12ページと前回ご紹介した1983年年次報告書の28ページに比較すると随分とシンプルなものだ。したがってAppleが最もアピールしたいあれこれが凝縮して記されていると考えて良いし無論触れられたくない部分はいかに隠し、話題を他に逸らせるかにも苦心するのは当然だろう(笑)。
さてそこに記されているスティーブ・ジョブズの役職名は1983年と同様に取締役会会長および上級副社長兼マック部門ジェネラルマネージャーだし、無論ジョン・スカリーは社長兼最高経営責任者だ。この点は変わっていない。
また2人のサインだが、1983年の時とは違って上下ではなく左右に列記されているものの今度は明らかに左に記されているジョン・スカリーの方が先と見て良いだろうし、事実最後のページにある "Officers" の記載を見るとスカリーがトップで次にジョブズの名が記されている。またスティーブ・ジョブズのサインは前回ご紹介したように1983年度の年次報告にはミドルネームが記されていたがこの “First Quarter Report 1985” にはそれがない。さらに印象的なのは前記した1983年の年次報告書のように2人並んだ写真は使われていない…。
こうした詮索は些細なことに見えるかも知れないが意外と当事者たちの心理やパワーバランスを表していることもあるので無視できないと考えている…。
※ジョン・スカリーとスティーブ・ジョブズのサインページ
“First Quarter Report 1985” の表紙は1984年4月にリリースされたApple IIcが使われている。また見開きのカラーで当時テキサスにあったApple IIc 製造ライン(自社工場)が紹介されているページが目立っている。
※当時テキサスにあった自社工場 Apple IIc製造ラインが見開きカラーで紹介されている
私見ながら1983年の年次報告書と比較してこの1985年第1四半期報告書はアップルフリークの眼で眺めても面白くない。
1983年のそれがダイナミック・デュオをアピールし、アップルの未来を明るいイメージに導こうとした印象だったのに対し、1985年の報告書は型どおり無難に収めた…といった感じだからだ。
繰り返すが表紙は自社製品の写真、内容も自社工場やユーザー事例としてなのだろう、才能ある若い人たちを支援するためのようだがScience Talent Searchという組織が主催した科学研究コンテストで入賞した女性をApple IIユーザー事例として紹介したりと何か大人しく納まった感じを受けるのだ。個人的にはもっと伝えるべき情報があってしかるべきだと思うが、どこかページ数をそれらで稼いでいると受け取るのは私の悪い癖か…(笑)。ともかくAppleらしい斬新さとか創造性といったエッセンスが感じられないのである。
※営業成績推移のデータが簡単なグラフで紹介されているページ
その原因・要因は前回で見てきたように、この頃Apple…特にエグゼクティブたちには暗雲が立ちこめていたからに違いない。報告書の細部にまで凝る余裕がなく制作会社任せになったのだろう…。
この1985年の四半期報告書は…繰り返すが、Appleがそうした軋轢にさらされていた時期のものだということを考慮に入れると、すでにジョブズとスカリーの仲はかなりギクシャクしていたに違いない。そして少しずつではあるが経営の実権はジョン・スカリーに移っていったのだろう…それが前記したようにサインの記載順にも表れていると思われる。
幸い1984年10月から12月までの1985年度第1四半期決算はクリスマス商戦に助けられたのか赤字は出ていないものの、Appleの社内は創立以来初めて大きな危機感が漂っていたはずなのだ。
そしてこの報告書が配られた前後には売れない Lisa 2/10 をMacintosh XLと改名し延命を図ろうとするが、これまた早々に出荷を停止するはめとなる。ましてやMacintoshの在庫も膨れあがり、その責任はスティーブ・ジョブズの言動にあるとして追求が始まりジョブズとスカリーの仲は修復不可能なまでとなり、同年の5月にジョブズは総ての職を解かれ、9月に辞表提出を余儀なくされた…。
くどいようだが、ここで2人のサインをもう1度確認するが、実は1983年のそれと比較して見ると面白いことが分かった。
前記したように1985年の四半期報告書のスティーブ・ジョブズのサインは1983年度年次報告書とは違い、ミドルネームがないことは明白だし両方のサインを比較してみれば明らかに別途書き直したものということが分かる。
※スティーブ・ジョブズのサイン。上が1983年、下が1985年
それに対してジョン・スカリーのサインは1983年のものと今回の1985年のものとをサイズや角度を合わせて重ねて見るとピッタリと符合するのである。これは明らかに1983年に使ったデータを1985年の四半期報告書にも再利用したことになり、深読みすれば余裕のなさと共に他人任せの感じがする。
※ジョン。スカリーの1985年のサインを1983のそれに重ねるとピッタリと符合する
まあまあ…相変わらず深読みが過ぎるかも知れないが、業績の悪化と共にジョブズとスカリーの関係は決定的な曲面を向かえることになり、残念なことはその後ジョブズが亡くなるまで2人の関係は修復されることがなかった。
後にジョブズはスタンフォード大学における有名なスピーチでアップルを離職したことは自分の人生にとってもっとも重要な出来事だったとポジティブに振り返った。無論心に大きな傷を受けたのはジョブズだけではなかった。スカリーにとってはその後「創業者を追い出した男」というレッテルが貼られたし、ことあるごとにあの時ジョブズを追いやったことは間違いだったと公言している姿は痛々しい。
そうそう…決算報告書の話をしてきたのに営業成績の結果にまったく触れないのはまずい…(笑)。まあ、今回の話題はあくまで数値ではなくApple社内の動向を考察したわけだが、最後に “First Quarter Report 1985” より同期比較の四半期決算の結果をご照会しておきたい。また四半期の時期は違うものの、先般発表された2012年9月29日を末日とする、2012年度第4四半期の業績も合わせて載せておくが、この約30年間でどれほどAppleが巨大な企業に成長したのかがこれらの数字だけでも分かっていただけるものと思う。
(各第1四半期/単位は千ドル)
・1983年 売上高 $316,229 純利益 $5,822
・1984年 売上高 $698,297 純利益 $46,099
(第4四半期/単位は千ドル)
・2012年 売上高 $36,000,000 純利益 $8,200,000
ロボットオペレーティングシステム市場レポートの概要トップキープレーヤーによる詳細情報ABB、ファナック株式会社、KUKA AG、iRobot Technologies、オムロン株式会社など
続きを読む:-
ディジタル・イクイップメント・コーポレーション
35の言語版
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ディジタル・イクイップメント・コーポレーション
Digital Equipment Corporation

略称DEC本社所在地

アメリカ合衆国
マサチューセッツ州メイナード設立1957年業種電気機器事業内容PDP, VAX, Alpha, DECnet, VT100, StrongARM, Digital Linear Tape従業員数140,000人以上(1987年時点)関係する人物ケン・オルセン
ゴードン・ベル特記事項:1998年にコンパックへ吸収合併。2002年にヒューレット・パッカードがコンパックを吸収合併。テンプレートを表示

ディジタル・イクイップメント・コーポレーション (Digital Equipment Corporation) は、かつてアメリカ合衆国を代表したコンピュータ企業の一つ。1957年、ケン・オルセンによってマサチューセッツ州メイナードに設立された。略称「DEC(デック)[注 1]」。欧米では「Digital」と略称されることも多い。
DECのPDPシリーズとVAXシリーズは、1970年代と1980年代の科学技術分野において最も一般的なミニコンピュータだった。DECの本社は1957年から1992年まで、マサチューセッツ州メイナードにあるかつてウール工場であった Clock Tower Place に置かれていた。
1998年にコンパックに買収された。そのコンパックがさらに2001年にヒューレット・パッカード (HP) に買収されたことから、DECの製品群はHPのブランド名で販売されている。かつてのDECの一部事業(特にコンパイラ関連)やマサチューセッツ州ハドソンの工場はインテルに売却された。詳細は「#終焉」の節を参照。
ロゴマークの青色や会社規模から、IBMの愛称"Big Blue"に対して、"Small Blue"の愛称で呼ばれた。後にロゴマークは青色からバーガンディへ変更された。
なお、社名に「Digital」を用いるデジタルリサーチやウェスタン・デジタルとは無関係である。
概要[編集]
当初は小型コンピュータ市場に集中したため、DECは強力なライバルのいない市場で成長することができた。1960年代にはPDPシリーズ、特に世界初の成功したミニコンピュータと言われるPDP-8が人気となった。1970年に発売したPDP-11はそれまでの小型機に取って代わり、DECはコンピュータ業界での地位を確立。PDP-11の後継として設計されたVAX-11は、32ビットミニコンピュータの先駆けとなり「スーパーミニコンピュータ」とも呼ばれた。これらは様々な場面でSystem/370などのメインフレームとも競合した。VAXシリーズもベストセラーとなり、同社が1980年代に世界第2位のコンピュータ企業となる原動力となった。最盛期にはマサチューセッツ州で州政府に次ぐ第2位の雇用者となっている。
1980年代後半にパーソナルコンピュータ市場が成長し、1990年代には強力な32ビットシステムがいくつも登場するようになると、DECのシェアは素早く侵食され始めた。DECの生き残りをかけた最後の大きな挑戦が、64ビットRISCプロセッサアーキテクチャ「DEC Alpha」であった。当初、VAXシリーズをAlphaで再実装しようとしたが、同時に高性能ワークステーションにも採用された。Alphaは良い性能を発揮したが、DECの業績を上向かせることはできなかった。
1998年6月、コンパックがDECを買収。当時のコンピュータ業界では最大となる買収であった。当時のコンパックは企業市場を中心に据える戦略をとっており、他にも大企業をいくつか買収している。その中でもDECはコンパックの弱点だったアメリカ国外で強かった。しかしコンパックは買収した企業群をその後どうするかについて明確なビジョンを持っていなかったため、財政的に苦境に立たされることになる。結局2002年5月、ヒューレット・パッカード (HP) がコンパックを吸収合併した。2007年時点でもDECの一部製品をHPが製造販売していた。
日本法人[編集]
日本 ディジタル イクイップメント株式会社
Digital Equipment Corporation Japan略称日本DEC本社所在地

日本
東京都豊島区東池袋 サンシャイン60 35階
東京都杉並区上荻1丁目2-1設立1982年9月24日業種電気機器事業内容米国本社で開発・製造されたコンピュータ、ネットワーク製品、周辺装置、ソフトウェアの日本国内における販売・サービス、他社製品を含めたクライアント・サーバーソリューション従業員数2,715人(1997年9月時点)[1]特記事項:1998年10月、コンパックコンピュータ株式会社へ吸収合併。テンプレートを表示
日本では、コアメモリを輸入販売していた理経(当時、理経産業)がDECのコアメモリ用検査装置を扱うことになり、これが縁になって同社のミニコンピュータの営業も開始した。1964年、日本で最初のDEC製ミニコンピュータとしてPDP-5を東京大学原子核研究所へ納入した[2][3]。
DECの日本支社は、1968年4月に8人の保守サービス部門からなるディジタル・イクイップメント・コーポレーション・インターナショナル・日本支社(略称:DEC日本支社)として設立され、販売代理店の理経が納入したミニコンピュータの保守サービスのみを手掛けることから始まった。1969年1月に営業部を設置し、理経の営業活動を支援した。1971年9月に大阪サービスセンターを開設、11月にソフトウェアサービス部を設置、1972年8月に製品開発部を設置し、日本での製品開発を本格化した。1973年7月、DEC日本支社が全製品の直接輸入販売を行うことになり、理経はDEC日本支社の代理店という位置づけになった[3]。
当時、外資法により外国資本会社が日本で製品を製造するには日本企業との合弁で日本法人を設立する必要があったが、DECは現地法人の設立を全額出資とすることに固執した[3]。
1980年に外資法が廃止され、その2年後の1982年、米国DECの100%子会社として日本 ディジタル イクイップメント株式会社(英文社名:Digital Equipment Corporation Japan、略称:日本DEC)が設立された[1]。1976年の売上高は36億円、1981年は190億円、1988年には730億円に急成長した[4]。1987年9月には千葉県市川市行徳の検査工場にVAXの組立ラインを設置し、日本での生産を開始した[5][6]。
パソコン分野では、1983年3月9日、米国同様にRainbow 100(英語版)やProfessional 300シリーズを発売して日本のパソコン市場に参入したが、商業的に失敗して一度撤退した。1992年5月、PC/AT互換機「DECpcシリーズ」を発売して日本のパソコン市場に再度参入した[7]。1998年10月、米国本社での動きと同様に日本法人もコンパックコンピュータへ吸収合併された。
歴史[編集]
起源[編集]
1957年、ケン・オルセンとハーラン・アンダーソン(英語版)が設立。彼らはマサチューセッツ工科大学 (MIT) のリンカーン研究所で働く技術者だった。リンカーン研究所は今で言う「インタラクティブ性」の研究で知られており、開発したコンピュータは動作中のプログラムをリアルタイムでオペレータが直接制御できる世界初のものだった。その端緒となったのが1944年のWhirlwindで、元々はアメリカ海軍のフライトシミュレータ向けに開発されたものだが、シミュレータとして使われることはなかった[8]。代わりにその成果はアメリカ空軍のSAGEシステムに採用され、オペレータがコンピュータに格納されたレーダーのデータと対話するために大きな画面とライトガンを使用した[9]。
空軍のプロジェクトが完了すると、リンカーン研究所はWhirlwindで使用していた真空管をトランジスタに置き換えたコンピュータの開発にとりかかった。新たな回路を試験するため、まず小型の18ビットマシン TX-0 を構築し、1956年に稼働させた[10]。TX-0の成功で基本コンセプトに間違いがないことが明らかになると、36ビットの大型システムの開発にとりかかった。これが64kワードの磁気コアメモリを備えたTX-2である。磁気コアメモリは高価だったので、TX-0のメモリ部品をTX-2に流用し、TX-0の残りの部分はマサチューセッツ工科大学に恒久的に貸与された[11]。
MITでオルセンとアンダーソンは奇妙な現象に気付いた。より高速なIBM製メインフレームも利用可能なのに、学生達は小さいTX-0を使うために何時間も並んだのである。2人は対話型コンピューティングが強い魅力を持っているためだと判断し、TX-0を製品化した小型マシンの市場があると考えた。それは、性能よりもグラフィカルな出力やリアルタイム操作が重視される市場である。また、特定タスクのための安価なソリューションを必要としているユーザー向けであり、そのような用途に36ビットの大型機は不要と思われた[12]。
1957年、2人とケンの兄弟スタンは資本金を求めたが、当時のアメリカ実業界ではコンピュータ会社への投資に懐疑的になっていた。1950年代に多数の中小コンピュータ企業が生まれては消えていった経緯があり、技術革新があまりにも急激だったため製品がすぐに陳腐化していた。また、RCAやゼネラル・エレクトリックといった大企業もコンピュータ事業で利益を出せないでいた。そんな中で唯一興味を示したのがジョルジュ・ドリオ(英語版)と彼の率いるベンチャーキャピタル American Research and Development Corporation (AR&D) である。コンピュータ会社の創業という話ではそれ以上の資金が集まらない懸念があったため、ドリオは新会社の事業計画をコンピュータを中心としない形に変更させ、社名も「ディジタル・コンピュータ・コーポレーション」から変更させた[12]。
2人は事業計画を更新し、会社を2段階で発展させる計画にした。まず、コンピュータのモジュールを独立したデバイスとして販売し、研究室などでそれを購入して各種デジタルシステムの構築に使用できるものとする。それによって会社がある程度自立したら、第二段階として完全なコンピュータを開発するという計画である[13]。改称したDECはAR&Dから7万ドルの資金(全資本金の70%)を得て[12]、マサチューセッツ州メイナードにあった南北戦争時代の毛織物工場だった建物で創業した。その工場だった建物を選んだのは、生産に使えるスペースが安価に得られたためである。
回路モジュール[編集]

1958年の早い時期に、DECはその最初の製品である "Digital Laboratory Module" のラインナップを出荷した。このモジュールは、電子部品とゲルマニウムトランジスタをプリント基板に装着したもので、その回路はTX-2の回路を基にしている[14]。
ひとつのDigital Laboratory Moduleは、論理回路の1、2個のフリップフロップ、ゲート、変換器などとして機能する。押し出し成型のアルミニウムでパッケージされており[15]、各モジュールの前面パネルにあるジャックをコードで繋いで機能させる。科学技術関連の実験などが可能だった。動作速度には5MHz(1957年)、500kHz(1959年)、10MHz(1960年)というバージョンがある[14]。特に他のコンピュータ企業が自社製システムの試験装置を構築するのによく使った。1950年代末の景気後退にもかかわらず、1958年だけで9万4千ドルを売り上げ、初年度で黒字を達成した[12]。
間もなく、内部は同じだが異なるパッケージの "Digital Systems Module" も発売した。これは後端にあるアンフェノール型の22ピンコネクタで相互接続するよう設計されており、専用19インチラックに複数収めることができる。ラックの1つの棚(高さ5.25インチ)に25モジュールを収納でき、高密度に収納することでコンピュータを構築可能である[14]。DEC自身もこれを使って磁気コアメモリシステムの試験装置を構築し、それを8年間で約50台販売した[16]。
このようなモジュールは、PDPシリーズでも "System Building Blocks" として使用された。
後に、同様の回路を "R" (red) シリーズ「フリップチップ」モジュールとしてパッケージ化した(訳注:「フリップチップ」は商標(en:Flip Chip (trademark))で、集積回路を基板に実装する技術の、チップを直接基板に接触させ実装する手法の名称であるフリップチップとは無関係)。後に、もっと高速高密度なモジュールも製品化された[17]。DECはモジュールに関して基礎から理解するための広範囲のデータを約A5版大、厚さ約2センチの無料のカタログ本(英文)の形で提供し、これが非常にポピュラーになった。
このカタログ本の無料提供はミニコンピュータでも継承されI/Oのハードウェア機能やインタフェース手法とアセンブリ言語を基礎から応用まで理解し、モジュールを買ったユーザは自ら制御システムを構築できた。事務用とは異なる制御用のコンピュータであるため、採用を検討しているユーザにも教科書(カタログ本)を広く配り、ユーザが独自に学び個々のシステムの構築することを促進する方針を採った。これら大量配布のカタログ本は自社内の印刷・製本部門で作られた。
PDP-1ファミリ[編集]
詳細は「PDP-1」を参照

創業後の最初の製品は成功を収め、DECは事業計画の第2段階であるコンピュータ市場への参入に向かった[13]。1959年8月、ベン・ガーリーはDEC初のコンピュータ PDP-1の設計を開始した。ドリオの命令を守り、Programmed Data Processor の略であるPDPをシリーズ名とし、コンピュータという言葉を避けている。1959年12月、ボストンでの合同コンピュータ会議で初めてプロトタイプが一般公開された[18]。PDP-1の一号機は1960年11月に Bolt, Beranek and Newman に納入され[19]、翌年の4月に正式に検収された[20]。基本構成の価格は12万ドルで、2011年時点の価値に換算すると90万ドルになる[21]。1969年に生産終了となるまでに約50台を出荷している[16][22][23]。
1ワードは18ビットで、基本構成では4096ワードの磁気コアメモリを搭載し、毎秒10万命令の基本性能である。いくつかの19インチラックに多数の System Building Blocks を収める形で構成され、ラック群を1つの大きなフレーム(メインフレーム)でパッケージしており、フレームの一端のテーブルぐらいの高さに六角形の制御パネルがあってスイッチとランプが並んでいる。制御パネルの上には標準入出力である紙テープリーダ/ライタがある。多くのシステムは、Type 30 ベクタグラフィックスディスプレイと Soroban Engineering がIBMのモデルBタイプライタを改造したコンソールタイプライタの2つの周辺機器を加えて購入された。Soroban の機構は信頼性に乏しいことで有名だった。オフラインのプリンターとして Friden Flexowriter 製の端末があり、紙テープリーダ/ライタ付きだった。磁気テープシステム、パンチカードリーダ/パンチ、高速紙テープ/プリンターシステムなどの周辺機器もあるが高価だった。
PDP-1を発表した際、DECは同じ設計に基づく24ビット、30ビット、36ビットのより大きなマシンについても言及していた[24]。PDP-1のプロトタイプを構築中、24ビットのPDP-2と36ビットのPDP-3の設計が並行して進められていた。PDP-2は初期設計のみでそれ以上開発は行われなかったが、PDP-3は最後まで設計された[25]。PDP-3は1960年、CIAの研究部門向けに1台だけ構築された。漏れ伝えられている情報によれば、CIAはそれをA-12偵察機のレーダー反射断面積データの処理に使ったという。ゴードン・ベルはPDP-3がその後オレゴン州で使われたと記憶しているが、誰が使っていたかは思い出せないという[26]。
1962年11月、標準価格6万5千ドルのPDP-4をリリース。命令セットなどはPDP-1と似ているが、メモリを低速なものにし、パッケージを変更して低価格化している。全部で約50台が販売され、顧客層もPDP-1と似ていた[27]。
1964年、DECはフリップチップ・モジュール設計を新たに採用し、PDP-4にそれを適用してPDP-7を生み出した。PDP-7は1964年12月にリリースされ、約100台を生産した[28][27]。1965年、Rシリーズ・フリップチップにアップグレードした PDP-7A をリリースしている[29]。PDP-7はUNIXオペレーティングシステムが誕生したプラットフォームとしてよく知られている[30]。
PDP-1シリーズへの大胆なアップグレードとして、1966年8月にPDP-9をリリース[31]。PDP-4やPDP-7と命令レベルで互換性があるが、PDP-7の約2倍の高速さで、より大きな構成で使用することを意図したものである。1968年時点で標準価格は19,900ドルだった[32]。PDP-9は約450台を売り上げ、それまでのPDP-1ファミリの中では最大のヒットとなった[33]。
PDP-9が登場したころ、既に後継機の設計が始まっており、1969年にPDP-15としてリリースされた。これはPDP-9を集積回路で構成しなおしたマシンである。基本構成でもPDP-9より高速だったが、さらにFPUと入出力用プロセッサを追加でき、さらに性能が向上する。発表から8カ月で400台以上の注文が入り、最終的に12機種で約800台が生産された[33]。しかしそのころには後述する他のファミリがより低価格で似たような市場に対応できるようになっていたため、18ビットファミリはPDP-15で終結することになった。
PDP-8ファミリ[編集]
詳細は「PDP-8」を参照

1962年、リンカーン研究所は System Building Blocks を使って小型の12ビットマシンを実装し、それに様々なアナログ-デジタル変換入出力機器を接続して、アナログの各種実験装置とインタフェースしやすくしていた。これがLINCである。LINCは科学界で強烈な関心を惹きつけ、小さな研究室でも使える安価で小さいマシンだとして世界初の真のミニコンピュータとも呼ばれた[34]。
LINCの成功を目にしたDECは1963年、その基本設計を踏襲してアナログ-デジタル変換機構を除いたPDP-5を開発した。PDP-1ファミリ以外の最初のマシンとして、1963年8月11日のWESTCONで発表。1964年の広告ではPDP-5の利点を「さあ、使われている磁気コアメモリの価格27,000ドルだけであなたもPDP-5を所有できます」と表現していた[35]。1967年初めに生産終了となるまでに約100台が生産された[27]。PDP-5は1964年(昭和39年)東京大学の旧田無市(現:西東京市)の原子核研究所(1997年3月閉所)に導入された日本初のPDP機だった。構成は、本体、タイプライタ、CRTディスプレイ、ライトペン、オシロスコープ・ディスプレイ、ニュークリアー・データ社製ADコンバータで、合計1900万円であった[2]。PDP-1と同様、PDP-5から基本設計が同じ一連の機種が生まれ、PDP-5よりも人気となった。
1965年3月22日、PDP-5で使用していたモジュールをRシリーズ・フリップチップで置換したPDP-8をリリース。小さな卓上型の筐体であり、CPUが格納された部分は半透明のプラスチックで覆われていて、外から配線が見えるようになっている。4kワード×12ビットの磁気コアメモリを搭載し、標準入出力機器としてASR-33を備えた基本構成で、18,000ドルだった。そのため、25,000ドルを割った世界初の「真の」ミニコンピュータと呼ばれた[36][37]。販売は予想通り非常に堅調で、PDP-5の市場にいくつかの企業が参入しはじめたがPDP-8には敵わなかった。これによりDECは市場を2年間ほぼ独占し[38]、同一設計の新機種が登場するまでに "straight eight"(最初のPDP-8)が約1400台生産された[35][39]。
DECはさらに低価格なPDP-8/S(Sは "serial" の意)をリリース。名前が示す通りシリアル演算ユニットを採用しており、低速だがコストも低減され1万ドル以下で売られた[40]。また、PDP-8のCPUとLINCのCPUを備えた2プロセッサ構成のLINC-8(英語版)をリリース。2つのCPUを切り替える命令を備えており、LINC用のプログラムとPDP-8用プログラムが実行可能である。ただしこれはあまり売れず、当初価格は38,500ドルで約140台を売り上げるに留まった[35][33]。LINCからPDP-5が生まれたように、LINC-8を修正してシングルプロセッサ機にしたのがPDP-12である。これは約1000台生産された[35]。1968年には回路設計を改めたPDP-8/IとPDP-8/Lをリリース[17]。1975年には前年のインターシルとの合意に基づき、PDP-8をシングルチップ化した Intersil 6100 が登場した。それにより、DEC自体はPDP-8ファミリの終結を発表したが、その後もPDP-8向けのソフトウェアを生かす手段が残された。
PDP-10ファミリ[編集]
詳細は「PDP-10」を参照

PDP-5の系統で低価格路線をとったころ、DECは1963年、36ビットのPDP-6でメインフレーム市場に参入した。しかし、IBMやハネウェルといったメインフレームメーカーの同様のマシンとの差別化ができず、約30万ドルという低価格だったが販売は苦戦した。PDP-6は約20台[41][27]しか売れなかった。あまり売れなかったため、PDP-6の改良版は開発されなかった。しかし歴史的には初期のタイムシェアリングOSである "Monitor" が導入されたプラットフォームとして重要であり、それが後のTOPS-10へと発展した[42]。
PDP-6は商業的にはあまり成功しなかったが、商業的にも価値のある様々な機能がそこから生まれた。フリップチップによる再実装でPDP-6のコストを大幅に低減できるようになると、DECは1968年、PDP-10で36ビット市場に再び参入した。PDP-10は大いに成功し、1984年に生産終了となるまでに約700台を売り上げた[33]。PDP-10は特に大学でよく採用され、1970年代のOSなどの発展に寄与した。DECは後に36ビットの全機種を "DECsystem-10" というブランド名にし、CPUの型番(例えば "KA10")で機種を示すようになった。さらに仮想記憶を実装したTOPS-20を搭載したシステムを "DECSYSTEM-20" と称した。
DECtape[編集]
PDP-10で最も特筆すべき周辺機器がDECtapeである。DECtapeは5インチリールに巻かれた3/4インチ幅の特殊な磁気テープである。10トラックで固定長ブロックの記録フォーマットで、ディレクトリを含む標準的なファイル構造をその上に記録できる。DECtape上でファイルの書き込み、読み出し、更新、削除が可能で、磁気ディスク装置のような使い方が可能である。効率向上のため、DECtapeはどちらの方向に巻いているときでも読み書き可能になっていた。
実際、磁気ディスク装置を全く装備しないPDP-10システムもあり、DECtapeだけを主要な二次記憶装置として使っていた。複数の紙テープを人手で読み込ませるよりも簡単なので、他のPDPシリーズでもDECtapeが広く使われた。初期のタイムシェアリングシステムはDECtapeをシステムデバイス兼スワップデバイスとして使用可能だった。紙テープより優れていたものの、DECtapeは低速であり、信頼性の高い磁気ディスク装置が利用可能になるとそれに置き換えられていった。
PDP-11[編集]
詳細は「PDP-11」を参照
1968年、DECではそれまでの6ビットの文字ではなく8ビットのバイトに基づいたPDPマシンを開発していた。"PDP-X" と名付けられたこのプロジェクトが中止されたため、一部のチームメンバーが退職して1968年5月にデータゼネラルを創業。すぐさま16ビットのミニコンピュータNovaを発売した。このため、8ビットのバイトという業界の潮流にDECは一時乗り遅れることになった。
16ビットコンピュータPDP-11は、ハロルド・マクファーランド、ゴードン・ベル、ロジャー・キャディらが突貫計画で設計した[43]。このプロジェクトはカーネギーメロン大学で16ビット設計を研究していたハロルド・マクファーランドが入ったことで進捗が加速された。経営陣に最初の提案を行った際あまり好印象ではなく、あやうくキャンセルされそうになったものの、より単純な設計がPDP-11となった[43]。
特にその新設計はアドレッシングモードがあまり豊富ではなく、DECの他のマシンやCISC設計全般で広く採用されていた豊富なアドレッシングモードによってプログラムを小さくするという技法が使えないものだった。それはメモリアクセスにより時間がかかり、システムが低速になることを意味していた。しかし、同時に多数の汎用レジスタを備えるという考え方も採用していたため、プログラミングの自由度が向上し、性能問題はそれである程度カバーされるようになっていた。
PDP-11の主要な改良点として、メモリマップドI/Oによって全周辺機器をサポートするUnibusがある。それにより、通常はバックプレーンにハードウェアインタフェースを挿入し、メモリにマッピングされたインタフェースを読み書きするソフトウェアをインストールするだけで新規機器を容易に追加することが可能となった。そのためPDP-11には、サードパーティによる巨大な周辺機器市場が出現し、それがPDP-11自体をさらに便利なものにするという相乗効果が生じた。
そうした技術革新によってPDP-11アーキテクチャは他社を圧倒して業界のリーダーとなり、DECの復権に寄与した。さらにページング方式とメモリ保護機構が追加されることで、マルチタスクやタイムシェアリングも容易になっていった。一部機種では命令とデータの空間を分離して128kBの仮想アドレス空間を使えるようにし、物理メモリ容量も最大4MBまで拡張している。後に、PDP-11はLSI化されたCPUを採用して小型化し、後継のVAX-11が発売されるまで好調な販売を維持した。
PDP-11にはいくつかのオペレーティングシステムがあった。ベル研究所のUNIXオペレーティングシステムやDECのRSX-11、RT-11、RSTS/Eなどである。初期のPDP-11用アプリケーションは紙テープユーティリティを使って開発された。最初のディスクオペレーティングシステムとしてDOS-11が登場したが、間もなくもっと高機能なOSに取って代わられた。RSX-11は汎用マルチタスク環境であり、各種プログラミング言語が動作した。IASはタイムシェアリング機能を追加したRSX-11である。RSTSとUNIXはタイムシェアリングシステムで、教育機関が無料(または低価格)で使うことができ、PDP-11は当時の技術者や情報工学者が様々なことを試す道具となった。1970年代には通信や工場の制御などでも広く使われている。AT&TはDECの最大の顧客となった。
RT-11は小さいメモリ容量で動作する実用的なリアルタイムオペレーティングシステムであり、DECは組み込みシステム向けのコンピュータ供給業者としても事業を展開した。歴史的には、当時PDP-11で経験を積んだプログラマが多く、そういった意味でRT-11はマイクロコンピュータ用OSにも影響を与えている。例えばCP/Mのコマンド構文はRT-11のそれと似ており、データコピー用プログラム PIP も模倣している。また、DECはコマンド行オプション(スイッチ)に "/" を使っており、それがMS-DOSでパス名に "\" を使うことに繋がっている(UNIXでは '/' が使われる)[44]。
競合他社はPDP-11風の様々なシステムを生み出した。COMECON諸国でもPDP-11のクローンが生み出され、多数生産された。
VAX[編集]
詳細は「VAX」を参照
1976年、DECはPDP-11アーキテクチャを32ビットに拡張し、完全な仮想記憶システムを追加することを決定。その結果、VAXアーキテクチャが生まれた。最初の機種はVAX-11/780で、DECはこれを「スーパーミニコンピュータ」と称した。それは世界初の32ビットミニコンピュータではなかったが、価格設定や販売戦略も相まって、1978年のリリースとともに市場のリーダーに躍り出た。VAXが大いに成功したため、DECは1983年にPDP-10の後継機開発プロジェクトをキャンセルし、VAXアーキテクチャを同社唯一のコンピュータアーキテクチャとして推進する方針を採用した[45]。
VAXの成功を支えた要因のひとつとして、VT52(英語版)端末の成功がある。それまでのあまり成功しなかった機種(VT05(英語版)やVT50)をベースとした、誰もが欲する機能を1つの筐体に全て納めた端末である。その後さらに成功を収めたVT100やその後継機が登場し、DECは業界でも屈指の端末ベンダーとなった。VTシリーズの成功によってDECはあらゆる周辺機器を備えたシステム全体を提供できるようになった。
VAXシリーズの命令セットは今日の一般的な命令セットから見ても非常に豊富な命令群(と豊富なアドレッシングモード)を持っていた。PDPシリーズのページング方式とメモリ保護機能に加えて、VAXは仮想記憶をサポートしている。VAXではUNIXとDEC独自のVMSオペレーティングシステムを使うことができる。
VAX-11シリーズの登場後、DECはシェア拡大のため、ローエンド/ハイエンド市場に向けて様々なバリエーションのシリーズ展開を行っていき、最終的には1990年代初めにマイクロプロセッサ実装のNVAX[46]とハイエンド機 VAX 7000/10000 を完成させた。
マイクロコンピュータ[編集]
汎用マイクロプロセッサの登場により、1975年ごろには世界初のマイクロコンピュータが必然的に登場した。当時のマイクロコンピュータは機能や性能が限定的で、ケン・オルセンは1977年にあざ笑うように「個人が自宅にコンピュータを所有する理由はない」と言ったとされた[注 2]。当然ながら当初DECはマイクロコンピュータ市場にはほとんど目を向けなかった。1980年代初めにDECが開発したVT180(コード名 "Robin")は、Z80ベースのマイクロコンピュータを内蔵してCP/Mが動作するVT100端末だったが、当初この製品はDEC従業員のみに販売された[47]。
パーソナルコンピュータ[編集]
1981年、IBMが IBM PC を発売すると、DECもこの市場に参入することにした。1982年、DECはそれぞれ異なる自社製品アーキテクチャと関連する3種類の非互換なマシンを発売。1つ目はPDP-11/23(後には11/73)をベースにした DEC Professional で、RSX-11M+にメニュー機能を追加したP/OS ("Professional Operating System") が動作した。これはPCよりも高性能だが同時に高価であり、IBM PC とはハードウェアもソフトウェアも互換性がなく、システムのカスタマイズもほとんどできない。CP/MやDOSとは異なり、このマシン用のあらゆるプログラムは個々のマシン毎に発行されるキーを入力しないと使えない仕様になっていた。この方針は当時としては普通の感覚であり、多くのソフトウェアはシステムの製造元から購入するか、個々の顧客向けに開発するのが普通だった。しかしそのために勃興期のサードパーティのソフトウェア企業がProfessionalを無視し、ソフトウェアの流通が容易な他のパーソナルコンピュータに集中した。DEC自体にとってもProfessionalのためによいソフトウェアを開発することは優先度が低く、むしろPDP-11のシェアが侵食されることを恐れていた。Professionalは優れたマシンだったが、結果としてほとんどソフトウェアが供給されなかった[48]。また、P/OSのメニューシステムは低速で柔軟性に欠けており、主流のPC-DOSやCP/Mとはかけ離れていた。2つ目はPDP-8をベースとした DECmate II だが、ワードプロセッサであって汎用コンピューティング向きではなかったし、ワング・ラボラトリーズのワードプロセッサにも太刀打ちできなかった。
DECの初期のパーソナルコンピュータとして最もよく知られているのは、Z80と8088を搭載した Rainbow 100(英語版) で、Z80上でCP/Mが動作し、8088上でCP/M-86が動作した[49]。また、UNIX System III を移植した Venix も動作した。CP/M向けアプリケーションソフトウェアを再コンパイルすれば実行することができたが、そのころ既にMS-DOS上でLotus 1-2-3のような出来合いのアプリケーションを実行する使用法が一般的になりつつあったのに対し、MS-DOS 2.0 の移植が1983年後半まで遅れてしまった。Rainbowは多少報道されたものの、高価であり、マーケティングのサポートもなかったため失敗に終わった[50]。
DECの初期のパーソナルコンピュータで使われたRX50[51]フロッピーディスクドライブ (FDD) の規格は、DECがこの市場にどういう形で臨んだかを端的に表している。そのドライブの機構は他社の5.25インチFDDとほぼ同じだが[52]、DECはディスクフォーマットを独自形式にすることで差別化を図ろうとした。DECのフォーマットは通常より高密度だったため、一般的なPC用FDDとは非互換だった。5.25インチ800KByteフロッピーディスクドライブを装備していた[49]。そのためユーザーは特殊なフォーマットを施された高価なフロッピーディスクを買わされることになった。DECはその独自フォーマットの著作権を主張して独占販売しようとし、そのフォーマットのフロッピーディスクを販売しようとする者にはライセンス契約とロイヤルティ支払いを要求した。フロッピーディスク媒体だけでなく、DECの製品はPC市場に出回っている通常のソフトウェアも使えなかった。ハッカーらがRX50のフォーマットをリバースエンジニアリングで解明したころには[51][53]、DEC製品の悪い評判は固まっていた。
1986年に登場した VAXmate は Microsoft Windows 1.0 が動作し、DECnet経由でVAX/VMSベースのサーバと接続して使用可能になっていた。Rainbowの後継であり、初期のディスクレス・ワークステーションの1つである。また、他社のIBM PCやNEC PC-9801とイーサネットを介して通信するためのソフトウェアとして DECnet-DOS をリリースしたり、マイクロソフト系のネットワークプロトコルをサポートした VAX/VMSサーバも発売している。
1995年からコンパックとの合併まで、PC/AT互換のノートPC、デスクトップPC、サーバを販売していた。
ネットワークとクラスタ[編集]
1984年、DECは10Mbit/sのイーサネットをリリースした。イーサネットはスケーラブルなネットワークを可能にし、VAXclusterはスケーラブルなコンピューティングを可能にした。DECnetとイーサネットに基づく端末サーバ (LAT) を組み合わせることで、DECはネットワーク化されたストレージアーキテクチャを生み出し、IBMと直接張り合えるようになった。イーサネットはトークンリングに取って代わり、今では最も広く使われているネットワーク形態となった。
1985年9月、DECは .com のドメイン名 (dec.com) を登録した5番目の企業となった。
VAXclusterはハードウェアとプロトコルとコンセプトで構成されており、複数のVAXマシンを相互接続して単一の大きなストレージシステムとする技術である。それにより、企業はクラスタに新たなVAXを追加することでサービスの規模拡大を図ることができるようになり、システム全体の買い替えをしなくて済むようになった。その柔軟性は注目を浴び、DECはそれまで手が届かなかったハイエンド市場に参入した。
多様化[編集]
マイクロコンピュータやパーソナルコンピュータでは失敗したが、PDP-11とVAXは記録的な売り上げを続けていた。1980年代中盤には、業界トップのIBMから20億ドルほど引き離された2位となって健闘していた。1986年にコンピュータ業界全体が不景気になるとDECの利益は38%低下したが、1987年にはIBMの業界1位の座を脅かすほど肉薄した[12]。
1980年代終盤のピーク時、DECは世界第2位の規模のコンピュータ企業となり、従業員は10万人を超えていた。そのころDECは中核であるコンピュータ製造とはかけ離れた様々なプロジェクトを展開していた。カスタムソフトウェア開発にも多額の資金をつぎ込んだ。1970年代やそれ以前、ソフトウェアは特定タスク向けに個別に書かれることが多かったが、1980年代までに関係データベースなどのソフトウェアが登場し、モジュール式で強力なソフトウェアを素早く開発できるようになってきた。オラクルなどのソフトウェア企業が急成長してきたため、DECはあらゆる「ホット」なニッチ市場向けのプロジェクトを開始し、同じニッチ(すき間)に複数のプロジェクトが乱立することもあった。そういった製品の一部はDECのパートナー企業の製品と競合することがあり、例えばRdbは数年前にパートナー契約を始めたオラクルのVAX向け製品と競合した。
それらは良く設計されていたが、多くはDEC独特の仕様であり、顧客はそれらを使わずにサードパーティ製品を使うことが多かった。この問題はオルセンが普通の広告を嫌い、技術が確かならば必ず売れるという信念を持っていたことで悪化する。これらのプロジェクトには多大な予算が注ぎ込まれたが、同時期にRISCアーキテクチャをベースとしたワークステーションがVAXの性能に迫ろうとしていた。
陰り[編集]
1980年代になってもマイクロプロセッサの発展が続き、間もなく次世代のマイクロプロセッサがDECのローエンドのミニコンピュータの性能を凌駕するようになることは明らかだった。さらに悪いことに、バークレーRISC(英語版)とスタンフォードMIPSの設計は32ビットであり、DECのドル箱であるVAXファミリの最高性能を凌駕することが予想された[54]。
独自のVAX/VMS製品があまりにも成功したため、DECはそれらの脅威に対して素早く反応できなかった。1990年代に入るとDECの売り上げは伸び悩み、同社初の人員整理も行われた。ミニコンピュータを生み出し、ネットワーク技術を支配し、世界初の個人用コンピュータと言われるものを生み出した会社は、かつてPDP-8が支配したローエンド市場を捨てることになる。この脅威に対してどう対応するかの決断が遅れ、DEC社内では内紛が発生した。
あるグループは、DECの技術力を結集して既存のマシンから飛びぬけた性能のVAXを開発することを提案した。それによって利益率の高いハイエンド市場だけは死守しようという戦略であり、DECはミニコンピュータメーカーとして生き残ることができる。この考え方に沿って開発されたのが VAX 9000 シリーズだが、そのリリースは当初の計画より2年遅れた1989年10月になった[55]。システムの価格はあまりにも高くなり、DECは望んでいた成功を勝ち取ることができなかった。
DEC社内の他の人々は、自前でRISCを設計し新たなマシンを構築するのが適切だと考えた。しかし、あからさまに開発を行うことはできず、4つの小さなプロジェクトがアメリカ各地の研究所で並行して始められた。結局それらプロジェクトは DEC PRISM(英語版) プロジェクトに集結し、新たなVAXの実装の基盤として使える独特の機能を持つ32ビットの設計を開始した[56]。しかしVAX部門との内紛でプロジェクトの資金集めは難しくなり、1988年4月時点で設計は完成せず、間もなくプロジェクト自体が中止となった[57]。
32ビットのMIPSシステムと64ビットのAlphaシステム[編集]
詳細は「DEC Alpha」を参照
DEC内の別のグループは、VAXシステムがその問題に対処する前にサン・マイクロシステムズやシリコングラフィックスのワークステーションがDECの既存顧客の大部分を奪ってしまうと考え、できるだけ早く自前のUnixワークステーションを開発する必要があると判断した。PRISMやVAXの遅々として進まない開発に業を煮やしたパロアルトのグループがプロジェクトを開始。MIPSプロセッサを採用したDECstationを開発し、1989年1月11日に DECstation 3100 をリリースした[58]。それらシステムは市場である程度成功を収めたが、後にAlphaベースの類似シリーズで完全に置換された。

1992年、DECはAlpha命令セットアーキテクチャを初めて実装した Alpha 21064 をリリースした。VAXの32ビットCISCアーキテクチャとは全く異なる64ビットRISCアーキテクチャであり、32ビットからの拡張ではない純粋な64ビットマイクロプロセッサとしても最初期の1つである。当初から性能面ではずば抜けており、2000年代まで高性能さを維持し続けた。2004年11月時点でも AlphaServer SC45 というスーパーコンピュータが性能で世界第6位に位置していた[59]。Alphaベースのコンピュータ(DEC AXPシリーズ。後にAlphaServer(英語版)とAlphaStation(英語版)に改称)はVAXアーキテクチャ製品とMIPSアーキテクチャのDECstationを代替することとなった。オペレーティングシステム (OS) としては、OpenVMS、DEC OSF/1 AXP(後に Digital Unix、さらには Tru64 UNIX と改称)、マイクロソフトの Windows NT が動作した。
1998年にDECがコンパックに買収されると、マイクロソフトはAlpha向け Windows NT の開発とサポートをやめることを決定。これがAlphaベースのコンピュータの終わりの始まりとなった。
DECはUNIXサーバ市場に対抗すべく、POSIX互換機能を追加してVMSをOpenVMSとし、また自前のUnix(PDP-11/VAX/MIPS用のUltrix、Alpha用のOSF/1)を売り出すため、積極的に広告を展開し始めた。しかし、DECは混沌としたUNIX市場に乗り込む準備ができていなかった。さらにインテル製CPUのWindows NTサーバがローエンド市場を侵食し始めた。かつてのDECの顧客を超えてシェアを獲得することは不可能だった。
StrongARM[編集]
詳細は「StrongARM」を参照
1990年代中ごろ、DECの半導体部門はARMと共同でStrongARMを開発した。StrongARMはARM7とDECの技術に基づいた組み込みシステムや携帯機器向けのマイクロプロセッサである。ARMv4アーキテクチャと高い互換性を維持しており、携帯情報端末市場でSuperHやMIPSアーキテクチャと競合して成功を収め、マイクロソフトが一時期 Windows CE の対象プラットフォームをARMアーキテクチャに限定したほどだった。1997年、訴訟にからんでStrongARM関連の知的資産をインテルに売却。インテルでもStrongARMを生産し続け、さらに XScale へと発展させた。2006年、インテルはこの事業をマーベル・テクノロジー・グループに売却した。
設計ソリューション[編集]
DECsystem-10/20、PDP、VAX、Alpha以外に、DECはDNA(Digital Network Architecture、これを実装したのがDECnet)やDSA (Digital Storage Architecture) などの工学的設計でよく知られている。技術的詳細はDigital Technical Journal誌のアーカイブ[1]を参照されたい。
終焉[編集]
1992年6月、ケン・オルセンは社長の座をロバート・パーマーに明け渡した。取締役会はパーマーにそれまでDECでは使ってこなかった最高経営責任者 (CEO) の肩書きを与えた。パーマーは1985年にDECに入社し、半導体部門を担当していた。Alphaマイクロプロセッサでの成功によってオルセンの後継者の座を勝ち取った。また、このときDECのロゴが変更されている[60]。
1990年代初めまで、DECでは一度も大規模な人員整理を行ったことがなかった[61]。しかし1992年から景気後退期に入ると、人員整理が日常茶飯事となり、DECはなんとか規模を縮小して生き残ろうと図った[62]。パーマーはDECをかつてのような収益を上げられる企業に戻すため、企業風土を変えようとしたり、新たな役員を社外から登用したり、中核でない事業部門を売却したりした[63]。
教育研修部門は、独立した会社「グローバル ナレッジ ネットワーク」として分離された[2]。
PDP-11とその一部のOSの権利は1994年にMentecに売却されたが、数年間はDECでもPDP-11ハードウェアが生産され続けた[64]。
1994年、TKシリーズの磁気テープ技術はクアンタムに売却され、今日のDLT および SuperDLTの技術基盤となった。
端末事業(VT100と後継機群)は1995年8月に Boundless Technologies に売却された。
1997年3月、CORBA関連の ObjectBroker や MessageQ といったソフトウェア事業をBEAシステムズに売却。
1997年5月、DECはPentium、Pentium Pro、Pentium IIの設計がAlphaの特許を侵害しているとしてインテルを訴えた[65]。結果として、DECの半導体部門がインテルに売却されることとなった。それにはDECのStrongARM(ARMアーキテクチャ)が含まれており、インテルはこれを元にIntel XScaleプロセッサを開発してPDAなどに採用された。XScaleプロセッサは後にマーベル・テクノロジー・グループに売却された。
1997年、プリンター部門は GENICOM に売却された。当時の機種は未だに DEC のロゴ付きで販売されている。
ほぼ同じ時期に、ネットワーク部門は Cabletron Systems に売却され、間もなく Digital Network Products Group としてスピンオフされた。
1997年時点でDECには、オーストリア、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、コロンビア、キプロス、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、ニュージーランド、オランダ、ノルウェー、ロシア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、イギリスなどに支社があった[66]。
1998年1月26日、ついにDECの残り全ての部分がコンパックに売却された[67]。当時としてはコンピュータ業界史上最大の買収である。コンパックは数年前にもDEC買収を検討したことがあるが、真剣に検討を始めたのはDECが周辺事業を整理してインターネット関連に集中するようになった1997年のことである。この買収でコンパックは企業向けサービス事業に参入してIBMと対抗することを意図しており、DECから受け継いだ部門により2001年にはそういったサービス事業での売り上げが全体の20%となっていた[68]。DECのPC事業は合併後に中止されている。また、コンパックは主要な供給業者であるインテルとの競合を避けるため、半導体部門(Alphaマイクロプロセッサ部門)をインテルに売却した。
コンパック自体も2002年にヒューレット・パッカード (HP) に吸収合併された。コンパックもHPもDEC製品をブランド名を付け替え、ロゴを付け替えて販売した。digital.comとDEC.comというドメインはHPのものとなりHPのサイトにリダイレクトされていた。
研究開発[編集]
DECにはいくつかの研究所があり、研究開発を主導していた。一部はコンパックに引き継がれ、さらに一部はヒューレット・パッカードに引き継がれている。次のような研究所があった。
Paris Research Laboratory (PRL) - パリ(フランス)
MetroWest Technology Campus (MTC) - マサチューセッツ州メイナード
これら研究所などで研究開発に携わっていた業界の著名人を以下に挙げる。
ゴードン・ベル - 技術部門副社長(1972年-1983年)。その後マイクロソフトリサーチへ
デヴィッド・カトラー - RSX-11MとVAX/VMSというオペレーティングシステム開発を主導。その後マイクロソフトで Windows NT開発を指揮
エドソン・デ・カストロ - データゼネラルを創業
ジム・ゲッティーズ(英語版) - X Window System の初期の開発
レスリー・ランポート - LATEXの開発などで知られる計算機科学者
バトラー・ランプソン - Altoの開発などでチューリング賞受賞
ラディア・パールマン - スパニングツリープロトコルを発明。その後サン・マイクロシステムズを経てインテルへ
マーカス・J・レイナム(英語版) - ネットワークセキュリティの専門家
また、半導体部門でAlphaやStrongARMの開発を主導したかつての従業員として以下の人々がいる。
Daniel W. Dobberpuhl - MicroVAX、Alpha、StrongARM
ジム・ケラー - x86-64、Zenマイクロアーキテクチャの開発
Rich Witek - StrongARM
研究所の活動の一部は1985年から1998年まで発行されていた Digital Technical Journal で知ることができる[69]。
成果[編集]
DECはANSI標準、特にASCII文字集合をサポートしてきた。それは現在UnicodeとISO文字集合に受け継がれている。またDEC独自の Multinational Character Set は、ISO 8859-1やUnicodeのLatin-1文字群に多大な影響を与えた。
UNIXは最初にDEC のマシンPDP-7上で作られ、後にPDP-11に移植された。この際、PDP-7のアセンブリ言語で書かれていたUNIXをポータブルに移植する(移植性を高める)ためにC言語が設計され、世界で最初に PDP-11 上に実装された。
VT-78は世界で初めて商業的に成功したワークステーションである。
DECが作り出したオペレーティングシステム (OS) として、OS/8、TOPS-10、TOPS-20、RSTS/E、RSX-11、RT-11、VMS、Digital UNIXがある。PDPシリーズの中でも PDP-11 は当時のプログラマやソフトウェア開発者に影響を与えた。PDP-11 を使用した工場ライン制御システムや交通制御システムが25年経った2004年まで使われていたとの話もある。DECはタイムシェアリングシステムでも業界をリードした。
グラフィカルユーザインターフェース (GUI) におけるAppleのように、DECはコマンド行インターフェイス (CLI) で重要な位置を占めている。起源や様々な発明はDEC以前にもあったが、CLIの形式を完成させたのはDECである。DCL(英語版)として成文化されたDECのOSに見られるコマンド行インターフェイスは、最近のCLIのユーザーから見れば非常に親しみ易い。一方、CTSS、IBMのJCL、UNIVACのタイムシェアリングシステムなどのCLIは全く別物に見えるだろう。CP/MやMS-DOSのCLIはDECのOSと近い特徴を多く有している。例えば、コマンド名(DIR、HELPなど)やファイル名にドットで区切って拡張子を付ける規則などである。
VMSを実行するVAXや(1980年代に広範囲に使われた)Micro-VAXコンピュータは、インターネット以前の重要なコンピュータネットワークDECnetを形成した。DECnetの通信プロトコルは初期のP2Pネットワーク標準のひとつとなった。市場がその価値に気づく以前から、電子メール、ファイル共有、企業内分散協調プロジェクトなどを実現していた。
DECはインテルやゼロックスと共にイーサネットの元になったDIX規格を策定。DECは特にイーサネットを商業的成功に導いた。当初、イーサネットはDECnetとLAT (Local Area Transport) プロトコルと共に使われ、VAXや端末サーバ(RS-232C接続端末を複数台接続し、イーサネット経由でホストシステムに接続する機器)を接続するのに使用された。DECはUnibus用など様々なイーサネットアダプタやコントローラを生み出し、それが業界標準となった。CI "computer interconnect" は、今日では一般的な送信と受信を内部的に分離した初めてのネットワークインターフェイスコントローラーである。
複数のマシンを論理的にひとつとして扱うコンピュータ・クラスター技術はDECが開発した(正確には製品としてクラスタを発売して最初に商業的に成功したのがDECである)。VMSclusterは単に分散処理ができるだけではなく、ディスクや磁気テープ装置なども共有できるようになっていた。
LA36とLA120ドットマトリックスプリンタは業界標準になり、テレタイプ端末の終焉をもたらしている。
VT100端末が業界標準になり、今日のPuTTY、Xtermなどの端末エミュレータでも、VT100をエミュレートできる(これら端末エミュレータのほとんどは、後継機種で上位互換のあるVT220をエミュレートする)。
X Window Systemはマサチューセッツ工科大学 (MIT) のProject Athenaとコンピュータ科学研究所が共同開発したが、DECはこのプロジェクトのメインスポンサーだった。
RSX-11M、RSX-11M+、VMSといったOS開発を手がけたデヴィッド・カトラーは1988年にDECを去り、マイクロソフトで Windows NT の開発を指揮。そのため、Windows NTの内部構造は VMS に似ている部分が多い。VMSを同様の思想のもとに設計しなおしたのが Windows NT カーネルといえる。この命名には諸説あるが、VMSから進化させたことを受けて、"VMS" の英字を1文字ずつ進めて "WNT"、つまりWindows NTとなったと言われている。カトラーはこの噂を否定も肯定もしていない。
Notes-11 とその後継プロジェクト VAXnotes はグループウェアの初期の研究である。Notes-11開発者の一人 Len Kawell は後にロータスに転職し、Lotus Notes開発に関わった。
DECは早くからインターネット関連事業を展開しており、1985年に dec.com というドメインを登録している[70]。World Wide Webが一般化する以前にはDECのソフトウェアリポジトリ gatekeeper.dec.com もよく知られていた。また、1993年10月1日には公式ウェブサイトを開設している[71]。Google以前にインターネット上を席巻していた検索エンジンAltavistaのスポンサーでもあった。
磁気テープ Digital Linear Tape (DLT) の発明は、冷蔵庫ほどの大きさのオープンリールテープ装置を小型化して 5.25" スロットに収まるようにしたのが始まりで、それが800ギガバイトを超える容量のテープ装置にまで発展した。
DECのDIGITAL HiNote Ultraシリーズは、当時としては考えられない程スリム(薄型)なノートパソコンだった。その優れたデザインや設計思想は、コンパック及びヒューレット・パッカードの製品に引き継がれている。
世界初のハードディスク内蔵型MP3プレイヤー Personal Jukebox はコンパックへの吸収合併の約1ヵ月前に DEC Systems Research Center で開始された。
コンパックのiPAQのベースとなったのはDECで研究開発されていたItsy Pocket Computerである。
ユーザー団体[編集]
DECのユーザーグループとしては、1960年代から1990年代まで DECUS (Digital Equipment Computer User Society) と呼ばれた団体がある。1998年にコンパックに買収されると、DECUSは CUO (Compaq Users' Organisation) と改称。2002年にコンパックがHPに買収されると HP-Interex となったが、いくつかの国ではDECUSがそのまま存続している。アメリカではEncompassがそれに相当する。
脚注[編集]
注釈[編集]
^ ディジタル・イクイップメント・コーポレーション自身が "DEC" を使った例: PDP11 Processor Handbook (1973): page 8, "DEC, PDP, UNIBUS are registered trademarks of Digital Equipment Corporation;" page 1-4, "Digital Equipment Corporation (DEC) designs and manufactures many of the peripheral devices offered with PDP-11's. As a designer and manufacturer of peripherals, DEC can offer extremely reliable equipment... The LA30 DECwriter, a totally DEC-designed and built teleprinter, can serve as an alternative to the Teletype."
^ 後にオルセンはホームオートメーションのことを言ったのだと主張した。"Ken Olsen"
出典[編集]
^ a b “DIGITAL Japan Profile”. 1998年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月17日閲覧。
^ a b 「インフォメーション」『Computer report』第4巻第12号、日本経営科学研究所、1964年、71頁、ISSN 0385-6658。
^ a b c 岩淵, 明男「日本DEC誕生までの道程」『超エクセレントカンパニーDEC』ティビーエス・ブリタニカ、1985年、168-184頁。ISBN 4-484-84214-9。
^ 『在日外資企業要覧 1984』日本工業新聞社、1983年、189頁。ISBN 4-8191-0308-3。
^ 日本ディジタルイクイップメント「日本DEC 昭和63年度6月期の決算報告 売り上げ高730億円、対前年度比25%の増収」『情報科学』第24巻第6号、情報科学研究所、1988年、88頁、ISSN 0368-3354。
^ 「企業研究:小さな巨人・DEC PART3 R&D戦略の拠点・日本DECの役割」『Decide』第5巻第3号、サバイバル出版、1987年、103-104頁、ISSN 0911-291X。
^ 「国内関係ニュース」『電子工業月報』第34巻第7号、日本電子工業振興協会、1992年、74頁。
^ "MITRE's Project Whirlwind Computer Collection Transferred to MIT", MITRE, 1 July 2009
^ "Semi-Automatic Ground Environment (SAGE)"Archived 2009年5月13日, at the Wayback Machine., MITRE, 25 January 2005
^ "TX-0 Computer", Computer History Museum
^ The Computer Museum Report Volume 8 Spring 1984, The Computer Museum, Boston, MA,
^ a b c d e "Digital Equipment Corporation", International Directory of Company Histories, Volume 6, St. James Press, 1992
^ a b "A Proposal to American Research and Development Corporation 27 May 1957"
^ a b c Richard Best, Russell Doane and John McNamara, "Digital Modules, The Basis for Computers", Computer Engineering, A DEC view of hardware systems design", Digital Press, 1978
^ "DEC Laboratory Module – FLIP-FLOP 201", Computer History Museum
^ a b Present 1978, p. 3
^ a b Present 1978, p. 10
^ Eastern Joint Computer Conference and Exhibition, official program of 1959 meeting in Boston
^ Computers and Automation, April 1961, pg. 8B
^ "Bureau of Labor Statistics Inflation Calculator, 1961–2011"
^ "History of Computing", Lexikon Services, ISBN 0-944601-78-2
^ Datamation, Volume 5 Number 6 (November/December), pg. 24
^ "Preliminary Specifications: Programmed Data Processor Model Three (PDP-3)", DEC, October 1960
^ Posting in "Announcements from The DEC Connection", The DEC Connection, 14 January 2007
^ Gordon Bell, "DIGITAL Computing Timeline, 1964, PDP-7"
^ Gordon Bell, "DIGITAL Computing Timeline, 1965, PDP-7A"
^ Eric Steven Raymond, "Origins and History of Unix, 1969–1995", 19 September 2003
^ Gordon Bell, "DIGITAL Computing Timeline, 1965, PDP-9"
^ DEC Advertisement, Chemical and Engineering News, Volume 46 (1968), pg. 85
^ Wesley Clark, "The Linc, Perhaps the First Mini-Computer", From Cave Paintings to the Internet
^ "DEC PDP-8 minicomputer, 1965", The Science Museum
^ "Internet History:1965", Computer History Museum
^ Present 1978, p. 7
^ Present 1978, p. 8
^ Gordon Bell, "DIGITAL Computing Timeline, 1964, PDP-6"
^ "PDP-6 Timesharing Software", DEC Publication F-61B
^ a b Larry McGowan, "How the PDP-11 Was Born (according to Larry McGowan), 19 August 1998
^ "The day Jupiter went out of orbit", Electronic Business, Volume 10 (1984), pg. 76–79
^ Croxton, Greg. “DEC Robin (VT-180) & documentation”. DigiBarn Computer Museum. 2011年3月21日閲覧。
^ Katan, M.B., Scholte, B.A., 1984. Application of a Professional 350 in a university department - a consumer’s report, in: Proceedings Digital Equipment Computer Users Society. Amsterdam, p. 368.
^ a b ASCII 1983年5月号, p. 98.
^ “The Rainbow 100 Frequently Asked Questions”. Drive W. Approximatrix, LLC (2009年). 2010年12月15日閲覧。
^ a b Stravers, Kees. “The RX50 FAQ”. Kees's VAX page. 2011年3月21日閲覧。
^ "Geek Historian". “MP01482 RX50 EngrDrws Jul82”. Tech History – Digital Equipment Corporation. 2011年3月21日閲覧。
^ Wilson, John. “PUTR.COM V2.01”. 2011年3月21日閲覧。This relatively-recent work is a well-developed example of programs to enhance interchange of data between DEC formatted media and standard PC systems
^ John Hennessy, David Patterson and David Goldberg, "Computer Architecture: A Quantitative Approach", Morgan Kaufmann, 2003, pg. 152
^ John Markoff, "Market Place; Digital Finally Follows a Trend", The New York Times, 16 July 1990
^ Dileep Bhandarkar et al., "High performance issue oriented architecture", Proceedings of Compcon Spring '90, pg. 153–160
^ Mark Smotherman, "PRISM (Parallel Reduced Instruction Set Machine)", Clemson University School of Computing, October 2009
^ Thomas Furlong et al., "Development of the DECstation 3100", Digital Technical Journal, Volume 2 Number 2 (Spring 1990), pg. 84–88
^ The digital LOGO Vt100.net
^ Schein 2003, pp. 67, 109
^ Schein 2003, p. 233
^ Schein 2003, pp. 128, 144, 234
^ "DEC, Cyrix sue Intel", by Gale Bradley and Jim Detar, Electronic News 43, #2168 (19 May 1997), ISSN 1061-6624.
^ SEC Web site retrieved 22 January 2008
^ “速報:米COMPAQ、米DECを96億ドルで買収”. PC Watch (1998年1月26日). 2012年8月30日閲覧。
^ Digital Equipment Corp - Takeover By Compaq Computer Corp.
参考文献[編集]
Digital Equipment Corporation: Nineteen Fifty-Seven to the Present, DEC Press, (1978)
Alan R. Earls, Digital Equipment Corporation; Arcadia Publishing, 2004, ISBN 0-7385-3587-7.
Edgar H. Schein, Peter S. DeLisi, Paul J. Kampas, and Michael M. Sonduck (2003). DEC Is Dead, Long Live DEC: The Lasting Legacy of Digital Equipment Corporation. San Francisco: Barrett-Koehler Pub. ISBN 1-57675-225-9
Jamie P. Pearson, Digital At Work – Snapshots of the First 35 Years; Digital Press, 1992, ISBN 1-55558-092-0
Glenn Rifkin, and George Harrar, The Ultimate Entrepreneur – The Story of Ken Olsen and Digital Equipment Corporation; Contemporary Books, 1988, ISBN 0-8092-4559-0.
C. Gordon Bell, J. Craig Mudge, and John E. McNamara (1978). Computer Engineering - A DEC View of Hardware Systems Design. Digital Press. ISBN 0-932376-00-2
「ASCII 1983年5月号」第7巻第5号、株式会社アスキー出版、1983年5月1日。関連項目[編集]
ウィキメディア・コモンズには、ディジタル・イクイップメント・コーポレーションに関連するカテゴリがあります。
ヒューレット・パッカード
79の言語版
ツール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "ヒューレット・パッカード" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2021年9月)

この項目では、HP.inc等の前身企業について説明しています。エイベックスのレコードノーベルについては「HPQ (エイベックスのレコードレーベル)」を、後身のNYSEコードが同名の企業については「HP Inc.」をご覧ください。
ヒューレット・パッカード
Hewlett-Packard Company


アメリカ合衆国
カリフォルニア州パロ・アルト、ハノーバー・ストリート3000本店所在地デラウェア州設立1939年1月1日業種情報・通信業事業内容パーソナル・コンピューティングその他のアクセス・デバイス
イメージングおよびプリンティング関連製品およびサービス代表者メグ・ホイットマン(社長兼CEOおよび取締役)資本金228億3千3百万米ドル(2012年10月31日時点)[1]売上高1,203億5千7百万米ドル(2012年10月期)[2]営業利益-110億5千7百万米ドル(2012年10月期)[3]純利益-126億5千0百万米ドル(2012年10月期)[4]総資産1,087億6千8百万米ドル(2012年10月31日時点)[5]従業員数331,800 人(2012年10月31日時点)[6]決算期10月末日主要株主シード・アンド・カンパニー(※) 94%
(2010年12月31日時点)主要子会社日本ヒューレット・パッカード
日本HPフィナンシャル・サービス株式会社関係する人物ウィリアム・ヒューレット(創業者)
デビッド・パッカード(創業者)外部リンクwww.hp.com/us-en/home.html特記事項:※実質株主に代わって株式を保有する名義人である。
1939年にパートナーシップとして創業。1947年8月18日にカリフォルニア州法人として設立。1998年5月20日に設立州をデラウェア州へ変更。テンプレートを表示

ヒューレット・パッカード(英: Hewlett-Packard Company)は、コンピューターと電子計測機器の製造、販売を営んでいたアメリカ合衆国の企業である。hp(エイチピー)の略称で呼ばれることが多い。本項でもhpと記す部分がある。
2015年時点のデータで、パーソナルコンピュータの売上世界2位、サーバ売上世界1位、プリンター売上世界1位を誇る。
1999年に計測機器、化学分析機器、医療機器、電子部品を分離してアジレント・テクノロジーを設立し、アジレント・テクノロジーは2014年に電子計測機器部門を分離してキーサイト・テクノロジーを設立した。
2015年11月1日に、パソコン、プリンターなどエンドユーザーに近い機器を扱うHP Inc.と、データセンター向けサーバー機器を扱うヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)の二つの法人に分割された(法人登記上はHP Inc.に社名を変更し、HPEを新設)。
本体の会社分割を受けて、従来の日本法人の日本ヒューレット・パッカードはヒューレット・パッカード・エンタープライズの日本法人となり、HP Inc.の日本法人として日本HPが設立された。
概要[編集]
1939年に、ウィリアム・ヒューレットとデビッド・パッカードによりアメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルトで創業した。2015年の会社分割まで同地域内に本社を置き、後継会社も同地域内に本社を置いている。当初はオシロスコープに代表される電気・電子計測器メーカーとして創業した。1980年代にUNIXサーバー、ワークステーション分野に参入し、ハードウエアとしてHP 9000、OSとしてHP-UXを販売し、大規模・ミッションクリティカルな分野で存在感を示した。
1999年に電気・電子計測器事業、化学分析機器・医療機器事業はアジレント・テクノロジーへ分割され別会社となった。電気・電子計測器事業はさらに2014年にキーサイト・テクノロジーに事業移転している。
2002年にコンピューター大手コンパックを買収し、以後はコンパックから事業を継承したIntelおよびアドバンスト・マイクロ・デバイセズのx86プロセッサを搭載するWindows・Linux向けサーバー機器、コンシューマー向けPCの存在感が高まり、事業の根幹となる。この合併後、PC事業はデルに次ぐ2番手の地位に甘んじていたが、2006年第3四半期におけるPCの販売台数が世界1位となった。以降、2013年第3四半期以降にレノボに抜かれるまでPCの世界シェア第1位の企業であった。2014年、2015年は2位となったが、2016年に再び1位に返り咲いている。
2006年11月16日に発表した2006年10月までの2006年会計年度によると、ヒューレット・パッカードの年間売上高は917億ドルで、IBMが発表した2006年度の決算額売上高914億ドルを上回り、当時の売上高で世界第1位のIT企業になった。2012年にAppleは売上高でヒューレット・パッカードを上回り売上高世界第1位のIT企業になった。ヒューレット・パッカードはサーバやPCなどハードウエアの拡販が進み、コンシューマ市場でもPCやプリンタの売上を強化した結果である。IBMは企業向けのシステムインテグレーションやアウトソーシング事業に傾注し、売上高よりも利益重視の経営へと進んでいることによる。両社の事業ポートフォリオは分かれつつあるが、企業向けのシステムインテグレーションやサーバ製品では、これまで通りの競合状況にあり、今後も業界盟主の座をかけた競合状況は進むと予想された。
2008年5月、ITサービスの分野で世界第2位のElectronic Data Systems(EDS)を買収し、この分野でもIBMへの追撃を図る。さらに同年10月には、無線LAN、無線ネットワークセキュリティを手がけるコルブリス・ネットワークス[注 1][注 2] も買収し、同社の製品を、有線・無線ネットワーク機器のブランドである「HP ProCurve」に統合した。
2010年4月、スリーコムを27億ドルで買収、同時にスリーコム社が中国のファーウェイと共同設立したH3Cテクノロジーズを100%子会社化しH3CブランドとProCurveブランドを統合、新たにHP Networkingブランドとしてネットワーク製品の提供を開始した。
2011年8月18日に、オートノミーを102億ドルで買収すること、WebOSを搭載する携帯電話機やタブレット機器などの開発中止、WebOSはソフトウェアとして開発継続、パソコン事業部門の15か月以内を目途とした再構築、を発表した。パソコン部門の再構築はパソコン分野から撤退と受け止められ、翌日の株価は20%下落した。この時点でパソコン市場では世界的にトップシェアで、大半の報道は低収益性によりパソコン分野から撤退すると決定的に報じたが、ヒューレット・パッカードはパソコン分野からの撤退は決定事項ではなく複数選択肢のひとつとしている。
2011年9月22日に、レオ・アポテカーからメグ・ホイットマンにCEOが交代して方針が転換され、10月27日にパソコン部門は継続されることが発表された。
2011年時点で、売上高が世界最大のIT機器メーカーであり、パソコン、サーバ、プリンターのすべてで世界トップシェアを持っていた。
2012年3月の時価総額は約470億米ドルで世界時価総額ランキング132位(※同時期のアップルの時価総額は約5,600億米ドルで1位、IBMの時価総額は約2,400億米ドルで5位)。
2013年9月20日に、ダウ平均株価採用銘柄から外れた。
2014年10月6日、メグ・ホイットマンCEOよりPC・プリンタ部門と企業向け部門が分割されることが発表された。PC・プリンタ部門は「HP Inc.」として、企業向け部門はヒューレット・パッカード・エンタープライズとしてそれぞれが上場企業となる計画である。2014年当時のロゴは HP Inc. が継承する。
2015年11月1日に会社分割が完了した。15年の売り上げは、パソコン世界2位、サーバ1位、プリンター1位であった。
Hewlett Packard Enterpriseは、2015年に緑色基調の新しいロゴマークへ移行し[7]、HP Inc.が継承した旧Hewlett-Packard Companyのブランドロゴも2016年に一部製品で変更された[8]。
歴代CEO[編集]
1964年 - 1968年 デビッド・パッカード(David Packard)
1969年 - 1978年 ウィリアム・ヒューレット(William R. Hewlett)
1978年 - 1992年10月31日 ジョン・ヤング(John A. Young)
1992年11月1日 - 1999年7月18日 ルイス・プラット(Lewis E. Platt)
1999年7月19日 - 2005年2月8日 カーリー・フィオリーナ(Carleton S. Fiorina)
2005年2月9日 - 2005年3月31日 ロバート・ウェイマン(Robert P. Wayman)
2010年8月7日 - 2010年10月31日 キャシー・レスジャック(Cathie Lesjack)
2010年11月1日 - 2011年9月22日 レオ・アポテカー(Léo Apotheker)
2011年9月22日 - 2015年11月1日 メグ・ホイットマン(Meg Whitman)
関連企業[編集]
後継企業[編集]
直接・間接に吸収した企業[編集]
製品群[編集]
コンピュータハードウェア[編集]

HP-IB - GP-IBの元となる規格
サーバ
HP ProLiant サーバ
DL System(ラックマウント型)
ML System(タワー型)
HP Integrity サーバ
HP 9000 サーバ
パーソナル・ワークステーション
HP Personal Workstation xwシリーズ
HP Personal Workstation Zシリーズ
(企業向け OpenGL 対応グラフィクス機能を強化したPC)
ネットワークセキュリティ機器
コンピュータソフトウェア[編集]
MC/ServiceGuard(Linuxでも動作)
Tru64 Unix(旧DEC時代はDigital Unix)
NonStop Kernel 旧タンデム社のOS。Nonstopサーバで動作する。
NonStop-UX 旧タンデム社のフォールトトレラントサーバで動作するUnix。
OpenVMS 旧DEC社のOS。Unixではない。
HP ArcSight 統合リスクマネージメントシステム
HP Fortify アプリケーション脆弱性検査
HP IceWall SSO シングルサインオン
マイクロプロセッサ[編集]

PA-RISC — ヒューレット・パッカードが独自に開発したRISC型プロセッサ。HP-UXを動かすHP-9000シリーズで使用。開発・生産共に終了済み。
DEC Alpha — 旧DECが開発したプロセッサ。当時の他のプロセッサより高速な上、Windows NTなど対応するシステムもバラエティに富んでおり、当時は人気があった。しかし、ヒューレット・パッカードはIA-64を提供しているため、Alphaは既存顧客のためだけに維持していた。開発終了済み。
プリンター[編集]
詳細は「ヒューレット・パッカードのプリンター」を参照
ヒューレット・パッカード製のインクジェットプリンターは、一部の機種やシリーズを除き、プリントヘッドとインクカートリッジが一体化していることが特徴であった。現在[いつ?]はインクカートリッジとヘッドが分離し、各色独立インクカートリッジを持つ機種が主力となり、ヘッド一体型インクカートリッジは廉価機種に限られる。世界でトップシェアだが、日本ではエプソン、キヤノン、ブラザーの次のグループである。
脚注[編集]
[脚注の使い方]
注釈[編集]
^ 2000年にマサチューセッツ州で創立した無線LANに特化した企業。この時点で、世界で唯一旅客機用デュアル無線Wi-Fi(IEEE 802.11n/a/b/gとa/b/g)を手がけている。そのほか、鉄道、ホテル、病院、公共施設、ISPなど、エンタープライズ向けWi-Fiソリューションを得意とする。
出典[編集]
^ Hewlett-Packard>Investor Relations>Latest Annual Report and Proxy>2012 Annual Report>80P>Consolidated Balance Sheets>Total stockholders’ equity
^ Hewlett-Packard>Investor Relations>Latest Annual Report and Proxy>2012 Annual Report>38P>ITEM 6. Selected Financial Data.>Net revenue
^ Hewlett-Packard>Investor Relations>Latest Annual Report and Proxy>2012 Annual Report>38P>ITEM 6. Selected Financial Data.>Earnings from operations
^ Hewlett-Packard>Investor Relations>Latest Annual Report and Proxy>2012 Annual Report>38P>ITEM 6. Selected Financial Data.>Net earnings
^ Hewlett-Packard>Investor Relations>Latest Annual Report and Proxy>2012 Annual Report>38P>ITEM 6. Selected Financial Data.>Total assets
^ Hewlett-Packard>Investor Relations>Latest Annual Report and Proxy>2012 Annual Report>15P>Employees
^ 「IT企業は青いロゴばかりなので、緑色にしました」――米HPが分社化、“Hewlett Packard Enterprise”始動 ITmedia、2015年11月2日
^ HPのカッコよすぎる新ロゴ 実は一度ボツになっていた? ITmedia、2016年4月10日
関連項目[編集]
外部リンク[編集]

ウィキメディア・コモンズには、ヒューレット・パッカードに関連するカテゴリがあります。
よろしければサポートお願い致します。いただいたサポートはこれからの投資のために使わせていただきます。
